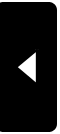2010年09月28日
10月定例会のお知らせ
青葉奨学会沖縄委員会では、2ヶ月に一度、基本的に偶数月の第一土曜日に定例会を持っています。
10月の定例会は、10月2日(土)午後7時から、すぺーす結(久茂地マンション402号室)で行います。
11月の初めに、3名の会員の方と一緒にベトナムを訪ねる予定です。
今回は3泊4日の短い日程ですが、ホーチミン市内とカンザー地区(ロンホア村、ビンカン村)の里子と会いたいと考えています。
そこで、今回の定例会は旅行の事前勉強会を兼ねて、青葉奨学会の支援の現状や、カンザー地区の様子についてご説明したいと思います。
参加予定者のお一人のSさんは、以前に2度カンザーを訪ねていらっしゃるので、Sさんのお話しも聞きたいと思っています。
もちろん、旅行に参加予定でない方も、定例会への参加を歓迎します。
会員でない方も、大歓迎です。いつも通り、一品持ち寄りで、気軽にやりたいと思います。
興味のある方、どうぞお越し下さい。
お問い合わせなどは、080-2719-4720(村田)までご連絡下さい。
10月の定例会は、10月2日(土)午後7時から、すぺーす結(久茂地マンション402号室)で行います。
11月の初めに、3名の会員の方と一緒にベトナムを訪ねる予定です。
今回は3泊4日の短い日程ですが、ホーチミン市内とカンザー地区(ロンホア村、ビンカン村)の里子と会いたいと考えています。
そこで、今回の定例会は旅行の事前勉強会を兼ねて、青葉奨学会の支援の現状や、カンザー地区の様子についてご説明したいと思います。
参加予定者のお一人のSさんは、以前に2度カンザーを訪ねていらっしゃるので、Sさんのお話しも聞きたいと思っています。
もちろん、旅行に参加予定でない方も、定例会への参加を歓迎します。
会員でない方も、大歓迎です。いつも通り、一品持ち寄りで、気軽にやりたいと思います。
興味のある方、どうぞお越し下さい。
お問い合わせなどは、080-2719-4720(村田)までご連絡下さい。
2010年09月25日
昔は「東京」、いまは「河内」
江戸が「東京」と改称されたのは、1868年のこと。
でもそれよりも400年以上も前の15世紀前半、東南アジアに「東京」と呼ばれる街がありました。その頃、東京(江戸)は、まだ海沿いの原野だったかもしれません。
かつて「東京」と呼ばれていた街とは、どこでしょうか。
答えは、ベトナムの首都ハノイです。
「東京」は、「トウキョウ」ではなく、「ドンキン」と読みます。
ハノイの名前は、歴史の中で何度も変わってきました。「大羅(ダイラ)」「昇龍(タンロン)」「東都(ドンド)」など。
1427年に、明と戦って独立を取り戻したレロイが、この都市を「東京(ドンキン)」と名付けました。
当時はベトナムでも漢字を使っていたので、実際に「東京」と書いていたはずです。
その後、日本の江戸が「東京」に変わる少し前の1831年、ベトナムではグエン朝のミンマン帝の時代に、この街が「河内」と呼ばれるようになったそうです。
「河内」は「かわち」と読みたくなりますが、ベトナムの読み方では「ハノイ」です。
ハノイは紅河という大きな川のほとりにあって、街の中にも、ホアンキエム湖や西湖など多くの湖があります。
河の内にある街、ということで、「河内(ハノイ)」になったそうです。
ちなみに、大阪の方に聞いたところ、大阪の河内地方にも大和川という大きな川があって、溜め池などもたくさんあるそうです。ハノイも河内も似た地形なのですね。
ただ、ハノイの古名としては、「東京(ドンキン)」よりも「昇龍(タンロン)」のほうが、ずっと知られています。
正式には「東京」だった時代も、人々の間では「昇龍」のほうが親しまれていた、とも聞きました。
李朝の始祖、李太祖(リタイトー)がここを都に定めたとき、黄色い龍が立ち昇った、という印象深い伝説があるためでしょうか。
ところで、そのハノイ、いま雰囲気がとても盛り上がっているようです。
今年は奈良遷都1300年だそうですが、ハノイは建都1000年の節目の年なのです。
10月10日には、大きなお祭りが行われるそうです。
ハノイの建都祭には、東京都知事も招待されて参加するそうです。
ハノイは、かつて「東京」と呼ばれた、ある意味では「もうひとつの東京」とも言える街。
そのハノイのお祝いに、東京都の知事が参加するのは面白いなあ、と思いかけたのですが、すぐに「げっ!」と思ってしまいました。
考えてみれば、東京都知事ってあの人ですよね…。
なんだかなあ…。
でもそれよりも400年以上も前の15世紀前半、東南アジアに「東京」と呼ばれる街がありました。その頃、東京(江戸)は、まだ海沿いの原野だったかもしれません。
かつて「東京」と呼ばれていた街とは、どこでしょうか。
答えは、ベトナムの首都ハノイです。
「東京」は、「トウキョウ」ではなく、「ドンキン」と読みます。
ハノイの名前は、歴史の中で何度も変わってきました。「大羅(ダイラ)」「昇龍(タンロン)」「東都(ドンド)」など。
1427年に、明と戦って独立を取り戻したレロイが、この都市を「東京(ドンキン)」と名付けました。
当時はベトナムでも漢字を使っていたので、実際に「東京」と書いていたはずです。
その後、日本の江戸が「東京」に変わる少し前の1831年、ベトナムではグエン朝のミンマン帝の時代に、この街が「河内」と呼ばれるようになったそうです。
「河内」は「かわち」と読みたくなりますが、ベトナムの読み方では「ハノイ」です。
ハノイは紅河という大きな川のほとりにあって、街の中にも、ホアンキエム湖や西湖など多くの湖があります。
河の内にある街、ということで、「河内(ハノイ)」になったそうです。
ちなみに、大阪の方に聞いたところ、大阪の河内地方にも大和川という大きな川があって、溜め池などもたくさんあるそうです。ハノイも河内も似た地形なのですね。
ただ、ハノイの古名としては、「東京(ドンキン)」よりも「昇龍(タンロン)」のほうが、ずっと知られています。
正式には「東京」だった時代も、人々の間では「昇龍」のほうが親しまれていた、とも聞きました。
李朝の始祖、李太祖(リタイトー)がここを都に定めたとき、黄色い龍が立ち昇った、という印象深い伝説があるためでしょうか。
ところで、そのハノイ、いま雰囲気がとても盛り上がっているようです。
今年は奈良遷都1300年だそうですが、ハノイは建都1000年の節目の年なのです。
10月10日には、大きなお祭りが行われるそうです。
ハノイの建都祭には、東京都知事も招待されて参加するそうです。
ハノイは、かつて「東京」と呼ばれた、ある意味では「もうひとつの東京」とも言える街。
そのハノイのお祝いに、東京都の知事が参加するのは面白いなあ、と思いかけたのですが、すぐに「げっ!」と思ってしまいました。
考えてみれば、東京都知事ってあの人ですよね…。
なんだかなあ…。
Posted by クアン at
21:14
│Comments(0)
2010年09月24日
中秋節のつどい報告
昨夜、沖縄NGOセンター事務所で、「中秋節の集い~ベトナム留学生と一緒に」を行いました。
厳密に言うと、昨日は中秋節の翌日ということになりますが…。
ベトナムの中秋節は、子どもたちのためのお祭りです。
中秋節のころ、ベトナムの子どもたちはデンロンという提灯を持って歩きます。
第一部は、留学生と一緒に、デンロン作りをしました。
参加者は10名あまり。ベトナム北部で8年間仕事をされていたSさんが家族ぐるみで来て下さいました。
子どもたちはベトナム生まれで、ベトナム語もある程度わかるようです。

デンロン作りは下準備をしておいたので、1時間を見込んでいましたが、わいわい言いながら作っていると、思ったよりも時間がかかります。
骨組みを完成させたところでいったん中断して、第二部の交流会に移りました。参加者も20名ほどに増えました。
私たちは生春巻やおにぎりを用意、参加者の方がヌックマムで味をつけた鶏の唐揚げ(子どもたちに大好評)や、おはぎを持ってきて下さいました。

留学生は、4人来てくれました。

自己紹介で、それぞれの「中秋節、お月見の思い出」を簡単に話していただきました。日本(沖縄)でも、地域によっていろんなお祝いの仕方や、食べ物があったようです。
沖縄委員会代表のすずよさんは、子ども時代は宮古にいましたが、中秋の名月の夜には、ある家の屋上に
子どもたちが集まって、歌や踊りを披露して遊んだそうです。この日の夜だけは、子どもが夜更かしして遊んでも咎められなかったそうです。
次に、留学生にベトナムの歌を披露してもらいました。
中秋節は子どものお祭りなので、「Cho con(わが子へ)」という歌をうたってもらいました。幼いわが子に対する、両親の深い想いをうたった、美しい歌です。
続いて、「Ruoc den thang tam」という、楽しい中秋節の歌を紹介してもらいました。ベトナムには中秋節の歌が多くあり、「Tet trung thu(中秋節)」というタイトルのCDもいくつか出ているほどなのですが、比較的新しい歌が多いそうです。
「Ruoc den trung thu」は、こんな感じの歌詞です(ちょっと間違っているかもしれません。あくまでもこんな感じ、ということで…)。
中秋節には、デンロン行列をして遊びに行くの
わたしは行列で、あちこちに行くのよ
デンロンを手にして、心もうきうき
満月の明かりの下で、歌って踊るのよ
星のかたちのデンロン 魚のデンロン
天女さまのデンロンに 蝶々のデンロン
わたしはデンロンを持って、お月さまに行くのよ
藍色のデンロンに 紫のデンロン
青いデンロンに 白いデンロン
色とりどりの、きれいな灯りに囲まれて
はるかな空のかなたに、丸くかわいらしい姿
やさしい光が、地上に降り注いでいる
8月の満月の中に、月の天女さまの姿
わたしは、天女さまと一緒に、歌って踊るのよ
獅子舞の太鼓が ジンジン ジンジン
わたしはデンロンを持って お月さまに行くのよ
獅子舞の太鼓が ジンジン ジンジン
わたしは天女さまと一緒に お祝いするのよ
なんかうきうきする歌詞ですね。そういえば、沖縄の「豊年音頭」でも、天女が浮かれて舞い踊りますね。
ベトナムの歌のお礼に、沖縄や日本の、中秋節やお月さまに関係する歌を紹介しようということになりました。
でも、あまりたくさんは思い浮かびません。
まず思い当たるのは、わらべ歌「十五夜お月さま」でしょうか。
うさぎうさぎ なに見て跳ねる
十五夜お月さま 見て跳ねる
沖縄では、やはり八重山の「月ぬ美しゃ」を思い出します。
すずよさんに、「月ぬ美しゃ」を歌ってもらいました。

月ぬ美しゃや 十日三日
みやらび美しゃ 七十
(月がいちばん美しいのは、満月になる前の十三夜。女性がいちばん美しいのは…七十歳)
あれ?そうでしたっけ…?
まあ、女性は十七も七十もやっぱり美しいということで…。
私はちょっと飲んでいたので、そのあとで「とぅばらーま」もどきを少し歌いました。すみません。
歌合戦の最後に、留学生がチン・コン・ソンの歌をうたってくれました。べトナム戦争中に作られた歌ですが、「戦うのはやめて、みんなで大きな輪になろう」といった意味の歌だそうです。私もメロディーは聞いたことがあるような気がしますが、意味は知りませんでした。
そのあと、留学生のカンくんが、ベトナムの中秋節の写真を紹介してくれました。
カンくんの故郷、タイビン省のヴートゥー郡で、2~3日前に行われた中秋節のお祝いの写真です。親戚の方に、メールで送ってもらったそうです。
こんな貴重な写真がみられるとは、びっくり。
が、ちょっと長くなってきましたので、その写真を含めて数日中に続きを紹介したいと思います。
厳密に言うと、昨日は中秋節の翌日ということになりますが…。
ベトナムの中秋節は、子どもたちのためのお祭りです。
中秋節のころ、ベトナムの子どもたちはデンロンという提灯を持って歩きます。
第一部は、留学生と一緒に、デンロン作りをしました。
参加者は10名あまり。ベトナム北部で8年間仕事をされていたSさんが家族ぐるみで来て下さいました。
子どもたちはベトナム生まれで、ベトナム語もある程度わかるようです。
デンロン作りは下準備をしておいたので、1時間を見込んでいましたが、わいわい言いながら作っていると、思ったよりも時間がかかります。
骨組みを完成させたところでいったん中断して、第二部の交流会に移りました。参加者も20名ほどに増えました。
私たちは生春巻やおにぎりを用意、参加者の方がヌックマムで味をつけた鶏の唐揚げ(子どもたちに大好評)や、おはぎを持ってきて下さいました。
留学生は、4人来てくれました。
自己紹介で、それぞれの「中秋節、お月見の思い出」を簡単に話していただきました。日本(沖縄)でも、地域によっていろんなお祝いの仕方や、食べ物があったようです。
沖縄委員会代表のすずよさんは、子ども時代は宮古にいましたが、中秋の名月の夜には、ある家の屋上に
子どもたちが集まって、歌や踊りを披露して遊んだそうです。この日の夜だけは、子どもが夜更かしして遊んでも咎められなかったそうです。
次に、留学生にベトナムの歌を披露してもらいました。
中秋節は子どものお祭りなので、「Cho con(わが子へ)」という歌をうたってもらいました。幼いわが子に対する、両親の深い想いをうたった、美しい歌です。
続いて、「Ruoc den thang tam」という、楽しい中秋節の歌を紹介してもらいました。ベトナムには中秋節の歌が多くあり、「Tet trung thu(中秋節)」というタイトルのCDもいくつか出ているほどなのですが、比較的新しい歌が多いそうです。
「Ruoc den trung thu」は、こんな感じの歌詞です(ちょっと間違っているかもしれません。あくまでもこんな感じ、ということで…)。
中秋節には、デンロン行列をして遊びに行くの
わたしは行列で、あちこちに行くのよ
デンロンを手にして、心もうきうき
満月の明かりの下で、歌って踊るのよ
星のかたちのデンロン 魚のデンロン
天女さまのデンロンに 蝶々のデンロン
わたしはデンロンを持って、お月さまに行くのよ
藍色のデンロンに 紫のデンロン
青いデンロンに 白いデンロン
色とりどりの、きれいな灯りに囲まれて
はるかな空のかなたに、丸くかわいらしい姿
やさしい光が、地上に降り注いでいる
8月の満月の中に、月の天女さまの姿
わたしは、天女さまと一緒に、歌って踊るのよ
獅子舞の太鼓が ジンジン ジンジン
わたしはデンロンを持って お月さまに行くのよ
獅子舞の太鼓が ジンジン ジンジン
わたしは天女さまと一緒に お祝いするのよ
なんかうきうきする歌詞ですね。そういえば、沖縄の「豊年音頭」でも、天女が浮かれて舞い踊りますね。
ベトナムの歌のお礼に、沖縄や日本の、中秋節やお月さまに関係する歌を紹介しようということになりました。
でも、あまりたくさんは思い浮かびません。
まず思い当たるのは、わらべ歌「十五夜お月さま」でしょうか。
うさぎうさぎ なに見て跳ねる
十五夜お月さま 見て跳ねる
沖縄では、やはり八重山の「月ぬ美しゃ」を思い出します。
すずよさんに、「月ぬ美しゃ」を歌ってもらいました。
月ぬ美しゃや 十日三日
みやらび美しゃ 七十
(月がいちばん美しいのは、満月になる前の十三夜。女性がいちばん美しいのは…七十歳)
あれ?そうでしたっけ…?
まあ、女性は十七も七十もやっぱり美しいということで…。
私はちょっと飲んでいたので、そのあとで「とぅばらーま」もどきを少し歌いました。すみません。
歌合戦の最後に、留学生がチン・コン・ソンの歌をうたってくれました。べトナム戦争中に作られた歌ですが、「戦うのはやめて、みんなで大きな輪になろう」といった意味の歌だそうです。私もメロディーは聞いたことがあるような気がしますが、意味は知りませんでした。
そのあと、留学生のカンくんが、ベトナムの中秋節の写真を紹介してくれました。
カンくんの故郷、タイビン省のヴートゥー郡で、2~3日前に行われた中秋節のお祝いの写真です。親戚の方に、メールで送ってもらったそうです。
こんな貴重な写真がみられるとは、びっくり。
が、ちょっと長くなってきましたので、その写真を含めて数日中に続きを紹介したいと思います。
Posted by クアン at
22:59
│Comments(0)
2010年09月21日
嬉しい知らせ
ベトナムから、嬉しい手紙が届きました。
奨学生のティエン・チュックさんからの手紙です。
チュックさんは、ホーチミン市ビンタン区に住む女の子。10年前、小学校低学年のときから青葉奨学金を受けて勉強し、この夏に高校を卒業しました。
お父さんは彼女が3つか4つのときに電気の事故で亡くなり、技術科の先生をしているお母さんが、チュックさんと妹さんを育てているそうです。
ベトナムでは、学校の先生は尊敬はされますが、給料は決して多くありません。数学や英語の先生などは、多くの場合、有料で補習授業を行ったり家庭教師をしたりして副収入を得られるのですが、技術科などの場合は難しいかもしれません。正規の給料だけだと、とくに母子家庭では生活はかなり厳しいと思います。その中で、チュックさんは頑張って勉強を続け、青年団活動などにも参加していました。
チュックさんは毎年、ていねいな手紙を里親の方に書いてくれます。私は彼女の里親ではありませんが、翻訳担当ですので、全員の手紙を読んでいます。彼女の手紙はいつも楽しいので、印象に残っていました。
昨年だったか、彼女は「将来は医師になりたい。そのために、なんとしてもファム・ゴック・タィック医科大学に進みたい」と書いていました。
今日届いた手紙には、入試に合格して、希望の大学に進んだことが書かれていました!
私は仕組みがよくわからないのですが、合格にも2種類あって、正規の合格と、正規外の合格というのがあるそうです。この大学の場合だけなのか、他の大学にもあるのか、わかりません。
正規の合格の場合は授業料がかなり安いのですが、正規外合格では、高い授業料を払わないと入学できないのだそうです。
チュックさんの場合は、正規の合格だったそうです。ですから、家族にそれほどの負担をかけることなく勉強が続けられるということです。
これから6年間、一生懸命に勉強して、医師になるという夢を実現したいと書いていました。
10年間支援を続けた子が、このように夢に向かって進んでいる様子を知るのは、本当に嬉しいです。
高校卒業後、進学や就職などで忙しいので、手紙を書いてくれる子はそれほど多くありません。まあ仕方ないかな、と思いますが、その中で彼女はこうして手紙を書いてくれました。
「里親さん、将来、医師になった私に会いに来て下さいね。でも、里親さんが私のお客さん(患者)になることは望んでいませんよ」
チュックさんはあまり身体が強くないみたいなので、無理をし過ぎないように、でも頑張ってほしいと思います。青葉奨学金の支援は原則として高校卒業までなので、これで支援は終わりになりますが、なんとか彼女の夢を実現できるよう、祈っています。
今日は、乾杯です!(って、私はちょっと飲みすぎかも…)
奨学生のティエン・チュックさんからの手紙です。
チュックさんは、ホーチミン市ビンタン区に住む女の子。10年前、小学校低学年のときから青葉奨学金を受けて勉強し、この夏に高校を卒業しました。
お父さんは彼女が3つか4つのときに電気の事故で亡くなり、技術科の先生をしているお母さんが、チュックさんと妹さんを育てているそうです。
ベトナムでは、学校の先生は尊敬はされますが、給料は決して多くありません。数学や英語の先生などは、多くの場合、有料で補習授業を行ったり家庭教師をしたりして副収入を得られるのですが、技術科などの場合は難しいかもしれません。正規の給料だけだと、とくに母子家庭では生活はかなり厳しいと思います。その中で、チュックさんは頑張って勉強を続け、青年団活動などにも参加していました。
チュックさんは毎年、ていねいな手紙を里親の方に書いてくれます。私は彼女の里親ではありませんが、翻訳担当ですので、全員の手紙を読んでいます。彼女の手紙はいつも楽しいので、印象に残っていました。
昨年だったか、彼女は「将来は医師になりたい。そのために、なんとしてもファム・ゴック・タィック医科大学に進みたい」と書いていました。
今日届いた手紙には、入試に合格して、希望の大学に進んだことが書かれていました!
私は仕組みがよくわからないのですが、合格にも2種類あって、正規の合格と、正規外の合格というのがあるそうです。この大学の場合だけなのか、他の大学にもあるのか、わかりません。
正規の合格の場合は授業料がかなり安いのですが、正規外合格では、高い授業料を払わないと入学できないのだそうです。
チュックさんの場合は、正規の合格だったそうです。ですから、家族にそれほどの負担をかけることなく勉強が続けられるということです。
これから6年間、一生懸命に勉強して、医師になるという夢を実現したいと書いていました。
10年間支援を続けた子が、このように夢に向かって進んでいる様子を知るのは、本当に嬉しいです。
高校卒業後、進学や就職などで忙しいので、手紙を書いてくれる子はそれほど多くありません。まあ仕方ないかな、と思いますが、その中で彼女はこうして手紙を書いてくれました。
「里親さん、将来、医師になった私に会いに来て下さいね。でも、里親さんが私のお客さん(患者)になることは望んでいませんよ」
チュックさんはあまり身体が強くないみたいなので、無理をし過ぎないように、でも頑張ってほしいと思います。青葉奨学金の支援は原則として高校卒業までなので、これで支援は終わりになりますが、なんとか彼女の夢を実現できるよう、祈っています。
今日は、乾杯です!(って、私はちょっと飲みすぎかも…)
2010年09月21日
アネッタさんからの伝言
沖縄委員会代表の高里鈴代さんが、10日間ほどニューヨークとプエルトリコに行ってこられました。
ニューヨークでは、アレン・ネルソンさんのお連れ合いのアネッタさんに会って、「アレン・ネルソン奨学金」について報告して下さったそうです。
私も、奨学金支給式や生徒の1人チョンくんの家族の写真を30枚ほど用意して、アネッタさんに渡していただくようにお願いしていました。
アネッタさんは中米のトリニダード・トバゴの出身で、12歳までそこで祖母に育てられ、その後母親のいるニューヨークに移ったそうです。
チョンくんの家の写真を見て、祖母と一緒だったころの暮らしを思い出していらっしゃったとか。アネッタさんの家でも豚やニワトリを飼っていて、台所もチョンくんの家と同じような台所で、外から薪を取ってきてくべていたそうです。
2005年に、アレンさんに同行してベトナムのダナンに行ったことも話して下さったそうです。そして、「これからも様子を知らせてほしい、自分にも出来ることをしたい」ということでした。
奨学金は、来年以降も続きます。アネッタさんにも、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います。
アネッタさん、すずよさん、どうもありがとうございました。
ニューヨークでは、アレン・ネルソンさんのお連れ合いのアネッタさんに会って、「アレン・ネルソン奨学金」について報告して下さったそうです。
私も、奨学金支給式や生徒の1人チョンくんの家族の写真を30枚ほど用意して、アネッタさんに渡していただくようにお願いしていました。
アネッタさんは中米のトリニダード・トバゴの出身で、12歳までそこで祖母に育てられ、その後母親のいるニューヨークに移ったそうです。
チョンくんの家の写真を見て、祖母と一緒だったころの暮らしを思い出していらっしゃったとか。アネッタさんの家でも豚やニワトリを飼っていて、台所もチョンくんの家と同じような台所で、外から薪を取ってきてくべていたそうです。
2005年に、アレンさんに同行してベトナムのダナンに行ったことも話して下さったそうです。そして、「これからも様子を知らせてほしい、自分にも出来ることをしたい」ということでした。
奨学金は、来年以降も続きます。アネッタさんにも、できるだけ詳しくお伝えしたいと思います。
アネッタさん、すずよさん、どうもありがとうございました。
2010年09月19日
いかだに乗って学校へ

なんだか気持ちよさそうにも見える光景ですが、このように穏やかな日ばかりではないでしょう。
トゥオイチェ・オンラインに、ベトナム中北部タインホア省の山間部、ランチャイン郡の子どもたちの登校風景が紹介されていました。(みんな少数民族ターイ族の子どもたちだそうです)
以下、記事を翻訳してみました。上の写真も、その記事の中にあったものです。
(例によって、誤訳の可能性があります。原文は、http://tuoitre.vn/Giao-duc/401117/Den-truong-bang-be-luong.htmlをご覧下さい)
タインホア省の山地ランチャイン郡に住む、100名ものターイ族の生徒たちは、粗末ないかだでアム川を渡って学校に通わなければならない。
いかだ(be luong)は、この地方の人々にはmang luongとも呼ばれており、洪水の時期には命がけの危険な乗り物である。
タムヴァン中学校副校長のグエン・ヴァン・マインさんによると、「アム川の対岸に暮らす生徒たちのほとんどは、貧しい家庭の人たちが営むいかだに乗って、学校に通っている」という。
いかだの主は、お客を乗せて川を渡り、渡し賃を取ることを、村から許可されている。子どもたちが川を渡るときにも、他の乗客と同じように、一人につき2000~2500ドン(川の水の多い・少ないによって変わる)を、いかだの主に支払わなければならない。
この川は滝や渕が多いため、大雨が続くと、川は増水し激流となる。そのため、アム川の対岸の子どもたちは、長い間学校を休まなければならず、授業や学習に大きな影響を及ぼしている。
学校では、村当局に対して、生徒たちから渡し賃を取らないことをいかだの主に勧告するように、たびたび交渉している。しかし、現在までこの問題は解決していない。
もしいかだの主が生徒たちから渡し賃を取り続けた場合、子どもたちが学業途中で学校をやめてしまう恐れが高いという。
私たちとの会見のさい、タムヴァン村党委員会書記のルオン・ヴァン・クインさんは、次のように認めた。「生徒たちがアム川を渡って学校に通わなければならない状況は、とても危険です。洪水の時期には、なおさらです」
アム川の村の流域では、ほとんど毎年のように水の事故が起こっており、多くは生命に関わる事故である。
いちばん最近では、2010年8月の末に、ファー地区に住むルオン・ティ・チエンさん(38歳)が、上流からの激流に呑まれ、流されてしまった。
ハー・ドン
2010年09月17日
「ベトナムにいる私の娘たち」
沖縄テレビのアナウンサーの阿佐慶涼子さんが、今日付け(9月17日)の琉球新報「南風」欄のエッセーで、青葉奨学会のことを取り上げて下さいました。
阿佐慶さんは、1990年代後半から、沖縄委員会の会員としてベトナムの里子への奨学金支援を続けて下さっています。
以下、阿佐慶さんのエッセーを転載します。
琉球新報 2010年9月17日「南風」
「ベトナムにいる私の娘たち」
阿佐慶涼子 沖縄テレビ報道部副部長 アナウンサー
地球のどこに生まれてもすべての子どもが、安全で親の愛情を存分に受けながら健やかに学び、成長してほしいもの。しかし、実際には紛争地域で危険にさらされている子や、学校に通いたくても働かざるを得ない子どもたちが多くいます。
そんな子どもたちを助けたいと活動しているのが「ベトナム青葉奨学会」。16年前に発足した沖縄委員会では、農村や漁村に暮らし、経済的な理由で教科書や学用品を買えず、思うように勉強ができないベトナムの小中高校生に学費を支援していて、これまでに380人の子どもたちの学びを支えています。私も縁あって、12年前からこの活動に参加しています。
小中高校で違いはありますが、9000円から15000円の奨学金で、子ども1人が1年間に必要な教科書やノートなどの学用品に不自由することなく、学べるのです。私はずっと小学生の女の子の里親をしています。
そして時折、写真とともに里子から手紙が届きます! 丁寧な直筆と、日本語に訳された手紙を初めて受け取り、うれしくてたまらなかった私は、当時保育園に通っていた娘にも「ベトナムの里子ちゃんからお手紙来たよ!」と見せたことがありました。それから数日後、保育園から帰ってきた娘が「私にもお姉ちゃんいるよね」と。どうやらお友達に自慢して来たようで…。初めての里子の女の子は、農業をしている両親を手伝いながら勉強を続け、この春無事に高校を卒業したという知らせが届きました。
彼女の未来が明るいものであることを心から祈っています。
そして先日届いた2人目の里子からの手紙には「里親さんと、私の夢について話したい」と書いてありました。いつか実現できたらと思っています。
ベトナム青葉奨学会について関心のある方は、すぺーす結(☎098-864-1539)へお問い合わせ下さい。
阿佐慶さんは、1990年代後半から、沖縄委員会の会員としてベトナムの里子への奨学金支援を続けて下さっています。
以下、阿佐慶さんのエッセーを転載します。
琉球新報 2010年9月17日「南風」
「ベトナムにいる私の娘たち」
阿佐慶涼子 沖縄テレビ報道部副部長 アナウンサー
地球のどこに生まれてもすべての子どもが、安全で親の愛情を存分に受けながら健やかに学び、成長してほしいもの。しかし、実際には紛争地域で危険にさらされている子や、学校に通いたくても働かざるを得ない子どもたちが多くいます。
そんな子どもたちを助けたいと活動しているのが「ベトナム青葉奨学会」。16年前に発足した沖縄委員会では、農村や漁村に暮らし、経済的な理由で教科書や学用品を買えず、思うように勉強ができないベトナムの小中高校生に学費を支援していて、これまでに380人の子どもたちの学びを支えています。私も縁あって、12年前からこの活動に参加しています。
小中高校で違いはありますが、9000円から15000円の奨学金で、子ども1人が1年間に必要な教科書やノートなどの学用品に不自由することなく、学べるのです。私はずっと小学生の女の子の里親をしています。
そして時折、写真とともに里子から手紙が届きます! 丁寧な直筆と、日本語に訳された手紙を初めて受け取り、うれしくてたまらなかった私は、当時保育園に通っていた娘にも「ベトナムの里子ちゃんからお手紙来たよ!」と見せたことがありました。それから数日後、保育園から帰ってきた娘が「私にもお姉ちゃんいるよね」と。どうやらお友達に自慢して来たようで…。初めての里子の女の子は、農業をしている両親を手伝いながら勉強を続け、この春無事に高校を卒業したという知らせが届きました。
彼女の未来が明るいものであることを心から祈っています。
そして先日届いた2人目の里子からの手紙には「里親さんと、私の夢について話したい」と書いてありました。いつか実現できたらと思っています。
ベトナム青葉奨学会について関心のある方は、すぺーす結(☎098-864-1539)へお問い合わせ下さい。
2010年09月16日
漢字をやめた国
NHKの「みんなでニホンGO!」という番組、なかなか面白くてよく見ているのですが、今日のテーマは「日本語が漢字をやめて、ローマ字表記になったかもしれない」というものでした。
第二次大戦が終わったあと、GHQが「漢字の使用が日本の民主化の障害になっている。日本は漢字を廃止してローマ字表記に改めるべきである」と主張したそうです。
このときにGHQが主張したのと同じように、かつて漢字を廃止してローマ字表記を採用した国が、実際にアジアにあるのです。それはどこでしょうか?
な~んて、これは「ベトナム青葉奨学会沖縄委員会」事務局のブログですので、当然、答えは「ベトナム」ってことになるわけですが…。
かつて、ベトナムは漢字を使っていました。そして、日本人が漢字を簡略化してひらがなやカタカナを作り出したように、ベトナム人は漢字をもとにして「チューノム」という民族文字を作り出しました。
漢字やチューノムを使った文学もかなり発達したのですが、20世紀に入るとローマ字表記が主流となり、漢字やチューノムは廃れていきました。
いま、ベトナム人のほとんどは、漢字もチューノムも読むことができません。
漢字やチューノムをやめて、ローマ字表記を広めようとしたのは、まずベトナムを支配していたフランス人たちでした。彼らにとっては、自分たちが覚えやすいローマ字表記のほうが都合がよかったわけです。
でも、ローマ字表記を推進したのは、フランス人たちだけではありませんでした。
植民地支配に抵抗し、独立を求めて闘っていたベトナム人たちも、熱心にローマ字表記を広めていました。
当時の一般民衆にとっては、漢字やチューノムを覚えるのは難しすぎる、ローマ字表記なら、それよりもはるかに容易に民衆が文字を獲得できる、というわけです。
こうして、ベトナム語のローマ字表記が急速に普及し、反対に、漢字やチューノムは使われなくなっていきました。
ベトナム語の例を考えると、「漢字は民主化の障害」とかいう突飛な発想も、なるほどそれなりの根拠はあるのかな、とも思えてきます。
当時、GHQだけでなく、日本人の中でも「漢字廃止論」は一定の支持を集めていたようです。
でもまあにほんごのばあいはかんじをやめたりろーまじひょうきにあらためたりするととんでもなくよみにくいものになってしまうので、あのときかんじをはいししなくてほんとうによかったなとおもうのですが…。
ベトナム語の場合、ローマ字表記にしても特別な不便は生じなかったようです。が、日本語はベトナム語と比べると発音がはるかに単純(貧弱といえるかも…)なので、漢字の助けを借りないと、もはや言語として成り立たないように思います。
たとえば、「こうえん」とか「ko-en」と書いても、それが「公園」なのか「公演」なのか「講演」なのか「後援」なのか、判断できません。実際の文章では文脈で区別できるでしょうが、かなりややこしくなるのは間違いありません。
ベトナムではローマ字表記がすっかり定着し、識字率も比較的高いわけですが、かつてベトナム人が築いてきた文化と切り離されてしまった、という問題が生じました。
たとえば、ベトナムのお寺や古い建物には、よく漢字が書かれています。外国人である私たちは、それをある程度読める(だいたいの意味は推測できる)のですが、地元に住んでいるベトナム人にはちんぷんかんぷんという、考えてみると不思議なことが起こるわけです。
いま、ベトナムの教育界では、「高校で漢字やチューノムを教えてはどうか」という議論があるそうです。
しかし、全国の高校で漢字を教えるためには、漢字を教えることに出来る人が、相当に多くいなければなりません。いまはそれだけの人がいないので、高校のカリキュラムに漢字を導入するのは当面は無理だろう、ということになっているようです。
近い将来、ベトナムでも、漢字やチューノムがもっと見直されるのでは、と私は思っていますが…。
日本語とベトナム語を比較して考えてみると、興味深い問題が次々に出てきます。いずれまた、書いてみたいと思います。
第二次大戦が終わったあと、GHQが「漢字の使用が日本の民主化の障害になっている。日本は漢字を廃止してローマ字表記に改めるべきである」と主張したそうです。
このときにGHQが主張したのと同じように、かつて漢字を廃止してローマ字表記を採用した国が、実際にアジアにあるのです。それはどこでしょうか?
な~んて、これは「ベトナム青葉奨学会沖縄委員会」事務局のブログですので、当然、答えは「ベトナム」ってことになるわけですが…。
かつて、ベトナムは漢字を使っていました。そして、日本人が漢字を簡略化してひらがなやカタカナを作り出したように、ベトナム人は漢字をもとにして「チューノム」という民族文字を作り出しました。
漢字やチューノムを使った文学もかなり発達したのですが、20世紀に入るとローマ字表記が主流となり、漢字やチューノムは廃れていきました。
いま、ベトナム人のほとんどは、漢字もチューノムも読むことができません。
漢字やチューノムをやめて、ローマ字表記を広めようとしたのは、まずベトナムを支配していたフランス人たちでした。彼らにとっては、自分たちが覚えやすいローマ字表記のほうが都合がよかったわけです。
でも、ローマ字表記を推進したのは、フランス人たちだけではありませんでした。
植民地支配に抵抗し、独立を求めて闘っていたベトナム人たちも、熱心にローマ字表記を広めていました。
当時の一般民衆にとっては、漢字やチューノムを覚えるのは難しすぎる、ローマ字表記なら、それよりもはるかに容易に民衆が文字を獲得できる、というわけです。
こうして、ベトナム語のローマ字表記が急速に普及し、反対に、漢字やチューノムは使われなくなっていきました。
ベトナム語の例を考えると、「漢字は民主化の障害」とかいう突飛な発想も、なるほどそれなりの根拠はあるのかな、とも思えてきます。
当時、GHQだけでなく、日本人の中でも「漢字廃止論」は一定の支持を集めていたようです。
でもまあにほんごのばあいはかんじをやめたりろーまじひょうきにあらためたりするととんでもなくよみにくいものになってしまうので、あのときかんじをはいししなくてほんとうによかったなとおもうのですが…。
ベトナム語の場合、ローマ字表記にしても特別な不便は生じなかったようです。が、日本語はベトナム語と比べると発音がはるかに単純(貧弱といえるかも…)なので、漢字の助けを借りないと、もはや言語として成り立たないように思います。
たとえば、「こうえん」とか「ko-en」と書いても、それが「公園」なのか「公演」なのか「講演」なのか「後援」なのか、判断できません。実際の文章では文脈で区別できるでしょうが、かなりややこしくなるのは間違いありません。
ベトナムではローマ字表記がすっかり定着し、識字率も比較的高いわけですが、かつてベトナム人が築いてきた文化と切り離されてしまった、という問題が生じました。
たとえば、ベトナムのお寺や古い建物には、よく漢字が書かれています。外国人である私たちは、それをある程度読める(だいたいの意味は推測できる)のですが、地元に住んでいるベトナム人にはちんぷんかんぷんという、考えてみると不思議なことが起こるわけです。
いま、ベトナムの教育界では、「高校で漢字やチューノムを教えてはどうか」という議論があるそうです。
しかし、全国の高校で漢字を教えるためには、漢字を教えることに出来る人が、相当に多くいなければなりません。いまはそれだけの人がいないので、高校のカリキュラムに漢字を導入するのは当面は無理だろう、ということになっているようです。
近い将来、ベトナムでも、漢字やチューノムがもっと見直されるのでは、と私は思っていますが…。
日本語とベトナム語を比較して考えてみると、興味深い問題が次々に出てきます。いずれまた、書いてみたいと思います。
2010年09月15日
会員の方々から
昨日、今日と、何名かの会員の方から連絡をいただきました。
発足当初から会員を続けてくださっているSさんからは、会社の事情で年金が一部カットされることになり、大変申し訳ないのだが継続するのが難しくなった、と電話をいただきました。
私たちの会は、あくまでもそれぞれが可能な範囲で支援を続けるという趣旨でやっているので、何らかの事情で継続が難しい場合は、一言ご連絡をいただければいつでも退会できます(当たり前のことですけど…)。
沖縄の経済事情も、決してよくありません。いろいろな事情で会を辞められる方も、毎年いらっしゃいます。これまで続けて下さったことに、本当に感謝の気持ちです。
先日統一地方選挙が行われましたが、宜野湾市議選に挑戦されていたTさんから、当選したとのメールをいただきました。
Tさんは、長い間女性や子どもの人権に取り組んでこられた方で、4年ほど前から青葉奨学会の会員にもなっていただいています。
何年か前、ある集まりで同席したTさんから、「青葉奨学会沖縄委員会って、まじめな団体なんですか?」と唐突に聞かれて、「いちおう、まじめにやっているつもりですよ」と答えたのを思い出します。
その後、会に加わっていただきました。お忙しい中、定例会への出席や会報への寄稿など、会の活動を手伝って下さっています。
これからの議員としての活躍にも、期待しています。まずは少しだけ身体を休めて下さいね。
琉球新報のエッセイを担当されているAさんからは、青葉奨学会の活動について次回のエッセイで紹介したい、と電話をいただきました。Aさんは沖縄テレビでアナウンサーをされている方ですが、10年ちょっと前から会員になって下さっています。
私からは、会が発足した年や現在の会員数など、簡単な情報をお伝えしました。
エッセイは、17日(今度の金曜日)に掲載予定とのことです。楽しみにしています。
発足当初から会員を続けてくださっているSさんからは、会社の事情で年金が一部カットされることになり、大変申し訳ないのだが継続するのが難しくなった、と電話をいただきました。
私たちの会は、あくまでもそれぞれが可能な範囲で支援を続けるという趣旨でやっているので、何らかの事情で継続が難しい場合は、一言ご連絡をいただければいつでも退会できます(当たり前のことですけど…)。
沖縄の経済事情も、決してよくありません。いろいろな事情で会を辞められる方も、毎年いらっしゃいます。これまで続けて下さったことに、本当に感謝の気持ちです。
先日統一地方選挙が行われましたが、宜野湾市議選に挑戦されていたTさんから、当選したとのメールをいただきました。
Tさんは、長い間女性や子どもの人権に取り組んでこられた方で、4年ほど前から青葉奨学会の会員にもなっていただいています。
何年か前、ある集まりで同席したTさんから、「青葉奨学会沖縄委員会って、まじめな団体なんですか?」と唐突に聞かれて、「いちおう、まじめにやっているつもりですよ」と答えたのを思い出します。
その後、会に加わっていただきました。お忙しい中、定例会への出席や会報への寄稿など、会の活動を手伝って下さっています。
これからの議員としての活躍にも、期待しています。まずは少しだけ身体を休めて下さいね。
琉球新報のエッセイを担当されているAさんからは、青葉奨学会の活動について次回のエッセイで紹介したい、と電話をいただきました。Aさんは沖縄テレビでアナウンサーをされている方ですが、10年ちょっと前から会員になって下さっています。
私からは、会が発足した年や現在の会員数など、簡単な情報をお伝えしました。
エッセイは、17日(今度の金曜日)に掲載予定とのことです。楽しみにしています。
2010年09月12日
こども絵画展「戦争と平和・世界のともだち」
23日の夜に予定している「中秋節のつどい」については、このブログでも何度か紹介しました。
この企画と並行して、沖縄NGOセンター事務所で、ミニ絵画展を行います(といっても原画ではなくコピーしたものですが…)。
絵画展のテーマは、「戦争と平和・世界のともだち」。ホーチミン市戦争証跡博物館の企画で、8歳から15歳ぐらいまでのベトナムの子どもたちが描いたものです。
今から10年前の2000年、友人の那須トゥエンさんたちが戦争証跡博物館を訪ねたさい、当時のトゥエット・ヴァン館長とゴック・ヴァン副館長から、「戦争と平和・世界のともだち」をテーマにしたベトナムの子どもたちの絵画展を沖縄で開催してもらえないか、との依頼を受けました。
私たちは実行委員会を作って準備を進め、2001年の1月から2月にかけて、佐喜眞美術館・くすぬち平和文化館・那覇市役所ロビー・名護市中央図書館の4ヶ所で絵画展を開催しました。あのときに見に来て下さった方もいるかもしれません。
期間中、ゴック・ヴァン副館長と石川文洋さんを招いて、講演会やワークショップを行ったり、「あなたと沖縄とベトナム戦争と」というテーマで、さまざまな立場の方に聞き取りを行ったりもしました。
私たちはお金がなかったので(いまもありませんが…)、印象的な絵を選んで絵はがきを作り、その売り上げを絵画展開催のための経費に充てました。
絵画展が終わって、絵はすべて送り返したのですが、とても個性的でアピール力のある絵が多かったので、その後も「うないフェスティバル」や「国際協力・交流フェスティバル」などに参加するさいに、絵のコピーを展示して紹介させてもらいました。
今回は、ONC事務所で展示させてもらうことになりました。9月14日から10月2日まで展示する予定です。
このブログでも、この機会にいくつかの絵を紹介したいと思います。(作者の子どもの年齢は絵を描いた当時のものなので、現在は大人になっている人もいます)
ベトナムこども絵画展【戦争と平和・世界のともだち】
歴史教科書の沖縄戦記述をめぐって、沖縄では検定意見の撤回を求める大きなうねりが巻き起こりました。沖縄戦体験者が少なくなっていく中、戦争体験の継承が大きな課題になっています。
ベトナムでも、1975年以降に生まれ、ベトナム戦争を知らない世代が人口の6割以上を占めるようになりました。こどもたちに戦争の体験を語り継ぎ、平和の尊さを伝えるためのひとつの試みとして、ホーチミン市戦争証跡博物館では「戦争と平和」をテーマにした絵画コンクールを毎年行っています。
2001年初め、私たちベトナム青葉奨学会沖縄委員会の有志は、戦争証跡博物館の依頼を受けて「ベトナムこども絵画展~戦争と平和・世界のともだち」を佐喜眞美術館など県内4ヶ所で開催しました。
2007年7月、1960年代のはじめに北部訓練場などで米軍が枯葉剤を散布していた、との衝撃的なニュースが流れました。沖縄がベトナム戦争と深く関わっていたことを、40年の時を経て改めて痛感させられる出来事でした。今回、2001年の絵画展のさいに展示した絵を中心に、戦争証跡博物館に所蔵されている新しい絵も加えて15枚の絵をご紹介します(原画ではありませんが…)。
米軍普天間基地の移設・撤去が大きな焦点となっているいま、ベトナムの人々の平和への深い想いに触れて、沖縄の現状を見つめ直すひとつのきっかけとなれば幸いです。

枯葉剤を浴びたともだち チャン・タイン・ヴィン 15歳

母の苦しみ オウ・フオン・リン 13歳

赤い髪留めをした獄中の女性 グエン・ホアン・アン 12歳

戦場で泣いている女性 チュオン・アイン・トゥエット 12歳

枯葉剤の恐怖 ブイ・ティ・オアイン 14歳

「やめて!」 レ・グエン・ゴック・トゥー 15歳

こどもには楽しく遊ぶ権利がある カオ・ホアン・ティ 8歳

故郷に春が来た レ・フオン・タオ 14歳

故郷に春が来た グエン・クイン・カイン・アン 12歳

故郷に戻ってきた平和な春 ダン・ホアン・ズイ 11歳

わたしの故郷 ファム・フオック・ゴック 12歳

世界の友人たちと一緒に ダウ・ホアン・ズオン 12歳
この企画と並行して、沖縄NGOセンター事務所で、ミニ絵画展を行います(といっても原画ではなくコピーしたものですが…)。
絵画展のテーマは、「戦争と平和・世界のともだち」。ホーチミン市戦争証跡博物館の企画で、8歳から15歳ぐらいまでのベトナムの子どもたちが描いたものです。
今から10年前の2000年、友人の那須トゥエンさんたちが戦争証跡博物館を訪ねたさい、当時のトゥエット・ヴァン館長とゴック・ヴァン副館長から、「戦争と平和・世界のともだち」をテーマにしたベトナムの子どもたちの絵画展を沖縄で開催してもらえないか、との依頼を受けました。
私たちは実行委員会を作って準備を進め、2001年の1月から2月にかけて、佐喜眞美術館・くすぬち平和文化館・那覇市役所ロビー・名護市中央図書館の4ヶ所で絵画展を開催しました。あのときに見に来て下さった方もいるかもしれません。
期間中、ゴック・ヴァン副館長と石川文洋さんを招いて、講演会やワークショップを行ったり、「あなたと沖縄とベトナム戦争と」というテーマで、さまざまな立場の方に聞き取りを行ったりもしました。
私たちはお金がなかったので(いまもありませんが…)、印象的な絵を選んで絵はがきを作り、その売り上げを絵画展開催のための経費に充てました。
絵画展が終わって、絵はすべて送り返したのですが、とても個性的でアピール力のある絵が多かったので、その後も「うないフェスティバル」や「国際協力・交流フェスティバル」などに参加するさいに、絵のコピーを展示して紹介させてもらいました。
今回は、ONC事務所で展示させてもらうことになりました。9月14日から10月2日まで展示する予定です。
このブログでも、この機会にいくつかの絵を紹介したいと思います。(作者の子どもの年齢は絵を描いた当時のものなので、現在は大人になっている人もいます)
ベトナムこども絵画展【戦争と平和・世界のともだち】
歴史教科書の沖縄戦記述をめぐって、沖縄では検定意見の撤回を求める大きなうねりが巻き起こりました。沖縄戦体験者が少なくなっていく中、戦争体験の継承が大きな課題になっています。
ベトナムでも、1975年以降に生まれ、ベトナム戦争を知らない世代が人口の6割以上を占めるようになりました。こどもたちに戦争の体験を語り継ぎ、平和の尊さを伝えるためのひとつの試みとして、ホーチミン市戦争証跡博物館では「戦争と平和」をテーマにした絵画コンクールを毎年行っています。
2001年初め、私たちベトナム青葉奨学会沖縄委員会の有志は、戦争証跡博物館の依頼を受けて「ベトナムこども絵画展~戦争と平和・世界のともだち」を佐喜眞美術館など県内4ヶ所で開催しました。
2007年7月、1960年代のはじめに北部訓練場などで米軍が枯葉剤を散布していた、との衝撃的なニュースが流れました。沖縄がベトナム戦争と深く関わっていたことを、40年の時を経て改めて痛感させられる出来事でした。今回、2001年の絵画展のさいに展示した絵を中心に、戦争証跡博物館に所蔵されている新しい絵も加えて15枚の絵をご紹介します(原画ではありませんが…)。
米軍普天間基地の移設・撤去が大きな焦点となっているいま、ベトナムの人々の平和への深い想いに触れて、沖縄の現状を見つめ直すひとつのきっかけとなれば幸いです。
枯葉剤を浴びたともだち チャン・タイン・ヴィン 15歳
母の苦しみ オウ・フオン・リン 13歳
赤い髪留めをした獄中の女性 グエン・ホアン・アン 12歳
戦場で泣いている女性 チュオン・アイン・トゥエット 12歳
枯葉剤の恐怖 ブイ・ティ・オアイン 14歳
「やめて!」 レ・グエン・ゴック・トゥー 15歳
こどもには楽しく遊ぶ権利がある カオ・ホアン・ティ 8歳
故郷に春が来た レ・フオン・タオ 14歳
故郷に春が来た グエン・クイン・カイン・アン 12歳
故郷に戻ってきた平和な春 ダン・ホアン・ズイ 11歳
わたしの故郷 ファム・フオック・ゴック 12歳

世界の友人たちと一緒に ダウ・ホアン・ズオン 12歳
Posted by クアン at
10:05
│Comments(0)
2010年09月12日
デンロン作り
「デンロンを作ってみましょうか」
9月23日に予定している「中秋節のつどい」。どんな内容にしようか、ベトナムの留学生と相談していたとき、カンくんからそんな提案がありました。
「あんまり時間もないけど、作れるの?」
「大丈夫ですよ。ぼくの子どものころには、みんな自分で作っていましたから」
デンロンとは、星や魚などをかたどった提灯のようなもので、中秋節の頃の夜、ベトナムの子どもたちはこれを持って歩きます。
23日のつどいでは、参加者の皆さんとデンロンを一緒に作りながら、留学生たちに中秋節の話をしてもらおうと考えています。
とはいっても、私はデンロンを作ったことがありません。
当日いきなりでは、うまくいくかどうか、心もとない。一度試しにデンロン作りをしてみよう、ということで、昨夜ONCに集まりました。
デンロンにもいろいろな形がありますが、まずはいちばん作りやすい星型のデンロン(デン・オンサオ)を作ろうということになりました。
カンくんやルオンくんに要領を教えてもらいながら、竹ひごを組み合わせていきます。

2つの星をあわせて、立体的にしていきます。慣れない作業なので、なかなかうまくいきませんが、みんなでわいわい言いながら作っていくのは楽しいものです。
ONCインターンのM子さんは、「めっちゃものづくりだよね!」
するとある人が、「それって、『超ものづくり』ってこと?」
「はあ?」 若い人の言葉は、おじさんにはよくわかりません…。

星の形になりました。

竹ひごの骨組みに、色セロハンを貼り付けていきます。

なかなかきれいなデンロンができました。中にろうそくや電球を入れるともっときれいになるそうですが、私たちの作品では、ろうそくはちょっと危ないかも…。
まあとりあえず大体の要領はわかりました。23日も、なんとかなりそうです。
いまではベトナムの子どもたちも、デンロンは自分で作るよりも店で買ってもらうことが多いようですが、手作りの素朴なデンロンもいいものですね。23日、楽しく作りましょう。
いい天気になりますように。
9月23日に予定している「中秋節のつどい」。どんな内容にしようか、ベトナムの留学生と相談していたとき、カンくんからそんな提案がありました。
「あんまり時間もないけど、作れるの?」
「大丈夫ですよ。ぼくの子どものころには、みんな自分で作っていましたから」
デンロンとは、星や魚などをかたどった提灯のようなもので、中秋節の頃の夜、ベトナムの子どもたちはこれを持って歩きます。
23日のつどいでは、参加者の皆さんとデンロンを一緒に作りながら、留学生たちに中秋節の話をしてもらおうと考えています。
とはいっても、私はデンロンを作ったことがありません。
当日いきなりでは、うまくいくかどうか、心もとない。一度試しにデンロン作りをしてみよう、ということで、昨夜ONCに集まりました。
デンロンにもいろいろな形がありますが、まずはいちばん作りやすい星型のデンロン(デン・オンサオ)を作ろうということになりました。
カンくんやルオンくんに要領を教えてもらいながら、竹ひごを組み合わせていきます。
2つの星をあわせて、立体的にしていきます。慣れない作業なので、なかなかうまくいきませんが、みんなでわいわい言いながら作っていくのは楽しいものです。
ONCインターンのM子さんは、「めっちゃものづくりだよね!」
するとある人が、「それって、『超ものづくり』ってこと?」
「はあ?」 若い人の言葉は、おじさんにはよくわかりません…。
星の形になりました。
竹ひごの骨組みに、色セロハンを貼り付けていきます。
なかなかきれいなデンロンができました。中にろうそくや電球を入れるともっときれいになるそうですが、私たちの作品では、ろうそくはちょっと危ないかも…。
まあとりあえず大体の要領はわかりました。23日も、なんとかなりそうです。
いまではベトナムの子どもたちも、デンロンは自分で作るよりも店で買ってもらうことが多いようですが、手作りの素朴なデンロンもいいものですね。23日、楽しく作りましょう。
いい天気になりますように。
2010年09月09日
映画で見る戦争(ベトナム)の真実
ベトナム戦争のすぐれたドキュメンタリー映画2本が、11日から桜坂劇場で公開されます。
「ハーツ・アンド・マインズ~ベトナム戦争の真実~」
「ウィンター・ソルジャー~ベトナム帰還兵の告白~」
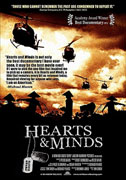
どちらも1970年代前半にアメリカで作られたドキュメンタリーで、アカデミー賞を受賞するなど高く評価されたのですが、いろいろないきさつがあって当時日本では公開されなかったそうです。
今年6月に東京で公開されて話題になり、NHKのニュースでもかなり詳しく紹介されました。
「私が映画を作ろうとカメラを手にしたのは、今も全く色あせることなく、意義ある作品であり続けるこの映画を見たからだ」
マイケル・ムーアは、この2本の映画について、こうコメントしているそうです。
上映日程などは、こちらをご覧下さい。
http://www.sakura-zaka.com/movie/1009/100911_hartsminds.html
http://www.sakura-zaka.com/movie/1009/100911_winteersol.html
ベトナム映画「Dung dot(邦題・きのう、平和の夢を見た)」も桜坂劇場にリクエストしてみたのですが、こちらの上映はちょっと難しいかな…?
「ハーツ・アンド・マインズ~ベトナム戦争の真実~」
「ウィンター・ソルジャー~ベトナム帰還兵の告白~」
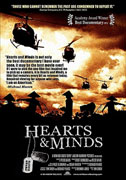
どちらも1970年代前半にアメリカで作られたドキュメンタリーで、アカデミー賞を受賞するなど高く評価されたのですが、いろいろないきさつがあって当時日本では公開されなかったそうです。
今年6月に東京で公開されて話題になり、NHKのニュースでもかなり詳しく紹介されました。
「私が映画を作ろうとカメラを手にしたのは、今も全く色あせることなく、意義ある作品であり続けるこの映画を見たからだ」
マイケル・ムーアは、この2本の映画について、こうコメントしているそうです。
上映日程などは、こちらをご覧下さい。
http://www.sakura-zaka.com/movie/1009/100911_hartsminds.html
http://www.sakura-zaka.com/movie/1009/100911_winteersol.html
ベトナム映画「Dung dot(邦題・きのう、平和の夢を見た)」も桜坂劇場にリクエストしてみたのですが、こちらの上映はちょっと難しいかな…?
Posted by クアン at
23:59
│Comments(0)
2010年09月09日
手紙の翻訳が終わりました
先月、奨学生たちの手紙が60通ほどまとめて届きました。
平日の夜や週末に少しずつ日本語訳をして、先週末までになんとか終わりました。
わからない部分は、留学生に教えてもらいました。翻訳は大変な仕事ですが、いい勉強になります。
生徒たちにとっては、(ほとんどの場合)会ったこともない外国の大人に向けて手紙を書くわけで、「何を書いたらいいのか、わからない」というのが正直なところだと思います。
ですから、多くの手紙は「わたしは奨学金を受け取りました。本当にありがとうございます。このご支援を無駄にしないように、いっしょうけんめいに勉強することをお約束します」という、お決まりの内容です。
私としては残念ですが、まあ仕方ないのかなあ、とも思います。
しかし、お決まりの内容だけではなく、自分の気持ちを切々と綴ってくれる子もいます。
奨学生の中には、お父さん、お母さんのどちらか、または両方がいない子も少なくありません。
幼いころに(または最近)別れてしまったお母さんやお父さんへの思いが綴られた手紙は、訳していても辛い気持ちになります。
でも、こうして文章にすることで、少しでも明るい気持ちになれるきっかけになったら嬉しいのですが…。
「里子」からの手紙を受け取って、返事を書いて下さる会員の方もいます。
Hさんの手紙を受け取った高校生のソンくんは、「ぼくはもう、子どものように泣く年齢ではありません。でも、お手紙をいただいて、ぼくは泣いてしまいました。それは、過ちを後悔する涙ではなく、ましてや叩かれた痛みの涙でもない。遠くにいる親しい方に見守られていることを知った、喜びの涙です」と書いてくれました。
彼の場合、家庭の事情で小さな頃から養父母に育てられていて、揺れる思いを抱えながら勉強にがんばっています。Hさんが手紙を書いて下さったことは、とても大きな励ましになったと思います。
とてもささやかなつながりではありますが、このような結びつきの橋渡しになれるのは、事務局をやっていて何よりも嬉しいことです。
平日の夜や週末に少しずつ日本語訳をして、先週末までになんとか終わりました。
わからない部分は、留学生に教えてもらいました。翻訳は大変な仕事ですが、いい勉強になります。
生徒たちにとっては、(ほとんどの場合)会ったこともない外国の大人に向けて手紙を書くわけで、「何を書いたらいいのか、わからない」というのが正直なところだと思います。
ですから、多くの手紙は「わたしは奨学金を受け取りました。本当にありがとうございます。このご支援を無駄にしないように、いっしょうけんめいに勉強することをお約束します」という、お決まりの内容です。
私としては残念ですが、まあ仕方ないのかなあ、とも思います。
しかし、お決まりの内容だけではなく、自分の気持ちを切々と綴ってくれる子もいます。
奨学生の中には、お父さん、お母さんのどちらか、または両方がいない子も少なくありません。
幼いころに(または最近)別れてしまったお母さんやお父さんへの思いが綴られた手紙は、訳していても辛い気持ちになります。
でも、こうして文章にすることで、少しでも明るい気持ちになれるきっかけになったら嬉しいのですが…。
「里子」からの手紙を受け取って、返事を書いて下さる会員の方もいます。
Hさんの手紙を受け取った高校生のソンくんは、「ぼくはもう、子どものように泣く年齢ではありません。でも、お手紙をいただいて、ぼくは泣いてしまいました。それは、過ちを後悔する涙ではなく、ましてや叩かれた痛みの涙でもない。遠くにいる親しい方に見守られていることを知った、喜びの涙です」と書いてくれました。
彼の場合、家庭の事情で小さな頃から養父母に育てられていて、揺れる思いを抱えながら勉強にがんばっています。Hさんが手紙を書いて下さったことは、とても大きな励ましになったと思います。
とてもささやかなつながりではありますが、このような結びつきの橋渡しになれるのは、事務局をやっていて何よりも嬉しいことです。
2010年08月26日
中秋節のつどい
待ちかにてぃ居たる 七月もけなてぃ
いちが八月ぬ 十五夜なゆが
お盆が終わったばかりで、ちょっと気が早いのですが、1ヵ月後の満月の夜、「中秋節」の企画のご紹介です。
沖縄NGOセンターと青葉奨学会沖縄委員会のコラボ企画ということで、9月23日の秋分の日に「中秋節のつどい」を行います。
ベトナムの中秋節(旧暦8月15日)は、子どもたちのためのお祭りです。
中秋節の夜、子どもたちは、星や魚などをかたどった「デンロン」と呼ばれる提灯を持って歩くそうです。
獅子舞なども出て、賑やかな夜になります。

今回、沖縄で勉強しているベトナム人留学生たちと一緒に、「デンロン」を作ってみようと思います。
留学生のカンくんに聞いたところ、子どものころ、毎年中秋節になるとデンロンを手作りしていたそうです。
デンロンを一緒に作りながら、中秋節のことや、子どもたちが好きな遊びや歌、食べ物のことなど、いろいろなお話しを聞いてみたいと思います。
生春巻など、ベトナムやアジアの料理も用意します。食べ物や飲み物の持ち込みも、もちろん歓迎です。
興味のある方、気軽に参加してみて下さい。親子での参加も大歓迎です。
「中秋節のつどい」
9月23日(秋分の日)
第一部「デンロン作り」午後5時~6時
第二部「交流会」午後6時~8時
場所 沖縄NGOセンター(宜野湾市宜野湾3-23-52・沖縄国際大学近く)
参加費 第一部と第二部に参加の方 1000円
第二部のみ参加の方 500円
参加申し込み・お問い合わせは、沖縄NGOセンターにお願いします。
電話 098-892-4758 FAX 098-892-9908 Eメール onc☆oki-ngo.or.tv(☆を@に変えて下さい)
参加ご希望の方は、お名前、連絡先、参加人数、デンロン作り参加を希望されるかどうかを明記して、電話・FAX、メールでお申し込み下さい。
準備の都合上、遅くとも3日前までにお願いします。申し込みが多い場合には、それ以前に締め切る場合もありますので、ご了承下さい。
いちが八月ぬ 十五夜なゆが
お盆が終わったばかりで、ちょっと気が早いのですが、1ヵ月後の満月の夜、「中秋節」の企画のご紹介です。
沖縄NGOセンターと青葉奨学会沖縄委員会のコラボ企画ということで、9月23日の秋分の日に「中秋節のつどい」を行います。
ベトナムの中秋節(旧暦8月15日)は、子どもたちのためのお祭りです。
中秋節の夜、子どもたちは、星や魚などをかたどった「デンロン」と呼ばれる提灯を持って歩くそうです。
獅子舞なども出て、賑やかな夜になります。
今回、沖縄で勉強しているベトナム人留学生たちと一緒に、「デンロン」を作ってみようと思います。
留学生のカンくんに聞いたところ、子どものころ、毎年中秋節になるとデンロンを手作りしていたそうです。
デンロンを一緒に作りながら、中秋節のことや、子どもたちが好きな遊びや歌、食べ物のことなど、いろいろなお話しを聞いてみたいと思います。
生春巻など、ベトナムやアジアの料理も用意します。食べ物や飲み物の持ち込みも、もちろん歓迎です。
興味のある方、気軽に参加してみて下さい。親子での参加も大歓迎です。
「中秋節のつどい」
9月23日(秋分の日)
第一部「デンロン作り」午後5時~6時
第二部「交流会」午後6時~8時
場所 沖縄NGOセンター(宜野湾市宜野湾3-23-52・沖縄国際大学近く)
参加費 第一部と第二部に参加の方 1000円
第二部のみ参加の方 500円
参加申し込み・お問い合わせは、沖縄NGOセンターにお願いします。
電話 098-892-4758 FAX 098-892-9908 Eメール onc☆oki-ngo.or.tv(☆を@に変えて下さい)
参加ご希望の方は、お名前、連絡先、参加人数、デンロン作り参加を希望されるかどうかを明記して、電話・FAX、メールでお申し込み下さい。
準備の都合上、遅くとも3日前までにお願いします。申し込みが多い場合には、それ以前に締め切る場合もありますので、ご了承下さい。
Posted by クアン at
21:50
│Comments(0)
2010年08月25日
手紙が届きました
先週と今週、奨学生たちからの手紙が、まとめて届きました。
今回の手紙は、カンザー郡タンアン村の生徒たちと、ロンホア村ホアヒエップの生徒たちからのものです。
生徒たちの思いのこもった手紙を読むのは、とても嬉しいことです。

いま私の手元には、50通ほどの手紙があります。
今月中に翻訳して、手紙と会報を会員の皆さんにお送りするつもりでしたが、もう少し時間がかかりそうです。
9月はじめにはなんとかしますので、もう少しお待ち下さい。
このブログでも、生徒たちの手紙のうちの何通かを、近いうちに紹介したいと思います。
今回の手紙は、カンザー郡タンアン村の生徒たちと、ロンホア村ホアヒエップの生徒たちからのものです。
生徒たちの思いのこもった手紙を読むのは、とても嬉しいことです。

いま私の手元には、50通ほどの手紙があります。
今月中に翻訳して、手紙と会報を会員の皆さんにお送りするつもりでしたが、もう少し時間がかかりそうです。
9月はじめにはなんとかしますので、もう少しお待ち下さい。
このブログでも、生徒たちの手紙のうちの何通かを、近いうちに紹介したいと思います。
2010年08月23日
B52が向かった先は…
先日、コザの戦後歴史資料館「ヒストリート」で、ベトナムに向けて嘉手納基地を飛び立つB52の写真を見ました。
50歳以上の方ですと、1960年代後半、実際にB52の出撃をやりきれない思いで目にした方も多いと思います。
私も写真では何度も見ている光景ですが、ベトナムを何度か訪ねて地理が多少わかるようになると、嘉手納を飛び立っていったB52は、ベトナムのどの場所を爆撃したのか、だんだん気になるようになりました。
ベトナム戦争時のB52というと、なんとなく「北爆」というイメージがあるのではないでしょうか。私も、漠然とそのように思っていました。
「沖縄の基地は、米軍の北爆の出撃拠点になった」という言い方も、よく目にします。
「北爆」といえば、当然、北ベトナム(当時の)領内への爆撃です。
ですから、嘉手納基地を飛び立ったB52も、やはりハノイなど北ベトナムの爆撃に向かったのでしょうか。
今年の4月、琉球新報文化面に「1次資料から見る日米安保改定50年」という特集の中で、新原昭治さんという方が、「嘉手納基地からのB52出撃」について、2度にわたって詳しく書いていらっしゃいました。
それによると、B52が嘉手納基地からベトナムへの系統的爆撃を始めたのは、1968年2月15日でした。ちょうどその時期は、北緯17度線のすぐ南にあるKhe Sanh(ケサン)の米軍陣地を巡って、解放勢力と米海兵隊の間で熾烈な攻防が続いていました。苦境に立たされていた海兵隊を守るために、米軍はB52を総動員して「ナイアガラ作戦」と称する猛爆撃を加えたのだそうです。
ケサンは、ベトナム中部クアンチ省の山間部にあります。私はクアンチ省の省都ドンハーには行ったことがありますが、山のほうには行ったことがありません。
ケサンはドンハーから50キロほど西。ほとんどラオスとの国境近くにあり、当時のホーチミンルートにもほど近く、戦略的にとても重要な場所だったそうです。
私は詳しくは知らないのですが、おそらくこの地域は、もともとは少数民族の人たちがつつましい暮らしを営んできた場所なのではないでしょうか。
それはともかくとして、1968年2月から3月の段階では、嘉手納を飛び立ったB52は、ケサンの爆撃に集中的に投入されていたようです。
ケサンの攻防は1968年の4月には一段落しました。新原さんの記事によると、その後も米軍は南ベトナムの解放区爆撃のためにB52を多用したということです。
これを読んで、「あれっ?」と思いました。そうすると、B52は、北爆というよりは、むしろ主に「南爆」に使われていた、ということになるわけです。ケサンも、ほぼ南北の境界線に位置しますが、南ベトナムの領内です。
1968年11月、20トンもの爆弾を積みベトナムに向けて嘉手納を飛び立とうとしたB52が、離陸後間もなく墜落、大爆発して、住民を恐怖のどん底に突き落としました。このB52も、間違いなく北爆ではなく、南ベトナムの解放区を爆撃しに行くところだったはずです。
米軍は、その直前の10月に北爆を全面停止していたからです。
嘉手納基地のB52が、住民の激しい反対運動もあってとりあえず撤去されたのは、1970年9月でした。
1968年2月から70年9月まで、2年半あまりにわたってB52は嘉手納に常駐し、爆弾を積んでベトナムに向かったわけです(1967年以前にも、常駐ではありませんが、「台風避難」などの名目で飛来したB52が、嘉手納から何度もベトナム爆撃に向かっています)。
嘉手納から撤去されたB52は、タイのウタバオ基地に移駐したそうです。
1968年10月から北爆を停止していた米軍は、1972年に北爆を再開、ハノイやハイフォンをはじめ北ベトナム各地に猛烈な爆撃を行います。この時期の北爆は、おもにタイから出撃していたのでしょうか。
北爆であれ「南爆」であれ、同じベトナム人を標的にして爆撃が行われたのですから、あまり違いはないと思います。
ただ、「沖縄は米軍のベトナムへの発進基地だった」と言う場合、具体的にベトナムのどの地域の、どのような人たちに対して攻撃が行われたのか、どうしても気になります。
一般に考えられているように(私も漠然と想像していたように)、嘉手納を飛び立ったB52は、おそらく北ベトナムへの爆撃も行ったのだろうと思います。「北爆の出撃拠点」といった言い方も、たぶん間違いではないでしょう。
でも、それ以上に「南ベトナム」の解放区で暮らし、戦っていた人たちに対して、はるかに多くの爆撃が行われていたようなのです。
B52が嘉手納から、いつ、何機が飛び立ち、ベトナムのどこを爆撃したのか、おそらくアメリカには詳しい記録が残っているはずです。
残念ながら、私はそれを探す能力も時間もお金もありません。でも、いつかそれを知りたいと思います。
観光地にもなっているクチトンネルから、サイゴン川を数十キロさかのぼると、ゴム農園に囲まれたミンホアという静かな村があります。
そのミンホアの村外れ、ゴム農園の中の小道を深く入っていたところに、ハイくんという奨学生の家族が暮らしています。
2004年にハイくんの家を訪ねたOさんによると、ハイくんのお母さんは、かつて解放戦線のゲリラとしてジャングルで戦ったことを話してくれたそうです。
若き日のハイくんのお母さんが、具体的にどの場所で暮らし、戦っていたのかは、わかりません。解放区だったのか、政府の支配地区だったのか、それとも競合地区だったのか。政府の支配地区や競合地区であれば、B52の攻撃は受けていないかも知れません。
しかし、ハイくんのお母さんと同じように南ベトナムの地で暮らし、戦っていた数多くの人たちの頭上に、嘉手納を飛び立ったB52が爆弾を降り注がせたということは間違いないでしょう。
ひょっとすると、多くの奨学生たちの両親や、おじいさん、おばあさんたちが、かつて嘉手納から出て行ったベーナンムイハイ(B52)の爆撃にさらされたのかもしれません。
米軍とベトナム軍が共同演習を行った、というニュースが伝えられる昨今ではあります。
しかし、私たちがいま関わっているベトナムの地で、ほんの40年前にこのような出来事があった、それは今も私たちの目の前にある米軍基地から出撃していったのだ、という事実は、しっかり胸に刻んでおきたいと思います。
50歳以上の方ですと、1960年代後半、実際にB52の出撃をやりきれない思いで目にした方も多いと思います。
私も写真では何度も見ている光景ですが、ベトナムを何度か訪ねて地理が多少わかるようになると、嘉手納を飛び立っていったB52は、ベトナムのどの場所を爆撃したのか、だんだん気になるようになりました。
ベトナム戦争時のB52というと、なんとなく「北爆」というイメージがあるのではないでしょうか。私も、漠然とそのように思っていました。
「沖縄の基地は、米軍の北爆の出撃拠点になった」という言い方も、よく目にします。
「北爆」といえば、当然、北ベトナム(当時の)領内への爆撃です。
ですから、嘉手納基地を飛び立ったB52も、やはりハノイなど北ベトナムの爆撃に向かったのでしょうか。
今年の4月、琉球新報文化面に「1次資料から見る日米安保改定50年」という特集の中で、新原昭治さんという方が、「嘉手納基地からのB52出撃」について、2度にわたって詳しく書いていらっしゃいました。
それによると、B52が嘉手納基地からベトナムへの系統的爆撃を始めたのは、1968年2月15日でした。ちょうどその時期は、北緯17度線のすぐ南にあるKhe Sanh(ケサン)の米軍陣地を巡って、解放勢力と米海兵隊の間で熾烈な攻防が続いていました。苦境に立たされていた海兵隊を守るために、米軍はB52を総動員して「ナイアガラ作戦」と称する猛爆撃を加えたのだそうです。
ケサンは、ベトナム中部クアンチ省の山間部にあります。私はクアンチ省の省都ドンハーには行ったことがありますが、山のほうには行ったことがありません。
ケサンはドンハーから50キロほど西。ほとんどラオスとの国境近くにあり、当時のホーチミンルートにもほど近く、戦略的にとても重要な場所だったそうです。
私は詳しくは知らないのですが、おそらくこの地域は、もともとは少数民族の人たちがつつましい暮らしを営んできた場所なのではないでしょうか。
それはともかくとして、1968年2月から3月の段階では、嘉手納を飛び立ったB52は、ケサンの爆撃に集中的に投入されていたようです。
ケサンの攻防は1968年の4月には一段落しました。新原さんの記事によると、その後も米軍は南ベトナムの解放区爆撃のためにB52を多用したということです。
これを読んで、「あれっ?」と思いました。そうすると、B52は、北爆というよりは、むしろ主に「南爆」に使われていた、ということになるわけです。ケサンも、ほぼ南北の境界線に位置しますが、南ベトナムの領内です。
1968年11月、20トンもの爆弾を積みベトナムに向けて嘉手納を飛び立とうとしたB52が、離陸後間もなく墜落、大爆発して、住民を恐怖のどん底に突き落としました。このB52も、間違いなく北爆ではなく、南ベトナムの解放区を爆撃しに行くところだったはずです。
米軍は、その直前の10月に北爆を全面停止していたからです。
嘉手納基地のB52が、住民の激しい反対運動もあってとりあえず撤去されたのは、1970年9月でした。
1968年2月から70年9月まで、2年半あまりにわたってB52は嘉手納に常駐し、爆弾を積んでベトナムに向かったわけです(1967年以前にも、常駐ではありませんが、「台風避難」などの名目で飛来したB52が、嘉手納から何度もベトナム爆撃に向かっています)。
嘉手納から撤去されたB52は、タイのウタバオ基地に移駐したそうです。
1968年10月から北爆を停止していた米軍は、1972年に北爆を再開、ハノイやハイフォンをはじめ北ベトナム各地に猛烈な爆撃を行います。この時期の北爆は、おもにタイから出撃していたのでしょうか。
北爆であれ「南爆」であれ、同じベトナム人を標的にして爆撃が行われたのですから、あまり違いはないと思います。
ただ、「沖縄は米軍のベトナムへの発進基地だった」と言う場合、具体的にベトナムのどの地域の、どのような人たちに対して攻撃が行われたのか、どうしても気になります。
一般に考えられているように(私も漠然と想像していたように)、嘉手納を飛び立ったB52は、おそらく北ベトナムへの爆撃も行ったのだろうと思います。「北爆の出撃拠点」といった言い方も、たぶん間違いではないでしょう。
でも、それ以上に「南ベトナム」の解放区で暮らし、戦っていた人たちに対して、はるかに多くの爆撃が行われていたようなのです。
B52が嘉手納から、いつ、何機が飛び立ち、ベトナムのどこを爆撃したのか、おそらくアメリカには詳しい記録が残っているはずです。
残念ながら、私はそれを探す能力も時間もお金もありません。でも、いつかそれを知りたいと思います。
観光地にもなっているクチトンネルから、サイゴン川を数十キロさかのぼると、ゴム農園に囲まれたミンホアという静かな村があります。
そのミンホアの村外れ、ゴム農園の中の小道を深く入っていたところに、ハイくんという奨学生の家族が暮らしています。
2004年にハイくんの家を訪ねたOさんによると、ハイくんのお母さんは、かつて解放戦線のゲリラとしてジャングルで戦ったことを話してくれたそうです。
若き日のハイくんのお母さんが、具体的にどの場所で暮らし、戦っていたのかは、わかりません。解放区だったのか、政府の支配地区だったのか、それとも競合地区だったのか。政府の支配地区や競合地区であれば、B52の攻撃は受けていないかも知れません。
しかし、ハイくんのお母さんと同じように南ベトナムの地で暮らし、戦っていた数多くの人たちの頭上に、嘉手納を飛び立ったB52が爆弾を降り注がせたということは間違いないでしょう。
ひょっとすると、多くの奨学生たちの両親や、おじいさん、おばあさんたちが、かつて嘉手納から出て行ったベーナンムイハイ(B52)の爆撃にさらされたのかもしれません。
米軍とベトナム軍が共同演習を行った、というニュースが伝えられる昨今ではあります。
しかし、私たちがいま関わっているベトナムの地で、ほんの40年前にこのような出来事があった、それは今も私たちの目の前にある米軍基地から出撃していったのだ、という事実は、しっかり胸に刻んでおきたいと思います。
2010年08月22日
旧暦とベトナム
今日は旧盆のウンケーですね。
興南の快挙のおかげで、とても楽しいお盆になると思います。
3日間天気もよさそうだし、各地のエイサーも盛り上がることでしょう。
私はヤマトゥンチュですが、沖縄に来て、旧暦がいまも生きていることに強い印象を受けました。
あるとき両親に聞いてみたのですが、両親が子どもの頃は、正月もお盆も旧暦でやっていたような気がする、と言っていました。
いつから新暦に変わったのか、と聞いてみると「そういえばいつの間にか変わっていたねえ…」と、ちょっと頼りない答え。戦後の混乱で大変な時期に変わったのでしょうか。
それにしても、日本では公式には明治の初期に太陽暦を採用したということですが、両親が生まれ育った福島の農村部では、第二次大戦までは旧暦が根強く生きていたようです。
ベトナムでも、旧暦(太陰太陽暦)はいまも生きています。
新暦の1月1日は公休日になってはいますが、お正月といえば、やはりテト(旧正月)ですし、その他にも、さまざまな行事が陰暦で行われます。
10年ちょっと前に、私たち青葉奨学会沖縄委員会は、タオちゃんという青葉奨学生(当時中学3年生)を沖縄に招待して交流を持ったことがあります。
いまでは考えにくいですが、日本航空ホーチミン支店が、航空券をプレゼントしてくれたのです。
ベトナム側の事務局からタオちゃん訪問の話をもらって、受け入れの準備を始めていたとき、突然「期日を1ヶ月ほど延期してほしい」との連絡を受けました。
パスポートを申請しにいったところ、タオちゃんの出生届けが陰暦で出されていたことがわかり、このままではパスポートを作れない。改めて新暦で出生届の手続きをしなければならず、そのために時間がかかる、ということでした。
いまはどうなのかわかりませんが、タオちゃんが生まれた1980年代前半の時点では、農村や漁村では出生届けなども陰暦が普通に使われていたようです。
その頃ベトナムの事務局で働いていた日本人スタッフのWさんは、期日の変更のことでとても申し訳なさそうにしていましたが、「沖縄でも陰暦はよく使われていますよ」と快く了解したところ、「沖縄でもそうなんですね」と興味深そうでした。
まあ、役所への届け出に旧暦を使う例は、沖縄ではあまりないとは思いますが…。
届け出などで新暦と旧暦が混同するとややこしいことになりますが、伝統行事などでは、新暦以外にもうひとつの暦が生きている、というのは、なかなかいいことだな、と思います。
日本でも、旧正月も元日ぐらい公休日にして、家族でゆっくり祝えるようにしてもよいのでは、と思うのですが…。
ところで、ベトナムにもお盆があるのか気になって、何人かのベトナム人に聞いてみたところ、旧暦7月15日は「Vu Lan(ヴーラン)」という行事があるそうです。
多くの人がお寺に行くそうですが、私が聞いた範囲では、それほど大きな行事とは考えられていないようです。盆踊りやエイサーなどのようなものも、ないみたいです。
「Vu Lan」は、漢字にすると「盂蘭」になるようです。
お盆のことを「盂蘭盆(ウラボン)」ともいいますが、その「盂蘭」ですから、やはり沖縄や日本のお盆と、なんらかのつながりのある行事なのだと思います。
ベトナムの場合、旧暦7月15日よりも、その1ヶ月後の旧暦8月15日の「Tet Trung Thu」のほうが大きな行事になっているようです。
こちらは、漢字で書くと「中秋節」です。「中秋節」は、ベトナムでは子どもたちのためのお祭りになっています。
今年の中秋節は新暦では9月22日になりますが、その翌日の23日(秋分の日)に、琉大などで学んでいるベトナム人留学生と一緒に、沖縄NGOセンターで中秋節のお祝いをしようと企画しています。
大人も子どもも一緒に楽しめて、ベトナムの文化にも触れられるようなものなるように、工夫したいと思います。
詳しくは、また近いうちにご紹介します。
興南の快挙のおかげで、とても楽しいお盆になると思います。
3日間天気もよさそうだし、各地のエイサーも盛り上がることでしょう。
私はヤマトゥンチュですが、沖縄に来て、旧暦がいまも生きていることに強い印象を受けました。
あるとき両親に聞いてみたのですが、両親が子どもの頃は、正月もお盆も旧暦でやっていたような気がする、と言っていました。
いつから新暦に変わったのか、と聞いてみると「そういえばいつの間にか変わっていたねえ…」と、ちょっと頼りない答え。戦後の混乱で大変な時期に変わったのでしょうか。
それにしても、日本では公式には明治の初期に太陽暦を採用したということですが、両親が生まれ育った福島の農村部では、第二次大戦までは旧暦が根強く生きていたようです。
ベトナムでも、旧暦(太陰太陽暦)はいまも生きています。
新暦の1月1日は公休日になってはいますが、お正月といえば、やはりテト(旧正月)ですし、その他にも、さまざまな行事が陰暦で行われます。
10年ちょっと前に、私たち青葉奨学会沖縄委員会は、タオちゃんという青葉奨学生(当時中学3年生)を沖縄に招待して交流を持ったことがあります。
いまでは考えにくいですが、日本航空ホーチミン支店が、航空券をプレゼントしてくれたのです。
ベトナム側の事務局からタオちゃん訪問の話をもらって、受け入れの準備を始めていたとき、突然「期日を1ヶ月ほど延期してほしい」との連絡を受けました。
パスポートを申請しにいったところ、タオちゃんの出生届けが陰暦で出されていたことがわかり、このままではパスポートを作れない。改めて新暦で出生届の手続きをしなければならず、そのために時間がかかる、ということでした。
いまはどうなのかわかりませんが、タオちゃんが生まれた1980年代前半の時点では、農村や漁村では出生届けなども陰暦が普通に使われていたようです。
その頃ベトナムの事務局で働いていた日本人スタッフのWさんは、期日の変更のことでとても申し訳なさそうにしていましたが、「沖縄でも陰暦はよく使われていますよ」と快く了解したところ、「沖縄でもそうなんですね」と興味深そうでした。
まあ、役所への届け出に旧暦を使う例は、沖縄ではあまりないとは思いますが…。
届け出などで新暦と旧暦が混同するとややこしいことになりますが、伝統行事などでは、新暦以外にもうひとつの暦が生きている、というのは、なかなかいいことだな、と思います。
日本でも、旧正月も元日ぐらい公休日にして、家族でゆっくり祝えるようにしてもよいのでは、と思うのですが…。
ところで、ベトナムにもお盆があるのか気になって、何人かのベトナム人に聞いてみたところ、旧暦7月15日は「Vu Lan(ヴーラン)」という行事があるそうです。
多くの人がお寺に行くそうですが、私が聞いた範囲では、それほど大きな行事とは考えられていないようです。盆踊りやエイサーなどのようなものも、ないみたいです。
「Vu Lan」は、漢字にすると「盂蘭」になるようです。
お盆のことを「盂蘭盆(ウラボン)」ともいいますが、その「盂蘭」ですから、やはり沖縄や日本のお盆と、なんらかのつながりのある行事なのだと思います。
ベトナムの場合、旧暦7月15日よりも、その1ヶ月後の旧暦8月15日の「Tet Trung Thu」のほうが大きな行事になっているようです。
こちらは、漢字で書くと「中秋節」です。「中秋節」は、ベトナムでは子どもたちのためのお祭りになっています。
今年の中秋節は新暦では9月22日になりますが、その翌日の23日(秋分の日)に、琉大などで学んでいるベトナム人留学生と一緒に、沖縄NGOセンターで中秋節のお祝いをしようと企画しています。
大人も子どもも一緒に楽しめて、ベトナムの文化にも触れられるようなものなるように、工夫したいと思います。
詳しくは、また近いうちにご紹介します。
2010年08月17日
会報「Cay Phuong」25号
青葉奨学会沖縄委員会会報「Cay Phuong(ホウオウボク)」の第25号が完成しました。
今号の内容は、次の通りです。
「アレン・ネルソン奨学金 第1回支給式報告」
留学生チャンさんのスピーチ「青葉奨学金と私」
奨学生たちからの手紙 チュオン・グエン・ホアン・フックくん(小学2年生)、グエン・ティエン・フオックさん(フエ医科薬科大学1年生)
Cay mua xuan 2010(春の木運動)「中部の台風被災生徒たちに学用品を支援」 ファム・タイン・スアンさんのレポート
沖縄の「ヒヌカン」とベトナムの「タオクアン」
青葉奨学会沖縄委員会会計報告ほか
現在、私の手元に生徒からの手紙20通余りがありますので、これを急いで翻訳して、旧盆明けぐらいをメドに、会報と一緒に会員の皆様にお送りする予定です。
また、会報第1号から今号までをまとめて、合本を作りました。
沖縄委員会事務所にありますので、ご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、お知らせ下さい。
今号の内容は、次の通りです。
「アレン・ネルソン奨学金 第1回支給式報告」
留学生チャンさんのスピーチ「青葉奨学金と私」
奨学生たちからの手紙 チュオン・グエン・ホアン・フックくん(小学2年生)、グエン・ティエン・フオックさん(フエ医科薬科大学1年生)
Cay mua xuan 2010(春の木運動)「中部の台風被災生徒たちに学用品を支援」 ファム・タイン・スアンさんのレポート
沖縄の「ヒヌカン」とベトナムの「タオクアン」
青葉奨学会沖縄委員会会計報告ほか
現在、私の手元に生徒からの手紙20通余りがありますので、これを急いで翻訳して、旧盆明けぐらいをメドに、会報と一緒に会員の皆様にお送りする予定です。
また、会報第1号から今号までをまとめて、合本を作りました。
沖縄委員会事務所にありますので、ご覧になりたい方がいらっしゃいましたら、お知らせ下さい。
2010年08月08日
偽札未遂事件
「これって偽札なんですか?」
6年前に会員の皆さんに呼びかけて行ったベトナム南北縦断ツアーの最終日。参加者のYさんが、10万ドン札を手に不思議なことを尋ねてきました。
買い物に行ったスーパーのレジでこのお札を出したところ、「これはダメ」と言われて、使えなかったそうなのです。
幸い、親切な店員さんだったようで、Yさんの財布の中から別の10万ドン札を取り出して「こっちはOKよ」と言ってくれて、問題にはならなかったようです。
Yさんはベトナム初訪問。「事情がわからない旅行者」ということで、怪しまれなかったのでしょう。
もし私だったら、中途半端なベトナム語で弁解をして、かえって怪しまれて警察に突き出されたかも知れません。
ところで、Yさんが見せてくれた10万ドン札。透かしもちゃんと入っているし、私の目では本物に見えたのですが、レジの人はすぐに偽札と見破ったとのこと。
興味があったのでYさんから譲ってもらい、帰国後にルーペを使って観察してみました。すると、左下の金色で刷られたマークの位置がずれていたり、紙質も本物とは少し違うことがわかりました。
また、光に透かすと縦に黒い筋が入っていて、そこに小さな文字が浮かび上がるのですが、本物と比べるとそれが不鮮明です。
やはり、本当に偽札のようです。
細かく観察すれば見破ることができますが、一見本物に思えるシロモノではあります。
まして、外国人旅行者がその場で偽札と見破ることは、まず不可能だと思いました。
その後、インターネットで調べてみると、10万ドンの偽札が大量に出回っていて、ホーチミン市の日本総領事館でも注意を呼びかけていることがわかりました。
総領事館では「偽札の疑いがある紙幣番号」も公表していましたが、その番号にも一致していました。
それから間もなく、ベトナムのお札は紙幣からポリマー製(プラスチックの一種)に変わりました。
やはり、偽造防止のためだと思います。その後もたまに偽札のニュースを目にしますが、大量に出回っていることはないみたいです(たぶん)。
ところで、最近、信じがたい偽札(?)事件の噂を目にしました。
沖縄のウチカビに相当する紙銭(あの世のお金)がベトナムにもあります。ベトナムのはとても種類が多くて、米ドルやユーロ紙幣まであります。
最近では、ベトナムの現在のお札に似せたものも作られています。経済発展のおかげで、あの世でもベトナムドンが通用するようになってきた、ということでしょうか。

ベトナムドンに似せたと言っても、本物のお札はホーチミンさんの肖像が刷られているのに対して、紙銭のほうは閻魔大王(かな?)の顔が刷られていて、独特の不思議な雰囲気をかもし出しています。
本物には「ベトナム国家銀行」とありますが、紙銭は「NGAN HANG DIA PHU(地府銀行)」と書かれています。
それにそもそも、本物のお札はポリマー製で、紙ではありません。
ベトナム人が本物と間違えることはありえません。
ただ、初めてベトナムを訪れた外国人旅行者だと、「これがベトナムのお札ですよ」と言われたら、そう思ってしまう可能性はあるかもしれません。
信じがたい事件の噂とは、ある外国人が、閻魔大王が刷られたあの世のお金を両替所に持ち込んで、偽札を使おうとした疑いで警察に逮捕された、というのです。
この噂、本当かどうか私はわからないのですが、もし本当だとしても、騙そうと考えてやったとは思えません。どう考えても、通用しませんから。
勘違いしたのか、それとも、冗談のつもりでやったのでは…? まあいろんな人がいますから、わかりませんが。
でも、もしこの事件が本当だとすると、ベトナムの本物のお札に似せた紙銭は、近いうちに禁止されるかもしれませんね…。
6年前に会員の皆さんに呼びかけて行ったベトナム南北縦断ツアーの最終日。参加者のYさんが、10万ドン札を手に不思議なことを尋ねてきました。
買い物に行ったスーパーのレジでこのお札を出したところ、「これはダメ」と言われて、使えなかったそうなのです。
幸い、親切な店員さんだったようで、Yさんの財布の中から別の10万ドン札を取り出して「こっちはOKよ」と言ってくれて、問題にはならなかったようです。
Yさんはベトナム初訪問。「事情がわからない旅行者」ということで、怪しまれなかったのでしょう。
もし私だったら、中途半端なベトナム語で弁解をして、かえって怪しまれて警察に突き出されたかも知れません。
ところで、Yさんが見せてくれた10万ドン札。透かしもちゃんと入っているし、私の目では本物に見えたのですが、レジの人はすぐに偽札と見破ったとのこと。
興味があったのでYさんから譲ってもらい、帰国後にルーペを使って観察してみました。すると、左下の金色で刷られたマークの位置がずれていたり、紙質も本物とは少し違うことがわかりました。
また、光に透かすと縦に黒い筋が入っていて、そこに小さな文字が浮かび上がるのですが、本物と比べるとそれが不鮮明です。
やはり、本当に偽札のようです。
細かく観察すれば見破ることができますが、一見本物に思えるシロモノではあります。
まして、外国人旅行者がその場で偽札と見破ることは、まず不可能だと思いました。
その後、インターネットで調べてみると、10万ドンの偽札が大量に出回っていて、ホーチミン市の日本総領事館でも注意を呼びかけていることがわかりました。
総領事館では「偽札の疑いがある紙幣番号」も公表していましたが、その番号にも一致していました。
それから間もなく、ベトナムのお札は紙幣からポリマー製(プラスチックの一種)に変わりました。
やはり、偽造防止のためだと思います。その後もたまに偽札のニュースを目にしますが、大量に出回っていることはないみたいです(たぶん)。
ところで、最近、信じがたい偽札(?)事件の噂を目にしました。
沖縄のウチカビに相当する紙銭(あの世のお金)がベトナムにもあります。ベトナムのはとても種類が多くて、米ドルやユーロ紙幣まであります。
最近では、ベトナムの現在のお札に似せたものも作られています。経済発展のおかげで、あの世でもベトナムドンが通用するようになってきた、ということでしょうか。
ベトナムドンに似せたと言っても、本物のお札はホーチミンさんの肖像が刷られているのに対して、紙銭のほうは閻魔大王(かな?)の顔が刷られていて、独特の不思議な雰囲気をかもし出しています。
本物には「ベトナム国家銀行」とありますが、紙銭は「NGAN HANG DIA PHU(地府銀行)」と書かれています。
それにそもそも、本物のお札はポリマー製で、紙ではありません。
ベトナム人が本物と間違えることはありえません。
ただ、初めてベトナムを訪れた外国人旅行者だと、「これがベトナムのお札ですよ」と言われたら、そう思ってしまう可能性はあるかもしれません。
信じがたい事件の噂とは、ある外国人が、閻魔大王が刷られたあの世のお金を両替所に持ち込んで、偽札を使おうとした疑いで警察に逮捕された、というのです。
この噂、本当かどうか私はわからないのですが、もし本当だとしても、騙そうと考えてやったとは思えません。どう考えても、通用しませんから。
勘違いしたのか、それとも、冗談のつもりでやったのでは…? まあいろんな人がいますから、わかりませんが。
でも、もしこの事件が本当だとすると、ベトナムの本物のお札に似せた紙銭は、近いうちに禁止されるかもしれませんね…。
Posted by クアン at
21:10
│Comments(0)
2010年08月06日
青葉奨学会の歩み
青葉奨学会沖縄委員会の8月定例会のお知らせです。
8月14日(土)午後7時より
場所 すぺーす結(那覇市一銀通りの安木屋向かいの久茂地マンション402号室)
参加費無料(一品持ち寄り歓迎)
お問い合わせ 携帯080-2719-4720(村田)
今回は、「青葉奨学会の歩みを振り返る」というテーマで行います。
私たち「青葉奨学会沖縄委員会」は小さな団体で、大した「歩み」をしてきたわけではありませんが、1994年の発足から数えると16年になります。
この間に、378名の生徒たちに奨学金を送りました。
16年間の出来事、支援してきた子どもたちのこと、この間のベトナム・沖縄の変化など、改めて振り返ってみたいと思います。
私たちが支援している「ベトナム青葉奨学会」は、1992年にグエン・ドゥック・ホーエさんが設立した団体です。
ホーエさんは1959年から74年まで、東京に滞在していました。
京都大学・東京大学大学院で物理学などを学び(すごいですね…)、ベトナム人留学生のリーダーとして東京に学生寮を作り、仲間たちの生活や勉学を励まし続けました。
故国では戦争が激しくなっていった時期。1965年、米軍による北爆に対して、日本で最初に(たぶん)抗議デモを組織したのも、ホーエさんたち南ベトナムからの留学生だったそうです。
70年代前半には、故国の子どもたちのために、「兄弟奨学金」という奨学金の活動も始めていました。
その後、1974年にホーエさんは戦火の続く南ベトナムに帰っていきました。
1975年の南部解放後、兄弟奨学金は活動を停止しました。
革命後の混乱の中、日本とベトナムで連絡を取り合うことも極めて難しくなり、ホーエさんは音信不通の状態が続きました。
ドイモイ政策が軌道に乗った1990年代初め、ホーエさんはホーチミン市で日本語学校を設立するとともに、貧しい家庭の子どもたちを対象に奨学金の活動を再開しました。
1970年代前半、東京でホーエさんと一緒に活動していた高里鈴代さん(沖縄委員会代表)に、その当時のことや、90年代のホーエさんとの再会、沖縄委員会設立のいきさつなどをお聞きしたいと思います。
これまでの歩みを振り返りながら、「これから」についても思いをめぐらせてみましょう。
いつもどおり、飲み物と軽食を囲んでやりますので、興味のある方は気軽にご参加下さい。
会員以外の方の参加も歓迎しますので、どうぞお越し下さい。
8月14日(土)午後7時より
場所 すぺーす結(那覇市一銀通りの安木屋向かいの久茂地マンション402号室)
参加費無料(一品持ち寄り歓迎)
お問い合わせ 携帯080-2719-4720(村田)
今回は、「青葉奨学会の歩みを振り返る」というテーマで行います。
私たち「青葉奨学会沖縄委員会」は小さな団体で、大した「歩み」をしてきたわけではありませんが、1994年の発足から数えると16年になります。
この間に、378名の生徒たちに奨学金を送りました。
16年間の出来事、支援してきた子どもたちのこと、この間のベトナム・沖縄の変化など、改めて振り返ってみたいと思います。
私たちが支援している「ベトナム青葉奨学会」は、1992年にグエン・ドゥック・ホーエさんが設立した団体です。
ホーエさんは1959年から74年まで、東京に滞在していました。
京都大学・東京大学大学院で物理学などを学び(すごいですね…)、ベトナム人留学生のリーダーとして東京に学生寮を作り、仲間たちの生活や勉学を励まし続けました。
故国では戦争が激しくなっていった時期。1965年、米軍による北爆に対して、日本で最初に(たぶん)抗議デモを組織したのも、ホーエさんたち南ベトナムからの留学生だったそうです。
70年代前半には、故国の子どもたちのために、「兄弟奨学金」という奨学金の活動も始めていました。
その後、1974年にホーエさんは戦火の続く南ベトナムに帰っていきました。
1975年の南部解放後、兄弟奨学金は活動を停止しました。
革命後の混乱の中、日本とベトナムで連絡を取り合うことも極めて難しくなり、ホーエさんは音信不通の状態が続きました。
ドイモイ政策が軌道に乗った1990年代初め、ホーエさんはホーチミン市で日本語学校を設立するとともに、貧しい家庭の子どもたちを対象に奨学金の活動を再開しました。
1970年代前半、東京でホーエさんと一緒に活動していた高里鈴代さん(沖縄委員会代表)に、その当時のことや、90年代のホーエさんとの再会、沖縄委員会設立のいきさつなどをお聞きしたいと思います。
これまでの歩みを振り返りながら、「これから」についても思いをめぐらせてみましょう。
いつもどおり、飲み物と軽食を囲んでやりますので、興味のある方は気軽にご参加下さい。
会員以外の方の参加も歓迎しますので、どうぞお越し下さい。