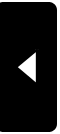2011年08月22日
「エージェント・オレンジを沖縄で埋却」
沖縄の枯葉剤に関する先日のジャパンタイムズの記事、「合意してないプロジェクト」の阿部小涼さんが日本語訳して下さったそうです。
「合意していないプロジェクト」のブログhttp://www.projectdisagree.org/2011/08/agent-orange-buried-on-okinawa-vet-says.html
から、転載させていただきます。
「Okinawa outreach」のブログでは、You tubeで退役軍人の証言を聴くことができます。関心のある方はぜひご覧下さい(英語なので、残念ながら私は聞き取れません…)。 http://okinawaoutreach.blogspot.com/2011/08/jon-mitchells-articles-on-agent-orange.html
エージェント・オレンジを沖縄で埋却、退役軍人が語る/
元兵士は米国がベトナム戦争時の枯葉剤を使用し廃棄したと主張
2011年8月13日
ジョン・ミッチェル
ジャパンタイムズへの特別寄稿
1960年代末、米軍は有害な枯葉剤「エージェント・オレンジ」の入った数十本のドラム缶を沖縄島の北谷町付近に埋めたと、米退役軍人がジャパン・タイムズ社に語った。
元兵士のこの主張よりわずか数日前、松本剛明外相は、1945-72年までの27年間の占領期に沖縄で使用した化学物質について明らかにするよう米国防省に対して求めていると語った。米政府は、沖縄におけるエージェント・オレンジの使用については記録がないと繰り返し主張し続けているのである。
元兵士の証言は、沖縄における関心を大いに高めるだろう。エージェント・オレンジは発がん性のダイオキシンを高濃度に含有し、数十年は土壌や水に残留する可能性がある。元兵士がドラム缶が埋められたと主張する場所は、人気の観光地や住宅地域に近い。
匿名での報道を求めているこの61歳の元兵士は、1968年から70年に沖縄に駐留し、米陸軍補給地区でフォークリフトを操作していた。この間、彼はエージェント・オレンジを含む補給物資を那覇港へ向かうトラックに搬入する作業に従事し、積荷は那覇港からベトナムへ輸送されていた。
元米兵は、1969年に補給船が座礁した際、その引き揚げ作業に加わらなければならなかったという。
「島中から作業員が那覇港に集められた。ボートを岩礁から降ろすのに、2、3日を要した。エージェント・オレンジのドラム缶が一杯に詰まったコンテナがいくつも破損していた。55ガロン(208リットル)缶には、オレンジの縞がぐるりと描かれてあった。破損して流れ出していたものもあり、私たちはみんなそれを浴びたのです」と、彼は語った。
破損したドラム缶の除去のあと、この元兵士は、米軍がそれらを広い敷地に埋却するのを目撃したと主張している。「彼らは長い溝を掘った。150フィート(46メートル)以上はあっただろう。クレーンが複数台あって、コンテナをつり上げていた。そして、中のドラム缶をぜんぶその溝に揺すり落とした。その後、土で埋めたのです」。
別のふたり、元米兵のマイケル・ジョーンズ氏と港湾作業に従事したジェイムズ・スペンサー氏が、ジャパン・タイムズのインタビューに答えて、何千缶もの除草剤の輸送拠点として那覇港が使われていたという元米兵の主張を裏付けた。スペンサー氏はまた、1969年の引き揚げ作業で座礁船からコンテナを積み降ろすところを目撃している。ただし、コンテナの中身が何であったかははっきり判らないと語った。
しかし、証言を行った元米兵は、確信を持っている。「あれはエージェント・オレンジだった。マチナト(補給地区)で(ドラム缶を)扱ったときの臭いで判ったのだ」。
救援作業の際に枯葉剤のダイオキシンを浴びたため、この元米兵は脳卒中と塩素座瘡を含む、深刻な病状に悩まされている。米国退役軍人省(VA)は、病気を患った退役軍人の補償を担当する窓口で、エージェント・オレンジ被曝の治療費として退役兵に対し月1000ドル以上を給付する。
しかしVAは、彼がベトナムに駐留した6ヶ月の間にダイオキシンに被曝したのだと主張している。
1991年に米連邦議会を通過したエージェント・オレンジ法の下で、ベトナムに派遣された経験のあるすべての米兵は枯葉剤と接触した可能性があるとみなされ、医療給付と補償を受ける資格を得た。
だが、エージェント・オレンジは沖縄に保管されたことはないと否定しつづけるペンタゴンのせいで、これらの補償が、この島でダイオキシンに被曝したと主張する元米兵には支払われない。
証言をした元米兵は、特に、駐留米軍の再編交渉が進行中の現在、沖縄をめぐって日米関係が神経過敏になっている時期に、この問題について語ることの危険性には気付いていると話した。「この件で実名が公表されれば、私の給付金は取り上げられてしまうかもしれない」。
2002年、沖縄県政は、北谷地域で内容不明の多数のドラム缶を発見したが、これは元米兵が目撃したと主張している掘削された溝の場所に近い。北谷町役場に近い筋の人物の話によれば、ドラム缶が発見された後、那覇を拠点とする沖縄防衛局(*当時の那覇防衛施設局のこと)がすぐに押収し、これは現在の防衛省の管轄下にある。
「私は北谷町の基地問題担当に、防衛施設局からの報告書を持っているかどうか問い合わせたが、答えはノーだった。町は、いまだに内容物が何であったのか知らないし、ドラム缶がどのように処理されたのか、防衛施設局が内容物についての調査を行ったのかどうかも判らない」と、その人物は語った。
この6ヶ月間で、ジャパン・タイムズ社が集めた12名の元米兵からの直接の証言によれば、1960年代半ばから1975年にかけて、嘉手納空軍基地、普天間飛行場など沖縄の9カ所の米軍施設でエージェント・オレンジを貯蔵し、噴霧し、輸送したとのことである。
証言に名乗り出た人々のうちのひとり、61歳の元米空軍整備兵ジョー・シパラ氏は、泡瀬通信施設の周囲で雑草を除去するために、定期的に枯葉剤を噴霧したという。また、キャンプ・シュワブ所属の海兵隊員であったスコット・パートン氏は、1971年、何十というエージェント・オレンジのドラム缶を基地内で見たと証言している。ふたりの証言は、沖縄で撮影された枯葉剤のドラム缶の写真によって裏付けられている。ふたりとも現在、2型糖尿病や前立腺疾患など、枯葉剤に接したことが原因の深刻な病状にあり、シパラ氏の子どもたちには、ダイオキシン被曝で起こる奇形の症状が現れている。ところが、VAはかれらの申請を却下し続けている。これは、米国防省が、枯葉剤の沖縄での存在を認めようとしないためである。
これら12名の元米兵の説明が示すのは、ベトナム戦争時、この島でエージェント・オレンジが広範囲に使用されていたということである。枯葉剤は、北部のやんばる地域から南部は那覇港まで、大量に貯蔵され使用されていたと彼らは語っている。枯葉剤の発がん性について充分に明らかになったのは、1980年代半ばになってようやくのことであった。
沖縄の人々は、この問題に関心を持っている。エージェント・オレンジが噴霧された9カ所の基地のうちのひとつに近い小学校に勤めていたという退職教員は、最近、彼女の教え子たちに白血病で亡くなった者が多いことを説明してくれた。白血病は、ダイオキシン被曝に由来すると米国政府が認めている病状に含まれている。
名護市議の大城敬人氏は、名護にあるキャンプ・シュワブで多数のドラム缶を見たという元海兵隊員パートン氏の主張について、調査を要求した。
米軍が有害廃棄物の処理についてこのように糾弾されるのは、これが初めてのことではない。
2005年、アラスカのフォート・メインライトでは、建設業者が宅地造成予定地の地下からPCB汚染された何トンもの土を発見したことが大々的に報道された。今年の5月には、3人の退役軍人が、1978年に韓国のキャンプ・キャロルでエージェント・オレンジのドラム缶を埋却する作業をしたと主張した。ペンタゴンは現在、この主張について調査中である。
沖縄国際大学で環境法を専門とする砂川かおり氏は、エージェント・オレンジによる汚染の可能性について関心を寄せている。
「沖縄の人々は、この件について真実を知る必要がある。政府は汚染が広がっているかどうか調査を実施すべき。今も健康や環境への危険性があるのかどうか、私たちは知る必要がある」と彼女は語った。
「合意していないプロジェクト」のブログhttp://www.projectdisagree.org/2011/08/agent-orange-buried-on-okinawa-vet-says.html
から、転載させていただきます。
「Okinawa outreach」のブログでは、You tubeで退役軍人の証言を聴くことができます。関心のある方はぜひご覧下さい(英語なので、残念ながら私は聞き取れません…)。 http://okinawaoutreach.blogspot.com/2011/08/jon-mitchells-articles-on-agent-orange.html
エージェント・オレンジを沖縄で埋却、退役軍人が語る/
元兵士は米国がベトナム戦争時の枯葉剤を使用し廃棄したと主張
2011年8月13日
ジョン・ミッチェル
ジャパンタイムズへの特別寄稿
1960年代末、米軍は有害な枯葉剤「エージェント・オレンジ」の入った数十本のドラム缶を沖縄島の北谷町付近に埋めたと、米退役軍人がジャパン・タイムズ社に語った。
元兵士のこの主張よりわずか数日前、松本剛明外相は、1945-72年までの27年間の占領期に沖縄で使用した化学物質について明らかにするよう米国防省に対して求めていると語った。米政府は、沖縄におけるエージェント・オレンジの使用については記録がないと繰り返し主張し続けているのである。
元兵士の証言は、沖縄における関心を大いに高めるだろう。エージェント・オレンジは発がん性のダイオキシンを高濃度に含有し、数十年は土壌や水に残留する可能性がある。元兵士がドラム缶が埋められたと主張する場所は、人気の観光地や住宅地域に近い。
匿名での報道を求めているこの61歳の元兵士は、1968年から70年に沖縄に駐留し、米陸軍補給地区でフォークリフトを操作していた。この間、彼はエージェント・オレンジを含む補給物資を那覇港へ向かうトラックに搬入する作業に従事し、積荷は那覇港からベトナムへ輸送されていた。
元米兵は、1969年に補給船が座礁した際、その引き揚げ作業に加わらなければならなかったという。
「島中から作業員が那覇港に集められた。ボートを岩礁から降ろすのに、2、3日を要した。エージェント・オレンジのドラム缶が一杯に詰まったコンテナがいくつも破損していた。55ガロン(208リットル)缶には、オレンジの縞がぐるりと描かれてあった。破損して流れ出していたものもあり、私たちはみんなそれを浴びたのです」と、彼は語った。
破損したドラム缶の除去のあと、この元兵士は、米軍がそれらを広い敷地に埋却するのを目撃したと主張している。「彼らは長い溝を掘った。150フィート(46メートル)以上はあっただろう。クレーンが複数台あって、コンテナをつり上げていた。そして、中のドラム缶をぜんぶその溝に揺すり落とした。その後、土で埋めたのです」。
別のふたり、元米兵のマイケル・ジョーンズ氏と港湾作業に従事したジェイムズ・スペンサー氏が、ジャパン・タイムズのインタビューに答えて、何千缶もの除草剤の輸送拠点として那覇港が使われていたという元米兵の主張を裏付けた。スペンサー氏はまた、1969年の引き揚げ作業で座礁船からコンテナを積み降ろすところを目撃している。ただし、コンテナの中身が何であったかははっきり判らないと語った。
しかし、証言を行った元米兵は、確信を持っている。「あれはエージェント・オレンジだった。マチナト(補給地区)で(ドラム缶を)扱ったときの臭いで判ったのだ」。
救援作業の際に枯葉剤のダイオキシンを浴びたため、この元米兵は脳卒中と塩素座瘡を含む、深刻な病状に悩まされている。米国退役軍人省(VA)は、病気を患った退役軍人の補償を担当する窓口で、エージェント・オレンジ被曝の治療費として退役兵に対し月1000ドル以上を給付する。
しかしVAは、彼がベトナムに駐留した6ヶ月の間にダイオキシンに被曝したのだと主張している。
1991年に米連邦議会を通過したエージェント・オレンジ法の下で、ベトナムに派遣された経験のあるすべての米兵は枯葉剤と接触した可能性があるとみなされ、医療給付と補償を受ける資格を得た。
だが、エージェント・オレンジは沖縄に保管されたことはないと否定しつづけるペンタゴンのせいで、これらの補償が、この島でダイオキシンに被曝したと主張する元米兵には支払われない。
証言をした元米兵は、特に、駐留米軍の再編交渉が進行中の現在、沖縄をめぐって日米関係が神経過敏になっている時期に、この問題について語ることの危険性には気付いていると話した。「この件で実名が公表されれば、私の給付金は取り上げられてしまうかもしれない」。
2002年、沖縄県政は、北谷地域で内容不明の多数のドラム缶を発見したが、これは元米兵が目撃したと主張している掘削された溝の場所に近い。北谷町役場に近い筋の人物の話によれば、ドラム缶が発見された後、那覇を拠点とする沖縄防衛局(*当時の那覇防衛施設局のこと)がすぐに押収し、これは現在の防衛省の管轄下にある。
「私は北谷町の基地問題担当に、防衛施設局からの報告書を持っているかどうか問い合わせたが、答えはノーだった。町は、いまだに内容物が何であったのか知らないし、ドラム缶がどのように処理されたのか、防衛施設局が内容物についての調査を行ったのかどうかも判らない」と、その人物は語った。
この6ヶ月間で、ジャパン・タイムズ社が集めた12名の元米兵からの直接の証言によれば、1960年代半ばから1975年にかけて、嘉手納空軍基地、普天間飛行場など沖縄の9カ所の米軍施設でエージェント・オレンジを貯蔵し、噴霧し、輸送したとのことである。
証言に名乗り出た人々のうちのひとり、61歳の元米空軍整備兵ジョー・シパラ氏は、泡瀬通信施設の周囲で雑草を除去するために、定期的に枯葉剤を噴霧したという。また、キャンプ・シュワブ所属の海兵隊員であったスコット・パートン氏は、1971年、何十というエージェント・オレンジのドラム缶を基地内で見たと証言している。ふたりの証言は、沖縄で撮影された枯葉剤のドラム缶の写真によって裏付けられている。ふたりとも現在、2型糖尿病や前立腺疾患など、枯葉剤に接したことが原因の深刻な病状にあり、シパラ氏の子どもたちには、ダイオキシン被曝で起こる奇形の症状が現れている。ところが、VAはかれらの申請を却下し続けている。これは、米国防省が、枯葉剤の沖縄での存在を認めようとしないためである。
これら12名の元米兵の説明が示すのは、ベトナム戦争時、この島でエージェント・オレンジが広範囲に使用されていたということである。枯葉剤は、北部のやんばる地域から南部は那覇港まで、大量に貯蔵され使用されていたと彼らは語っている。枯葉剤の発がん性について充分に明らかになったのは、1980年代半ばになってようやくのことであった。
沖縄の人々は、この問題に関心を持っている。エージェント・オレンジが噴霧された9カ所の基地のうちのひとつに近い小学校に勤めていたという退職教員は、最近、彼女の教え子たちに白血病で亡くなった者が多いことを説明してくれた。白血病は、ダイオキシン被曝に由来すると米国政府が認めている病状に含まれている。
名護市議の大城敬人氏は、名護にあるキャンプ・シュワブで多数のドラム缶を見たという元海兵隊員パートン氏の主張について、調査を要求した。
米軍が有害廃棄物の処理についてこのように糾弾されるのは、これが初めてのことではない。
2005年、アラスカのフォート・メインライトでは、建設業者が宅地造成予定地の地下からPCB汚染された何トンもの土を発見したことが大々的に報道された。今年の5月には、3人の退役軍人が、1978年に韓国のキャンプ・キャロルでエージェント・オレンジのドラム缶を埋却する作業をしたと主張した。ペンタゴンは現在、この主張について調査中である。
沖縄国際大学で環境法を専門とする砂川かおり氏は、エージェント・オレンジによる汚染の可能性について関心を寄せている。
「沖縄の人々は、この件について真実を知る必要がある。政府は汚染が広がっているかどうか調査を実施すべき。今も健康や環境への危険性があるのかどうか、私たちは知る必要がある」と彼女は語った。
2011年08月18日
北谷に埋められた枯葉剤?
「1969年に、枯葉剤の入った大量のドラム缶を北谷町で埋めた」という元米兵の証言が、波紋を広げています。
QAB(琉球朝日放送)の14日の報道を転載します。
ベトナム戦争で使われたダイオキシンを含む枯れ葉剤が北谷町に埋められていた可能性があることがわかりました。
これはフリージャーナリストのジョン・ミッチェルさんが沖縄に駐留していた元アメリカ軍人を取材し、13日づけのジャパンタイムスで報じたものです。
元アメリカ軍人の証言によると1969年、補給船が座礁した際、船に積み込まれていた枯れ葉剤とみられる大量のドラム缶が回収され、北谷町に大きな穴を掘って埋めたということです。
また、これ以外にも船の座礁事故やドラム缶の処理作業について証言している男性がいるということです。アメリカ政府は、これまで、沖縄における枯れ葉剤の存在を否定しています。
(転載ここまで)
ジャパンタイムズの記事(英語)は、ここにあります。
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110813a1.html
日本語訳してみようと思ったのですが、私は英語が本当に苦手なので、めちゃくちゃ長い時間がかかってしまいそうです。
沖縄の多くの基地で枯葉剤が使われたことはほぼ間違いないだろうと思っていましたが、「北谷に埋めた」という証言には、正直驚きました。
10日のブログで、私は次のように書きました。
「枯葉剤が使われていたのは、1960年代から70年代初め。今から40年以上前のことです。亜熱帯の沖縄では、しばしば激しい雨が降り、土壌が流出します。除草のために何度か枯葉剤を使った場所で、いまも土壌からダイオキシンなどが検出される、というのは考えにくいことです。
ベトナムでも、枯葉剤が撒かれた場所の多くでは、現在では高濃度のダイオキシンなどは検出されないようです。いまも枯葉剤の汚染が残っているホットスポットは、①枯葉剤が貯蔵され、積み込みの作業などで毎日のように漏れ出していた場所。つまりかつての米軍基地。ダナン、ビエンホアなど。②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所。などということになっているようです。
沖縄の場合も、枯葉剤使用による汚染が広範囲で残っている、ということは考えにくいです。ただし、枯葉剤がどのように扱われていたかによりますが、局地的にホットスポットが存在する可能性はあると思います。」
今回問題になっている北谷の例は、もし証言が確かなものだとすれば、「②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所」にあたり、ベトナムのホットスポットと同じように、枯葉剤による環境汚染が続いている可能性があります。
沖縄の枯葉剤問題、私が思っていたよりも、ずっと深刻なのかもしれません。
今日は、北谷町長が国と県に対して事実関係の調査を要求したそうです。
もう一度、QABの報道(17日)を転載します(すみません…)。
元アメリカ軍人がベトナム戦争当時にダイオキシンを含む枯れ葉剤を、北谷町に埋めたと証言しているのを受け、北谷町の野国町長が8月17日、国と県に対して事実関係の調査を求めました。
これは8月13日、英字新聞ジャパンタイムズが報じたもので、1969年、アメリカ軍の補給船が座礁した際、破損して回収された枯れ葉剤の容器を北谷町に埋めたという元軍人の証言が掲載されています。
外務省沖縄事務所を訪ねた野国町長は、「町民の不安を払しょくするためにも、アメリカ軍やアメリカ政府に対し、事実確認をしてほしい」と求めました。
これに対して伊従誠副所長は、松本外務大臣がアメリカに事実関係を確認していると述べ、「なるべく早く回答を得られるようにしたい」と答えました。
野国町長は、「跡地を抱える市町村として、皆同じでしょうけど、いわゆる使用の履歴というようなことを明らかにするようにと、しておりますけれども、なかなかそういったことが米軍から明らかにされていないと。実際に使った側から、きちんと証明してもらわないといけない」と話しました。
この後、野国町長は、県に対しても同様の要請を行い、対応した又吉知事公室長は、「少しでも疑念があれば住民の不安につながることですので、直ちに県としては政府に事実関係の確認を求めたということであります」と答えました。
野国町長は県内にもこの作業に携わった人がいないか情報を求めています。
(転載ここまで)
真相を明らかにさせるよう、野国町長や北谷町民を、多くの県民でバックアップしていきましょう。
QAB(琉球朝日放送)の14日の報道を転載します。
ベトナム戦争で使われたダイオキシンを含む枯れ葉剤が北谷町に埋められていた可能性があることがわかりました。
これはフリージャーナリストのジョン・ミッチェルさんが沖縄に駐留していた元アメリカ軍人を取材し、13日づけのジャパンタイムスで報じたものです。
元アメリカ軍人の証言によると1969年、補給船が座礁した際、船に積み込まれていた枯れ葉剤とみられる大量のドラム缶が回収され、北谷町に大きな穴を掘って埋めたということです。
また、これ以外にも船の座礁事故やドラム缶の処理作業について証言している男性がいるということです。アメリカ政府は、これまで、沖縄における枯れ葉剤の存在を否定しています。
(転載ここまで)
ジャパンタイムズの記事(英語)は、ここにあります。
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20110813a1.html
日本語訳してみようと思ったのですが、私は英語が本当に苦手なので、めちゃくちゃ長い時間がかかってしまいそうです。
沖縄の多くの基地で枯葉剤が使われたことはほぼ間違いないだろうと思っていましたが、「北谷に埋めた」という証言には、正直驚きました。
10日のブログで、私は次のように書きました。
「枯葉剤が使われていたのは、1960年代から70年代初め。今から40年以上前のことです。亜熱帯の沖縄では、しばしば激しい雨が降り、土壌が流出します。除草のために何度か枯葉剤を使った場所で、いまも土壌からダイオキシンなどが検出される、というのは考えにくいことです。
ベトナムでも、枯葉剤が撒かれた場所の多くでは、現在では高濃度のダイオキシンなどは検出されないようです。いまも枯葉剤の汚染が残っているホットスポットは、①枯葉剤が貯蔵され、積み込みの作業などで毎日のように漏れ出していた場所。つまりかつての米軍基地。ダナン、ビエンホアなど。②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所。などということになっているようです。
沖縄の場合も、枯葉剤使用による汚染が広範囲で残っている、ということは考えにくいです。ただし、枯葉剤がどのように扱われていたかによりますが、局地的にホットスポットが存在する可能性はあると思います。」
今回問題になっている北谷の例は、もし証言が確かなものだとすれば、「②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所」にあたり、ベトナムのホットスポットと同じように、枯葉剤による環境汚染が続いている可能性があります。
沖縄の枯葉剤問題、私が思っていたよりも、ずっと深刻なのかもしれません。
今日は、北谷町長が国と県に対して事実関係の調査を要求したそうです。
もう一度、QABの報道(17日)を転載します(すみません…)。
元アメリカ軍人がベトナム戦争当時にダイオキシンを含む枯れ葉剤を、北谷町に埋めたと証言しているのを受け、北谷町の野国町長が8月17日、国と県に対して事実関係の調査を求めました。
これは8月13日、英字新聞ジャパンタイムズが報じたもので、1969年、アメリカ軍の補給船が座礁した際、破損して回収された枯れ葉剤の容器を北谷町に埋めたという元軍人の証言が掲載されています。
外務省沖縄事務所を訪ねた野国町長は、「町民の不安を払しょくするためにも、アメリカ軍やアメリカ政府に対し、事実確認をしてほしい」と求めました。
これに対して伊従誠副所長は、松本外務大臣がアメリカに事実関係を確認していると述べ、「なるべく早く回答を得られるようにしたい」と答えました。
野国町長は、「跡地を抱える市町村として、皆同じでしょうけど、いわゆる使用の履歴というようなことを明らかにするようにと、しておりますけれども、なかなかそういったことが米軍から明らかにされていないと。実際に使った側から、きちんと証明してもらわないといけない」と話しました。
この後、野国町長は、県に対しても同様の要請を行い、対応した又吉知事公室長は、「少しでも疑念があれば住民の不安につながることですので、直ちに県としては政府に事実関係の確認を求めたということであります」と答えました。
野国町長は県内にもこの作業に携わった人がいないか情報を求めています。
(転載ここまで)
真相を明らかにさせるよう、野国町長や北谷町民を、多くの県民でバックアップしていきましょう。
2011年08月12日
「母さんの仕事」
以前、青葉奨学金を受けて勉強し、いまはホーチミン市で会社勤めをしているTさんのブログから、「母さんの仕事」という文章を紹介します。
わからない単語が多くて苦労しましたが、頑張って日本語に訳しました。
Tさんの家族は、カンザー郡ビンカン村に住んでいます。ここは、ホーチミン市中心部からそれほど遠くない場所ですが、ドンナイ川という大きな川で隔てられていて、フェリーを使わないと行くことができません(近い将来、橋がかかる予定だと聞いています)。
Tさんのお父さんは早く亡くなり、お母さんが「ban hang rong」(天秤棒などで品物を担いで、露天で商売する)の仕事で生計を立て、5人の子どもたちを育ててきました。
そのお母さんの仕事ぶりや、お母さんに対するTさんの思いを綴ったのが、この文章です。
子ども時代のある日、Tさんは、お母さんと一緒に都会に商売に行くという体験をします。
午前3時ごろ、Tさんは、ニッパヤシの実を担いだお母さんに手を引かれて家を出ます。
街へ向かう途中、川の真ん中で渡し舟のエンジンが止まってしまったり、市場のそばで商売を始めると、役人の取締りを受けて売り物を没収されてしまったり、麻薬中毒の人たちに品物を売ったり、激しいスコールに見舞われて寒さに震えたり…、そんな波乱に満ちた1日(でも、お母さんにとってはごく普通の1日)が、Tさんの目を通して生き生きと描写されています。
「露天商」という仕事は、ベトナム社会の中で、どちらかというと差別されるというか、軽く見られているのでは、と思います。取締りの対象になることも少なくありません。
でも、その仕事で自分たちを育ててくれたお母さんに対して、Tさんは感謝と強い誇りを感じています。
「お母さんの仕事は?」と聞かれたら、「いまは市場で働いていますが、以前は露天商をしていました」と答えるでしょう、というくだりで、この文章は結ばれています。
前置きが長くなりました。拙い翻訳なので、原文の雰囲気がうまく表せていませんし、誤訳も多々あると思います。
ベトナム語を読める方は、ぜひ原文を読んでみて下さい(ベトナム語がわからない方も、雰囲気だけでも…)。
http://vn.360plus.yahoo.com/htt_759/article?mid=269&prev=64&next=219
母さんの仕事
今日、友人がわたしに聞いた。「3月8日(女性の日)は、どこか遊びに行く予定はある?」
わたしは答えた。「いつもの年と同じよ。わたしは家にいて、母さんと一緒に過ごすの」
友人は続けて聞いた。「お母さんは、何の仕事をしているの?」
そういえば、知り合ってずいぶん長くなるのに、友人にそのことを質問されるのは初めてのことだ(もっとも、わたしの方も同じようなものね)。
それから2人は、自分の家族について語り始めた。
わたしの父さんは、早く亡くなった。母さんは、30歳を過ぎたばかりのときから、たった1人で、5人の子どもたちを養わなければならなかった。
そのことを知って、友人は、母さんの仕事について、とても興味を持ったようだった。
わたしは、母さんについて話した。
母さんは、とても小さな頃から、おじいさんと一緒に、川で漁網を引く仕事をしていた。
それは危険に満ちたものだった。強盗やワニが現れたり、ときには人の死体まで流れてくることもあった。その頃、国はまだ平和になっていなかったからね。
母さんは、小さなときから賢い子だった。だからこそ、父さんのお父さん(父方のおじいさん)は、母さんを父さんに引き合わせた。誰もが冗談だろうと思っていたことが、現実になった。
やがて、母さんは父さんと一緒に家庭を持った。そして、毎日、家でさまざまな食べ物を売るようになった。
それはバインミーティット(ベトナム風のサンドウィッチ)だったり(その頃は、みんなフランスパンを「豚小屋」風に並べて売っていた。それがとても面白くて、わたしはいつも進んでパンを並べる仕事をしたのを覚えている)、バインクオン(水餃子に似た食べ物)やサトウキビジュースだったりした。
サトウキビジュースを売る手押し車は、2番目の姉さんがよく中に潜り込んで遊ぶ場所だった。悪い癖で、ジュースを啜っていたのね。あるとき、姉さんは手押し車の中に入ったまま眠ってしまった。母さんは姉さんを捜したけれど見つからず、泣いてしまったことがあった。
その後、母さんはいろいろな日用品を売るようになった。
それは、母さんにとっていちばん幸せな時間だった。心優しい、愛する夫を持ち、幼い子どもたちの世話をして過ごす時間…。
でも、そのささやかな幸せは、13年足らずで終わった。
父さんが永遠に旅立ってしまった。
本当にあっけなく、あまりにも突然に訪れた別れに、誰もが呆然とし、嘆き悲しんだ。
そのときから、母さんの人生は、苦難に満ちた新しい1ページが始まった。
5人の子どもは、いちばん大きな子が12歳、いちばん小さな子は、まだ3ヶ月だった。
すべての重荷が、母さんの肩にのしかかった。
間もなく借金がふくらんでいき、毎日、借金取りが家に来るようになった。彼らは、来るたびに家財道具を叩き壊し、脅し文句を吐き捨てていった。
わたしたち母子は、崩れかけた家の中で、お互いに抱き合って泣くことしかできなかった。
もう家で日用品を売ることはできなくなり、母さんは生計を立てるために家を離れて仕事をしなければならなかった。母さんは、露天商となり、品物を担いで売り歩くようになった。
わたしたち姉妹は、母さんが早朝に家を出て、夕方になってやっと帰ってくるのを見ていた。
母さんの疲れた表情から、大変な仕事だということが感じられたけれど、それがどのような苦労なのか、本当のことは何もわかっていなかった。
なぜなら、遠い場所での露天商について、母さんはいつも楽しい話ばかりをわたしたちに聞かせてくれていたから。
「都会ってのは、とってもおかしなところなんだよ。どの家も戸を閉めてしーんとしているもんだから、母さんは、ここには誰もいないんだと思った。でも、呼び込みをすると、どこかから人が大勢出てくるんだよ」
「都会の露天商の人たちは、とっても気が荒いのさ。彼らは、商売の場所を取るために、よく喧嘩をするんだ。でもね。母さんはここに来たばかりの新入りだから、いつも場所を譲ってもらったり、助けてもらったりしている。きっと、父さんが見守ってくれているんだね」
母さんがそのような楽しい話をしてくれていたので、わたしたちは、母さんの仕事は体力的にきついだけで、危険な目に遭わなければならない仕事だとは思っていなかった。ある日の出来事までは。
その日、どうして母さんがわたしを連れて商売に出ることになったのか、覚えていない。おそらく、わたしを病院に連れて行くためだったのかもしれない。
わたしのような子どもには、母さんに連れられて都会に出るのは、めまいがするようなことだった。都会がどんなに美しい場所であるかを、目にできるのだ…。
その日の未明、午前3時ごろ、母さんはわたしを連れて行くために、起こしてくれた。
母さんの片手には、10キロほどの(と母さんは言った)ニッパヤシの実を入れたカゴを提げ、もう一方の手には量りやビニール袋、そしてわたしの手を引いて家を出た。
木の葉がざわざわと騒ぎ立てる、暗くてさびしい夜道を通って(いまでは、その道は明るく、賑わっている。それに、遠いというほどの距離でもないのに、そのときのわたしは、恐ろしく遠い道のりだと感じていた)、わたしと母さんは船着場に着いた。
多くの人たちと一緒に、小さな渡し舟に、積み重なるように乗り込んだ。
はじめのうちは、何でもなかったけれど、川の真ん中に達したところで、突然エンジンが止まってしまい、船は漂い始めた。そして、みんなが騒ぎ出した。
「まいったな。海まで流されてしまうぞ」
「船頭は、酒を飲んでデタラメな操縦をしてるじゃないか。なんて無責任なやつだ!」
「明かりを灯せ。他の船に助けてもらうんだ」
幸い、船はエンジンがかかって、再び走り始めた。
でも、ほっとする間もなく、大きな波がやってきた。渡し舟は高い波に乗り上げると、いきなり谷間に落ちていく。
目の前には、大きな水しぶき(わたしは、いまも時々、このときのことを夢に見るの)。水が、浴びるように身体に降りかかった。
そのとき、わたしは母さんに抱きついて、恐ろしさで泣くことしかできなかった。
そして初めて理解した。毎日、母さんはこんなにも危険な思いをして、仕事に出かけているんだということを。
それでも、ようやく岸に上がることができた。よかった!
母さんとわたしは、先に進んだ。
「ブージョー」という車に乗ると(みんなこんな風に呼んでいた。その車を、正確にはなんて言うのか、わからないの)、母さんはすぐに眠ってしまった。
父さんがまだ生きていたとき、母さんは車酔いをしてしまって、どこにも出かけられなかったのを覚えている。
でも、たぶんとても疲れているからなのだろう、いまでは、母さんは車に乗るとすぐに眠ってしまう。
それからどれぐらい走ったのか、はっきり覚えていないけれど、目的地に着いたとき、空はまだ暗かった。
それでも、その市場には、商品を準備する人たちが大勢いた。
都会の市場は、なんて賑やかなんだろう!
突然、騒がしく言い争う人たちの声が聞こえた。母さんは言った。「商売のために、場所争いをしているんだよ。見てはいけないよ」
何人かの人たちが母さんに挨拶をしに来て、親しく話をしていった。おそらく、母さんがよく話してくれた、親切な人たちなのだろう。
市場の外れにしゃがんで、商売を始めて間もなく、突然、警笛の音が響き渡った。
すると、母さんと同じような露天商の人たちが、いっせいに走り出した。
母さんもわたしの手を引いて走ったけれど、間に合わなかった。
青い制服を着た人たちが(いまでは、その人たちが都市秩序管理局の役人だということが、やっとわかった)、ニッパヤシの入った母さんのカゴや量りを取り上げた。そして他の露天商の品物と一緒に、三輪自動車に詰め込んで、持ち去ってしまった。
母さんは、わたしの手をつかんで、泣きながら走った。そして、許してくれるように頼み込んだ。
母さんが泣いているのを見て、わたしも一緒に泣いてしまった。
おそらく、取り上げられた品物は、普通の人たちにとっては、何ということもないものなのだろう。でも、わたしたち母子のような貧しい人にとっては、生計を立てていくための、なけなしの元手のすべてなのだ…。
他の人たちと一緒に、わたしたち母子は、事務所まで走って行った。そこは少し広い部屋で、多くの品物が置かれていた(すべて、青い制服の人たちが集めたものだ)。
みんなは、母さんを助けてくれるように、頼み込んでくれた。
役人のおじさんたちは、取り上げた品物を母さんに返して、もう露天で商売をしてはいけないと諭した。
母さんはお礼を言い、ニッパヤシのカゴを担いで、わたしの手を引いていき……、そして商売を再開した(だって、商売をしなかったら、生きていけないのだから)。
市場の周りでは商売ができなくなってしまったので、母さんはわたしを連れて狭い路地に入っていった。
母さんが言ったとおり、そこには人がいなかったけれど、少しすると、とっても混雑してきた(深呼吸したいくらい)。
恐ろしい風貌の人たちもいた。身体には異様な刺青があって、うつろな目つきをして、手には注射針が握られていた。
母さんは、見てはいけないとわたしに諭した。
以前わたしは、麻薬中毒の人たちは、薬を買うお金を手に入れるためなら何でもする、強盗や殺人だって辞さない、という話を聞いていた。
でも、母さんは堂々と、ニッパヤシの実を彼らにも売った。
恐ろしかったけれど、母さんは平然とした顔をしていた。
ザーッとスコールが降ってきた。その人たちは、すばやく家に逃げ込んでいった。
母さんは急いでわたしの手を取り、路地の中の、お茶を出す店の軒下に逃げ込んだ。
雨足はとっても強かった。母さんはビニール袋を取り出して、わたしの身体にかぶせてくれたけれど、そのときわたしは恐ろしく寒かった。
それでも、母さんは毎日商売に出なければならないんだ…。
母さんと一緒に商売に行った、たった1日の経験を通して、わたしはそれがどれほど大変で、危険に満ちた仕事であるかを理解した。
姉妹にその話をすると、みんな心配して、もう遠くまで仕事に行かないように、母さんに頼み込んだ。でも、そんなこと、できるはずがない。
それからあとの日々は、わたしたち姉妹にとって、とっても気がかりで不安な毎日になった。
来る日も来る日も、朝から夕方まで落ち着かずにそわそわし、母さんが早く家に、わたしたちのところに帰ってきてくれるように祈っていた。
お天道さまは、まだわたしたちを愛してくれていた。
それから何年か後、ある人の助けで、家から遠くない場所を貸してもらえるようになった。
母さんは、干物やライスペーパーなどを借り入れて、商売の元手にした。
その頃、わたしはよく母さんの商売のお手伝いをしたけれど、仲のよい男の子が、いつも手伝いに来てくれていた。それで、2人の仲についての大げさなうわさを、みんなに立てられたのを覚えている(それとこれは別の話よ。2人の間には、なんにも、な・か・っ・た・の…。この話は、もうやめたほうがいいわね…)。
ここでの商売も、やっぱり苦労が多かった。
夜遅くまでの仕事、腰が痛くなったり、雨や風に見舞われたり…(大雨のときには、誰かの家の軒下で雨宿りさせてもらった。雨粒が、激しく叩きつけていた。それでも、焼きライスペーパーを買いに来てくれる人がいた。そのときには、誰かが上になって雨を防いで、下にいる人がライスペーパーを焼き、お客さんが持ち帰れるようにビニール袋に入れて渡した)。
それでも、母さんが遠くまで露天商に出ていたときよりは、ずっと楽だった。
時間はまた流れていき、母さんは市場で豚肉を売る仕事をもらった。
それは、その頃にでき始めたばかりの「チョムホム(うづくまる)市場」と呼ばれる非公認の露天市場で、ときどき「青い制服の人たち」に品物を没収されては返してもらいに行く、ということがあった。
やがて、母さんはある人の家の庭を貸してもらい、そこで商売をするようになった。それで、ようやく落ち着いて仕事ができるようになった。
その「チョムホム」市場は、いま、正式な市場よりもずっと賑わっている。
やがて、母さんは豚肉を売る仕事をやめたけれど、ブン(米麺)、豆腐、バインテット、おこわ、お茶、バインボー(もち米のお菓子)、それに袋茸や唐辛子まで、手当たり次第何でも売っていた。
ときどき、母さんは、お年寄りたちから野菜を買い取って、それを売ってあげていた(とても古くなった豆の葉っぱを母さんに売ったおじいさんもいた。母さんはそれも売ろうとしたけれど、誰も買わなかったわね)。
しばし話をすると、友人は言った。「お母さんは本当にすばらしいね」。
わたしは嬉しくて笑った。「みんなそう言ってくれるのよ」。
そう、小さい頃から今まで、わたしはその言葉を何度も何度も聞いてきた。
わたしは知っている。5人の子どもを育てるために、母さんがどれほどの苦労を味わってきたかということを。病気のときは、いちばん大変だった。
わたしたちがご飯を食べたり、服を着たり、勉強をしてきたお金は、どれもみんな、母さんの-かつて露天商をしてきた人の-、汗と涙の結晶なのだ。
いま、わたしの家族の暮らしは、以前と比べると、とってもよくなっている。
生活は安定して、母さんは楽しく仕事を続けている。
時間は流れていき、あらゆることが変わっていくかもしれない。でも、わたしの心の中で、かつての母さんの記憶は、決して色褪せることはないだろう。
もし、「お母さんは何の仕事をしているの?」と誰かに聞かれたら、わたしはこう答えるだろう。「いま、母さんは市場で働いてるの。でも、以前は露天商をしていたのよ」と。
わからない単語が多くて苦労しましたが、頑張って日本語に訳しました。
Tさんの家族は、カンザー郡ビンカン村に住んでいます。ここは、ホーチミン市中心部からそれほど遠くない場所ですが、ドンナイ川という大きな川で隔てられていて、フェリーを使わないと行くことができません(近い将来、橋がかかる予定だと聞いています)。
Tさんのお父さんは早く亡くなり、お母さんが「ban hang rong」(天秤棒などで品物を担いで、露天で商売する)の仕事で生計を立て、5人の子どもたちを育ててきました。
そのお母さんの仕事ぶりや、お母さんに対するTさんの思いを綴ったのが、この文章です。
子ども時代のある日、Tさんは、お母さんと一緒に都会に商売に行くという体験をします。
午前3時ごろ、Tさんは、ニッパヤシの実を担いだお母さんに手を引かれて家を出ます。
街へ向かう途中、川の真ん中で渡し舟のエンジンが止まってしまったり、市場のそばで商売を始めると、役人の取締りを受けて売り物を没収されてしまったり、麻薬中毒の人たちに品物を売ったり、激しいスコールに見舞われて寒さに震えたり…、そんな波乱に満ちた1日(でも、お母さんにとってはごく普通の1日)が、Tさんの目を通して生き生きと描写されています。
「露天商」という仕事は、ベトナム社会の中で、どちらかというと差別されるというか、軽く見られているのでは、と思います。取締りの対象になることも少なくありません。
でも、その仕事で自分たちを育ててくれたお母さんに対して、Tさんは感謝と強い誇りを感じています。
「お母さんの仕事は?」と聞かれたら、「いまは市場で働いていますが、以前は露天商をしていました」と答えるでしょう、というくだりで、この文章は結ばれています。
前置きが長くなりました。拙い翻訳なので、原文の雰囲気がうまく表せていませんし、誤訳も多々あると思います。
ベトナム語を読める方は、ぜひ原文を読んでみて下さい(ベトナム語がわからない方も、雰囲気だけでも…)。
http://vn.360plus.yahoo.com/htt_759/article?mid=269&prev=64&next=219
母さんの仕事
今日、友人がわたしに聞いた。「3月8日(女性の日)は、どこか遊びに行く予定はある?」
わたしは答えた。「いつもの年と同じよ。わたしは家にいて、母さんと一緒に過ごすの」
友人は続けて聞いた。「お母さんは、何の仕事をしているの?」
そういえば、知り合ってずいぶん長くなるのに、友人にそのことを質問されるのは初めてのことだ(もっとも、わたしの方も同じようなものね)。
それから2人は、自分の家族について語り始めた。
わたしの父さんは、早く亡くなった。母さんは、30歳を過ぎたばかりのときから、たった1人で、5人の子どもたちを養わなければならなかった。
そのことを知って、友人は、母さんの仕事について、とても興味を持ったようだった。
わたしは、母さんについて話した。
母さんは、とても小さな頃から、おじいさんと一緒に、川で漁網を引く仕事をしていた。
それは危険に満ちたものだった。強盗やワニが現れたり、ときには人の死体まで流れてくることもあった。その頃、国はまだ平和になっていなかったからね。
母さんは、小さなときから賢い子だった。だからこそ、父さんのお父さん(父方のおじいさん)は、母さんを父さんに引き合わせた。誰もが冗談だろうと思っていたことが、現実になった。
やがて、母さんは父さんと一緒に家庭を持った。そして、毎日、家でさまざまな食べ物を売るようになった。
それはバインミーティット(ベトナム風のサンドウィッチ)だったり(その頃は、みんなフランスパンを「豚小屋」風に並べて売っていた。それがとても面白くて、わたしはいつも進んでパンを並べる仕事をしたのを覚えている)、バインクオン(水餃子に似た食べ物)やサトウキビジュースだったりした。
サトウキビジュースを売る手押し車は、2番目の姉さんがよく中に潜り込んで遊ぶ場所だった。悪い癖で、ジュースを啜っていたのね。あるとき、姉さんは手押し車の中に入ったまま眠ってしまった。母さんは姉さんを捜したけれど見つからず、泣いてしまったことがあった。
その後、母さんはいろいろな日用品を売るようになった。
それは、母さんにとっていちばん幸せな時間だった。心優しい、愛する夫を持ち、幼い子どもたちの世話をして過ごす時間…。
でも、そのささやかな幸せは、13年足らずで終わった。
父さんが永遠に旅立ってしまった。
本当にあっけなく、あまりにも突然に訪れた別れに、誰もが呆然とし、嘆き悲しんだ。
そのときから、母さんの人生は、苦難に満ちた新しい1ページが始まった。
5人の子どもは、いちばん大きな子が12歳、いちばん小さな子は、まだ3ヶ月だった。
すべての重荷が、母さんの肩にのしかかった。
間もなく借金がふくらんでいき、毎日、借金取りが家に来るようになった。彼らは、来るたびに家財道具を叩き壊し、脅し文句を吐き捨てていった。
わたしたち母子は、崩れかけた家の中で、お互いに抱き合って泣くことしかできなかった。
もう家で日用品を売ることはできなくなり、母さんは生計を立てるために家を離れて仕事をしなければならなかった。母さんは、露天商となり、品物を担いで売り歩くようになった。
わたしたち姉妹は、母さんが早朝に家を出て、夕方になってやっと帰ってくるのを見ていた。
母さんの疲れた表情から、大変な仕事だということが感じられたけれど、それがどのような苦労なのか、本当のことは何もわかっていなかった。
なぜなら、遠い場所での露天商について、母さんはいつも楽しい話ばかりをわたしたちに聞かせてくれていたから。
「都会ってのは、とってもおかしなところなんだよ。どの家も戸を閉めてしーんとしているもんだから、母さんは、ここには誰もいないんだと思った。でも、呼び込みをすると、どこかから人が大勢出てくるんだよ」
「都会の露天商の人たちは、とっても気が荒いのさ。彼らは、商売の場所を取るために、よく喧嘩をするんだ。でもね。母さんはここに来たばかりの新入りだから、いつも場所を譲ってもらったり、助けてもらったりしている。きっと、父さんが見守ってくれているんだね」
母さんがそのような楽しい話をしてくれていたので、わたしたちは、母さんの仕事は体力的にきついだけで、危険な目に遭わなければならない仕事だとは思っていなかった。ある日の出来事までは。
その日、どうして母さんがわたしを連れて商売に出ることになったのか、覚えていない。おそらく、わたしを病院に連れて行くためだったのかもしれない。
わたしのような子どもには、母さんに連れられて都会に出るのは、めまいがするようなことだった。都会がどんなに美しい場所であるかを、目にできるのだ…。
その日の未明、午前3時ごろ、母さんはわたしを連れて行くために、起こしてくれた。
母さんの片手には、10キロほどの(と母さんは言った)ニッパヤシの実を入れたカゴを提げ、もう一方の手には量りやビニール袋、そしてわたしの手を引いて家を出た。
木の葉がざわざわと騒ぎ立てる、暗くてさびしい夜道を通って(いまでは、その道は明るく、賑わっている。それに、遠いというほどの距離でもないのに、そのときのわたしは、恐ろしく遠い道のりだと感じていた)、わたしと母さんは船着場に着いた。
多くの人たちと一緒に、小さな渡し舟に、積み重なるように乗り込んだ。
はじめのうちは、何でもなかったけれど、川の真ん中に達したところで、突然エンジンが止まってしまい、船は漂い始めた。そして、みんなが騒ぎ出した。
「まいったな。海まで流されてしまうぞ」
「船頭は、酒を飲んでデタラメな操縦をしてるじゃないか。なんて無責任なやつだ!」
「明かりを灯せ。他の船に助けてもらうんだ」
幸い、船はエンジンがかかって、再び走り始めた。
でも、ほっとする間もなく、大きな波がやってきた。渡し舟は高い波に乗り上げると、いきなり谷間に落ちていく。
目の前には、大きな水しぶき(わたしは、いまも時々、このときのことを夢に見るの)。水が、浴びるように身体に降りかかった。
そのとき、わたしは母さんに抱きついて、恐ろしさで泣くことしかできなかった。
そして初めて理解した。毎日、母さんはこんなにも危険な思いをして、仕事に出かけているんだということを。
それでも、ようやく岸に上がることができた。よかった!
母さんとわたしは、先に進んだ。
「ブージョー」という車に乗ると(みんなこんな風に呼んでいた。その車を、正確にはなんて言うのか、わからないの)、母さんはすぐに眠ってしまった。
父さんがまだ生きていたとき、母さんは車酔いをしてしまって、どこにも出かけられなかったのを覚えている。
でも、たぶんとても疲れているからなのだろう、いまでは、母さんは車に乗るとすぐに眠ってしまう。
それからどれぐらい走ったのか、はっきり覚えていないけれど、目的地に着いたとき、空はまだ暗かった。
それでも、その市場には、商品を準備する人たちが大勢いた。
都会の市場は、なんて賑やかなんだろう!
突然、騒がしく言い争う人たちの声が聞こえた。母さんは言った。「商売のために、場所争いをしているんだよ。見てはいけないよ」
何人かの人たちが母さんに挨拶をしに来て、親しく話をしていった。おそらく、母さんがよく話してくれた、親切な人たちなのだろう。
市場の外れにしゃがんで、商売を始めて間もなく、突然、警笛の音が響き渡った。
すると、母さんと同じような露天商の人たちが、いっせいに走り出した。
母さんもわたしの手を引いて走ったけれど、間に合わなかった。
青い制服を着た人たちが(いまでは、その人たちが都市秩序管理局の役人だということが、やっとわかった)、ニッパヤシの入った母さんのカゴや量りを取り上げた。そして他の露天商の品物と一緒に、三輪自動車に詰め込んで、持ち去ってしまった。
母さんは、わたしの手をつかんで、泣きながら走った。そして、許してくれるように頼み込んだ。
母さんが泣いているのを見て、わたしも一緒に泣いてしまった。
おそらく、取り上げられた品物は、普通の人たちにとっては、何ということもないものなのだろう。でも、わたしたち母子のような貧しい人にとっては、生計を立てていくための、なけなしの元手のすべてなのだ…。
他の人たちと一緒に、わたしたち母子は、事務所まで走って行った。そこは少し広い部屋で、多くの品物が置かれていた(すべて、青い制服の人たちが集めたものだ)。
みんなは、母さんを助けてくれるように、頼み込んでくれた。
役人のおじさんたちは、取り上げた品物を母さんに返して、もう露天で商売をしてはいけないと諭した。
母さんはお礼を言い、ニッパヤシのカゴを担いで、わたしの手を引いていき……、そして商売を再開した(だって、商売をしなかったら、生きていけないのだから)。
市場の周りでは商売ができなくなってしまったので、母さんはわたしを連れて狭い路地に入っていった。
母さんが言ったとおり、そこには人がいなかったけれど、少しすると、とっても混雑してきた(深呼吸したいくらい)。
恐ろしい風貌の人たちもいた。身体には異様な刺青があって、うつろな目つきをして、手には注射針が握られていた。
母さんは、見てはいけないとわたしに諭した。
以前わたしは、麻薬中毒の人たちは、薬を買うお金を手に入れるためなら何でもする、強盗や殺人だって辞さない、という話を聞いていた。
でも、母さんは堂々と、ニッパヤシの実を彼らにも売った。
恐ろしかったけれど、母さんは平然とした顔をしていた。
ザーッとスコールが降ってきた。その人たちは、すばやく家に逃げ込んでいった。
母さんは急いでわたしの手を取り、路地の中の、お茶を出す店の軒下に逃げ込んだ。
雨足はとっても強かった。母さんはビニール袋を取り出して、わたしの身体にかぶせてくれたけれど、そのときわたしは恐ろしく寒かった。
それでも、母さんは毎日商売に出なければならないんだ…。
母さんと一緒に商売に行った、たった1日の経験を通して、わたしはそれがどれほど大変で、危険に満ちた仕事であるかを理解した。
姉妹にその話をすると、みんな心配して、もう遠くまで仕事に行かないように、母さんに頼み込んだ。でも、そんなこと、できるはずがない。
それからあとの日々は、わたしたち姉妹にとって、とっても気がかりで不安な毎日になった。
来る日も来る日も、朝から夕方まで落ち着かずにそわそわし、母さんが早く家に、わたしたちのところに帰ってきてくれるように祈っていた。
お天道さまは、まだわたしたちを愛してくれていた。
それから何年か後、ある人の助けで、家から遠くない場所を貸してもらえるようになった。
母さんは、干物やライスペーパーなどを借り入れて、商売の元手にした。
その頃、わたしはよく母さんの商売のお手伝いをしたけれど、仲のよい男の子が、いつも手伝いに来てくれていた。それで、2人の仲についての大げさなうわさを、みんなに立てられたのを覚えている(それとこれは別の話よ。2人の間には、なんにも、な・か・っ・た・の…。この話は、もうやめたほうがいいわね…)。
ここでの商売も、やっぱり苦労が多かった。
夜遅くまでの仕事、腰が痛くなったり、雨や風に見舞われたり…(大雨のときには、誰かの家の軒下で雨宿りさせてもらった。雨粒が、激しく叩きつけていた。それでも、焼きライスペーパーを買いに来てくれる人がいた。そのときには、誰かが上になって雨を防いで、下にいる人がライスペーパーを焼き、お客さんが持ち帰れるようにビニール袋に入れて渡した)。
それでも、母さんが遠くまで露天商に出ていたときよりは、ずっと楽だった。
時間はまた流れていき、母さんは市場で豚肉を売る仕事をもらった。
それは、その頃にでき始めたばかりの「チョムホム(うづくまる)市場」と呼ばれる非公認の露天市場で、ときどき「青い制服の人たち」に品物を没収されては返してもらいに行く、ということがあった。
やがて、母さんはある人の家の庭を貸してもらい、そこで商売をするようになった。それで、ようやく落ち着いて仕事ができるようになった。
その「チョムホム」市場は、いま、正式な市場よりもずっと賑わっている。
やがて、母さんは豚肉を売る仕事をやめたけれど、ブン(米麺)、豆腐、バインテット、おこわ、お茶、バインボー(もち米のお菓子)、それに袋茸や唐辛子まで、手当たり次第何でも売っていた。
ときどき、母さんは、お年寄りたちから野菜を買い取って、それを売ってあげていた(とても古くなった豆の葉っぱを母さんに売ったおじいさんもいた。母さんはそれも売ろうとしたけれど、誰も買わなかったわね)。
しばし話をすると、友人は言った。「お母さんは本当にすばらしいね」。
わたしは嬉しくて笑った。「みんなそう言ってくれるのよ」。
そう、小さい頃から今まで、わたしはその言葉を何度も何度も聞いてきた。
わたしは知っている。5人の子どもを育てるために、母さんがどれほどの苦労を味わってきたかということを。病気のときは、いちばん大変だった。
わたしたちがご飯を食べたり、服を着たり、勉強をしてきたお金は、どれもみんな、母さんの-かつて露天商をしてきた人の-、汗と涙の結晶なのだ。
いま、わたしの家族の暮らしは、以前と比べると、とってもよくなっている。
生活は安定して、母さんは楽しく仕事を続けている。
時間は流れていき、あらゆることが変わっていくかもしれない。でも、わたしの心の中で、かつての母さんの記憶は、決して色褪せることはないだろう。
もし、「お母さんは何の仕事をしているの?」と誰かに聞かれたら、わたしはこう答えるだろう。「いま、母さんは市場で働いてるの。でも、以前は露天商をしていたのよ」と。
2011年08月12日
沖縄の枯葉剤・実態解明に向けて
QAB(琉球朝日放送)の記者の方から、9日夕方のニュースで沖縄の枯葉剤問題の特集を取り上げることを教えていただきました。
その時間、私は外出していてテレビを見られなかったのですが、あとでインターネットで見ました。
とてもわかりやすく、的確にまとめられていると思います。こちらで見ることができます。
http://www.qab.co.jp/news/2011080930040.html
私たちは、2008年の10月に、『「枯葉剤」を考える~ベトナムで 沖縄で 何か行われたのか~』と題した小さなブックレットを作りました(素人が作った、不十分なものではありますが…)。
ブックレットの「はじめに」の部分と、本文の最後の部分を、転載します。
はじめに
2007年7月9日、「北部訓練場で枯葉剤散布」というニュースが報じられました。
「1961年から62年にかけて、沖縄本島の北部訓練場などで米軍がダイオキシンを含む枯葉剤を散布。作業に当たった元米兵が、前立腺ガンなどの後遺症を米退役軍人省から認定されていた」ことが、アメリカの公文書で明らかになったという内容でした。
琉球新報・沖縄タイムス両紙とも夕刊の1面トップという大きな扱いだったので、記事をご覧になった方も多いと思います。
でも、改めて考えてみると、「枯葉剤」とは、一体どのようなものなのでしょうか。そして、現在はどのような影響が残っているのでしょうか。
私たち「ベトナム青葉奨学会沖縄委員会」は、1994年から、ベトナムの貧困家庭の生徒たちにささやかな学費援助を続けています。
私たちの支援する奨学生の約半数は、ホーチミン市の南東に位置するカンザーという地域で暮らしています。
マングローブの湿地帯の中に7つの村が点在しており、住民は沿岸漁業や塩づくり、エビの養殖、ニッパヤシの栽培などで生計を立てています。
1998年に初めてカンザーを訪ねたとき、でこぼこ道の両側に続くマングローブの広大な森に圧倒されました。
ところが、この地域の2万ヘクタールを超える広大なマングローブの森は、すべて住民の手によって植林されたのだと聞かされ、さらに驚きました。
もともと存在した森は、1960年代に米軍が散布した枯葉剤のために全滅。現在の森は、1978年以降、カマウ岬から種子を運んで、住民が一本一本植えて蘇らせたものだというのです。
2万ヘクタールというと、沖縄本島北部のヤンバルの森に匹敵するような広さです。
私たちは、カンザーの人たちの地道な営みに感動すると同時に、とても複雑な想いも抱かされました。
ベトナムで使われた枯葉剤は、私たちの暮らす沖縄の基地から運ばれていたのではないか、という噂を聞いていたからです。
「沖縄でも枯葉剤が集積・使用されていた」という新聞記事を目にして、「やはりそうだったのか」と思いました。
そして、この機会に枯葉剤について改めて勉強してみようということになりました。
これまで何度かベトナムを訪ねる中で目にしたことや、何かの折りに集めた資料などを整理して、2007年8月の定例ミーティングで「枯葉剤」についての勉強会を行いました。
そのときに痛感したのは、私たち自身、枯葉剤についていかに知らなかったか、ということでした。
北部訓練場での枯葉剤使用について報道されたあと、日本政府はアメリカに事実関係を照会、米側は「沖縄での枯葉剤使用を裏付ける証拠を有していない」と回答したそうです。
日本政府は、「この問題はこれで決着した。北部訓練場内の環境調査を米軍に求める予定はない」という立場を表明しています。
しかし、県民の生命や健康に関わる問題について、こんなに簡単に「決着した」と言ってしまってよいのでしょうか。
問題がなければそれに越したことはないのですが、いまひとつ釈然としない気持ちが残ります。
専門家でもなく、特別な情報も持たない私たちにできることは限られていますが、沖縄でベトナムと関わっているグループとして、もう少しこの問題にこだわってみよう、そのような思いもあって、2007年11月の「うないフェスティバル」と2008年5月の「第2回うないフォーラム」のさいに、元高校教諭(化学担当)の伊波義安先生に講師をお願いして、枯葉剤についての学習会を企画しました。
そして、これまでの学習をもとにして、枯葉剤に関する小さなブックレットを作ることを思い立ちました。
たいへん不十分なものですが、沖縄でも使用されていたという「枯葉剤」について考える上で、多少ともお役に立てば嬉しく思います。
思い違いや事実誤認などもあるかもしれませんので、お気づきの点がありましたら、ご指摘下さると幸いです。
(以下、本文の最後の部分)
1960年代に沖縄の米軍基地で枯葉剤の集積が行われていたこと、そしてベトナムに運ばれていったことは、ほぼ間違いないでしょう。
私たち(青葉奨学会沖縄委員会)が支援する生徒たちが暮らすカンザーなどの地域で、かつて大量に散布された枯葉剤は、やはり沖縄から運ばれていた可能性が高い、と考えざるをえません。
また、1961年から62年にかけて北部訓練場で相当量の枯葉剤散布が行われたことも、ほぼ確実でしょう。
が、それ以上の事実になると、残念ながらほとんど手がかりがないのです。
北部訓練場のあるヤンバルの森は、世界的にも貴重な生物の宝庫であると同時に、県民の水がめの森でもあります。
何よりも大切なことは、いつ、どこで、どのように枯葉剤が貯蔵され、使用されたのか、その実態を明らかにすることではないでしょうか。
日本政府は、それを徹底的に調査し、県民に対して明らかにする責任があると思います。
(転載ここまで)
今回のジョン・ミッチェルさんの講演をきっかけにして、沖縄の枯葉剤問題が改めて注目を集めました。
どうやら、北部訓練場だけでなく、沖縄の多くの基地で枯葉剤が保管・使用され、ここからベトナムに運ばれていたらしいことが明らかになってきました。
しかし、アメリカは沖縄での枯葉剤の存在について否定したままですし、まだまだわからない部分がたくさんあります。
一時的な注目で終わらせるのでなく、実態の解明に向けて、少しずつでも進んでいきたいものです
その時間、私は外出していてテレビを見られなかったのですが、あとでインターネットで見ました。
とてもわかりやすく、的確にまとめられていると思います。こちらで見ることができます。
http://www.qab.co.jp/news/2011080930040.html
私たちは、2008年の10月に、『「枯葉剤」を考える~ベトナムで 沖縄で 何か行われたのか~』と題した小さなブックレットを作りました(素人が作った、不十分なものではありますが…)。
ブックレットの「はじめに」の部分と、本文の最後の部分を、転載します。
はじめに
2007年7月9日、「北部訓練場で枯葉剤散布」というニュースが報じられました。
「1961年から62年にかけて、沖縄本島の北部訓練場などで米軍がダイオキシンを含む枯葉剤を散布。作業に当たった元米兵が、前立腺ガンなどの後遺症を米退役軍人省から認定されていた」ことが、アメリカの公文書で明らかになったという内容でした。
琉球新報・沖縄タイムス両紙とも夕刊の1面トップという大きな扱いだったので、記事をご覧になった方も多いと思います。
でも、改めて考えてみると、「枯葉剤」とは、一体どのようなものなのでしょうか。そして、現在はどのような影響が残っているのでしょうか。
私たち「ベトナム青葉奨学会沖縄委員会」は、1994年から、ベトナムの貧困家庭の生徒たちにささやかな学費援助を続けています。
私たちの支援する奨学生の約半数は、ホーチミン市の南東に位置するカンザーという地域で暮らしています。
マングローブの湿地帯の中に7つの村が点在しており、住民は沿岸漁業や塩づくり、エビの養殖、ニッパヤシの栽培などで生計を立てています。
1998年に初めてカンザーを訪ねたとき、でこぼこ道の両側に続くマングローブの広大な森に圧倒されました。
ところが、この地域の2万ヘクタールを超える広大なマングローブの森は、すべて住民の手によって植林されたのだと聞かされ、さらに驚きました。
もともと存在した森は、1960年代に米軍が散布した枯葉剤のために全滅。現在の森は、1978年以降、カマウ岬から種子を運んで、住民が一本一本植えて蘇らせたものだというのです。
2万ヘクタールというと、沖縄本島北部のヤンバルの森に匹敵するような広さです。
私たちは、カンザーの人たちの地道な営みに感動すると同時に、とても複雑な想いも抱かされました。
ベトナムで使われた枯葉剤は、私たちの暮らす沖縄の基地から運ばれていたのではないか、という噂を聞いていたからです。
「沖縄でも枯葉剤が集積・使用されていた」という新聞記事を目にして、「やはりそうだったのか」と思いました。
そして、この機会に枯葉剤について改めて勉強してみようということになりました。
これまで何度かベトナムを訪ねる中で目にしたことや、何かの折りに集めた資料などを整理して、2007年8月の定例ミーティングで「枯葉剤」についての勉強会を行いました。
そのときに痛感したのは、私たち自身、枯葉剤についていかに知らなかったか、ということでした。
北部訓練場での枯葉剤使用について報道されたあと、日本政府はアメリカに事実関係を照会、米側は「沖縄での枯葉剤使用を裏付ける証拠を有していない」と回答したそうです。
日本政府は、「この問題はこれで決着した。北部訓練場内の環境調査を米軍に求める予定はない」という立場を表明しています。
しかし、県民の生命や健康に関わる問題について、こんなに簡単に「決着した」と言ってしまってよいのでしょうか。
問題がなければそれに越したことはないのですが、いまひとつ釈然としない気持ちが残ります。
専門家でもなく、特別な情報も持たない私たちにできることは限られていますが、沖縄でベトナムと関わっているグループとして、もう少しこの問題にこだわってみよう、そのような思いもあって、2007年11月の「うないフェスティバル」と2008年5月の「第2回うないフォーラム」のさいに、元高校教諭(化学担当)の伊波義安先生に講師をお願いして、枯葉剤についての学習会を企画しました。
そして、これまでの学習をもとにして、枯葉剤に関する小さなブックレットを作ることを思い立ちました。
たいへん不十分なものですが、沖縄でも使用されていたという「枯葉剤」について考える上で、多少ともお役に立てば嬉しく思います。
思い違いや事実誤認などもあるかもしれませんので、お気づきの点がありましたら、ご指摘下さると幸いです。
(以下、本文の最後の部分)
1960年代に沖縄の米軍基地で枯葉剤の集積が行われていたこと、そしてベトナムに運ばれていったことは、ほぼ間違いないでしょう。
私たち(青葉奨学会沖縄委員会)が支援する生徒たちが暮らすカンザーなどの地域で、かつて大量に散布された枯葉剤は、やはり沖縄から運ばれていた可能性が高い、と考えざるをえません。
また、1961年から62年にかけて北部訓練場で相当量の枯葉剤散布が行われたことも、ほぼ確実でしょう。
が、それ以上の事実になると、残念ながらほとんど手がかりがないのです。
北部訓練場のあるヤンバルの森は、世界的にも貴重な生物の宝庫であると同時に、県民の水がめの森でもあります。
何よりも大切なことは、いつ、どこで、どのように枯葉剤が貯蔵され、使用されたのか、その実態を明らかにすることではないでしょうか。
日本政府は、それを徹底的に調査し、県民に対して明らかにする責任があると思います。
(転載ここまで)
今回のジョン・ミッチェルさんの講演をきっかけにして、沖縄の枯葉剤問題が改めて注目を集めました。
どうやら、北部訓練場だけでなく、沖縄の多くの基地で枯葉剤が保管・使用され、ここからベトナムに運ばれていたらしいことが明らかになってきました。
しかし、アメリカは沖縄での枯葉剤の存在について否定したままですし、まだまだわからない部分がたくさんあります。
一時的な注目で終わらせるのでなく、実態の解明に向けて、少しずつでも進んでいきたいものです
2011年08月10日
ジョン・ミッチェルさんの報告
昨日の「占領下における対話」で、ジョン・ミッチェルさんが沖縄における枯葉剤についての報告をしました。
今日(8月9日付)の琉球新報の記事を転載します。
米軍の枯れ葉剤散布問題を取材し続けている英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏が8日、沖縄キリスト教学院大学で講演した。
ミッチェル氏はベトナムでは1960~70年代のベトナム戦争で米軍が散布した枯れ葉剤による土壌汚染問題が現在も続いていると指摘。
県内米軍施設での枯れ葉剤使用に関する証言が相次いでいることを踏まえ、基地内の土壌調査をすべきだと強調した。
講演は6日に開幕した国際会議「占領下における対話(DUO)」の一環。
ミッチェル氏は在沖米軍基地の退役軍人から枯れ葉剤使用に関する証言を集めており「何千ものドラム缶に入った枯れ葉剤を見た」などの証言を紹介した。
県内の広範囲にわたる米軍基地に勤務した退役軍人らが、施設内や周辺での枯れ葉剤の散布、貯蔵、運搬などで健康被害を受けたとして米政府に被害認定を求めている。
一方、米軍は「沖縄で枯れ葉剤が使用、貯蔵された記録や資料がない」として、当時の枯れ葉剤の存在を否定し続けていることを挙げ、「ベトナム戦争時ではあらゆる物資が前線基地の沖縄を経由した。枯れ葉剤だけなかったというのは理にかなわない」と強調した。
転載ここまで
私もミッチェルさんの報告を聞いたので、何点か簡単に付け加えたいと思います。
(同時通訳の方の日本語をイヤホンで聞きながらメモしたものですので、聞き間違いをしている部分があるかもしれません)
ミッチェルさんがなぜ沖縄の枯葉剤について調べようと考えたのか、その動機を知りたいと思っていたところ、講演の最初で、次のように説明されました。
ミッチェルさんは横浜を拠点に活動していますが、主な関心は沖縄のことだそうです。あるとき、ヤンバルについての記事を発表したところ、あるアメリカの退役軍人の方から、「私はヤンバルの基地で枯葉剤を扱った。それについて話をしたい」との申し出を受け、それがきっかけで取材を進めることになったそうです。
土壌調査については、ミッチェルさん自身も、大変難しいだろうと話されていました。
枯葉剤が使われていたのは、1960年代から70年代初め。今から40年以上前のことです。亜熱帯の沖縄では、しばしば激しい雨が降り、土壌が流出します。除草のために何度か枯葉剤を使った場所で、いまも土壌からダイオキシンなどが検出される、というのは考えにくいことです。
ベトナムでも、枯葉剤が撒かれた場所の多くでは、現在では高濃度のダイオキシンなどは検出されないようです。いまも枯葉剤の汚染が残っているホットスポットは、①枯葉剤が貯蔵され、積み込みの作業などで毎日のように漏れ出していた場所。つまりかつての米軍基地。ダナン、ビエンホアなど。②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所。などということになっているようです。
沖縄の場合も、枯葉剤使用による汚染が広範囲で残っている、ということは考えにくいです。ただし、枯葉剤がどのように扱われていたかによりますが、局地的にホットスポットが存在する可能性はあると思います。
それを見つけ出すのは非常に難しいでしょうが、米軍基地では枯葉剤以外にもさまざまな危険な兵器が置かれているわけで、環境調査を要求するのはとても大切なことだと思います。
米軍がなぜ沖縄での枯葉剤の存在を否定し続けるのか、その理由についてミッチェルさんに質問しようと思いましたが、質疑応答の中で伊波洋一さんが次のように話されていました。
枯葉剤が沖縄の基地で広く貯蔵・使用されていたことを認めてしまうと、沖縄の反基地感情を強く刺激する可能性がある。そのリスクを避けるために、政治的な判断として、否定し続けているのではないか、ということです。
私としては、退役軍人への補償の範囲を限定するために、沖縄での枯葉剤の存在を否定しているのでは、と思っていましたが、なるほど、そのような政治的な判断もあるのでしょう。さすが伊波さん、と思いました。
高里鈴代さんが、「枯葉剤の輸送に関するアメリカの記録は残っていないだろうか、それを公開させることはできないか」ということをおっしゃっていました。
ミッチェルさんは、そのような記録について何度か問い合わせたが、答えはいつも「そのような記録はない」というものだった。私は横浜で生活しているので、アメリカに対してそれ以上の交渉をするのは難しい、ということでした。
ベトナムでの枯葉剤散布については、具体的な散布のルートなど、かなり詳しい記録があきらかになっているので、輸送についても何らかの記録が残っているのでは、と思います。
それを探し出すには、アメリカで協力して下さる方が必要かもしれません。
私は、沖縄で枯葉剤を散布した目的が「除草」だけだったのか、ベトナムでの本格的な使用に向けてデータを集める「実験」の目的もあったのでは、と思っています。
そこで、「沖縄の基地で枯葉剤の実験を行っていたという具体的な証言はありませんか」と、ミッチェルさんにお聞きしました。
ミッチェルさんの答えは、「実験をしていたとの証言は聞いていない」ということでした。
また、「当時は他の場所で枯葉剤の実験を行っていたので、沖縄で実験をする必要はなかったのでは、と思います」と話されていました。
この部分については、私はちょっと納得できない部分があります。ベトナムの森林とある程度気候条件が似ていて、実際にベトナムのジャングルを想定した訓練が行われていた北部訓練場は、やはり米軍にとって枯葉剤の効果を試したい場所だったのではないか、と思っています。
ただ、私の考えはただの推測ですし、いまのところ、実験に関する具体的な証言はないみたいです。
仮りに実験が行われていたとして、詳しい事情を知っていたのはある程度立場が上の人に限られるでしょうから、証言を得るのはとても難しいのかもしれません。
その他、名護の方が「80年代に、キャンプシュワーブの谷間の土地が、トラック数十台分の土砂を持ち込んで埋め立てられたことがある。何か汚染があるのではと思って土壌を持ち帰って調査をしてみたが、その時は何も見つけられなかった。でも、ひょっとすると枯葉剤との関連があるのでは」といった証言をされていました。
ミッチェルさんの取材・報告をきっかけにして、いろいろな情報が出てきています。
米軍が行った歴史的な戦争犯罪である「枯葉剤散布」に、沖縄の基地がどのように関わらせられたのか、また環境や健康に対して、どのような影響を及ぼしたのか、少しずつでも明らかにしていきたいですね。
今日(8月9日付)の琉球新報の記事を転載します。
米軍の枯れ葉剤散布問題を取材し続けている英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏が8日、沖縄キリスト教学院大学で講演した。
ミッチェル氏はベトナムでは1960~70年代のベトナム戦争で米軍が散布した枯れ葉剤による土壌汚染問題が現在も続いていると指摘。
県内米軍施設での枯れ葉剤使用に関する証言が相次いでいることを踏まえ、基地内の土壌調査をすべきだと強調した。
講演は6日に開幕した国際会議「占領下における対話(DUO)」の一環。
ミッチェル氏は在沖米軍基地の退役軍人から枯れ葉剤使用に関する証言を集めており「何千ものドラム缶に入った枯れ葉剤を見た」などの証言を紹介した。
県内の広範囲にわたる米軍基地に勤務した退役軍人らが、施設内や周辺での枯れ葉剤の散布、貯蔵、運搬などで健康被害を受けたとして米政府に被害認定を求めている。
一方、米軍は「沖縄で枯れ葉剤が使用、貯蔵された記録や資料がない」として、当時の枯れ葉剤の存在を否定し続けていることを挙げ、「ベトナム戦争時ではあらゆる物資が前線基地の沖縄を経由した。枯れ葉剤だけなかったというのは理にかなわない」と強調した。
転載ここまで
私もミッチェルさんの報告を聞いたので、何点か簡単に付け加えたいと思います。
(同時通訳の方の日本語をイヤホンで聞きながらメモしたものですので、聞き間違いをしている部分があるかもしれません)
ミッチェルさんがなぜ沖縄の枯葉剤について調べようと考えたのか、その動機を知りたいと思っていたところ、講演の最初で、次のように説明されました。
ミッチェルさんは横浜を拠点に活動していますが、主な関心は沖縄のことだそうです。あるとき、ヤンバルについての記事を発表したところ、あるアメリカの退役軍人の方から、「私はヤンバルの基地で枯葉剤を扱った。それについて話をしたい」との申し出を受け、それがきっかけで取材を進めることになったそうです。
土壌調査については、ミッチェルさん自身も、大変難しいだろうと話されていました。
枯葉剤が使われていたのは、1960年代から70年代初め。今から40年以上前のことです。亜熱帯の沖縄では、しばしば激しい雨が降り、土壌が流出します。除草のために何度か枯葉剤を使った場所で、いまも土壌からダイオキシンなどが検出される、というのは考えにくいことです。
ベトナムでも、枯葉剤が撒かれた場所の多くでは、現在では高濃度のダイオキシンなどは検出されないようです。いまも枯葉剤の汚染が残っているホットスポットは、①枯葉剤が貯蔵され、積み込みの作業などで毎日のように漏れ出していた場所。つまりかつての米軍基地。ダナン、ビエンホアなど。②なんらかの事情で、きわめて大量の枯葉剤が捨てられた場所。などということになっているようです。
沖縄の場合も、枯葉剤使用による汚染が広範囲で残っている、ということは考えにくいです。ただし、枯葉剤がどのように扱われていたかによりますが、局地的にホットスポットが存在する可能性はあると思います。
それを見つけ出すのは非常に難しいでしょうが、米軍基地では枯葉剤以外にもさまざまな危険な兵器が置かれているわけで、環境調査を要求するのはとても大切なことだと思います。
米軍がなぜ沖縄での枯葉剤の存在を否定し続けるのか、その理由についてミッチェルさんに質問しようと思いましたが、質疑応答の中で伊波洋一さんが次のように話されていました。
枯葉剤が沖縄の基地で広く貯蔵・使用されていたことを認めてしまうと、沖縄の反基地感情を強く刺激する可能性がある。そのリスクを避けるために、政治的な判断として、否定し続けているのではないか、ということです。
私としては、退役軍人への補償の範囲を限定するために、沖縄での枯葉剤の存在を否定しているのでは、と思っていましたが、なるほど、そのような政治的な判断もあるのでしょう。さすが伊波さん、と思いました。
高里鈴代さんが、「枯葉剤の輸送に関するアメリカの記録は残っていないだろうか、それを公開させることはできないか」ということをおっしゃっていました。
ミッチェルさんは、そのような記録について何度か問い合わせたが、答えはいつも「そのような記録はない」というものだった。私は横浜で生活しているので、アメリカに対してそれ以上の交渉をするのは難しい、ということでした。
ベトナムでの枯葉剤散布については、具体的な散布のルートなど、かなり詳しい記録があきらかになっているので、輸送についても何らかの記録が残っているのでは、と思います。
それを探し出すには、アメリカで協力して下さる方が必要かもしれません。
私は、沖縄で枯葉剤を散布した目的が「除草」だけだったのか、ベトナムでの本格的な使用に向けてデータを集める「実験」の目的もあったのでは、と思っています。
そこで、「沖縄の基地で枯葉剤の実験を行っていたという具体的な証言はありませんか」と、ミッチェルさんにお聞きしました。
ミッチェルさんの答えは、「実験をしていたとの証言は聞いていない」ということでした。
また、「当時は他の場所で枯葉剤の実験を行っていたので、沖縄で実験をする必要はなかったのでは、と思います」と話されていました。
この部分については、私はちょっと納得できない部分があります。ベトナムの森林とある程度気候条件が似ていて、実際にベトナムのジャングルを想定した訓練が行われていた北部訓練場は、やはり米軍にとって枯葉剤の効果を試したい場所だったのではないか、と思っています。
ただ、私の考えはただの推測ですし、いまのところ、実験に関する具体的な証言はないみたいです。
仮りに実験が行われていたとして、詳しい事情を知っていたのはある程度立場が上の人に限られるでしょうから、証言を得るのはとても難しいのかもしれません。
その他、名護の方が「80年代に、キャンプシュワーブの谷間の土地が、トラック数十台分の土砂を持ち込んで埋め立てられたことがある。何か汚染があるのではと思って土壌を持ち帰って調査をしてみたが、その時は何も見つけられなかった。でも、ひょっとすると枯葉剤との関連があるのでは」といった証言をされていました。
ミッチェルさんの取材・報告をきっかけにして、いろいろな情報が出てきています。
米軍が行った歴史的な戦争犯罪である「枯葉剤散布」に、沖縄の基地がどのように関わらせられたのか、また環境や健康に対して、どのような影響を及ぼしたのか、少しずつでも明らかにしていきたいですね。
2011年08月08日
沖縄の枯葉剤 琉球新報の報道
沖縄の枯葉剤について、昨日の琉球新報でも記事が取り上げられていました。
以下、琉球新報の記事を転載します。
60~70年代、枯れ葉剤8施設で使用
元在沖軍人、被害認定求める
1960~70年代に在沖米軍基地に駐留した元軍人ら100人以上が、猛毒のダイオキシンを含む枯れ葉剤を散布、貯蔵、運搬したことで健康被害を受けたとして、退役軍人省に被害の認定を申請していたことが6日までに分かった。
同じく枯れ葉剤による健康被害を訴えている元在沖米空軍所属の男性らが、同省の公文書などで申請の事実を確認した。
枯れ葉剤による健康被害認定申請を出した元軍人の駐留施設は、琉球新報が公文書で把握しただけでも8施設に上り、枯れ葉剤が在沖基地で広範囲に使用、貯蔵、運搬され、多くの健康被害を出した実態が浮かび上がった。
(島袋良太)
在沖米軍基地の枯れ葉剤についてはこれまで北部訓練場で使用し、前立腺がんになったとの元米軍人の訴えを退役軍人省が98年に認定した1例しか明らかになっていなかった。
枯れ葉剤は60~75年のベトナム戦争時に米軍が空中散布し、先天性異常児の出産や流産、循環器や皮膚などの病気の発生が問題になった。
自然界では分解しづらく、残留期間が長いとされ、ベトナムでは現在も土壌汚染問題が続いている。
公文書などで被害を調査したのは米ノースカロライナ州に住み、70年に泡瀬通信施設に勤務したジョー・シパラ氏(61)。
シパラ氏は勤務中、同施設への侵入者を監視しやすくするとの理由から、施設内の雑草処分のため、上官の指示で週に1度、「エージェントオレンジ(オレンジ剤)」と呼ばれる枯れ葉剤を通信設備周辺約55ヘクタールに、2週間に1度の頻度でフェンス周辺の約2ヘクタールに散布した。
その結果、自身も糖尿病や皮膚疾患になったと主張している。
退役軍人省の文書によると、枯れ葉剤の散布や運搬、貯蔵による健康被害を申請した元米軍人らが勤務していた施設は泡瀬通信施設のほかに那覇軍港、北部訓練場、キャンプ・シュワブ、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ、天願桟橋、普天間飛行場。
また枯れ葉剤問題の取材を続けている英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏はキャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、キャンプ・キンザーでも枯れ葉剤使用・貯蔵の証言があったと説明している。
転載ここまで
ジョン・ミッチェルさんによる取材をきっかけに、さまざまな新しい情報が出てきています。
今日行われた国際会議「占領下における対話」で、ミッチェルさんは沖縄の枯葉剤について報告されました。
私も参加しましたが、参加者の関心がとても高く、活発な質疑応答が行われました。
以下、琉球新報の記事を転載します。
60~70年代、枯れ葉剤8施設で使用
元在沖軍人、被害認定求める
1960~70年代に在沖米軍基地に駐留した元軍人ら100人以上が、猛毒のダイオキシンを含む枯れ葉剤を散布、貯蔵、運搬したことで健康被害を受けたとして、退役軍人省に被害の認定を申請していたことが6日までに分かった。
同じく枯れ葉剤による健康被害を訴えている元在沖米空軍所属の男性らが、同省の公文書などで申請の事実を確認した。
枯れ葉剤による健康被害認定申請を出した元軍人の駐留施設は、琉球新報が公文書で把握しただけでも8施設に上り、枯れ葉剤が在沖基地で広範囲に使用、貯蔵、運搬され、多くの健康被害を出した実態が浮かび上がった。
(島袋良太)
在沖米軍基地の枯れ葉剤についてはこれまで北部訓練場で使用し、前立腺がんになったとの元米軍人の訴えを退役軍人省が98年に認定した1例しか明らかになっていなかった。
枯れ葉剤は60~75年のベトナム戦争時に米軍が空中散布し、先天性異常児の出産や流産、循環器や皮膚などの病気の発生が問題になった。
自然界では分解しづらく、残留期間が長いとされ、ベトナムでは現在も土壌汚染問題が続いている。
公文書などで被害を調査したのは米ノースカロライナ州に住み、70年に泡瀬通信施設に勤務したジョー・シパラ氏(61)。
シパラ氏は勤務中、同施設への侵入者を監視しやすくするとの理由から、施設内の雑草処分のため、上官の指示で週に1度、「エージェントオレンジ(オレンジ剤)」と呼ばれる枯れ葉剤を通信設備周辺約55ヘクタールに、2週間に1度の頻度でフェンス周辺の約2ヘクタールに散布した。
その結果、自身も糖尿病や皮膚疾患になったと主張している。
退役軍人省の文書によると、枯れ葉剤の散布や運搬、貯蔵による健康被害を申請した元米軍人らが勤務していた施設は泡瀬通信施設のほかに那覇軍港、北部訓練場、キャンプ・シュワブ、嘉手納飛行場、ホワイトビーチ、天願桟橋、普天間飛行場。
また枯れ葉剤問題の取材を続けている英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェル氏はキャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧、キャンプ・キンザーでも枯れ葉剤使用・貯蔵の証言があったと説明している。
転載ここまで
ジョン・ミッチェルさんによる取材をきっかけに、さまざまな新しい情報が出てきています。
今日行われた国際会議「占領下における対話」で、ミッチェルさんは沖縄の枯葉剤について報告されました。
私も参加しましたが、参加者の関心がとても高く、活発な質疑応答が行われました。
2011年08月07日
「枯葉剤、沖縄の9施設で使用」
今からちょうど50年前の1961年8月10日、ベトナム中部高原地方のコントゥム省ダクトというところで、米軍による最初の枯葉剤散布が行われました。
8月10日は、ベトナムでは「枯葉剤被害者の日」とされていますが、今年は50年目の節目ということで、さまざまな行事が行われるようです。
ところで、昨日8月6日、沖縄タイムスに、沖縄での枯葉剤使用に関する記事が載りました。
以下、沖縄タイムスの記事を転載します。
枯れ葉剤9施設で使用
元在沖米軍人証言 60~70年代前半
フェンス際の除草にも
1960年代から70年代前半の米軍普天間飛行場やホワイトビーチ、キャンプ・キンザーなど県内の9米軍施設で、ベトナム戦争で使用された猛毒の枯れ葉剤(エージェント・オレンジ)を使用、貯蔵していた可能性が高いことが5日までに分かった。
北部訓練場での使用は2007年に判明しているが、広範囲な使用、貯蔵が明らかになるのは初めて。
当時、効果的な除草剤として一般県民が入手した可能性があることも分かった。
環境への影響や基地従業員などへの健康被害は未解明のままだ。
英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんが沖縄に駐留した退役軍人十数人から証言を得た。
証言によると、米本国などから沖縄に運ばれた枯れ葉剤は、多くが嘉手納基地や那覇軍港からベトナムへ輸送された。
しかし、県内の米軍基地でもフェンス際や滑走路周辺で除草剤として使われていた。
危険物との認識はなく、マスクや手袋もせず、雑草処理として散布された。
キンザーでフォークリフトの運転手をしていた退役軍人(61)は、何百ものドラム缶に入った枯れ葉剤を各地の基地に送ったと証言。
ドラム缶が割れ、液が地面に流れ、体にかかることもあった。
キャンプ桑江やシュワブ、泡瀬通信施設でも使用されたという。
ミッチェルさんは「枯れ葉剤の問題は、過去の問題ではなく、沖縄の人たちにとって現在の問題だ」と話し、米軍基地内の環境調査の必要性を訴えている。
(知念清張)
枯れ葉剤「基地内調査を」
否定し続ける米政府
ジョン・ミッチェル氏に聞く
米軍がベトナム戦争中の1961年に初めて枯れ葉剤を散布してから10日で50年。
ベトナムでの被害は広く知られているが、その補給・前線基地となった沖縄で枯れ葉剤の使用の実態については、ほとんど知られていない。
ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんは「ダイオキシンの影響は何十年後も続く。福島第1原発の放射能の問題が騒がれているが、沖縄の枯れ葉剤問題が忘れられてはいけない」と訴えている。
取材に応じ情報を提供した退役軍人の多くは60~70代で多くが体調を崩している。
「米国政府から恩給を受けて政治的な問題に発展することを嫌って口をつぐむ人も多い」が、死を身近に感じている人ほど「沖縄の人にも健康被害を与えた」と取材に協力的だった。
「通常の除草剤の10倍の効き目があった」
枯れ葉剤は米兵が恐れていたハブ除けの効果もあり、重用された。
ベトナム戦争当時によくあった「米軍の食料と地元のビールを交換するような感覚の物々交換」や、個人的売買も普通だったといい、枯れ葉剤が県民の手に渡った可能性も否定できないという。
そのころ、基地内で枯れ葉剤の扱いは「かなり雑だった」という証言が多く集まった。
1970~71年、19歳から20歳の時、キャンプ・シュワブで従軍したスコット・パートンさんは枯れ葉剤を散布中、誤って皮膚に触れることもよくあった。
また、枯れ葉剤を入れていたドラム缶は使用後はごみを焼くために使われた。
パートンさんは、枯れ葉剤の影響とみられる前立腺がんなどを患っている。
一方、米国政府は沖縄での枯れ葉剤使用について、報告書も書類もないと否定したままだ。
ミッチェルさんは「ベトナム戦争では、すべての物資が沖縄を経由した。枯れ葉剤の記録がないというのは論理的におかしい」と指摘。
退役軍人の証言とベトナムの枯れ葉剤被害と酷似する健康被害があっても否定する米国政府に、沖縄での使用を認めさせるには「基地内で土壌検査や水質調査を行うことが不可欠だ」と指摘する。
ミッチェルさんは、国際会議「占領下における対話」に参加するため来沖。
6日午前11時から、沖縄国際大学で「沖縄の枯れ葉剤」をテーマに報告する。
転載ここまで
ジョン・ミッチェルさんの地道な取材のおかげで、これまでほとんどわかっていなかった沖縄での枯葉剤使用の実態の一端が見えてきました。
今年の4月にミッチェルさんがジャパンタイムズに寄せた記事「沖縄におけるエージェントオレンジの証拠」は、こちらに載せています。
http://aobaokinawa.ti-da.net/e3350823.html
なお、「占領下における対話」のスケジュールはノロノロ台風9号の影響で大幅に変わり、ミッチェルさんの報告は、明日8月8日(月)午後2時50分から3時20分まで、沖縄キリスト教学院大学・シャローム会館で行われるそうです。
私も聞きに行こうと思っています。
8月10日は、ベトナムでは「枯葉剤被害者の日」とされていますが、今年は50年目の節目ということで、さまざまな行事が行われるようです。
ところで、昨日8月6日、沖縄タイムスに、沖縄での枯葉剤使用に関する記事が載りました。
以下、沖縄タイムスの記事を転載します。
枯れ葉剤9施設で使用
元在沖米軍人証言 60~70年代前半
フェンス際の除草にも
1960年代から70年代前半の米軍普天間飛行場やホワイトビーチ、キャンプ・キンザーなど県内の9米軍施設で、ベトナム戦争で使用された猛毒の枯れ葉剤(エージェント・オレンジ)を使用、貯蔵していた可能性が高いことが5日までに分かった。
北部訓練場での使用は2007年に判明しているが、広範囲な使用、貯蔵が明らかになるのは初めて。
当時、効果的な除草剤として一般県民が入手した可能性があることも分かった。
環境への影響や基地従業員などへの健康被害は未解明のままだ。
英国系ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんが沖縄に駐留した退役軍人十数人から証言を得た。
証言によると、米本国などから沖縄に運ばれた枯れ葉剤は、多くが嘉手納基地や那覇軍港からベトナムへ輸送された。
しかし、県内の米軍基地でもフェンス際や滑走路周辺で除草剤として使われていた。
危険物との認識はなく、マスクや手袋もせず、雑草処理として散布された。
キンザーでフォークリフトの運転手をしていた退役軍人(61)は、何百ものドラム缶に入った枯れ葉剤を各地の基地に送ったと証言。
ドラム缶が割れ、液が地面に流れ、体にかかることもあった。
キャンプ桑江やシュワブ、泡瀬通信施設でも使用されたという。
ミッチェルさんは「枯れ葉剤の問題は、過去の問題ではなく、沖縄の人たちにとって現在の問題だ」と話し、米軍基地内の環境調査の必要性を訴えている。
(知念清張)
枯れ葉剤「基地内調査を」
否定し続ける米政府
ジョン・ミッチェル氏に聞く
米軍がベトナム戦争中の1961年に初めて枯れ葉剤を散布してから10日で50年。
ベトナムでの被害は広く知られているが、その補給・前線基地となった沖縄で枯れ葉剤の使用の実態については、ほとんど知られていない。
ジャーナリストのジョン・ミッチェルさんは「ダイオキシンの影響は何十年後も続く。福島第1原発の放射能の問題が騒がれているが、沖縄の枯れ葉剤問題が忘れられてはいけない」と訴えている。
取材に応じ情報を提供した退役軍人の多くは60~70代で多くが体調を崩している。
「米国政府から恩給を受けて政治的な問題に発展することを嫌って口をつぐむ人も多い」が、死を身近に感じている人ほど「沖縄の人にも健康被害を与えた」と取材に協力的だった。
「通常の除草剤の10倍の効き目があった」
枯れ葉剤は米兵が恐れていたハブ除けの効果もあり、重用された。
ベトナム戦争当時によくあった「米軍の食料と地元のビールを交換するような感覚の物々交換」や、個人的売買も普通だったといい、枯れ葉剤が県民の手に渡った可能性も否定できないという。
そのころ、基地内で枯れ葉剤の扱いは「かなり雑だった」という証言が多く集まった。
1970~71年、19歳から20歳の時、キャンプ・シュワブで従軍したスコット・パートンさんは枯れ葉剤を散布中、誤って皮膚に触れることもよくあった。
また、枯れ葉剤を入れていたドラム缶は使用後はごみを焼くために使われた。
パートンさんは、枯れ葉剤の影響とみられる前立腺がんなどを患っている。
一方、米国政府は沖縄での枯れ葉剤使用について、報告書も書類もないと否定したままだ。
ミッチェルさんは「ベトナム戦争では、すべての物資が沖縄を経由した。枯れ葉剤の記録がないというのは論理的におかしい」と指摘。
退役軍人の証言とベトナムの枯れ葉剤被害と酷似する健康被害があっても否定する米国政府に、沖縄での使用を認めさせるには「基地内で土壌検査や水質調査を行うことが不可欠だ」と指摘する。
ミッチェルさんは、国際会議「占領下における対話」に参加するため来沖。
6日午前11時から、沖縄国際大学で「沖縄の枯れ葉剤」をテーマに報告する。
転載ここまで
ジョン・ミッチェルさんの地道な取材のおかげで、これまでほとんどわかっていなかった沖縄での枯葉剤使用の実態の一端が見えてきました。
今年の4月にミッチェルさんがジャパンタイムズに寄せた記事「沖縄におけるエージェントオレンジの証拠」は、こちらに載せています。
http://aobaokinawa.ti-da.net/e3350823.html
なお、「占領下における対話」のスケジュールはノロノロ台風9号の影響で大幅に変わり、ミッチェルさんの報告は、明日8月8日(月)午後2時50分から3時20分まで、沖縄キリスト教学院大学・シャローム会館で行われるそうです。
私も聞きに行こうと思っています。
2011年08月05日
チャンさんのこと
2ヶ月ぐらい前、奨学生たちから届いた20通ほどの手紙の中に、なつかしい名前を見つけました。
タオ・チャンさん。
9年前にカンザーのビンカン高校を卒業して、いまはホーチミン市内の会社で働いている女性です。
チャンさんは、こんな手紙をくれたのです。
「わたしの名前は、タオ・チャンです。
1995年から2001年まで、わたしは沖縄のSさんが送って下さった奨学金をいただいていました。
わたしが高校を卒業したあと、Sさんは、わたしの妹に支援を続けて下さっています。
妹は、2002年から2010年まで、奨学金をいただいています。
先日、日本で恐ろしい地震が起こったことを知って、わたしはとても胸が痛み、Sさんとご家族のことをとても心配しています。
いまわたしはこのお手紙を書いて、青葉奨学会の先生方に、Sさんとご家族に連絡を取って下さるようにお願いします。
わたしは、Sさんたちの安否と、いまどのような生活をされているのかを、とても知りたいのです。
わたしのメールアドレスは、○○○です。
わたしは、先生方からのお返事を、待ち侘びています。
わたしは何度もメールを送りましたが、うまく届かないようなので、このお手紙を書いています。
先生方のご健康をお祈りいたします。」
チャンさんの手紙は、青葉奨学会のベトナムの事務局宛のものでしたが、そこから私のところに転送されてきました。
私は以前にチャンさんの手紙を何度か翻訳していて、手書きの字にもどこか見覚えがありました。
いつもていねいな手紙を書いてくれる子で、とくに印象に残っている奨学生の1人です。
チャンさんに奨学金を送っていたSさんは、そのころ学校の先生を目指して勉強中でした。
Sさんは、2001年に私たちが企画した「遊歴越南・素顔のベトナムと出会う旅」に参加して、はじめてチャンさんの家を訪ねました。
そのときチャンさんはたしか高校3年生。チャンさんも学校の先生を目指していると聞き、「いっしょに頑張ろう」と励ましあったそうです。
その後、Sさんは見事に教員採用試験に合格して、いまは先生になっています。
チャンさんのほうは、師範大学の受験に失敗し、短大を出て会社員になったと聞きました。
家庭の事情からいって、もう一度挑戦する、ということはできなかったのだと思います。
チャンさんの手紙を受け取って、さっそく、沖縄では地震の直接の影響はなく、みんな平穏に暮らしていること、Sさんも無事であることを書いて、手紙に書かれていたアドレスに送りました。
しばらくしてもチャンさんからの返事がないため、半月ほどあとにもう一度送ってみると、チャンさんからのメールが届きました。迷惑メールに入ったりして、うまく届かなかったようです。
チャンさんのご家族は、Sさんたちの無事を知って、とても喜んでくれた様子でした。
それから何度か、チャンさんとメールのやりとりをしたのですが、先日のメールで「もし時間があったら、私のブログを見て下さい」と、ブログのアドレスを教えてくれました。
ベトナムのニュースのサイトなどは時々見ていますが、ベトナムの人が書いたブログを見るのは初めてです。
ヤフー・ベトナムが運営するブログサイト。開いてみると、記事の内容にあったBGMが流れてきたりして、かなり工夫したつくりになっています。
チャンさんのブログは、「Song de yeu thuong」というタイトルがついています。「愛するために生きる」という感じでしょうか。
読んでみると(少し難しいので、辞書を引きながらでないと読めませんが)、家族や友人のこと、ボランティア活動のことなど、とても生き生きと描かれています。
いま、チャンさんが書いた「Nghe cua me(母さんの仕事)」という記事を、少しずつ日本語に訳しています。
行商をして家族の生計を支えたお母さんの苦労や、お母さんを見つめるチャンさんの思いが詰まった文章です。
もしできれば、このブログで紹介してみたいと思います。
タオ・チャンさん。
9年前にカンザーのビンカン高校を卒業して、いまはホーチミン市内の会社で働いている女性です。
チャンさんは、こんな手紙をくれたのです。
「わたしの名前は、タオ・チャンです。
1995年から2001年まで、わたしは沖縄のSさんが送って下さった奨学金をいただいていました。
わたしが高校を卒業したあと、Sさんは、わたしの妹に支援を続けて下さっています。
妹は、2002年から2010年まで、奨学金をいただいています。
先日、日本で恐ろしい地震が起こったことを知って、わたしはとても胸が痛み、Sさんとご家族のことをとても心配しています。
いまわたしはこのお手紙を書いて、青葉奨学会の先生方に、Sさんとご家族に連絡を取って下さるようにお願いします。
わたしは、Sさんたちの安否と、いまどのような生活をされているのかを、とても知りたいのです。
わたしのメールアドレスは、○○○です。
わたしは、先生方からのお返事を、待ち侘びています。
わたしは何度もメールを送りましたが、うまく届かないようなので、このお手紙を書いています。
先生方のご健康をお祈りいたします。」
チャンさんの手紙は、青葉奨学会のベトナムの事務局宛のものでしたが、そこから私のところに転送されてきました。
私は以前にチャンさんの手紙を何度か翻訳していて、手書きの字にもどこか見覚えがありました。
いつもていねいな手紙を書いてくれる子で、とくに印象に残っている奨学生の1人です。
チャンさんに奨学金を送っていたSさんは、そのころ学校の先生を目指して勉強中でした。
Sさんは、2001年に私たちが企画した「遊歴越南・素顔のベトナムと出会う旅」に参加して、はじめてチャンさんの家を訪ねました。
そのときチャンさんはたしか高校3年生。チャンさんも学校の先生を目指していると聞き、「いっしょに頑張ろう」と励ましあったそうです。
その後、Sさんは見事に教員採用試験に合格して、いまは先生になっています。
チャンさんのほうは、師範大学の受験に失敗し、短大を出て会社員になったと聞きました。
家庭の事情からいって、もう一度挑戦する、ということはできなかったのだと思います。
チャンさんの手紙を受け取って、さっそく、沖縄では地震の直接の影響はなく、みんな平穏に暮らしていること、Sさんも無事であることを書いて、手紙に書かれていたアドレスに送りました。
しばらくしてもチャンさんからの返事がないため、半月ほどあとにもう一度送ってみると、チャンさんからのメールが届きました。迷惑メールに入ったりして、うまく届かなかったようです。
チャンさんのご家族は、Sさんたちの無事を知って、とても喜んでくれた様子でした。
それから何度か、チャンさんとメールのやりとりをしたのですが、先日のメールで「もし時間があったら、私のブログを見て下さい」と、ブログのアドレスを教えてくれました。
ベトナムのニュースのサイトなどは時々見ていますが、ベトナムの人が書いたブログを見るのは初めてです。
ヤフー・ベトナムが運営するブログサイト。開いてみると、記事の内容にあったBGMが流れてきたりして、かなり工夫したつくりになっています。
チャンさんのブログは、「Song de yeu thuong」というタイトルがついています。「愛するために生きる」という感じでしょうか。
読んでみると(少し難しいので、辞書を引きながらでないと読めませんが)、家族や友人のこと、ボランティア活動のことなど、とても生き生きと描かれています。
いま、チャンさんが書いた「Nghe cua me(母さんの仕事)」という記事を、少しずつ日本語に訳しています。
行商をして家族の生計を支えたお母さんの苦労や、お母さんを見つめるチャンさんの思いが詰まった文章です。
もしできれば、このブログで紹介してみたいと思います。
2011年08月04日
謎の唐辛子
トムヤムクンに麻婆豆腐、キムチやさまざまなカレーなど、アジアは辛い料理の宝庫だと思います。
その中で、ベトナム料理にはあまり辛いというイメージがありません。
ベトナムの代表的な辛い料理といえば、あまりたくさんは思い浮かびませんが、ブンボーフエあたりでしょうか。
牛肉や香草をのせた辛口のうどんで、私も大好きな食べ物です。
ただ、ブンボーフエなどとは比較にならない、恐ろしい辛さに、何度か遭遇したことがあります。
それは、バインミーティット。フランスパンにレバーペーストをぬり、なますやハムなどをはさみ、香草やヌオックマムをかけて食べる、ベトナム風のサンドウィッチです。
これが、格別に美味しいのです(お店によって、美味しさに差はありますが…)。
フランスが持ち込んだパンを使ってベトナム人が作り上げた、大傑作といえるでしょう。
このバインミーティット、普通は辛い料理とは考えられていないのですが、かなり厚めに輪切りされた生唐辛子が、何切れか入っていることがあります。
これをまともに口に入れてしまうと、「辛い」どころか、口の中全体がしびれて、しばしもだえ苦しむことになります。
あの絶妙な味わいのバインミーティットの中に、すべてをぶち壊してしまうようなデンジャラスなものを、どうして忍び込ませるのか、なんとも不思議でした。
唐辛子をもっと細かく刻んで、適度な辛味を加えるようにしたら、ずっと食べやすいと思うのですが…。
ベトナム人は、みんなこれを好んで食するのでしょうか。
あるとき、ベトナム人の知人がバインミーティットを買うのを見ていたら、「唐辛子は入れないで」と注文していました。
聞いてみると、ベトナム人でもバインミーティットの唐辛子は食べられない人が結構いる、ということでした。
やっぱりそうなんだ…。その後、私もバインミーティットを買う際には、唐辛子抜きを注文することにしました。
とはいえ、多数派のベトナム人は、唐辛子の入ったデンジャラスなバインミーティットを好んでいるのも事実なわけです。
先日、栄町市場にある「真南蛮・さんぴん食堂」で、「コーレーグスの来し方・行く末」と題した、唐辛子についての勉強会(?)がありました。
台湾、フィリピン、ミャンマー、ネパールの人たちが、それぞれの地域の唐辛子を使った食べ物について、話してくれました。
そのお話しのあと、ミャンマー人女性のチョチョカイさんが、激辛の島唐辛子を、ご飯と一緒に顔色も変えずに一個まるごと食べてしまうのを見ました。
私も試しに、ほんの小さなひとつまみを口に入れてみたのですが、その瞬間、激痛に襲われました。
その痛みは口の中だけでなく、鼻の下や目、おでこにまで広がり、30分近く、のたうちまわりました。
こんなものを、どうして平気で食べられるのか。チョチョカイさんによると「食べ方のコツがある」のだそうです。
なるほど、舌には辛味に敏感な場所と、そうでない場所があるわけです。
そうはいっても、これほどデンジャラスなものを平然と食べられるのは、やっぱり私の理解を超えています。
唐辛子という強烈なものを少量用いることで、料理の風味はとても豊かになります。でも、とても「少量」とは言いがたい量の唐辛子を、好んで食べる人たちもいるわけです。
やはり、強烈な刺激を楽しんでいるのでしょうか。
バインミーティットに生唐辛子を入れて楽しんでいるベトナム人も、たぶん同じ感覚なのでしょう。
まあインドに近いミャンマーの場合、おそらく辛い料理がたくさんあって、小さな頃から辛味に親しんでいるのかもしれません。
しかし、ベトナムの人たちの場合、日頃は辛い料理にそれほど馴染んでいるとも思えないのですが…。
バインミーティットの唐辛子、やっぱり私には謎です。
その中で、ベトナム料理にはあまり辛いというイメージがありません。
ベトナムの代表的な辛い料理といえば、あまりたくさんは思い浮かびませんが、ブンボーフエあたりでしょうか。
牛肉や香草をのせた辛口のうどんで、私も大好きな食べ物です。
ただ、ブンボーフエなどとは比較にならない、恐ろしい辛さに、何度か遭遇したことがあります。
それは、バインミーティット。フランスパンにレバーペーストをぬり、なますやハムなどをはさみ、香草やヌオックマムをかけて食べる、ベトナム風のサンドウィッチです。
これが、格別に美味しいのです(お店によって、美味しさに差はありますが…)。
フランスが持ち込んだパンを使ってベトナム人が作り上げた、大傑作といえるでしょう。
このバインミーティット、普通は辛い料理とは考えられていないのですが、かなり厚めに輪切りされた生唐辛子が、何切れか入っていることがあります。
これをまともに口に入れてしまうと、「辛い」どころか、口の中全体がしびれて、しばしもだえ苦しむことになります。
あの絶妙な味わいのバインミーティットの中に、すべてをぶち壊してしまうようなデンジャラスなものを、どうして忍び込ませるのか、なんとも不思議でした。
唐辛子をもっと細かく刻んで、適度な辛味を加えるようにしたら、ずっと食べやすいと思うのですが…。
ベトナム人は、みんなこれを好んで食するのでしょうか。
あるとき、ベトナム人の知人がバインミーティットを買うのを見ていたら、「唐辛子は入れないで」と注文していました。
聞いてみると、ベトナム人でもバインミーティットの唐辛子は食べられない人が結構いる、ということでした。
やっぱりそうなんだ…。その後、私もバインミーティットを買う際には、唐辛子抜きを注文することにしました。
とはいえ、多数派のベトナム人は、唐辛子の入ったデンジャラスなバインミーティットを好んでいるのも事実なわけです。
先日、栄町市場にある「真南蛮・さんぴん食堂」で、「コーレーグスの来し方・行く末」と題した、唐辛子についての勉強会(?)がありました。
台湾、フィリピン、ミャンマー、ネパールの人たちが、それぞれの地域の唐辛子を使った食べ物について、話してくれました。
そのお話しのあと、ミャンマー人女性のチョチョカイさんが、激辛の島唐辛子を、ご飯と一緒に顔色も変えずに一個まるごと食べてしまうのを見ました。
私も試しに、ほんの小さなひとつまみを口に入れてみたのですが、その瞬間、激痛に襲われました。
その痛みは口の中だけでなく、鼻の下や目、おでこにまで広がり、30分近く、のたうちまわりました。
こんなものを、どうして平気で食べられるのか。チョチョカイさんによると「食べ方のコツがある」のだそうです。
なるほど、舌には辛味に敏感な場所と、そうでない場所があるわけです。
そうはいっても、これほどデンジャラスなものを平然と食べられるのは、やっぱり私の理解を超えています。
唐辛子という強烈なものを少量用いることで、料理の風味はとても豊かになります。でも、とても「少量」とは言いがたい量の唐辛子を、好んで食べる人たちもいるわけです。
やはり、強烈な刺激を楽しんでいるのでしょうか。
バインミーティットに生唐辛子を入れて楽しんでいるベトナム人も、たぶん同じ感覚なのでしょう。
まあインドに近いミャンマーの場合、おそらく辛い料理がたくさんあって、小さな頃から辛味に親しんでいるのかもしれません。
しかし、ベトナムの人たちの場合、日頃は辛い料理にそれほど馴染んでいるとも思えないのですが…。
バインミーティットの唐辛子、やっぱり私には謎です。
2011年07月30日
地球幸福度指数
昨夜、NHKの番組を見ていたら、「世界一幸福な国」として中米のコスタリカが紹介されていました。
なんでも、イギリスのシンクタンク、ニューエコノミック・ファンデーション(新経済財団)という団体が「地球幸福度指数」という指標を考案し、その指数(2009年度)で1位になったのがコスタリカだということでした。
コスタリカといえば、生態系の豊かさや、平和憲法を持っていることなどで知られていますが、昨夜の番組では、女性にとっての幸福という視点を取り上げていて、とても興味深い内容でした。
さて、この「地球幸福度指数」は、①平均寿命、②生活満足度、③生態系フットプリントの3つで計算しているそうです。
この指数で見ると、143か国中、日本は75位、アメリカ合州国は114位になるのだそうです。
この指数では、ベトナムの幸福度はどれぐらいの位置なのだろう、日本よりもかなり上かも知れないと思って、インターネットで探したところ、ランクが見つかりました。
上位10カ国は、次の通りです。
①コスタリカ
②ドミニカ
③ジャマイカ
④グアテマラ
⑤ベトナム
⑥コロンビア
⑦キューバ
⑧エルサルバドル
⑨ブラジル
⑩ホンジュラス
中南米諸国が並ぶ中、なんとベトナムは5位に入っています。
ベトナムの場合、平均寿命はそれなりに長く、生活満足度もまあまあ、フットプリントはかなり軽いので、上位にランクされたようです。
日本よりはだいぶ上だろうと思いましたが、アジアではダントツ、世界でもトップクラスとはちょっと意外でした。
幸福度の高い国というと、私などは福祉の充実した北欧諸国をイメージするのですが、フットプリントの重さが影響して、スウェーデン53位、フィンランド57位、ノルウェー88位、デンマーク105位と、おしなべて中位から下位にランクされています。
逆に、上位は中南米諸国をはじめ、東南アジア・南アジアの国々が並んでいます。
サハラ以南のアフリカ諸国は、平均寿命の短さのため、やはりほとんどが下位に入っています。
この指数には、もちろん疑問もあります。たとえば、混乱の続くハイチ(42位)が、北欧諸国などよりも幸福度が高いというのは、ちょっとうなずけない気がします。
極端に貧しい国の場合、生態系フットプリントの低さを幸福と結びつけて考えるのは、無理があるかもしれません。
とはいえ、「環境に与えている負担」や「持続可能性」を重視したこのような指数は、とても興味深いものだと思います。
たとえば、私たち日本人が食べているエビを生産するために、ベトナムやインドネシアなど、東南アジアの海やマングローブを破壊してきた事実があります。
他国の環境を破壊するのと引き換えに手に入れた豊かさを、この指数では幸福とは認めないわけです。
幸福度指数、ベトナムが5位、日本が75位。
日本とベトナムとどちらが幸福か、なんて比べてもあまり意味がありませんが、将来に希望を持ち、生活を楽しんでいるのは、確かにベトナム人のほうがずっと多いようにも思います。
ただし、いまベトナム政府が考えている経済発展の方向を進めていくと、この地球幸福度指数で言うと、ランクが下がっていくのかもしれません。
私たちのベトナムとの関わり方や、私たち自身の暮らしについても、いろいろなことを考えさせてくれる「地球幸福度指数」です。
なんでも、イギリスのシンクタンク、ニューエコノミック・ファンデーション(新経済財団)という団体が「地球幸福度指数」という指標を考案し、その指数(2009年度)で1位になったのがコスタリカだということでした。
コスタリカといえば、生態系の豊かさや、平和憲法を持っていることなどで知られていますが、昨夜の番組では、女性にとっての幸福という視点を取り上げていて、とても興味深い内容でした。
さて、この「地球幸福度指数」は、①平均寿命、②生活満足度、③生態系フットプリントの3つで計算しているそうです。
この指数で見ると、143か国中、日本は75位、アメリカ合州国は114位になるのだそうです。
この指数では、ベトナムの幸福度はどれぐらいの位置なのだろう、日本よりもかなり上かも知れないと思って、インターネットで探したところ、ランクが見つかりました。
上位10カ国は、次の通りです。
①コスタリカ
②ドミニカ
③ジャマイカ
④グアテマラ
⑤ベトナム
⑥コロンビア
⑦キューバ
⑧エルサルバドル
⑨ブラジル
⑩ホンジュラス
中南米諸国が並ぶ中、なんとベトナムは5位に入っています。
ベトナムの場合、平均寿命はそれなりに長く、生活満足度もまあまあ、フットプリントはかなり軽いので、上位にランクされたようです。
日本よりはだいぶ上だろうと思いましたが、アジアではダントツ、世界でもトップクラスとはちょっと意外でした。
幸福度の高い国というと、私などは福祉の充実した北欧諸国をイメージするのですが、フットプリントの重さが影響して、スウェーデン53位、フィンランド57位、ノルウェー88位、デンマーク105位と、おしなべて中位から下位にランクされています。
逆に、上位は中南米諸国をはじめ、東南アジア・南アジアの国々が並んでいます。
サハラ以南のアフリカ諸国は、平均寿命の短さのため、やはりほとんどが下位に入っています。
この指数には、もちろん疑問もあります。たとえば、混乱の続くハイチ(42位)が、北欧諸国などよりも幸福度が高いというのは、ちょっとうなずけない気がします。
極端に貧しい国の場合、生態系フットプリントの低さを幸福と結びつけて考えるのは、無理があるかもしれません。
とはいえ、「環境に与えている負担」や「持続可能性」を重視したこのような指数は、とても興味深いものだと思います。
たとえば、私たち日本人が食べているエビを生産するために、ベトナムやインドネシアなど、東南アジアの海やマングローブを破壊してきた事実があります。
他国の環境を破壊するのと引き換えに手に入れた豊かさを、この指数では幸福とは認めないわけです。
幸福度指数、ベトナムが5位、日本が75位。
日本とベトナムとどちらが幸福か、なんて比べてもあまり意味がありませんが、将来に希望を持ち、生活を楽しんでいるのは、確かにベトナム人のほうがずっと多いようにも思います。
ただし、いまベトナム政府が考えている経済発展の方向を進めていくと、この地球幸福度指数で言うと、ランクが下がっていくのかもしれません。
私たちのベトナムとの関わり方や、私たち自身の暮らしについても、いろいろなことを考えさせてくれる「地球幸福度指数」です。
Posted by クアン at
00:31
│Comments(0)
2011年07月29日
さいおんスクエアとサイゴンスクエア
先日、久しぶりにモノレール牧志駅の前を通ったら、すっかり様子が変わっているのに驚きました。
大きくてきれいな建物ができていて、「SAION SQUARE」と書かれていました。
そういえば、2週間ぐらい前だったか、「さいおんスクエアがオープン」といって、ラジオなどで話題になっていたのを思い出しました。
建物の中には、公民館や飲食店、ホテルなどが入っているみたいです。久茂地にあったプラネタリウムもここに移ったとか。
私が通りかかったときは、人影はまばらだったのですが、これから賑わうといいなと思います。
ところで、「SAION SQUARE」って、どこかで見たような名前です。
そう、ベトナムのホーチミン市に、「SAIGON SQUARE」があるのです。
以前は、「SAIGON SQUARE」はレユアン通りに面した場所にあって、その中の一角に「M&Toi」という音楽カフェがありました。
私はベトナムには年に一度か二度、数日間訪ねるぐらいですが、それでも「M&Toi」には通算で4回か5回ぐらい行って、ミー・リンやクアン・リンの歌謡ショーを聴きました。
どのライブも楽しかったので、ちょっと思い出深い場所になっています。
いまでは「M&Toi」はなくなってしまい、「サイゴンスクエア」自体も、レロイ通りのあたりに移転したと聞きました。
さて、「さいおんスクエア」という名前は、言うまでもなく、18世紀前半の琉球の優れた政治家、蔡温から取られたものです。
近くに「蔡温橋」があるので、この名前になったようですが、国際通りの一角に、歴史的な人物の名前を冠した建物が誕生したのは、なかなか面白いと思います。
ベトナムでは、道路の名前などに、歴史的な人物の名前がつけられています。
歴史上、たびたび外国の侵略に苦しめられたベトナムでは、国の独立のために戦った英雄がたくさんいます。
街を歩くと、それらの英雄の名前がつけられた通りが、数多くあります。
ハイ・バー・チュン(チュン姉妹)、レ・ロイ、チャン・フン・ダオ、グエン・フエなど…。
また、レ・ホン・フォンやチャン・フー、グエン・ティ・ミン・カイなど、若くして命を落とした革命家たちの名前も、よく見かけます。
パスツールなど、医学の発展に貢献した外国人の名前も目にします。
学校の名前も、もちろん地名がつけられたものが多いのですが、人物の名前を冠した学校もたくさんあります。
ベトナム関係の本を見ていると、学校名で見たことのある名前が出てきて、「この名前は、こういう人だったのか」と思わぬ発見をすることがよくあります。
私がよく利用するホテルの近くには、「ルオン・ディン・クア小学校」というのがあって、なんとなく気になっていたのですが、何年か前に『ハノイから吹く風』という本を読んでいたら、この名前が出てきました。
なんと、著者の中村信子さんが、ルオン・ディン・クアさんのお連れ合いなのだそうです。
ルオン・ディン・クアさんは、1940年代に日本に留学していた農学者で、帰国後、北ベトナムの農業の発展に尽くした人です。
沖縄でも、「さいおんスクエア」だけでなく、「蔡温小学校」があっても面白いかもしれませんね。
そういえば那覇市内には、「天妃小学校」がありますね。天妃(媽祖)は、宋の時代に実在した黙娘という若い女性が神になったもの、と言われているそうです。まあ「天妃」の場合、人物というよりは、神様の名前というべきかもしれませんが…。
「玉城朝薫小学校」とか、「伊波普猷小学校」「山之口貘小学校」なんていう学校があったら素敵だな、と思います。
ヤマトのほうでいうと、「織田信長小学校」とか「坂本竜馬小学校」、「菅原道真小学校」など、人気のある人物名の学校があったら、入学希望者が殺到するかもしれませんね。
大きくてきれいな建物ができていて、「SAION SQUARE」と書かれていました。
そういえば、2週間ぐらい前だったか、「さいおんスクエアがオープン」といって、ラジオなどで話題になっていたのを思い出しました。
建物の中には、公民館や飲食店、ホテルなどが入っているみたいです。久茂地にあったプラネタリウムもここに移ったとか。
私が通りかかったときは、人影はまばらだったのですが、これから賑わうといいなと思います。
ところで、「SAION SQUARE」って、どこかで見たような名前です。
そう、ベトナムのホーチミン市に、「SAIGON SQUARE」があるのです。
以前は、「SAIGON SQUARE」はレユアン通りに面した場所にあって、その中の一角に「M&Toi」という音楽カフェがありました。
私はベトナムには年に一度か二度、数日間訪ねるぐらいですが、それでも「M&Toi」には通算で4回か5回ぐらい行って、ミー・リンやクアン・リンの歌謡ショーを聴きました。
どのライブも楽しかったので、ちょっと思い出深い場所になっています。
いまでは「M&Toi」はなくなってしまい、「サイゴンスクエア」自体も、レロイ通りのあたりに移転したと聞きました。
さて、「さいおんスクエア」という名前は、言うまでもなく、18世紀前半の琉球の優れた政治家、蔡温から取られたものです。
近くに「蔡温橋」があるので、この名前になったようですが、国際通りの一角に、歴史的な人物の名前を冠した建物が誕生したのは、なかなか面白いと思います。
ベトナムでは、道路の名前などに、歴史的な人物の名前がつけられています。
歴史上、たびたび外国の侵略に苦しめられたベトナムでは、国の独立のために戦った英雄がたくさんいます。
街を歩くと、それらの英雄の名前がつけられた通りが、数多くあります。
ハイ・バー・チュン(チュン姉妹)、レ・ロイ、チャン・フン・ダオ、グエン・フエなど…。
また、レ・ホン・フォンやチャン・フー、グエン・ティ・ミン・カイなど、若くして命を落とした革命家たちの名前も、よく見かけます。
パスツールなど、医学の発展に貢献した外国人の名前も目にします。
学校の名前も、もちろん地名がつけられたものが多いのですが、人物の名前を冠した学校もたくさんあります。
ベトナム関係の本を見ていると、学校名で見たことのある名前が出てきて、「この名前は、こういう人だったのか」と思わぬ発見をすることがよくあります。
私がよく利用するホテルの近くには、「ルオン・ディン・クア小学校」というのがあって、なんとなく気になっていたのですが、何年か前に『ハノイから吹く風』という本を読んでいたら、この名前が出てきました。
なんと、著者の中村信子さんが、ルオン・ディン・クアさんのお連れ合いなのだそうです。
ルオン・ディン・クアさんは、1940年代に日本に留学していた農学者で、帰国後、北ベトナムの農業の発展に尽くした人です。
沖縄でも、「さいおんスクエア」だけでなく、「蔡温小学校」があっても面白いかもしれませんね。
そういえば那覇市内には、「天妃小学校」がありますね。天妃(媽祖)は、宋の時代に実在した黙娘という若い女性が神になったもの、と言われているそうです。まあ「天妃」の場合、人物というよりは、神様の名前というべきかもしれませんが…。
「玉城朝薫小学校」とか、「伊波普猷小学校」「山之口貘小学校」なんていう学校があったら素敵だな、と思います。
ヤマトのほうでいうと、「織田信長小学校」とか「坂本竜馬小学校」、「菅原道真小学校」など、人気のある人物名の学校があったら、入学希望者が殺到するかもしれませんね。
Posted by クアン at
00:13
│Comments(0)
2011年07月23日
グエン・タック&ホン・ベト
先日東京に行ったさい、「ホン・ベト」というバンドの松島さんから、「バンドのメンバーで暑気払いをするので、よかったら遊びに来てみませんか」と声をかけていただきました。
ちょうど時間が空いていたので、練馬区の松島さんのお宅にお邪魔することにしました。
「ホン・ベト(Hon Viet)」とは、「ベトナムの魂」という意味です。
ベトナム各地の民謡や、国民的作曲家チン・コン・ソンの作品をはじめとする歌謡曲・ポップスを演奏するグループです。
ベトナム人歌手のグエン・タック(Nguyen Ngoc Bich Thach)さんと一緒に、「グエン・タック&ホン・ベト」として、東京を中心に活動しています。
「ホン・ベト」のメンバーは、すべて日本人。ギターの松島さんを中心に、デジタルホンやベース、ピアノ、ベトナムの伝統楽器ダンバウ(一弦琴)といった編成で、笛やダングエット(月琴)なども加わることがあるみたいです。
私はバンドの誰とも面識がなかったのですが、あたたかく迎えていただき、チン・コン・ソンの「Mot buoi sang mua xuan(ある春の朝)」という曲を聞かせてくれました。
地雷を踏んで亡くなった子どものことを歌った曲で、悲しくも本当に美しいメロディーです。
この歌には日本語の歌訳もあるのですが、原詩とは大きく違った内容で、恋の歌になっています(これはこれで素敵な歌ですが…)。
松島さんは、やはり元の歌の思いを伝えたいということで、原詩に近い日本語の歌詞を新しく作って、ベトナム語の歌詞と一緒に歌っています。
タックさんは、ファム・ズイの「Ba me Gio Linh(ゾーリンのお母さん)」を歌ってくれました。
抗仏戦争の時代の歌で、静かな曲調でも、すさまじい抵抗を歌った歌詞です。
以前、私はこの歌詞を翻訳してみて、あまりの内容にショックを受けたのですが、タックさんたちベトナム人にとっても、特別な思い入れのある歌のようです。
タックさんとホン・ベトの皆さんは、さまざまチャリティーコンサートやイベント、留学生たちの集まりなどで、積極的に演奏活動をされています。
私自身、ベトナムの歌を少しでも紹介したいと思って、沖縄NGOセンターの勉強会で「ベトナム歌謡の夕べ」と題した集まりを持ったり(CDやDVDを紹介しただけですが)、ごくささやかな試みをしてきました。
今回初めて、東京でベトナム人と日本人が心を合わせて、ベトナムの歌を紹介しているグループがあることを知り、とても感動しました。
その2日後、浦和の「土瑠茶(ドルチェ)」という喫茶店で、グエン・タック&ホン・ベトの小さなライブがありました。
幸運にも、沖縄に戻る飛行機に間に合う時間だったので、聴きにいくことができました。
集まった方々も、それぞれベトナムと関わりのある方々で、素敵なライブでした。
タックさんとホン・ベトの皆さんは、11月3日に文京区でコンサートを予定されているそうです。
私も、ぜひ聴きにいきたい、もし可能なら、何らかの形で少しでもお手伝いができれば、と思っています。
ちょうど時間が空いていたので、練馬区の松島さんのお宅にお邪魔することにしました。
「ホン・ベト(Hon Viet)」とは、「ベトナムの魂」という意味です。
ベトナム各地の民謡や、国民的作曲家チン・コン・ソンの作品をはじめとする歌謡曲・ポップスを演奏するグループです。
ベトナム人歌手のグエン・タック(Nguyen Ngoc Bich Thach)さんと一緒に、「グエン・タック&ホン・ベト」として、東京を中心に活動しています。
「ホン・ベト」のメンバーは、すべて日本人。ギターの松島さんを中心に、デジタルホンやベース、ピアノ、ベトナムの伝統楽器ダンバウ(一弦琴)といった編成で、笛やダングエット(月琴)なども加わることがあるみたいです。
私はバンドの誰とも面識がなかったのですが、あたたかく迎えていただき、チン・コン・ソンの「Mot buoi sang mua xuan(ある春の朝)」という曲を聞かせてくれました。
地雷を踏んで亡くなった子どものことを歌った曲で、悲しくも本当に美しいメロディーです。
この歌には日本語の歌訳もあるのですが、原詩とは大きく違った内容で、恋の歌になっています(これはこれで素敵な歌ですが…)。
松島さんは、やはり元の歌の思いを伝えたいということで、原詩に近い日本語の歌詞を新しく作って、ベトナム語の歌詞と一緒に歌っています。
タックさんは、ファム・ズイの「Ba me Gio Linh(ゾーリンのお母さん)」を歌ってくれました。
抗仏戦争の時代の歌で、静かな曲調でも、すさまじい抵抗を歌った歌詞です。
以前、私はこの歌詞を翻訳してみて、あまりの内容にショックを受けたのですが、タックさんたちベトナム人にとっても、特別な思い入れのある歌のようです。
タックさんとホン・ベトの皆さんは、さまざまチャリティーコンサートやイベント、留学生たちの集まりなどで、積極的に演奏活動をされています。
私自身、ベトナムの歌を少しでも紹介したいと思って、沖縄NGOセンターの勉強会で「ベトナム歌謡の夕べ」と題した集まりを持ったり(CDやDVDを紹介しただけですが)、ごくささやかな試みをしてきました。
今回初めて、東京でベトナム人と日本人が心を合わせて、ベトナムの歌を紹介しているグループがあることを知り、とても感動しました。
その2日後、浦和の「土瑠茶(ドルチェ)」という喫茶店で、グエン・タック&ホン・ベトの小さなライブがありました。
幸運にも、沖縄に戻る飛行機に間に合う時間だったので、聴きにいくことができました。
集まった方々も、それぞれベトナムと関わりのある方々で、素敵なライブでした。
タックさんとホン・ベトの皆さんは、11月3日に文京区でコンサートを予定されているそうです。
私も、ぜひ聴きにいきたい、もし可能なら、何らかの形で少しでもお手伝いができれば、と思っています。
2011年07月23日
「台風ダー川」からの贈り物
この夏は、街路樹のホウオウボクの赤い花が、本当に鮮やかです。
何度かこのブログでも書きましたが、ホウオウボクの花(Hoa Phuong)は、ベトナムでも大変親しまれている花で、「Hoa hoc tro(生徒の花)」とも呼ばれています。
私はホウオウボクの花を見るたびに、ベトナムのことや、青葉奨学生たちのことを思い出します。
沖縄でもベトナムでも人気のあるホウオウボクは、実は、アフリカ大陸の東にあるマダガスカル原産の木だそうです。
沖縄ではいつごろから植えられたのか、よくわかりませんが、ある知人がこんなことを話してくれました。
「私の父が亡くなる前に、『今日とても珍しい、きれいな花を見た』と言っていたのを覚えています。その花が、ホウオウボクだったんですね。父は戦後早い時期に亡くなったので、ホウオウボクも、戦後間もない時期から植えられ始めたのかもしれませんね。たくさん植えられるようになったのは、比較的最近のことだと思いますが…」
私は20年ちょっと前に沖縄に来て、それから毎年ホウオウボクを見ていますが、今年ほどきれいに咲いているのを見た記憶はありません。
ひょっとすると、この夏は、沖縄でホウオウボクが植えられて以降、最も鮮やかに花を咲かせた夏、ということになるかもしれません。
なぜ今年はこんなにホウオウボクの花がきれいなのか、こんな感じの話を聞きました。
ホウオウボクが花を咲かせ始める時期の5月に、季節外れの台風2号が来襲した。暴風によって、咲き始めた花がすべて吹き飛ばされてしまったが、生命の危機を感じとった木が、次の世代をたくさん残すために、その後いっせいに花を咲かせたのではないか…。
なるほど、確かなことはわかりませんが、大いにありそうな話だと思います。
5月下旬に来襲した台風2号は、久しぶりに本当に強烈な台風でした。風がとくに強かったのは2時間ほどでしたが、那覇空港の観測では、平均風速で40メートルに達していたようです。
この台風2号、アジアの共通名では、「Song Da(ソン・ダー)」という名前でした。ベトナム語で「ダー川」という意味です。
ダー川は、ベトナム北部を流れる大きな川です。ヒマラヤの雪融け水が源流で、水量の豊かな川として知られ、ベトナムで最大の水力発電所があることでも有名です。
「ダー川」なんていう名前がついていると、私はちょっと親しみを感じてしまったのですが、農家の方をはじめとして、相当に大きな被害をもたらした台風でした。暴風のために怪我をされた方も少なくなかったのでは、と思います。
でも、この台風が去って2ヵ月、ホウオウボクの花が、これまでに記憶にないほど鮮やかに咲き誇っています。
もしかすると、「台風ダー川」がもたらしてくれた、思いがけない贈り物なのかもしれません。
先日の台風6号で、またすべて吹き飛ばされてしまうのでは、と心配しましたが、大きな影響はありませんでした。まだしばらく、真っ赤な花が目を楽しませてくれそうです。
何度かこのブログでも書きましたが、ホウオウボクの花(Hoa Phuong)は、ベトナムでも大変親しまれている花で、「Hoa hoc tro(生徒の花)」とも呼ばれています。
私はホウオウボクの花を見るたびに、ベトナムのことや、青葉奨学生たちのことを思い出します。
沖縄でもベトナムでも人気のあるホウオウボクは、実は、アフリカ大陸の東にあるマダガスカル原産の木だそうです。
沖縄ではいつごろから植えられたのか、よくわかりませんが、ある知人がこんなことを話してくれました。
「私の父が亡くなる前に、『今日とても珍しい、きれいな花を見た』と言っていたのを覚えています。その花が、ホウオウボクだったんですね。父は戦後早い時期に亡くなったので、ホウオウボクも、戦後間もない時期から植えられ始めたのかもしれませんね。たくさん植えられるようになったのは、比較的最近のことだと思いますが…」
私は20年ちょっと前に沖縄に来て、それから毎年ホウオウボクを見ていますが、今年ほどきれいに咲いているのを見た記憶はありません。
ひょっとすると、この夏は、沖縄でホウオウボクが植えられて以降、最も鮮やかに花を咲かせた夏、ということになるかもしれません。
なぜ今年はこんなにホウオウボクの花がきれいなのか、こんな感じの話を聞きました。
ホウオウボクが花を咲かせ始める時期の5月に、季節外れの台風2号が来襲した。暴風によって、咲き始めた花がすべて吹き飛ばされてしまったが、生命の危機を感じとった木が、次の世代をたくさん残すために、その後いっせいに花を咲かせたのではないか…。
なるほど、確かなことはわかりませんが、大いにありそうな話だと思います。
5月下旬に来襲した台風2号は、久しぶりに本当に強烈な台風でした。風がとくに強かったのは2時間ほどでしたが、那覇空港の観測では、平均風速で40メートルに達していたようです。
この台風2号、アジアの共通名では、「Song Da(ソン・ダー)」という名前でした。ベトナム語で「ダー川」という意味です。
ダー川は、ベトナム北部を流れる大きな川です。ヒマラヤの雪融け水が源流で、水量の豊かな川として知られ、ベトナムで最大の水力発電所があることでも有名です。
「ダー川」なんていう名前がついていると、私はちょっと親しみを感じてしまったのですが、農家の方をはじめとして、相当に大きな被害をもたらした台風でした。暴風のために怪我をされた方も少なくなかったのでは、と思います。
でも、この台風が去って2ヵ月、ホウオウボクの花が、これまでに記憶にないほど鮮やかに咲き誇っています。
もしかすると、「台風ダー川」がもたらしてくれた、思いがけない贈り物なのかもしれません。
先日の台風6号で、またすべて吹き飛ばされてしまうのでは、と心配しましたが、大きな影響はありませんでした。まだしばらく、真っ赤な花が目を楽しませてくれそうです。
Posted by クアン at
21:00
│Comments(0)
2011年07月21日
ベトナムから原発研修生6000人?
先日、知人からちょっと気になる話を教えてもらいました。
「ベトナムから、近く6000人もの原発研修生が日本に来る」というのです。
ベトナムでは、2030年までに34基の原発を建設する予定だと聞いています。
そのうち、ニントゥアン省に計画している2基は、2014年にも着工予定だそうです。
ベトナムで多くの原発を稼動させていくためには(善し悪しは別にして)、大勢の技術者を養成する必要があるのはわかります。
それにしても、6000人とは…。それも、福島の事故の収束もままならない、この時期の日本に…。
にわかには信じられないような話で、なにかの間違いなのでは、と思いました。
確認してみると、7月3日付の産経新聞ウェブ版に、この件のニュースが載っていることがわかりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110703-00000516-san-bus_all
確かに、6000人の研修生を受け入れるということです。
私の理解では、ベトナム側の要望を日本が受け入れたというよりも、日本側の国際人材育成機構(アイムジャパン)という団体が主導して、ベトナム側に働きかけているように思えます。
それに、年間1000人、計6000人という人数…。研修生は高卒以上を条件にするとか、事前に日本語や算数の研修を受けさせる、とは書いてありますが、専門知識を持つ技術者を養成するというよりは、低賃金で原発の労働に従事させるだけ、ということにならないでしょうか。
もともと、アイムジャパンなどが行っている途上国からの研修生受け入れは、日本のバブル期の人手不足を解消するために始められた、という指摘もあります。
ネット上では、「被曝の危険が高い福島第1原発の事故処理を、ベトナム人にやらせるつもりなのでは」と懸念する声も出ているようです。
産経の記事は、こう結ばれています。
「柳澤共栄会長は「原発が建設されると周辺に商店や溶接工場などができ、産業を興すことにつながる。地域住民にとってもためになる話なので、人材の育成に努めたい」と話している。」
福島の事故を経験したあとの発言とは、とても思えないのですが…。
このような感覚を持った人たちが進めている「研修生受け入れ」。
また、共産党一党独裁が続くベトナムの場合、地域の人たちが不安を感じていても、政府の方針に逆らって異論を唱えることは極めて難しい、という事情もあります。
ベトナムでどのように研修生を募集するのかわかりませんが、もしかすると、青葉奨学生の卒業生が「日本に行けるチャンス」と考えて応募する可能性だって、あるかもしれません。いや、その可能性は少なくないように思います。
このニュース、とても他人事とは思えません。
これからの情報に注意していきたいと思います。
「ベトナムから、近く6000人もの原発研修生が日本に来る」というのです。
ベトナムでは、2030年までに34基の原発を建設する予定だと聞いています。
そのうち、ニントゥアン省に計画している2基は、2014年にも着工予定だそうです。
ベトナムで多くの原発を稼動させていくためには(善し悪しは別にして)、大勢の技術者を養成する必要があるのはわかります。
それにしても、6000人とは…。それも、福島の事故の収束もままならない、この時期の日本に…。
にわかには信じられないような話で、なにかの間違いなのでは、と思いました。
確認してみると、7月3日付の産経新聞ウェブ版に、この件のニュースが載っていることがわかりました。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110703-00000516-san-bus_all
確かに、6000人の研修生を受け入れるということです。
私の理解では、ベトナム側の要望を日本が受け入れたというよりも、日本側の国際人材育成機構(アイムジャパン)という団体が主導して、ベトナム側に働きかけているように思えます。
それに、年間1000人、計6000人という人数…。研修生は高卒以上を条件にするとか、事前に日本語や算数の研修を受けさせる、とは書いてありますが、専門知識を持つ技術者を養成するというよりは、低賃金で原発の労働に従事させるだけ、ということにならないでしょうか。
もともと、アイムジャパンなどが行っている途上国からの研修生受け入れは、日本のバブル期の人手不足を解消するために始められた、という指摘もあります。
ネット上では、「被曝の危険が高い福島第1原発の事故処理を、ベトナム人にやらせるつもりなのでは」と懸念する声も出ているようです。
産経の記事は、こう結ばれています。
「柳澤共栄会長は「原発が建設されると周辺に商店や溶接工場などができ、産業を興すことにつながる。地域住民にとってもためになる話なので、人材の育成に努めたい」と話している。」
福島の事故を経験したあとの発言とは、とても思えないのですが…。
このような感覚を持った人たちが進めている「研修生受け入れ」。
また、共産党一党独裁が続くベトナムの場合、地域の人たちが不安を感じていても、政府の方針に逆らって異論を唱えることは極めて難しい、という事情もあります。
ベトナムでどのように研修生を募集するのかわかりませんが、もしかすると、青葉奨学生の卒業生が「日本に行けるチャンス」と考えて応募する可能性だって、あるかもしれません。いや、その可能性は少なくないように思います。
このニュース、とても他人事とは思えません。
これからの情報に注意していきたいと思います。
Posted by クアン at
21:33
│Comments(0)
2011年07月12日
高江にあった「ベトナム村」
今日のQAB(琉球朝日放送)の報道番組「ステーションQ」の中で、「高江にあったベトナム村」という特集が放映されました。
高江は、自然豊かなやんばるの森に囲まれた、東村にある小さな集落。しかし周囲には米海兵隊の北部訓練場があり、さらに集落を囲むように新たなヘリパッド建設が進められています。
「ノグチゲラの繁殖期が終わり、7月から工事を再開する予定の東村高江のヘリパッド建設。10日たち、まだ動きはありません。しかし、アメリカ軍の訓練場の隣で生活をする住民の苦労は、今に始まったことではありません。
今から48年前、高江の近くに「ベトナム村」と呼ばれるアメリカ軍のゲリラ訓練施設があり、ベトナム風の家や家畜も飼われ、訓練の時には高江区民がベトナム人の役をさせられたという歴史がありました。」
北部訓練場がジャングルでの戦闘訓練に使われていることはもちろん知っていましたが、かつて「ベトナム村」があって住民がベトナム人の役までさせられていた、とは知りませんでした。
これは1964年の8月に行われたようですが、ちょうど「トンキン湾事件」が起こった時期。海兵隊の戦闘部隊がダナンに上陸する、ほぼ半年前。高等弁務官までが訓練を視察したということなので、アメリカにとって、よほど重要な訓練だったのでしょう。
沖縄の基地とベトナムの関わりについて考える上で、また現在進められているヘリパッド建設について考える上でも、必見の特集だと思います。
http://www.qab.co.jp/news/2011071229340.html
高江は、自然豊かなやんばるの森に囲まれた、東村にある小さな集落。しかし周囲には米海兵隊の北部訓練場があり、さらに集落を囲むように新たなヘリパッド建設が進められています。
「ノグチゲラの繁殖期が終わり、7月から工事を再開する予定の東村高江のヘリパッド建設。10日たち、まだ動きはありません。しかし、アメリカ軍の訓練場の隣で生活をする住民の苦労は、今に始まったことではありません。
今から48年前、高江の近くに「ベトナム村」と呼ばれるアメリカ軍のゲリラ訓練施設があり、ベトナム風の家や家畜も飼われ、訓練の時には高江区民がベトナム人の役をさせられたという歴史がありました。」
北部訓練場がジャングルでの戦闘訓練に使われていることはもちろん知っていましたが、かつて「ベトナム村」があって住民がベトナム人の役までさせられていた、とは知りませんでした。
これは1964年の8月に行われたようですが、ちょうど「トンキン湾事件」が起こった時期。海兵隊の戦闘部隊がダナンに上陸する、ほぼ半年前。高等弁務官までが訓練を視察したということなので、アメリカにとって、よほど重要な訓練だったのでしょう。
沖縄の基地とベトナムの関わりについて考える上で、また現在進められているヘリパッド建設について考える上でも、必見の特集だと思います。
http://www.qab.co.jp/news/2011071229340.html
2011年05月31日
6月定例会のお知らせ
いろいろとバタバタしてしまって、長い間ブログを更新することができませんでした。
青葉奨学会沖縄委員会の6月定例会を、次のように行います。
会員の皆様には郵便やメールでお知らせしていますが、会員以外の方の参加も大歓迎です。
今回は、年に一回の「総会」ということにします。
「総会」という名前にすると、去年もおととしも人数がとても少なかったのですが、今年は第二部で福島の方にお話しをお願いしていますので、お時間のある方、ぜひご参加下さい。
6月4日(土)午後7時より
すぺーす結(那覇市一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)にて
7時から8時 「総会」
近況報告、昨年度の活動・会計報告、役員(代表・事務局長・会計・監査)選出など
会の活動について、ご意見・ご質問がありましたら、ぜひお寄せ下さい。
また、もし「役員になりたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さい。
8時から9時 おはなし
「原発震災の中で~福島からの報告」
福島第一原発は、依然として厳しい状況が続いているようです。
影響は広い範囲に及んでいますが、とくに福島県の子どもたちの健康被害がたいへん心配されています。
そのような中で、日本からベトナムへの「原発輸出」の計画が進んでいるのも、気になります。
ご家族が福島市在住で、震災後は津波や原発被災者の支援活動に取り組んでこられた後藤さんに、福島の様子や人々の思いなどについて、お話しを伺いたいと思います。
お忙しいと思いますが、都合のつく方はぜひ気軽にお越し下さい。
また、いつも通り一品持ち寄りも歓迎します。
お問い合わせは、080-2719-4720村田まで。
青葉奨学会沖縄委員会の6月定例会を、次のように行います。
会員の皆様には郵便やメールでお知らせしていますが、会員以外の方の参加も大歓迎です。
今回は、年に一回の「総会」ということにします。
「総会」という名前にすると、去年もおととしも人数がとても少なかったのですが、今年は第二部で福島の方にお話しをお願いしていますので、お時間のある方、ぜひご参加下さい。
6月4日(土)午後7時より
すぺーす結(那覇市一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)にて
7時から8時 「総会」
近況報告、昨年度の活動・会計報告、役員(代表・事務局長・会計・監査)選出など
会の活動について、ご意見・ご質問がありましたら、ぜひお寄せ下さい。
また、もし「役員になりたい」という方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡下さい。
8時から9時 おはなし
「原発震災の中で~福島からの報告」
福島第一原発は、依然として厳しい状況が続いているようです。
影響は広い範囲に及んでいますが、とくに福島県の子どもたちの健康被害がたいへん心配されています。
そのような中で、日本からベトナムへの「原発輸出」の計画が進んでいるのも、気になります。
ご家族が福島市在住で、震災後は津波や原発被災者の支援活動に取り組んでこられた後藤さんに、福島の様子や人々の思いなどについて、お話しを伺いたいと思います。
お忙しいと思いますが、都合のつく方はぜひ気軽にお越し下さい。
また、いつも通り一品持ち寄りも歓迎します。
お問い合わせは、080-2719-4720村田まで。
2011年04月18日
「沖縄におけるエージェント・オレンジの証拠」
高里鈴代さんの知人の方から、沖縄での枯葉剤の貯蔵・使用についての情報をいただきました。
ジャパンタイムス4月12日付けに掲載されたものです。
沖縄での枯葉剤については情報が少ないので、とても重要な情報だと思います。
沖縄での枯葉剤使用の実態や汚染状況について明らかにする上で、貴重な手がかりになるかもしれません。
以下、転載します。
4/12ジャパンタイムスに米軍による沖縄での枯葉剤について記事が掲載されています。
日本語訳が送られてきたので参考まで。
オリジナル英文はここ
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20110412zg.html
2011年4月12日
「沖縄におけるエージェント・オレンジの証拠:米退役軍人たちが、その健康被害と正義の闘いを語る」
ジョン・ミッチェル
『ジャパン・タイムズ』への特別寄稿
1960年代末、ジェイムズ・スペンサーは沖縄の軍港で働く米海軍の港湾労働者だった。
「この頃、私たちはあらゆる種の積荷を扱っていました。オレンジの縞模様の入ったこの缶も含まれていました。荷下ろしのときに、それがこぼれて『エージェント・オレンジ(Agent Orange: ヴェトナム戦争時、米軍が使用した枯葉剤のひとつ)』をかぶっていたのでしょう。まさに雨を浴びるようにね」。
1965年から1967年の間、ラマー・スリートはこの島のキャンプ・クエの衛生兵だった。
「エージェント・オレンジは嘉手納(空軍基地)に貯蔵されていて、沖縄の植生管理に使用されていました。私は個人的に軍病院のグラウンドの周囲で噴霧作業班を見かけたことがあるし、服に枯葉剤が染みこんだ作業員がER(救急救命)に運び込まれたときに、その場に立ち会ったこともあります」。
1970年、ジョー・シパラは、沖縄本島中部にある泡瀬通信施設に勤務していた。
「アンテナは『ミッション・クリティカル(mission critical: 24時間365日稼働を要求される基幹的システム)』に分類されていたため、周囲に雑草が生い茂ることは許されません。数週間おきにトラックが来て、この施設のエージェント・オレンジの缶を充填していました。それを混合して境界線のフェンス周辺の雑草に噴霧するのが私の担当でした」。
『ジャパン・タイムズ』紙のためにインタビューに答えたこの3人の退役軍人だけでなく、退役軍人管理局(V.A.)の記録には、1960年代末から1970年代初頭にかけて沖縄で使用されたエージェント・オレンジについて、数百に上る同様の証言が存在する。
当時、この島は米国支配下にあり、ヴェトナムにおける米国の戦闘の前線基地としての役割を担わされていた。
これらの証言が明らかにするのは、ダイオキシンを含む枯葉剤が、戦闘地域に移送される前に、沖縄に大規模に貯蔵されていただけでなく、軍事施設の除草や、北部の山原(やんばる)のジャングルでの実験に定期的に使用されていたという事実である。
島におけるこの長期で広範囲にわたるエージェント・オレンジの使用は、それを取り扱った兵士の多くに深刻な病状をもたらした。
スペンサー、スリート、シパラは、現在、癌、2型糖尿病、虚血性心疾患など、止めどなく続くダイオキシンにまつわる症状に悩まされている。
さらに、シパラの死産となった最初の子は、赤ん坊が日の目を見なかったことを感謝するべきだと医者に言われるほどの奇形で、生誕したふたりの子どもはエージェント・オレンジによる中毒症状と合致する奇形に冒されている。
もしもかれら退役軍人たちが、ヴェトナムで[枯葉剤を]浴びていたならば、米国政府は有害な枯葉剤に接したすべての兵士を承認しているため、V.A.による医療費の補助を受けることができただろう。
しかし、かれらは沖縄で被害に晒されたために、その補償要求は、この島でのエージェント・オレンジの存在を認めない国務省のために、繰り返し拒絶されてきた。
2004年7月、統合参謀本部議長リチャード・マイヤーズ大将が、政府の「記録には沖縄におけるエージェント・オレンジやその他の枯葉剤の貯蔵や使用を裏付ける情報は一切ない」と発表したのは、こうした姿勢を示すもっとも最近の一例である。
このような否定のために米退役軍人がV.A.から補償を勝ち取るのが困難になっている。
シパラの例は、退役軍人が向き合う困難を如実に示している。
彼の軍命令書は、当時かれが沖縄に駐留していたことを示しているし、彼の病歴は、ダイオキシン被曝の症例に合致する。
バイクに乗ってエージェント・オレンジの缶の横を通り過ぎる彼の写真は、決定的証拠として、彼のケースが退役軍人たちを代表すべきことを物語っている。
11ヶ月に及ぶ協議の後、V.A.は、二つの根拠を挙げてシパラの要求を拒絶した。
第一に、被曝によって病気が進行したという証拠がない。
シパラはこれに反論している。「沖縄から帰還した直後に糖尿病を発症したことは、私の医療記録から明らかです。なぜその当時の医者は、それがエージェント・オレンジによるものだと言わなかったのでしょうか。それが1970年のことで、まだ誰も被曝の危険性についてよく知らなかったからです。」
第二に、V.A.は、「日本の沖縄における、あなたの隊の兵員による、エージェント・オレンジの噴霧、試験、貯蔵に関するいかなる証拠も見つけることができなかった」と言った。
この言葉は、V.A.が却下する際に共通の表現で、そのことが、シパラを困惑させた。
「記録がないからという理由で、どうして却下しつづけられるのか、理解できない。だれでも枯葉剤を使っていた沖縄で、1998年裁定が当てはまるのは限られたひとつの例だけだなどと誰が信じると思うのか。」
シパラが言っているV.A.の裁定というのは、2007年に報告され世界的なニュースになったものだ。
1998年1月付けで、1961年から62年の間に沖縄の路肩に噴霧しトラックで運搬したエージェント・オレンジを浴びたと主張した退役軍人の事件に関する1998年1月付けの裁定のことである。兵士はそのために前立腺癌を患った。
V.A.は、「この退役軍人が沖縄で軍務中にダイオキシンに晒された可能性を根拠づける信頼できる証拠がある」と退役軍人の側に立つ結論を出したのである。
この裁定は、最終的に米軍がこの島でエージェント・オレンジを使用したことを認める道を拓くだろうという期待をもたらした。
今日に至って、しかし、1998年裁定は、沖縄駐留軍人のうちただひとつの成功例にとどまっている。
何年にもわたってV.A.は、先の決定は判例として確立していないと、何百という同様の要求を却下している。
2010年のある却下の文書には、「それぞれの事件は、個別の事実に基づいて決定される」なる文言が書かれていた。
しばしば、V.A.は、エージェント・オレンジの使用に関して手書きの文書証拠を求める。
そのような文書は、しかし、追求不可能であることが判る。化学品を浴びた兵士の入院記録が事件直後にいかに紛失するものか、スリートはよく知っている。
シパラは、「手書きの命令書など存在しない。我々は何をしろと口頭で言われ、それをしたのだ。国防省は起こったことを簡単に忘れることができるような仕組みになっているんだ」と言い足した。
当時の軍事行動の機密度が、退役軍人が沖縄についての情報を入手することをいっそう困難にしている。
たとえば、1960年代を通じて、アメリカが生物化学兵器を貯蔵していただろうと沖縄住民は考えてきた。
しかし当局は1969年になって、神経ガスが漏れ23名の米兵が負傷するまで、この主張を認めなかった。
この事件をめぐる国際的な非難の高まりを背景に、軍は、レッドハット作戦を実行した。
1万2000トンもの毒ガス兵器を沖縄から太平洋の真ん中にあるジョンストン島へ移送する、8ヶ月に及ぶ作戦である。
退役軍人の多くは、軍が、エージェント・オレンジの備蓄の大部分もレッドハット作戦の間に同時に移送したと信じている。
かれらの推測がどうやら正しいことを示すのは、「レッドハット作戦の記録が、1969年8月から1972年3月にかけて、沖縄に枯葉剤が貯蔵され、後に廃棄されたことを示している」という2009年のV.A.の裁定だ。
マイヤーズの2004年の否定と直ちに矛盾するこのような文書は、救済を求める退役軍人をいらだたせ続けている。
しかし、楽観できる見通しもある。
2000年まで、米国政府は、軍による枯葉剤使用はヴェトナムのみだったとしてきた。
しかし、1968年から1971年にかけて、韓国の非武装地帯での使用を証拠が明らかにし、当時そこに駐留していた退役軍人にダイオキシン関連の医療費支給が認められた。
同様に、グアムにおけるエージェント・オレンジ被曝の退役軍人を支持するV.A.の裁定に引き続き、バラク・オバマ大統領は、軍隊の枯葉剤配備地域のリストにミクロネシア領を加えるよう求める圧力をかけられている。
沖縄を、この増え続けるリストに加える可能性について問われた際に、ヴェトナム戦争海軍退役軍人会の議会における代弁者であるジェフ・ディヴィスは、三方向による取り組みを実施するよう助言した。
「第一に、噴霧器を背負ったり、トラックに積み込んだり、ヴェトナムを往復する輸送船からの積み込みや積み卸し作業を補助したということを証言する個々の宣誓供述書。次に、沖縄に駐留した退役軍人の間に、エージェント・オレンジ関連と公認されている一連の疾患の罹患率が非常に高いという調査。最後に、科学的根拠、すなわち、ダイオキシンの存在を示す飲料水や土のサンプル(を集める必要がある)」。
この最後の点は、退役軍人たちに枯葉剤関連の疾病を証明できる希望の道を拓く。
しかし、それは同時に、恐ろしい予想を招来する。
ダイオキシン被曝は、現在駐留中の米兵とその家族たちにも及んでいるかもしれないということだ。
退役軍人の説明でもっとも多く言及される地域は、嘉手納空軍基地と、北部訓練場で、現在もなお、米軍の管理下に置かれ続けている場所である。
皮肉にも、このことは、危険性をアメリカ管理地域に閉じ込めることによって、沖縄の市民の大多数を、ダイオキシン被曝から守っていると言えるのかもしれない。
2009年、科学者たちは、ヴェトナムで、戦中に米国がエージェント・オレンジを貯蔵していたダイオキシン危険地帯を発見した。
正確に類推するならば、沖縄の現在の基地は、軍の枯葉剤によって重度に汚染されたままということになるだろう。
いずれにしても、政府が、かつて国に仕えた人々への義務を無視し続ける間に、V.A.に要求を拒絶され続ける何百という退役軍人たちが、いっそう病に冒され続ける日々が続くのだろうと、シパラは考えている。
「退役軍人の間では、V.A.の非公式のモットーとは『認めない、認めない、彼らが死ぬまで』だと言わ
れている。政府にかれらが行ったことを認めさせる唯一の方法は、私たちがもっとたくさん立ち上がって、世界に向けて自分たちのことを話すことだ」。
本稿発表の時点において、『ジャパン・タイムズ』のコメントの要求に対し、米国退役軍人管理局も、国防省も、無回答のままである。
沖縄とエージェント・オレンジに関する経過
1952 サンフランシスコ条約で沖縄は米国管理下に
1962 米空軍、沖縄で米の収穫に生物兵器実験
1963 米輸送船、おおよそ1万2000トンの生物化学兵器を沖縄に搬入
1969 嘉手納空軍基地で神経ガス漏れ、23人の米兵が病院へ
1971 レッドハット作戦、生物化学兵器の在庫をジョンストン島へ移送
1972 沖縄の施政権が日本へ返還される
1998 V.A.沖縄のエージェント・オレンジ被曝を主張する退役軍人に賠償
2004 米政府、沖縄におけるエージェント・オレンジを否定
2009 V.A.決定、レッドハット作戦にエージェント・オレンジが含まれていたことに言及
ジャパンタイムス4月12日付けに掲載されたものです。
沖縄での枯葉剤については情報が少ないので、とても重要な情報だと思います。
沖縄での枯葉剤使用の実態や汚染状況について明らかにする上で、貴重な手がかりになるかもしれません。
以下、転載します。
4/12ジャパンタイムスに米軍による沖縄での枯葉剤について記事が掲載されています。
日本語訳が送られてきたので参考まで。
オリジナル英文はここ
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/fl20110412zg.html
2011年4月12日
「沖縄におけるエージェント・オレンジの証拠:米退役軍人たちが、その健康被害と正義の闘いを語る」
ジョン・ミッチェル
『ジャパン・タイムズ』への特別寄稿
1960年代末、ジェイムズ・スペンサーは沖縄の軍港で働く米海軍の港湾労働者だった。
「この頃、私たちはあらゆる種の積荷を扱っていました。オレンジの縞模様の入ったこの缶も含まれていました。荷下ろしのときに、それがこぼれて『エージェント・オレンジ(Agent Orange: ヴェトナム戦争時、米軍が使用した枯葉剤のひとつ)』をかぶっていたのでしょう。まさに雨を浴びるようにね」。
1965年から1967年の間、ラマー・スリートはこの島のキャンプ・クエの衛生兵だった。
「エージェント・オレンジは嘉手納(空軍基地)に貯蔵されていて、沖縄の植生管理に使用されていました。私は個人的に軍病院のグラウンドの周囲で噴霧作業班を見かけたことがあるし、服に枯葉剤が染みこんだ作業員がER(救急救命)に運び込まれたときに、その場に立ち会ったこともあります」。
1970年、ジョー・シパラは、沖縄本島中部にある泡瀬通信施設に勤務していた。
「アンテナは『ミッション・クリティカル(mission critical: 24時間365日稼働を要求される基幹的システム)』に分類されていたため、周囲に雑草が生い茂ることは許されません。数週間おきにトラックが来て、この施設のエージェント・オレンジの缶を充填していました。それを混合して境界線のフェンス周辺の雑草に噴霧するのが私の担当でした」。
『ジャパン・タイムズ』紙のためにインタビューに答えたこの3人の退役軍人だけでなく、退役軍人管理局(V.A.)の記録には、1960年代末から1970年代初頭にかけて沖縄で使用されたエージェント・オレンジについて、数百に上る同様の証言が存在する。
当時、この島は米国支配下にあり、ヴェトナムにおける米国の戦闘の前線基地としての役割を担わされていた。
これらの証言が明らかにするのは、ダイオキシンを含む枯葉剤が、戦闘地域に移送される前に、沖縄に大規模に貯蔵されていただけでなく、軍事施設の除草や、北部の山原(やんばる)のジャングルでの実験に定期的に使用されていたという事実である。
島におけるこの長期で広範囲にわたるエージェント・オレンジの使用は、それを取り扱った兵士の多くに深刻な病状をもたらした。
スペンサー、スリート、シパラは、現在、癌、2型糖尿病、虚血性心疾患など、止めどなく続くダイオキシンにまつわる症状に悩まされている。
さらに、シパラの死産となった最初の子は、赤ん坊が日の目を見なかったことを感謝するべきだと医者に言われるほどの奇形で、生誕したふたりの子どもはエージェント・オレンジによる中毒症状と合致する奇形に冒されている。
もしもかれら退役軍人たちが、ヴェトナムで[枯葉剤を]浴びていたならば、米国政府は有害な枯葉剤に接したすべての兵士を承認しているため、V.A.による医療費の補助を受けることができただろう。
しかし、かれらは沖縄で被害に晒されたために、その補償要求は、この島でのエージェント・オレンジの存在を認めない国務省のために、繰り返し拒絶されてきた。
2004年7月、統合参謀本部議長リチャード・マイヤーズ大将が、政府の「記録には沖縄におけるエージェント・オレンジやその他の枯葉剤の貯蔵や使用を裏付ける情報は一切ない」と発表したのは、こうした姿勢を示すもっとも最近の一例である。
このような否定のために米退役軍人がV.A.から補償を勝ち取るのが困難になっている。
シパラの例は、退役軍人が向き合う困難を如実に示している。
彼の軍命令書は、当時かれが沖縄に駐留していたことを示しているし、彼の病歴は、ダイオキシン被曝の症例に合致する。
バイクに乗ってエージェント・オレンジの缶の横を通り過ぎる彼の写真は、決定的証拠として、彼のケースが退役軍人たちを代表すべきことを物語っている。
11ヶ月に及ぶ協議の後、V.A.は、二つの根拠を挙げてシパラの要求を拒絶した。
第一に、被曝によって病気が進行したという証拠がない。
シパラはこれに反論している。「沖縄から帰還した直後に糖尿病を発症したことは、私の医療記録から明らかです。なぜその当時の医者は、それがエージェント・オレンジによるものだと言わなかったのでしょうか。それが1970年のことで、まだ誰も被曝の危険性についてよく知らなかったからです。」
第二に、V.A.は、「日本の沖縄における、あなたの隊の兵員による、エージェント・オレンジの噴霧、試験、貯蔵に関するいかなる証拠も見つけることができなかった」と言った。
この言葉は、V.A.が却下する際に共通の表現で、そのことが、シパラを困惑させた。
「記録がないからという理由で、どうして却下しつづけられるのか、理解できない。だれでも枯葉剤を使っていた沖縄で、1998年裁定が当てはまるのは限られたひとつの例だけだなどと誰が信じると思うのか。」
シパラが言っているV.A.の裁定というのは、2007年に報告され世界的なニュースになったものだ。
1998年1月付けで、1961年から62年の間に沖縄の路肩に噴霧しトラックで運搬したエージェント・オレンジを浴びたと主張した退役軍人の事件に関する1998年1月付けの裁定のことである。兵士はそのために前立腺癌を患った。
V.A.は、「この退役軍人が沖縄で軍務中にダイオキシンに晒された可能性を根拠づける信頼できる証拠がある」と退役軍人の側に立つ結論を出したのである。
この裁定は、最終的に米軍がこの島でエージェント・オレンジを使用したことを認める道を拓くだろうという期待をもたらした。
今日に至って、しかし、1998年裁定は、沖縄駐留軍人のうちただひとつの成功例にとどまっている。
何年にもわたってV.A.は、先の決定は判例として確立していないと、何百という同様の要求を却下している。
2010年のある却下の文書には、「それぞれの事件は、個別の事実に基づいて決定される」なる文言が書かれていた。
しばしば、V.A.は、エージェント・オレンジの使用に関して手書きの文書証拠を求める。
そのような文書は、しかし、追求不可能であることが判る。化学品を浴びた兵士の入院記録が事件直後にいかに紛失するものか、スリートはよく知っている。
シパラは、「手書きの命令書など存在しない。我々は何をしろと口頭で言われ、それをしたのだ。国防省は起こったことを簡単に忘れることができるような仕組みになっているんだ」と言い足した。
当時の軍事行動の機密度が、退役軍人が沖縄についての情報を入手することをいっそう困難にしている。
たとえば、1960年代を通じて、アメリカが生物化学兵器を貯蔵していただろうと沖縄住民は考えてきた。
しかし当局は1969年になって、神経ガスが漏れ23名の米兵が負傷するまで、この主張を認めなかった。
この事件をめぐる国際的な非難の高まりを背景に、軍は、レッドハット作戦を実行した。
1万2000トンもの毒ガス兵器を沖縄から太平洋の真ん中にあるジョンストン島へ移送する、8ヶ月に及ぶ作戦である。
退役軍人の多くは、軍が、エージェント・オレンジの備蓄の大部分もレッドハット作戦の間に同時に移送したと信じている。
かれらの推測がどうやら正しいことを示すのは、「レッドハット作戦の記録が、1969年8月から1972年3月にかけて、沖縄に枯葉剤が貯蔵され、後に廃棄されたことを示している」という2009年のV.A.の裁定だ。
マイヤーズの2004年の否定と直ちに矛盾するこのような文書は、救済を求める退役軍人をいらだたせ続けている。
しかし、楽観できる見通しもある。
2000年まで、米国政府は、軍による枯葉剤使用はヴェトナムのみだったとしてきた。
しかし、1968年から1971年にかけて、韓国の非武装地帯での使用を証拠が明らかにし、当時そこに駐留していた退役軍人にダイオキシン関連の医療費支給が認められた。
同様に、グアムにおけるエージェント・オレンジ被曝の退役軍人を支持するV.A.の裁定に引き続き、バラク・オバマ大統領は、軍隊の枯葉剤配備地域のリストにミクロネシア領を加えるよう求める圧力をかけられている。
沖縄を、この増え続けるリストに加える可能性について問われた際に、ヴェトナム戦争海軍退役軍人会の議会における代弁者であるジェフ・ディヴィスは、三方向による取り組みを実施するよう助言した。
「第一に、噴霧器を背負ったり、トラックに積み込んだり、ヴェトナムを往復する輸送船からの積み込みや積み卸し作業を補助したということを証言する個々の宣誓供述書。次に、沖縄に駐留した退役軍人の間に、エージェント・オレンジ関連と公認されている一連の疾患の罹患率が非常に高いという調査。最後に、科学的根拠、すなわち、ダイオキシンの存在を示す飲料水や土のサンプル(を集める必要がある)」。
この最後の点は、退役軍人たちに枯葉剤関連の疾病を証明できる希望の道を拓く。
しかし、それは同時に、恐ろしい予想を招来する。
ダイオキシン被曝は、現在駐留中の米兵とその家族たちにも及んでいるかもしれないということだ。
退役軍人の説明でもっとも多く言及される地域は、嘉手納空軍基地と、北部訓練場で、現在もなお、米軍の管理下に置かれ続けている場所である。
皮肉にも、このことは、危険性をアメリカ管理地域に閉じ込めることによって、沖縄の市民の大多数を、ダイオキシン被曝から守っていると言えるのかもしれない。
2009年、科学者たちは、ヴェトナムで、戦中に米国がエージェント・オレンジを貯蔵していたダイオキシン危険地帯を発見した。
正確に類推するならば、沖縄の現在の基地は、軍の枯葉剤によって重度に汚染されたままということになるだろう。
いずれにしても、政府が、かつて国に仕えた人々への義務を無視し続ける間に、V.A.に要求を拒絶され続ける何百という退役軍人たちが、いっそう病に冒され続ける日々が続くのだろうと、シパラは考えている。
「退役軍人の間では、V.A.の非公式のモットーとは『認めない、認めない、彼らが死ぬまで』だと言わ
れている。政府にかれらが行ったことを認めさせる唯一の方法は、私たちがもっとたくさん立ち上がって、世界に向けて自分たちのことを話すことだ」。
本稿発表の時点において、『ジャパン・タイムズ』のコメントの要求に対し、米国退役軍人管理局も、国防省も、無回答のままである。
沖縄とエージェント・オレンジに関する経過
1952 サンフランシスコ条約で沖縄は米国管理下に
1962 米空軍、沖縄で米の収穫に生物兵器実験
1963 米輸送船、おおよそ1万2000トンの生物化学兵器を沖縄に搬入
1969 嘉手納空軍基地で神経ガス漏れ、23人の米兵が病院へ
1971 レッドハット作戦、生物化学兵器の在庫をジョンストン島へ移送
1972 沖縄の施政権が日本へ返還される
1998 V.A.沖縄のエージェント・オレンジ被曝を主張する退役軍人に賠償
2004 米政府、沖縄におけるエージェント・オレンジを否定
2009 V.A.決定、レッドハット作戦にエージェント・オレンジが含まれていたことに言及
2011年04月17日
フオックさんからの手紙
奨学生のフオックさんから、里親のOさんへの手紙が届きました。
フオックさんは、中部のクアンチ省の出身。現在はフエ市の医科大学で勉強しています。
3月11日の震災のニュースを見て、心配して手紙を書いてくれたようです。
以下、フオックさんの手紙を紹介します。
フエ 2011年3月14日
わたしは、インターネットでニュースを見たところです。地震、津波、原発事故についての情報を読みました。すべてが、とても恐ろしいことです。
震災のあとの荒廃した写真を目にしたとき、わたしは自分の目が信じられませんでした。
でもわたしは、沖縄が震災の被害を受けたのかどうか、わかりません。
里親さんとご家族の皆様は、ご無事でいらっしゃいますよね?
東京にいる息子さんは、被害を受けてはいらっしゃいませんよね?
いま、日本の方々は、言葉にできないほどの恐ろしいパニック、被害に直面しなければなりません。
でもわたしは、堅固な精神と、民族の素晴らしい団結によって、日本はきっと震災から立ち上がると信じています。
わたしは、こんな災害が起こらなければよかったのに、と思います。
そして、里親さんの国が、早くこのショックを乗り越え、痛みを忘れて、日常の暮らしに戻られることを願っています。それは本当に難しいことではありますが…。
わたしはまた、里親さんと青葉奨学会のメンバーの方々のご無事とご健康を、そして震災を乗り越えられることを願っています。
いま、わたしにできることは、自然の穏やかさが日本の国土に戻ってくることや、日本の方々がこのような大変な災害にこれ以上遭われないこと、地震・津波の被災者の方々が、国内外の友人たちの支援を受けて早く安定した生活に戻れることを願うことだけで、他には何もできません。
このお手紙が、早く里親さんの手に届きますように。
最後にもう一度、里親さんとご家族の皆様のご健康と幸福を、多くの幸運に恵まれますことを、お祈りします。
グエン・ティエン・フオック
フオックさんは、中部のクアンチ省の出身。現在はフエ市の医科大学で勉強しています。
3月11日の震災のニュースを見て、心配して手紙を書いてくれたようです。
以下、フオックさんの手紙を紹介します。
フエ 2011年3月14日
わたしは、インターネットでニュースを見たところです。地震、津波、原発事故についての情報を読みました。すべてが、とても恐ろしいことです。
震災のあとの荒廃した写真を目にしたとき、わたしは自分の目が信じられませんでした。
でもわたしは、沖縄が震災の被害を受けたのかどうか、わかりません。
里親さんとご家族の皆様は、ご無事でいらっしゃいますよね?
東京にいる息子さんは、被害を受けてはいらっしゃいませんよね?
いま、日本の方々は、言葉にできないほどの恐ろしいパニック、被害に直面しなければなりません。
でもわたしは、堅固な精神と、民族の素晴らしい団結によって、日本はきっと震災から立ち上がると信じています。
わたしは、こんな災害が起こらなければよかったのに、と思います。
そして、里親さんの国が、早くこのショックを乗り越え、痛みを忘れて、日常の暮らしに戻られることを願っています。それは本当に難しいことではありますが…。
わたしはまた、里親さんと青葉奨学会のメンバーの方々のご無事とご健康を、そして震災を乗り越えられることを願っています。
いま、わたしにできることは、自然の穏やかさが日本の国土に戻ってくることや、日本の方々がこのような大変な災害にこれ以上遭われないこと、地震・津波の被災者の方々が、国内外の友人たちの支援を受けて早く安定した生活に戻れることを願うことだけで、他には何もできません。
このお手紙が、早く里親さんの手に届きますように。
最後にもう一度、里親さんとご家族の皆様のご健康と幸福を、多くの幸運に恵まれますことを、お祈りします。
グエン・ティエン・フオック
2011年04月10日
春の風が運んでくるもの
先日のホエ先生からのお見舞い状にもあるように、ベトナムは原子力発電所の建設を計画しています。
2030年までに14基の原子炉を建設して、電力の1割を原子力でまかなうことを予定しているそうです。
ホーチミン市から東北東に300キロ弱のところに、ニントゥアンという地域があります。
ちょうど、東京から見た福島県のような位置関係になります。
ニントゥアンの海辺の地域には、4基の原発が建設される予定で、そのうち2基はロシアの企業に発注、残りは日本企業に発注が決まっているとのことです。
昨年、民主党政権の閣僚たちが相次いでベトナムを訪問、原発のセールスに奔走していました。
民主党は自民党以上に原発輸出に熱心だね、と呆れて見ていたものです。
ベトナムでは経済発展にともなって電力の需要が急増、慢性的に電力不足になっていて、ホーチミン市などでは「計画停電」もときどき行われているそうです。
共産党政府はどうしても原発が必要だと考えているらしく、福島での事故のあとも、原発建設の計画を進める、と発表しています。
ベトナムの人たちが、リスクを十分に承知の上で、やはり原発は必要だと考えるのであれば、私たちがどうこう言える筋合いはないと思います。
でも、複雑な気持ちは残ります。
福島県の阿武隈山地の山麓に、「三春」という美しい名前の町があります。
日本の春を象徴する三つの花、梅・桜・桃が一斉に花開くので、この名前なのだと聞きました。
厳しい冬が終わるこの季節、三春では、阿武隈山地の向こうの海のほうから、さわやかな東風が吹くそうです。
春をもたらすこの東風を、地域の人たちは何よりも楽しみにしている、ということです。
しかし今年は、その東風が、とんでもなく恐ろしいものになっています。
三春から東に50キロ足らずのところに、福島第1原子力発電所があるからです。
今年の東風は、放射性ヨウ素とか、セシウムとかいう、目に見えないけれど禍々しいものを運んできているのです。
原発の3号機が爆発した日、三春町は、40歳以下の町民に対して安定ヨウ素剤を配布、服用を勧めたとのことです。
三春町は、私の両親が生まれ育った町です。
私自身は三春で暮らしたことはなく、三春の春の美しさは知りませんが、名前の由来は両親からよく聞かされてきました。
子どもの頃の夏休みには、毎年三春にある両親の実家を訪ねて、いとこたちと遊ぶのがとても楽しみでした。
いまも、多くの親戚の人たちが、三春とその周辺に住んでいます。
三春は原発から30キロ圏の外にあるので、避難地域には入っていません。
そのため、20キロ圏や30キロ圏から逃れてきた方々の多くが、三春で避難生活を送っているそうです(いとこの1人は、ふだんは神奈川県に住んでいますが、避難民の方々の支援のために三春に戻っていると聞きました)。
しかし、ここも危ないと感じて、より遠くに避難する人たちも多いそうです。
三春の人たちは、いつ安らかな春を迎えられるのでしょうか。
避難している方々が、安心して故郷に戻れる日は来るのでしょうか。
いま福島原発の現場で、命がけで立ち向かっている方々には、心から敬意と感謝を感じています。
状況はいまも相当に厳しいと思うのですが、なんとかこれ以上事態を悪化させることなく、安定に向かってほしいと思います。
と同時に、これ以上の原発建設はストップさせ、既存の原発も危険度の高いものから止めていくように、強く望んでいます。
2030年までに14基の原子炉を建設して、電力の1割を原子力でまかなうことを予定しているそうです。
ホーチミン市から東北東に300キロ弱のところに、ニントゥアンという地域があります。
ちょうど、東京から見た福島県のような位置関係になります。
ニントゥアンの海辺の地域には、4基の原発が建設される予定で、そのうち2基はロシアの企業に発注、残りは日本企業に発注が決まっているとのことです。
昨年、民主党政権の閣僚たちが相次いでベトナムを訪問、原発のセールスに奔走していました。
民主党は自民党以上に原発輸出に熱心だね、と呆れて見ていたものです。
ベトナムでは経済発展にともなって電力の需要が急増、慢性的に電力不足になっていて、ホーチミン市などでは「計画停電」もときどき行われているそうです。
共産党政府はどうしても原発が必要だと考えているらしく、福島での事故のあとも、原発建設の計画を進める、と発表しています。
ベトナムの人たちが、リスクを十分に承知の上で、やはり原発は必要だと考えるのであれば、私たちがどうこう言える筋合いはないと思います。
でも、複雑な気持ちは残ります。
福島県の阿武隈山地の山麓に、「三春」という美しい名前の町があります。
日本の春を象徴する三つの花、梅・桜・桃が一斉に花開くので、この名前なのだと聞きました。
厳しい冬が終わるこの季節、三春では、阿武隈山地の向こうの海のほうから、さわやかな東風が吹くそうです。
春をもたらすこの東風を、地域の人たちは何よりも楽しみにしている、ということです。
しかし今年は、その東風が、とんでもなく恐ろしいものになっています。
三春から東に50キロ足らずのところに、福島第1原子力発電所があるからです。
今年の東風は、放射性ヨウ素とか、セシウムとかいう、目に見えないけれど禍々しいものを運んできているのです。
原発の3号機が爆発した日、三春町は、40歳以下の町民に対して安定ヨウ素剤を配布、服用を勧めたとのことです。
三春町は、私の両親が生まれ育った町です。
私自身は三春で暮らしたことはなく、三春の春の美しさは知りませんが、名前の由来は両親からよく聞かされてきました。
子どもの頃の夏休みには、毎年三春にある両親の実家を訪ねて、いとこたちと遊ぶのがとても楽しみでした。
いまも、多くの親戚の人たちが、三春とその周辺に住んでいます。
三春は原発から30キロ圏の外にあるので、避難地域には入っていません。
そのため、20キロ圏や30キロ圏から逃れてきた方々の多くが、三春で避難生活を送っているそうです(いとこの1人は、ふだんは神奈川県に住んでいますが、避難民の方々の支援のために三春に戻っていると聞きました)。
しかし、ここも危ないと感じて、より遠くに避難する人たちも多いそうです。
三春の人たちは、いつ安らかな春を迎えられるのでしょうか。
避難している方々が、安心して故郷に戻れる日は来るのでしょうか。
いま福島原発の現場で、命がけで立ち向かっている方々には、心から敬意と感謝を感じています。
状況はいまも相当に厳しいと思うのですが、なんとかこれ以上事態を悪化させることなく、安定に向かってほしいと思います。
と同時に、これ以上の原発建設はストップさせ、既存の原発も危険度の高いものから止めていくように、強く望んでいます。
Posted by クアン at
21:44
│Comments(0)
2011年03月25日
奨学生たちへの手紙
日本の震災のニュースは、ベトナムでも大きく報道されています。
青葉奨学生たちも、ニュースを聞いて驚き、とても心配していると思います。
中には、津波の恐ろしい映像を見て、ショックを受けている子もいるかもしれません。
私たちが無事に暮らしていることを、生徒たちに知ってもらえるように、短い手紙を書きました。
ベトナム語に翻訳して生徒たちに届けるよう、ベトナムの事務局にお願いしました。
以下のような内容です。
会員の皆さんも、もしよろしければそれぞれの里子に手紙を書いてあげて下さい。
青葉奨学生のみなさんへ
みなさん、お元気ですか。
わたしたちは元気です。
みなさんも聞いたと思いますが、先日、日本では大きな地震がありました。
たくさんの人が亡くなったり、家や財産を失ったりしました。
とても悲しい出来事でした。
みなさんの中にも、ニュースで恐ろしい映像を見た人がいるかもしれません。
でも、わたしたちのほとんどは別の場所に住んでいるので、無事に暮らしています。
いつもと同じように、家でご飯を食べて、仕事をしています。
ですから、今年もみなさんに奨学金を送ることができます。
どうか安心して下さいね。
地震の被害を受けた人たちは、いまも苦しい生活をしています。
日本では、みんなで力を合わせて、被害を受けた人たちを助けようと頑張っています。
たくさんのベトナムの人たちも、応援して下さっています。
みなさんは、元気で勉強を頑張ったり、友だちと楽しく遊んだりして下さいね。
みなさんが元気で頑張ってくれることが、わたしたちにとって、いちばんの励ましになります。
もうすぐ学年末になります。
暑い季節です。からだに気をつけて、楽しく勉強して下さい。
ときどき、お手紙でみなさんの様子を知らせて下さいね。
ご家族のみなさんにも、よろしくお伝えして下さい。
日本の里親一同より
青葉奨学生たちも、ニュースを聞いて驚き、とても心配していると思います。
中には、津波の恐ろしい映像を見て、ショックを受けている子もいるかもしれません。
私たちが無事に暮らしていることを、生徒たちに知ってもらえるように、短い手紙を書きました。
ベトナム語に翻訳して生徒たちに届けるよう、ベトナムの事務局にお願いしました。
以下のような内容です。
会員の皆さんも、もしよろしければそれぞれの里子に手紙を書いてあげて下さい。
青葉奨学生のみなさんへ
みなさん、お元気ですか。
わたしたちは元気です。
みなさんも聞いたと思いますが、先日、日本では大きな地震がありました。
たくさんの人が亡くなったり、家や財産を失ったりしました。
とても悲しい出来事でした。
みなさんの中にも、ニュースで恐ろしい映像を見た人がいるかもしれません。
でも、わたしたちのほとんどは別の場所に住んでいるので、無事に暮らしています。
いつもと同じように、家でご飯を食べて、仕事をしています。
ですから、今年もみなさんに奨学金を送ることができます。
どうか安心して下さいね。
地震の被害を受けた人たちは、いまも苦しい生活をしています。
日本では、みんなで力を合わせて、被害を受けた人たちを助けようと頑張っています。
たくさんのベトナムの人たちも、応援して下さっています。
みなさんは、元気で勉強を頑張ったり、友だちと楽しく遊んだりして下さいね。
みなさんが元気で頑張ってくれることが、わたしたちにとって、いちばんの励ましになります。
もうすぐ学年末になります。
暑い季節です。からだに気をつけて、楽しく勉強して下さい。
ときどき、お手紙でみなさんの様子を知らせて下さいね。
ご家族のみなさんにも、よろしくお伝えして下さい。
日本の里親一同より
Posted by クアン at
23:14
│Comments(0)