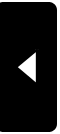2011年03月25日
災害翻訳ボランティア
友人から、災害翻訳ボランティアを至急求めている、という情報をいただきました。
私もメールを見ただけなので、まったく詳しくはないのですが、群馬大学の方などが取り組んでいるプロジェクトで、日本で災害に遭った外国人のために、避難所や生活物資などの必要な情報を多くの言語で提供する、というものだそうです。
今回の震災では、おもに茨城県で被災した外国人のために運用されているのですが、とくにベトナム語とインドネシア語の需要が多く、登録者が少ないため、お手伝いできる方を至急求めている、ということでした。
これまで留学生などに聞いた範囲では、ベトナム人が大きな被害を受けたという情報は受けていない、と聞きましたが、これほどの震災なので、いろいろな形で被害を受けて支援を求めている方がいるのだと思います。
登録するとメールで翻訳の依頼が流れ、できる方がメールで回答して、翻訳して送る、というやり方になっているそうです。
また、スカイプ電話を使った通訳のサービスも始めているということです。
登録は、http://www.multiculture.jp/htdocs/?page_id=24 からできます。
私も知人にメールを転送したところ、東京周辺に住む何名ものベトナム人の方から「登録しました」「詳しいことを教えて」といったメールが返ってきました。
すばやく応じてくれて、感謝です。
昨夜のニュースでは、今回の震災で、なんと700名以上のタイ人が行方不明になっており、ほとんどは日本人と結婚した女性たちだと聞きました。
あまりの人数の多さにびっくりしましたが、タイ人の方たちだけでなく、本当に多くの外国人が被災して、切実に情報を求めているのだと思います。
インターネットを利用した翻訳・通訳ボランティア、被災直後は停電してしまうので機能しないかもしれませんが、その後の生活支援には、とても有意義な取り組みだと思います。
私もできればお手伝いしたいですが、まだまだ実力不足なので、たぶん意味不明なベトナム語になってしまって、かえって混乱させてしまうでしょう。残念です…。
私もメールを見ただけなので、まったく詳しくはないのですが、群馬大学の方などが取り組んでいるプロジェクトで、日本で災害に遭った外国人のために、避難所や生活物資などの必要な情報を多くの言語で提供する、というものだそうです。
今回の震災では、おもに茨城県で被災した外国人のために運用されているのですが、とくにベトナム語とインドネシア語の需要が多く、登録者が少ないため、お手伝いできる方を至急求めている、ということでした。
これまで留学生などに聞いた範囲では、ベトナム人が大きな被害を受けたという情報は受けていない、と聞きましたが、これほどの震災なので、いろいろな形で被害を受けて支援を求めている方がいるのだと思います。
登録するとメールで翻訳の依頼が流れ、できる方がメールで回答して、翻訳して送る、というやり方になっているそうです。
また、スカイプ電話を使った通訳のサービスも始めているということです。
登録は、http://www.multiculture.jp/htdocs/?page_id=24 からできます。
私も知人にメールを転送したところ、東京周辺に住む何名ものベトナム人の方から「登録しました」「詳しいことを教えて」といったメールが返ってきました。
すばやく応じてくれて、感謝です。
昨夜のニュースでは、今回の震災で、なんと700名以上のタイ人が行方不明になっており、ほとんどは日本人と結婚した女性たちだと聞きました。
あまりの人数の多さにびっくりしましたが、タイ人の方たちだけでなく、本当に多くの外国人が被災して、切実に情報を求めているのだと思います。
インターネットを利用した翻訳・通訳ボランティア、被災直後は停電してしまうので機能しないかもしれませんが、その後の生活支援には、とても有意義な取り組みだと思います。
私もできればお手伝いしたいですが、まだまだ実力不足なので、たぶん意味不明なベトナム語になってしまって、かえって混乱させてしまうでしょう。残念です…。
Posted by クアン at
05:56
│Comments(0)
2011年03月23日
ベトナムからのお見舞い状
先日の震災に関して、ベトナムの青葉奨学会事務局からお見舞い状をいただきました。
私たち沖縄委員会では、もちろん震災の直接的な影響は受けていないのですが、東京のグループには東北在住の会員の方もいて、何名かが被災されたそうです。
いまも連絡が取れない方もいるそうで、なんとかご無事でいていただきたいと、願わずにはいられません。
以下、ベトナムからのお見舞い状です。
ベトナムの子どもたちを支援してくださる皆様へ
東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
このニュースは、こちらでも連日報道されています。
3月11日の地震に始まり、信じられないような津波被害の映像も流れています。
また、福島原発での放射能漏れ事故もベトナムでは注目のニュースです。
日本から技術支援を受けて原子力発電所を建設しようとしているベトナムにとって、他人事のニュースではありません。
現在も被災地では、物資の輸送が大変で、ガソリン、食料などが不足していると聞いております。
氷点下の中、暖を取ることもできずに、不安な夜を布団の中でうずくまるように過ごされている方が大勢いると思います。
長い時間お風呂にも入ることができない人がいるとも聞いています。
被災地の方々は本当に辛い思いをしていると考えると涙が出てきます。
貧しいですが、毎日ご飯を食べることができるだけでも、私たちは幸せだと、心から感じています。
そんな大変な状況にも関わらず、日本人の秩序ある行動、冷静さには本当に頭が下がる思いで、感動いたしました。
今まで、私たちは日本の友人に多くの助けをいただいてきました。
今度は、私たちが日本の皆様に恩返しするときです。
私たちは、裕福ではありませんから、大きなことはできません。
でも、気持ちだけでも被災地で頑張っている方々に届け、少しでも被災地の方を勇気付けることができれば、こんなにうれしいことはありません。
今、日本は大変な時期だと思いますが、日本全国の皆様が一致団結して、日本を復興し、頼れるアニキとして甦ることを信じています。
遠くからですが、一人でも多くの方が無事でいらっしゃることを心からお祈りしております。
ベトナム青葉奨学会
代表 グエン・ドク・ホゥエ
そろそろ奨学金を送金する時期なのですが、ベトナム側からは、今年は奨学金の受け取りを辞退したい旨の打診もありました。
震災のあまりのすさまじさに深く心を痛め、日本で苦しんでいる人たちがたくさんいるのに、自分たちがお金を受け取るわけにはいかない、ということでした。
私たちとしては、すでにお金は集まっているので、例年通り生徒たちに奨学金を支給するようにお願いして、ベトナム側も了解してくれました。
今年はかなりの円高になっているので、ベトナムに送金する上では、とても有利な条件になります(もちろん、円高にはマイナスの影響もたくさんありますが…)。
会員の方々と相談して、円高で浮いた分のお金を、今年は義援金にしようと決めました。
今日、「国際ボランティアセンター山形」の口座に、少しですが義援金を振り込みました。
このグループでは、「東北広域震災NGOセンター」を立ち上げて、宮城県の被災地への救援物資の運搬、ボランティアの派遣、炊き出しなどに取り組んでいるそうです。
活動の様子が、ブログで詳しく報告されています。http://ameblo.jp/ivyjimukyokublog/
私たちは何もできませんが、被災地で頑張っていらっしゃる方々に、心から敬意を表したいと思います。
今夜はとても冷え込んでいるとのこと。皆さん体調を崩されませんように。
私たち沖縄委員会では、もちろん震災の直接的な影響は受けていないのですが、東京のグループには東北在住の会員の方もいて、何名かが被災されたそうです。
いまも連絡が取れない方もいるそうで、なんとかご無事でいていただきたいと、願わずにはいられません。
以下、ベトナムからのお見舞い状です。
ベトナムの子どもたちを支援してくださる皆様へ
東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
このニュースは、こちらでも連日報道されています。
3月11日の地震に始まり、信じられないような津波被害の映像も流れています。
また、福島原発での放射能漏れ事故もベトナムでは注目のニュースです。
日本から技術支援を受けて原子力発電所を建設しようとしているベトナムにとって、他人事のニュースではありません。
現在も被災地では、物資の輸送が大変で、ガソリン、食料などが不足していると聞いております。
氷点下の中、暖を取ることもできずに、不安な夜を布団の中でうずくまるように過ごされている方が大勢いると思います。
長い時間お風呂にも入ることができない人がいるとも聞いています。
被災地の方々は本当に辛い思いをしていると考えると涙が出てきます。
貧しいですが、毎日ご飯を食べることができるだけでも、私たちは幸せだと、心から感じています。
そんな大変な状況にも関わらず、日本人の秩序ある行動、冷静さには本当に頭が下がる思いで、感動いたしました。
今まで、私たちは日本の友人に多くの助けをいただいてきました。
今度は、私たちが日本の皆様に恩返しするときです。
私たちは、裕福ではありませんから、大きなことはできません。
でも、気持ちだけでも被災地で頑張っている方々に届け、少しでも被災地の方を勇気付けることができれば、こんなにうれしいことはありません。
今、日本は大変な時期だと思いますが、日本全国の皆様が一致団結して、日本を復興し、頼れるアニキとして甦ることを信じています。
遠くからですが、一人でも多くの方が無事でいらっしゃることを心からお祈りしております。
ベトナム青葉奨学会
代表 グエン・ドク・ホゥエ
そろそろ奨学金を送金する時期なのですが、ベトナム側からは、今年は奨学金の受け取りを辞退したい旨の打診もありました。
震災のあまりのすさまじさに深く心を痛め、日本で苦しんでいる人たちがたくさんいるのに、自分たちがお金を受け取るわけにはいかない、ということでした。
私たちとしては、すでにお金は集まっているので、例年通り生徒たちに奨学金を支給するようにお願いして、ベトナム側も了解してくれました。
今年はかなりの円高になっているので、ベトナムに送金する上では、とても有利な条件になります(もちろん、円高にはマイナスの影響もたくさんありますが…)。
会員の方々と相談して、円高で浮いた分のお金を、今年は義援金にしようと決めました。
今日、「国際ボランティアセンター山形」の口座に、少しですが義援金を振り込みました。
このグループでは、「東北広域震災NGOセンター」を立ち上げて、宮城県の被災地への救援物資の運搬、ボランティアの派遣、炊き出しなどに取り組んでいるそうです。
活動の様子が、ブログで詳しく報告されています。http://ameblo.jp/ivyjimukyokublog/
私たちは何もできませんが、被災地で頑張っていらっしゃる方々に、心から敬意を表したいと思います。
今夜はとても冷え込んでいるとのこと。皆さん体調を崩されませんように。
Posted by クアン at
23:05
│Comments(0)
2011年03月14日
大震災、ベトナム人の声
東日本大震災と原発事故のニュース、ベトナムのメディアでも、引き続き大きく報じられているようです。
「トゥオイチェ」などのオンライン版には、被災者と日本に思いを寄せてくれているベトナム人読者の声が、数多く紹介されています。
時間がないので、ほんの一部になりますが、ベトナム人の声を紹介します。
(例によって、翻訳の間違いがあるかもしれません。ご了承下さい)
仕事から帰って間もなく、日本で地震と津波が起きたニュースを知りました。
私は、自分の耳が信じられないような思いでした。
日本にとって、その被害は、あまりにも大きなものです。
私は、日本の友人たち、とくに2000名以上の犠牲者のご家族と、心より悲しみを分かち合います。
でも私は、日本はこの困難を乗り越えると信じています。日本人の向上心は、とても高いからです。
チャン・ティ・キム・トゥイ
私は、地球上でこのような災害がまた起きるとは、考えたこともありませんでした。
早朝、会社でパソコンを立ち上げると、1200名近くが死亡・行方不明というニュースが出てきました。
みなさん、日本の人たちがこの被害を乗り越えられるように、いっしょに手を差し伸べましょうね!
ダン・トゥー・フオン
今夜、仕事から帰ると、日本の地震のニュースを子どもから聞きました。
津波が起きて、とても多くの人命と財産が失われたというのです。
私は、この話が本当なのかどうか確かめるために、慌ててパソコンをつけました。
私は、これが本当のことだとは信じることができませんでした。
日本の国土と人々が直面しなければならなかった出来事に、私は涙があふれました。
私は、この痛みを皆さんと分かち合います。
幸せで安らかな日々が、私の愛する国と人々に、早く訪れますように。
チン・トゥアン
「トゥオイチェ」などのオンライン版には、被災者と日本に思いを寄せてくれているベトナム人読者の声が、数多く紹介されています。
時間がないので、ほんの一部になりますが、ベトナム人の声を紹介します。
(例によって、翻訳の間違いがあるかもしれません。ご了承下さい)
仕事から帰って間もなく、日本で地震と津波が起きたニュースを知りました。
私は、自分の耳が信じられないような思いでした。
日本にとって、その被害は、あまりにも大きなものです。
私は、日本の友人たち、とくに2000名以上の犠牲者のご家族と、心より悲しみを分かち合います。
でも私は、日本はこの困難を乗り越えると信じています。日本人の向上心は、とても高いからです。
チャン・ティ・キム・トゥイ
私は、地球上でこのような災害がまた起きるとは、考えたこともありませんでした。
早朝、会社でパソコンを立ち上げると、1200名近くが死亡・行方不明というニュースが出てきました。
みなさん、日本の人たちがこの被害を乗り越えられるように、いっしょに手を差し伸べましょうね!
ダン・トゥー・フオン
今夜、仕事から帰ると、日本の地震のニュースを子どもから聞きました。
津波が起きて、とても多くの人命と財産が失われたというのです。
私は、この話が本当なのかどうか確かめるために、慌ててパソコンをつけました。
私は、これが本当のことだとは信じることができませんでした。
日本の国土と人々が直面しなければならなかった出来事に、私は涙があふれました。
私は、この痛みを皆さんと分かち合います。
幸せで安らかな日々が、私の愛する国と人々に、早く訪れますように。
チン・トゥアン
Posted by クアン at
23:32
│Comments(1)
2011年03月13日
ドンズー日本語学校20周年、ですが…
きのうは、青葉奨学会事務局のあるドンズー日本語学校(ホーチミン市)の設立20周年記念式典の日でした。
しかし、東北・関東地方で起こった、想像を絶する地震・津波の被害…。
ベトナムにあるドンズー日本語学校でも、お祝いどころではなかったと思います。
以前から予定していたことなので、式典は実施したと思いますが…。
ドンズー日本語学校では、多くのベトナム人留学生を日本各地に送っています。
たぶん、仙台など東北地方で学んでいる学生の安否確認に追われたのでは?
NHKのベトナム語放送やベトナムの新聞報道(オンライン版)などによると、仙台では100人前後のベトナム人留学生がいるそうですが、いまのところ、誰かが被害に遭ったという情報はない、ということです。
ベトナムでも、今回の地震・津波・原発事故について、詳しい報道がなされているようです。
多くの青葉奨学生たちも、おそらく日本の地震のニュースを知って、胸を痛めているのでは、と思います。
どうかこれ以上被害が広がりませんように。
私たちも、何かできることがないか、早急に考えたいと思います。
しかし、東北・関東地方で起こった、想像を絶する地震・津波の被害…。
ベトナムにあるドンズー日本語学校でも、お祝いどころではなかったと思います。
以前から予定していたことなので、式典は実施したと思いますが…。
ドンズー日本語学校では、多くのベトナム人留学生を日本各地に送っています。
たぶん、仙台など東北地方で学んでいる学生の安否確認に追われたのでは?
NHKのベトナム語放送やベトナムの新聞報道(オンライン版)などによると、仙台では100人前後のベトナム人留学生がいるそうですが、いまのところ、誰かが被害に遭ったという情報はない、ということです。
ベトナムでも、今回の地震・津波・原発事故について、詳しい報道がなされているようです。
多くの青葉奨学生たちも、おそらく日本の地震のニュースを知って、胸を痛めているのでは、と思います。
どうかこれ以上被害が広がりませんように。
私たちも、何かできることがないか、早急に考えたいと思います。
Posted by クアン at
23:15
│Comments(0)
2011年03月06日
枯葉剤と沖縄
ETV特集「枯葉剤の傷痕を見つめて」が、今夜、NHK教育テレビで再放送されるようです。
つい1ヶ月前の番組のアンコール放送ということなので、相当な反響やリクエストがあったのだと思います。
坂田雅子さんには、2年前に「花はどこへ行った」の上映で沖縄に来られたときに、私も少しお話しさせていただきました。
その後も、地道に、またエネルギッシュに取材を続けていらっしゃることを知り、本当に感服です。
私たちが奨学金を支援している地域のひとつ、ホーチミン市の南東にあるカンザー地区は、ベトナム戦争中、最もひどく枯葉剤の被害を受けた場所のひとつです。
また、ビンズオンやビンディン、ダナンなど、奨学生たちが暮らしている地域を訪ねるたび、何度も枯葉剤の話を聞かされました。
私たちの奨学金支援は、とくに枯葉剤被害者を対象にしているというわけではないのですが、枯葉剤のことはずっと気になっていました。
いまから4年前の2007年7月9日、「北部訓練場で枯葉剤散布」というニュースが報じられました。
「1961年から62年にかけて、沖縄本島の北部訓練場などで米軍がダイオキシンを含む枯葉剤を散布。作業に当たった元米兵が、前立腺ガンなどの後遺症を米退役軍人省から認定されていた」ことが、アメリカの公文書で明らかになった、という内容でした。
琉球新報、沖縄タイムスともに、夕刊の1面トップ記事という大きな扱いでした。
「ベトナムで使われた枯葉剤は、どうやら沖縄の基地から運ばれていたらしい」という話は、それまでも何度か聞いたことがありましたが、私の知る範囲では、はっきりした確証はありませんでした。
それが、「沖縄の基地で枯葉剤を散布し、そこからベトナムにも運んでいたことを、アメリカの公的機関が認めていた」というのですから、とても驚かされました。
その後、私たちは、化学の先生にお願いして枯葉剤についての小さな勉強会を行ったり、自分たちでも資料を集めたりして調べてみました。
1961年というと、米軍がベトナムで初めて枯葉剤散布を実施した年です。散布量としては、まだ多くはありませんでした。
また、ベトナムでの本格的な使用に向けてだと思うのですが、プエルトリコやタイなど、世界の各地で枯葉剤の散布実験を行い、データを集めていた時期だということがわかりました。
この時期に米軍が北部訓練場などで枯葉剤散布をしていたというのが事実だとすると、データ収集の目的もあったのではないか、そう考えるのが自然なように思います。
2007年7月に明らかになった公文書以外に、米軍が沖縄で枯葉剤を使っていたことを示すような資料は、いまのところ見つかっていないようです(私が知らないだけかもしれませんが…)。
でも、アメリカ政府にとって不都合な請求を、他ならぬアメリカの役所が認定しているわけですから、相当な根拠があっての判断なのだとおもいます。
枯葉剤の後遺症を認定された元米兵は、1961年か2月から1962年4月まで沖縄に滞在。ベトナムに行ったことはないそうです。
沖縄では自動車運転を専門とし、海兵隊の輸送部隊に所属。ベトナム行きの待機中の部隊に枯葉剤などを輸送する作戦に従事したほか、枯葉剤をディーゼル油などと混合して、ドラム缶に注入する作業も担当。
北部訓練場の基地周辺や道路脇などで、枯葉剤が入った容器を背負って散布したこともあり、このような作業は最低でも2ヶ月以上続いた、ということです。
かなり具体的なことが書かれている、という印象を持ちます。
沖縄の米軍基地がベトナム戦争の兵站・出撃基地になったのは言うまでもないことですが、枯葉剤の貯蔵や実験なども行われていたのでしょうか。
ベトナムの人たちの上に撒かれた枯葉剤は、やはり沖縄から運ばれていたのでしょうか。
まだはっきりしないことばかりなのですが、とても気になります。
つい1ヶ月前の番組のアンコール放送ということなので、相当な反響やリクエストがあったのだと思います。
坂田雅子さんには、2年前に「花はどこへ行った」の上映で沖縄に来られたときに、私も少しお話しさせていただきました。
その後も、地道に、またエネルギッシュに取材を続けていらっしゃることを知り、本当に感服です。
私たちが奨学金を支援している地域のひとつ、ホーチミン市の南東にあるカンザー地区は、ベトナム戦争中、最もひどく枯葉剤の被害を受けた場所のひとつです。
また、ビンズオンやビンディン、ダナンなど、奨学生たちが暮らしている地域を訪ねるたび、何度も枯葉剤の話を聞かされました。
私たちの奨学金支援は、とくに枯葉剤被害者を対象にしているというわけではないのですが、枯葉剤のことはずっと気になっていました。
いまから4年前の2007年7月9日、「北部訓練場で枯葉剤散布」というニュースが報じられました。
「1961年から62年にかけて、沖縄本島の北部訓練場などで米軍がダイオキシンを含む枯葉剤を散布。作業に当たった元米兵が、前立腺ガンなどの後遺症を米退役軍人省から認定されていた」ことが、アメリカの公文書で明らかになった、という内容でした。
琉球新報、沖縄タイムスともに、夕刊の1面トップ記事という大きな扱いでした。
「ベトナムで使われた枯葉剤は、どうやら沖縄の基地から運ばれていたらしい」という話は、それまでも何度か聞いたことがありましたが、私の知る範囲では、はっきりした確証はありませんでした。
それが、「沖縄の基地で枯葉剤を散布し、そこからベトナムにも運んでいたことを、アメリカの公的機関が認めていた」というのですから、とても驚かされました。
その後、私たちは、化学の先生にお願いして枯葉剤についての小さな勉強会を行ったり、自分たちでも資料を集めたりして調べてみました。
1961年というと、米軍がベトナムで初めて枯葉剤散布を実施した年です。散布量としては、まだ多くはありませんでした。
また、ベトナムでの本格的な使用に向けてだと思うのですが、プエルトリコやタイなど、世界の各地で枯葉剤の散布実験を行い、データを集めていた時期だということがわかりました。
この時期に米軍が北部訓練場などで枯葉剤散布をしていたというのが事実だとすると、データ収集の目的もあったのではないか、そう考えるのが自然なように思います。
2007年7月に明らかになった公文書以外に、米軍が沖縄で枯葉剤を使っていたことを示すような資料は、いまのところ見つかっていないようです(私が知らないだけかもしれませんが…)。
でも、アメリカ政府にとって不都合な請求を、他ならぬアメリカの役所が認定しているわけですから、相当な根拠があっての判断なのだとおもいます。
枯葉剤の後遺症を認定された元米兵は、1961年か2月から1962年4月まで沖縄に滞在。ベトナムに行ったことはないそうです。
沖縄では自動車運転を専門とし、海兵隊の輸送部隊に所属。ベトナム行きの待機中の部隊に枯葉剤などを輸送する作戦に従事したほか、枯葉剤をディーゼル油などと混合して、ドラム缶に注入する作業も担当。
北部訓練場の基地周辺や道路脇などで、枯葉剤が入った容器を背負って散布したこともあり、このような作業は最低でも2ヶ月以上続いた、ということです。
かなり具体的なことが書かれている、という印象を持ちます。
沖縄の米軍基地がベトナム戦争の兵站・出撃基地になったのは言うまでもないことですが、枯葉剤の貯蔵や実験なども行われていたのでしょうか。
ベトナムの人たちの上に撒かれた枯葉剤は、やはり沖縄から運ばれていたのでしょうか。
まだはっきりしないことばかりなのですが、とても気になります。
2011年02月27日
消えようとしているある漁村
30名余りの青葉奨学生が暮らしている、タンアンという漁村があります。
ホーチミン市の南東にあたるカンザーの中でも、最も交通不便な場所で、カンタン町から渡し舟を使っていかなければなりません。
この村は、2006年12月のドリアン台風で多くの家屋が全壊するという被害を受けました(このとき、ほとんどの青葉奨学生の家も倒れてしまったそうです)。
その後、行政の指導もあって、近い将来に住民全員が内陸部に移住することに決まったそうです。
少し古い記事ですが、2007年10月18日の「トゥオイチェ」新聞に、「タンアン島、最後の渡し舟」というタンアン村の訪問記事が出ていました。
沖縄委員会会報「Cay Phuong」第20号に載せたものですが、このブログでも紹介したいと思います。
なお、いつもながら翻訳に間違いがあるかもしれませんので、ご了承ください。
(その後、移住について村の人に訊ねたことがありますが、数千人規模の移住になるため、まだかなり先の話になるだろうということでした。)
タンアン島、最後の渡し舟
ホーチミン市カンザー郡。カンタン町の港からタンアン島へ渡る定期船には、客はあまり乗っていなかったが、船体はいつもよりも重そうに見えた。
年老いた船頭は、タバコを吸いながらつぶやいた。
「たぶん、この渡し船も、もうすぐなくなっちまうんだろうな…」
多くの人、多くの家族が、数世代にわたってこの島で生を受け、暮らしを営んできた。
上空から見下ろすと、島はまるで海に浮かんだ木の葉のように頼りなく見える。
ここ数年、台風が続けて襲来し、島を吹き飛ばそうとしているかのように荒れ狂った。
近年、台風はますます凶暴になり、人々は内陸への移住を考えている。
しかし、島を離れるにしても残るにしても、ここの住民にとって、決して容易な選択ではないのだ…。
豊かだった時代
タンアンの古くからの住民の1人、ブイ・ヴァン・ハイさん(81歳)は、タンアン島のヴンタウに面した側の海岸で堤防がひどく崩れかかっており、島全体が海に呑み込まれてしまう危機にある、ということを教えてくれた。
住民と行政は、波を防いで島が生き残れるように、力を合わせて石の防波堤を築かなければならなかった、という。
ハイさんはまた、古老が語り継いできた、島の始まりについての歴史を教えてくれた。
それは、戦争や飢饉を避けて、土地の支配者の下から逃れてきた流民の話であった。
はじめ、彼らは漁をしに来ていたのだが、ヴンタウ・ドンナイ・カンザーに囲まれた湾の中に、美しい地形をした小さな島があるのを、偶然に発見した。
彼らは内陸の土地を捨てて、誘い合ってこの島に住み着くようになった。
島の土地は低く、つねに海水に浸されるため、高床の家を建てなければならなかった。
1960年代からは、島に次々と家が建つようになった。集まって暮らす人々は、数千人にもなり、海の仕事で生計を立てた。
その頃、タンアンはとても暮らしやすいところだった。
この海域は魚やエビが豊かだった。貧しくて船を持てなくても、海岸で漁網を投げるだけで、十分に食べることができた。
引退して20年近くになる77歳の元漁民、クアン・ヴァン・マイさんは、豊かなこの海を駆け回った時代を回想し、熱っぽく語った。
「1日漁に出れば、半月は食っていけたもんだよ」
その黄金時代、マイさんは島でもっとも裕福な民であった。
彼は4隻の漁船を持ち、漁に出るときには60人のタンアンの青年を引き連れていた。
船は魚やエビで重くなり、彼らはその足でヴンタウの街に行って売りさばいた。
過去を語るときに、古くからの住民は、その頃は海の恵みで豊かに暮らせただけではなく、現在のような不測の天災の心配もなかったと口を揃える。
人々は木と葉っぱで簡素な家を建てれば、安心して暮らすことができた。
彼らにとって、台風など、どこか遠いところの話でしかなかったのだ。
現在の不安
「ドリアン台風(2006年12月)がやってきたとき、はじめ、人々はとても楽観的に考えていました。台風がこの小さな島を破壊してしまうかもしれない、などとは、人々にはとても信じられなかったのです」。
タンアン農民会主席のレ・ホン・フックさんは、思い出しながら語った。
台風が通り過ぎ、100戸以上の家が倒壊し廃墟になったさまを目にして、海に囲まれたこの小さな島があまりにも脆い存在であるということを、人々は初めて痛感させられたのだった。
フックさんによれば、それでも天の神様はタンアンを見放してはいなかった。
もし台風が連続してやってきて、幅が数百メートルしかない島に高潮と高波が襲いかかり、家屋を押し潰してしまっていたら、島の人々の生命と財産にもっと重大な被害が出ていただろう、と。
私を案内してくれたバイクタクシー運転手(10分足らずで島のすべての道を走り尽くしてしまったのだが)のグエン・タン・ドゥックさんは言う。
「去年のドリアン台風のあと、タンアンの人たちは、この島が海に浮かぶ木の葉のように頼りないものだと感じて、恐れを抱くようになりました」。
多くの専門家も、次の点を指摘している。
この島があまりにも小さく、土地は非常に低く、家は簡素に建てられていること。
また、高波や暴風から身を守ってくれる高台や森がなく、内陸の街からはエンジン船で少なくとも30分以上かかるため、もし大きな台風に直撃されれば、想像もつかないような被害を蒙ることになるだろう。
とくに、最近では大型台風が頻繁にやってくるようになり、自然災害の規模はますます予測しがたくなっている、という。
ホーチミン市人民委員会のレ・ホアン・クアン主席は、カンザーを視察したあと、島の人々を速やかに内陸に移住させることを決定した。
タンアン農民会のフックさんは、昼間に青年たちがたむろして、賭けトランプ遊びなどをしている様子を私に見せ、これもまた島が抱えている問題なのだと指摘した。
「自然災害のほかに、経済の行き詰まりと社会問題もまた、移住しなければならない理由なのです」。
島で生まれ、40歳過ぎになるフックさんは、タンアンの経済状況について熟知している。
フックさんによると、タンアン一帯の漁場の水産資源は、1990年代以後、次第に減少している。
とくに、ティヴァイ川の水が工場排水によってひどく汚染されるようになったあとは、魚やエビが激減してしまった。
「かつて、タンアンの漁民は1日働けば半月は生活できる、と言われたものですが、いまではその日食べる分を獲るのが精一杯です。船の燃料代にも満たない日さえあります」。
私が島を離れる前、ホーチミン市人民議会の代表が、タンアン住民との意見交換会を行った。
移住の件に関して、多くの意見が集中した。
数名の住民は、生まれ育ったこの土地を離れたくない、と主張したが、多数の住民は移住に同意した。
彼らは、内陸に移ることは自分たち自身のためだけでなく、彼らの子や孫にとってもよい結果をもたらすと信じている。
おそらく、内陸では危険な災害から身を守ることもより容易だろうし、将来、子どもたちの学業や就職、医療その他の社会生活の面でもプラスになるだろうと考えている。
三世代の親族が島で暮らしているレ・ヴァン・チュンさん(カンザー郡祖国戦線副主席・元タンアン村主席)は、故郷の人々の気持ちを代弁した。
「親族がいまいちばん不安に思っていることは、海で生きてきた民が、内陸でどのように暮らしていけるのか、ということです。海の中の孤島を出てカンタンの街に定住することは、とてもよいことでしょう。でも、彼らはこれからも漁業や塩作りの仕事をうまくやっていけるでしょうか。もしできないとすれば、代わりにどんな仕事をして生きていけばよいのでしょうか」。
島を出て内陸に戻る船は、ゆっくりと進んでいた。海は穏やかだった。
船にはやはり客が少なかったが、タンアンの人々の苦悶を運んでいるかのように、船の足取りは重く感じられたのだった。
クオック・ヴィエト
ホーチミン市の南東にあたるカンザーの中でも、最も交通不便な場所で、カンタン町から渡し舟を使っていかなければなりません。
この村は、2006年12月のドリアン台風で多くの家屋が全壊するという被害を受けました(このとき、ほとんどの青葉奨学生の家も倒れてしまったそうです)。
その後、行政の指導もあって、近い将来に住民全員が内陸部に移住することに決まったそうです。
少し古い記事ですが、2007年10月18日の「トゥオイチェ」新聞に、「タンアン島、最後の渡し舟」というタンアン村の訪問記事が出ていました。
沖縄委員会会報「Cay Phuong」第20号に載せたものですが、このブログでも紹介したいと思います。
なお、いつもながら翻訳に間違いがあるかもしれませんので、ご了承ください。
(その後、移住について村の人に訊ねたことがありますが、数千人規模の移住になるため、まだかなり先の話になるだろうということでした。)
タンアン島、最後の渡し舟
ホーチミン市カンザー郡。カンタン町の港からタンアン島へ渡る定期船には、客はあまり乗っていなかったが、船体はいつもよりも重そうに見えた。
年老いた船頭は、タバコを吸いながらつぶやいた。
「たぶん、この渡し船も、もうすぐなくなっちまうんだろうな…」
多くの人、多くの家族が、数世代にわたってこの島で生を受け、暮らしを営んできた。
上空から見下ろすと、島はまるで海に浮かんだ木の葉のように頼りなく見える。
ここ数年、台風が続けて襲来し、島を吹き飛ばそうとしているかのように荒れ狂った。
近年、台風はますます凶暴になり、人々は内陸への移住を考えている。
しかし、島を離れるにしても残るにしても、ここの住民にとって、決して容易な選択ではないのだ…。
豊かだった時代
タンアンの古くからの住民の1人、ブイ・ヴァン・ハイさん(81歳)は、タンアン島のヴンタウに面した側の海岸で堤防がひどく崩れかかっており、島全体が海に呑み込まれてしまう危機にある、ということを教えてくれた。
住民と行政は、波を防いで島が生き残れるように、力を合わせて石の防波堤を築かなければならなかった、という。
ハイさんはまた、古老が語り継いできた、島の始まりについての歴史を教えてくれた。
それは、戦争や飢饉を避けて、土地の支配者の下から逃れてきた流民の話であった。
はじめ、彼らは漁をしに来ていたのだが、ヴンタウ・ドンナイ・カンザーに囲まれた湾の中に、美しい地形をした小さな島があるのを、偶然に発見した。
彼らは内陸の土地を捨てて、誘い合ってこの島に住み着くようになった。
島の土地は低く、つねに海水に浸されるため、高床の家を建てなければならなかった。
1960年代からは、島に次々と家が建つようになった。集まって暮らす人々は、数千人にもなり、海の仕事で生計を立てた。
その頃、タンアンはとても暮らしやすいところだった。
この海域は魚やエビが豊かだった。貧しくて船を持てなくても、海岸で漁網を投げるだけで、十分に食べることができた。
引退して20年近くになる77歳の元漁民、クアン・ヴァン・マイさんは、豊かなこの海を駆け回った時代を回想し、熱っぽく語った。
「1日漁に出れば、半月は食っていけたもんだよ」
その黄金時代、マイさんは島でもっとも裕福な民であった。
彼は4隻の漁船を持ち、漁に出るときには60人のタンアンの青年を引き連れていた。
船は魚やエビで重くなり、彼らはその足でヴンタウの街に行って売りさばいた。
過去を語るときに、古くからの住民は、その頃は海の恵みで豊かに暮らせただけではなく、現在のような不測の天災の心配もなかったと口を揃える。
人々は木と葉っぱで簡素な家を建てれば、安心して暮らすことができた。
彼らにとって、台風など、どこか遠いところの話でしかなかったのだ。
現在の不安
「ドリアン台風(2006年12月)がやってきたとき、はじめ、人々はとても楽観的に考えていました。台風がこの小さな島を破壊してしまうかもしれない、などとは、人々にはとても信じられなかったのです」。
タンアン農民会主席のレ・ホン・フックさんは、思い出しながら語った。
台風が通り過ぎ、100戸以上の家が倒壊し廃墟になったさまを目にして、海に囲まれたこの小さな島があまりにも脆い存在であるということを、人々は初めて痛感させられたのだった。
フックさんによれば、それでも天の神様はタンアンを見放してはいなかった。
もし台風が連続してやってきて、幅が数百メートルしかない島に高潮と高波が襲いかかり、家屋を押し潰してしまっていたら、島の人々の生命と財産にもっと重大な被害が出ていただろう、と。
私を案内してくれたバイクタクシー運転手(10分足らずで島のすべての道を走り尽くしてしまったのだが)のグエン・タン・ドゥックさんは言う。
「去年のドリアン台風のあと、タンアンの人たちは、この島が海に浮かぶ木の葉のように頼りないものだと感じて、恐れを抱くようになりました」。
多くの専門家も、次の点を指摘している。
この島があまりにも小さく、土地は非常に低く、家は簡素に建てられていること。
また、高波や暴風から身を守ってくれる高台や森がなく、内陸の街からはエンジン船で少なくとも30分以上かかるため、もし大きな台風に直撃されれば、想像もつかないような被害を蒙ることになるだろう。
とくに、最近では大型台風が頻繁にやってくるようになり、自然災害の規模はますます予測しがたくなっている、という。
ホーチミン市人民委員会のレ・ホアン・クアン主席は、カンザーを視察したあと、島の人々を速やかに内陸に移住させることを決定した。
タンアン農民会のフックさんは、昼間に青年たちがたむろして、賭けトランプ遊びなどをしている様子を私に見せ、これもまた島が抱えている問題なのだと指摘した。
「自然災害のほかに、経済の行き詰まりと社会問題もまた、移住しなければならない理由なのです」。
島で生まれ、40歳過ぎになるフックさんは、タンアンの経済状況について熟知している。
フックさんによると、タンアン一帯の漁場の水産資源は、1990年代以後、次第に減少している。
とくに、ティヴァイ川の水が工場排水によってひどく汚染されるようになったあとは、魚やエビが激減してしまった。
「かつて、タンアンの漁民は1日働けば半月は生活できる、と言われたものですが、いまではその日食べる分を獲るのが精一杯です。船の燃料代にも満たない日さえあります」。
私が島を離れる前、ホーチミン市人民議会の代表が、タンアン住民との意見交換会を行った。
移住の件に関して、多くの意見が集中した。
数名の住民は、生まれ育ったこの土地を離れたくない、と主張したが、多数の住民は移住に同意した。
彼らは、内陸に移ることは自分たち自身のためだけでなく、彼らの子や孫にとってもよい結果をもたらすと信じている。
おそらく、内陸では危険な災害から身を守ることもより容易だろうし、将来、子どもたちの学業や就職、医療その他の社会生活の面でもプラスになるだろうと考えている。
三世代の親族が島で暮らしているレ・ヴァン・チュンさん(カンザー郡祖国戦線副主席・元タンアン村主席)は、故郷の人々の気持ちを代弁した。
「親族がいまいちばん不安に思っていることは、海で生きてきた民が、内陸でどのように暮らしていけるのか、ということです。海の中の孤島を出てカンタンの街に定住することは、とてもよいことでしょう。でも、彼らはこれからも漁業や塩作りの仕事をうまくやっていけるでしょうか。もしできないとすれば、代わりにどんな仕事をして生きていけばよいのでしょうか」。
島を出て内陸に戻る船は、ゆっくりと進んでいた。海は穏やかだった。
船にはやはり客が少なかったが、タンアンの人々の苦悶を運んでいるかのように、船の足取りは重く感じられたのだった。
クオック・ヴィエト
2011年02月21日
「バッチリ話せるベトナム語」
私は、ベトナム語をバッチリ話すことはできないのですが…。
「バッチリ話せる…」は、ベトナム語の学習書のタイトルです。
先月、東京の出版社・三修社から『バッチリ話せるベトナム語』という本が出ました。

監修者は、一橋大学大学院で経済学を学んだライ・ティ・フーン・ニュンさん。
先日届いた「ベトナム子ども基金通信」によると、このニュンさん、なんと元青葉奨学生だそうです。
青葉奨学会代表のホーエ先生(ドンズー日本語学校校長)は、ベトナムの学生を日本に留学させることにも力を入れています。
ドンズーの留学プログラムでは、新聞配達などのアルバイトをしながら2年間日本語を学び、その後日本の大学に入って専門的な勉強をします。
裕福でない家庭の学生でも留学のチャンスが得られるように配慮がされていて、青葉奨学金を受けて勉強した学生たちも、高校卒業後に日本に留学に来る例があります。
ドンズーのプログラムで留学に来た学生とは、私は10名程度しか会ったことがありませんが、みんな本当によく頑張っています。
ニュンさんもその1人で、勉強や仕事のかたわら、アジア文化会館などのベトナム語講座で講師をつとめているそうです。
多くの日本人にベトナム語を教えた経験を生かして、今回、学習書の出版をしたということです。
「このテキストは、ベトナム語の基礎文法を紹介するのはもちろん、実用的なシーン別ですぐに使える表現と語彙も紹介するので、いろいろな目的に使えると思います。例えば、ベトナム旅行に行く前にベトナム語を勉強しておきたい方々、ベトナムとビジネスをする方々、ベトナム語を長く勉強したい方々などです」
青葉の卒業生たちがさまざまな分野で活躍している様子を知るのは、何よりも嬉しいことです。
元奨学生がベトナムと日本の架け橋となって、日本でベトナム語の学習書を出版するなんて、ちょっと感動です。
私はニュンさんにはお会いしたことがありませんが、ぜひ一度お話しを聞いてみたいものです。
ニュンさん、ありがとう。
「バッチリ話せる…」は、ベトナム語の学習書のタイトルです。
先月、東京の出版社・三修社から『バッチリ話せるベトナム語』という本が出ました。

監修者は、一橋大学大学院で経済学を学んだライ・ティ・フーン・ニュンさん。
先日届いた「ベトナム子ども基金通信」によると、このニュンさん、なんと元青葉奨学生だそうです。
青葉奨学会代表のホーエ先生(ドンズー日本語学校校長)は、ベトナムの学生を日本に留学させることにも力を入れています。
ドンズーの留学プログラムでは、新聞配達などのアルバイトをしながら2年間日本語を学び、その後日本の大学に入って専門的な勉強をします。
裕福でない家庭の学生でも留学のチャンスが得られるように配慮がされていて、青葉奨学金を受けて勉強した学生たちも、高校卒業後に日本に留学に来る例があります。
ドンズーのプログラムで留学に来た学生とは、私は10名程度しか会ったことがありませんが、みんな本当によく頑張っています。
ニュンさんもその1人で、勉強や仕事のかたわら、アジア文化会館などのベトナム語講座で講師をつとめているそうです。
多くの日本人にベトナム語を教えた経験を生かして、今回、学習書の出版をしたということです。
「このテキストは、ベトナム語の基礎文法を紹介するのはもちろん、実用的なシーン別ですぐに使える表現と語彙も紹介するので、いろいろな目的に使えると思います。例えば、ベトナム旅行に行く前にベトナム語を勉強しておきたい方々、ベトナムとビジネスをする方々、ベトナム語を長く勉強したい方々などです」
青葉の卒業生たちがさまざまな分野で活躍している様子を知るのは、何よりも嬉しいことです。
元奨学生がベトナムと日本の架け橋となって、日本でベトナム語の学習書を出版するなんて、ちょっと感動です。
私はニュンさんにはお会いしたことがありませんが、ぜひ一度お話しを聞いてみたいものです。
ニュンさん、ありがとう。
Posted by クアン at
23:42
│Comments(1)
2011年02月20日
2011年アレン・ネルソン奨学金支給式
ベトナムから、2011年のアレン・ネルソン奨学金支給式の報告が届きました。
昨年の第1回支給式には私も参加しましたが、今回は現地に行くことはできませんでした。
ドンズー日本語学校ダナン校の方々が支給式に参加して、子どもたちにお金を渡してくれました。
今回の支給式は、1月25日に、クアンナム省タムキー市の公会堂で行われました。
タムキー市は、1966年から翌年にかけてアレン・ネルソンさんが米海兵隊員として駐留していた場所です。
今回の奨学金は、タムキー市の近郊に住む小学生120名に、それぞれ50万ドン(約2200円)が配られました。
ホーチミン市の銀行には、200万円余りのお金がアレン・ネルソン基金として預けられていて、青葉奨学会の管理のもと、その利子が奨学金として活用されています。

タムキー市の学習奨励会には、就学支援を必要としている生徒たちの名簿があり、優先度の高いほうから120名の小学生が選ばれた、ということです。
奨学金の配布にあたって、ドンズー・ダナン校のタン先生が、アレン・ネルソンさんのことや、奨学金発足にいたるいきさつについて説明してくれました。

奨学金の配布などを手伝って下さったスタッフの皆さんです。ドンズー・ダナン校の皆さんは、学校の運営で忙しい中、多くの時間を割いて奨学金の準備や配布をしてくれました。

今回もアレンさんの本のベトナム語版を配ってもらうつもりでいたのですが、支給式までに送ることができず、本は配布できませんでした。
できれば、これからでも奨学生たちに配れるように手配したいと思います。
昨年支給式に参加したさい、私たちは会場で1人の子どもにお願いして、家を訪ねさせてもらいました。
タムキー市近郊のつつましい農家で、大きな台風被害の後ということもあって、生活はかなり厳しそうでした。
学習奨励会の方々は、奨学生の選考を良心的にやって下さっている、という印象を持ちました。
今年も、基本的に同じような家庭状況の子どもたちが選ばれていると思います。
来年以降も、利子を活用して奨学金の支給が続けられる予定です。
私の印象では、お金は有効に活用されていると感じていますが、現在のやり方では、相手の顔が見えにくいという問題があると思います。
アレン・ネルソンさんの名前をつけた奨学金ですので、アレンさんの友人や支援者の方々と、奨学金の対象となる子どもたちや地域の方々が、何らかの継続的なつながりを持てるような方法を工夫できないか、と思っています。
クアンナム省の山間部のいくつかの村に対象を絞って、継続的に支援をするような形ができないか、または、施設の子どもたちへの奨学金支援はどうなのか、などを考えています。
いずれにしても、ベトナム側の意向や事情がとても大切なので、私たちが勝手に決めることはできません。
もし可能であれば、近いうちに一度ダナンとクアンナムを訪ねて、これからの進め方について現地の方々と話し合ってみたいと思っています。
ご意見などありましたら、お寄せいただけると幸いです。
昨年の第1回支給式には私も参加しましたが、今回は現地に行くことはできませんでした。
ドンズー日本語学校ダナン校の方々が支給式に参加して、子どもたちにお金を渡してくれました。
今回の支給式は、1月25日に、クアンナム省タムキー市の公会堂で行われました。
タムキー市は、1966年から翌年にかけてアレン・ネルソンさんが米海兵隊員として駐留していた場所です。
今回の奨学金は、タムキー市の近郊に住む小学生120名に、それぞれ50万ドン(約2200円)が配られました。
ホーチミン市の銀行には、200万円余りのお金がアレン・ネルソン基金として預けられていて、青葉奨学会の管理のもと、その利子が奨学金として活用されています。
タムキー市の学習奨励会には、就学支援を必要としている生徒たちの名簿があり、優先度の高いほうから120名の小学生が選ばれた、ということです。
奨学金の配布にあたって、ドンズー・ダナン校のタン先生が、アレン・ネルソンさんのことや、奨学金発足にいたるいきさつについて説明してくれました。
奨学金の配布などを手伝って下さったスタッフの皆さんです。ドンズー・ダナン校の皆さんは、学校の運営で忙しい中、多くの時間を割いて奨学金の準備や配布をしてくれました。
今回もアレンさんの本のベトナム語版を配ってもらうつもりでいたのですが、支給式までに送ることができず、本は配布できませんでした。
できれば、これからでも奨学生たちに配れるように手配したいと思います。
昨年支給式に参加したさい、私たちは会場で1人の子どもにお願いして、家を訪ねさせてもらいました。
タムキー市近郊のつつましい農家で、大きな台風被害の後ということもあって、生活はかなり厳しそうでした。
学習奨励会の方々は、奨学生の選考を良心的にやって下さっている、という印象を持ちました。
今年も、基本的に同じような家庭状況の子どもたちが選ばれていると思います。
来年以降も、利子を活用して奨学金の支給が続けられる予定です。
私の印象では、お金は有効に活用されていると感じていますが、現在のやり方では、相手の顔が見えにくいという問題があると思います。
アレン・ネルソンさんの名前をつけた奨学金ですので、アレンさんの友人や支援者の方々と、奨学金の対象となる子どもたちや地域の方々が、何らかの継続的なつながりを持てるような方法を工夫できないか、と思っています。
クアンナム省の山間部のいくつかの村に対象を絞って、継続的に支援をするような形ができないか、または、施設の子どもたちへの奨学金支援はどうなのか、などを考えています。
いずれにしても、ベトナム側の意向や事情がとても大切なので、私たちが勝手に決めることはできません。
もし可能であれば、近いうちに一度ダナンとクアンナムを訪ねて、これからの進め方について現地の方々と話し合ってみたいと思っています。
ご意見などありましたら、お寄せいただけると幸いです。
2011年02月11日
ベトナムの「雪の華」
何年か前になりますが、私たちのベトナム語講座に、Tさんというベトナム人の若い神父さんが時々遊びに来てくれました。
Tさんは歌が好きな人で、何曲か披露してくれたこともありました。
日本の歌の中でいちばん好きなのは何かと訊ねてみると、中島美嘉さんの「雪の華」ということでした。
その後、ホーチミン市で日本語を勉強している女の子と何度かメールのやりとりをする機会がありました。
彼女も歌が好きで、日本の歌の練習をしていると言っていました。
いちばん好きなのは中島美嘉さんの「雪の華」と絢香の「三日月」なのだが、どちらもたいへん難しい、というようなことを教えてくれました。
私の狭い見聞ではありますが、「雪の華」はベトナム人にかなり好かれているみたいです。
私は何度か聞いたことがあるぐらいで、それほどよく知らなかったのですが、改めて聞いてみると素晴らしい曲で、大好きな歌になりました。
私にとっては、ベトナム人たちが教えてくれた名曲です。
調べてみると、「雪の華」はベトナム人の歌手もカバーしています。
ただし、タイトルは「Xin loi anh yeu em」になっています。「ごめん愛してる」という感じで、元の日本語の歌詞とはだいぶ内容が違っているみたいです。ベトナム語の歌詞の中には、雪は出てきません。
これは、Minh Vuongという男性歌手が歌っている「Xin loi anh yeu em」、ベトナム語版「雪の華」です。
実は、「ごめん愛してる」というのは、6年ぐらい前に韓国で人気になったドラマのタイトルで、その主題歌に「雪の華」が使われていたそうです。
日本と同じように、ベトナムでも韓流ドラマは大人気です。私がよく利用しているホテルのロビーでは、韓国のドラマの時間になると、オーナーの家族や従業員たちがいつもテレビに見入っています。
おそらく、このドラマもベトナムで放映されて、人気を集めたのでしょう。
それで、主題歌の「雪の華」が、「ごめん愛してる」というタイトルでカバーされたのだと思います。
日本に関心の深い人は別として、多くのベトナム人は、この歌は韓国の歌だと思っているかもしれませんね。
ところで、「雪の華」は中国でもよく知られているみたいです。
こちらは失恋の歌になっていて、舞台はなぜか「伊豆温泉(?)」だそうです。なんか不思議…。
歌っているのは韓雪(ハン・シュエ)という、とても美人の歌手。うっとり見とれてしまいます。
韓雪さんが歌っているのは「飄雪」というタイトルになっていますが、「雪の華」は「対不起、我愛你」というタイトルでも歌われているそうです。
私は中国語は「你好」と「謝謝」と「迷你裙」ぐらいしか知りませんが、「対不起、我愛你」はたぶん「ごめん愛してる」でしょう。
韓流ドラマの影響力は、中国でもすごいみたいです。
日本で生まれた名曲が、韓国のドラマに取り入れられて、アジアの各地で受け入れられていくのって面白いなあと思います。
ベトナムの歌も、日本でももっと知られるといいなあ…。
そんなわけで、日本・ベトナム・中国それぞれの「雪の華」でした。
Tさんは歌が好きな人で、何曲か披露してくれたこともありました。
日本の歌の中でいちばん好きなのは何かと訊ねてみると、中島美嘉さんの「雪の華」ということでした。
その後、ホーチミン市で日本語を勉強している女の子と何度かメールのやりとりをする機会がありました。
彼女も歌が好きで、日本の歌の練習をしていると言っていました。
いちばん好きなのは中島美嘉さんの「雪の華」と絢香の「三日月」なのだが、どちらもたいへん難しい、というようなことを教えてくれました。
私の狭い見聞ではありますが、「雪の華」はベトナム人にかなり好かれているみたいです。
私は何度か聞いたことがあるぐらいで、それほどよく知らなかったのですが、改めて聞いてみると素晴らしい曲で、大好きな歌になりました。
私にとっては、ベトナム人たちが教えてくれた名曲です。
調べてみると、「雪の華」はベトナム人の歌手もカバーしています。
ただし、タイトルは「Xin loi anh yeu em」になっています。「ごめん愛してる」という感じで、元の日本語の歌詞とはだいぶ内容が違っているみたいです。ベトナム語の歌詞の中には、雪は出てきません。
これは、Minh Vuongという男性歌手が歌っている「Xin loi anh yeu em」、ベトナム語版「雪の華」です。
実は、「ごめん愛してる」というのは、6年ぐらい前に韓国で人気になったドラマのタイトルで、その主題歌に「雪の華」が使われていたそうです。
日本と同じように、ベトナムでも韓流ドラマは大人気です。私がよく利用しているホテルのロビーでは、韓国のドラマの時間になると、オーナーの家族や従業員たちがいつもテレビに見入っています。
おそらく、このドラマもベトナムで放映されて、人気を集めたのでしょう。
それで、主題歌の「雪の華」が、「ごめん愛してる」というタイトルでカバーされたのだと思います。
日本に関心の深い人は別として、多くのベトナム人は、この歌は韓国の歌だと思っているかもしれませんね。
ところで、「雪の華」は中国でもよく知られているみたいです。
こちらは失恋の歌になっていて、舞台はなぜか「伊豆温泉(?)」だそうです。なんか不思議…。
歌っているのは韓雪(ハン・シュエ)という、とても美人の歌手。うっとり見とれてしまいます。
韓雪さんが歌っているのは「飄雪」というタイトルになっていますが、「雪の華」は「対不起、我愛你」というタイトルでも歌われているそうです。
私は中国語は「你好」と「謝謝」と「迷你裙」ぐらいしか知りませんが、「対不起、我愛你」はたぶん「ごめん愛してる」でしょう。
韓流ドラマの影響力は、中国でもすごいみたいです。
日本で生まれた名曲が、韓国のドラマに取り入れられて、アジアの各地で受け入れられていくのって面白いなあと思います。
ベトナムの歌も、日本でももっと知られるといいなあ…。
そんなわけで、日本・ベトナム・中国それぞれの「雪の華」でした。
2011年01月30日
2月定例会のお知らせ
青葉奨学会沖縄委員会の今年最初の定例会を、2月5日に行います。
2月5日(土)午後7時より
場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)
参加費 500円
今回は、沖縄NGOセンターの皆さんと一緒に企画した集まりです。
フィリピンやモンゴルなど、さまざまな国や地域と関わっている人たちのお話しを聞けると思います。
また、2月5日は旧暦の1月3日になりますので、テト(旧正月)のお祝いも兼ねて行います。
ベトナムの正月料理の定番「バインチュン」も用意する予定です(そのため、今回に限り有料としました)。
いつも通り、一品持ち寄りも歓迎します。
会員でない方の参加も、もちろん大歓迎です。
ベトナムや各地のお話しを聞いてみたい方、「バインチュンってどんなもの?食べてみたい」という方、どうぞ気軽にお越し下さい。
お問い合わせは、080-2719-4720(村田)までお願いします。
2月5日(土)午後7時より
場所 すぺーす結(一銀通り安木屋向かいの久茂地マンション402号室)
参加費 500円
今回は、沖縄NGOセンターの皆さんと一緒に企画した集まりです。
フィリピンやモンゴルなど、さまざまな国や地域と関わっている人たちのお話しを聞けると思います。
また、2月5日は旧暦の1月3日になりますので、テト(旧正月)のお祝いも兼ねて行います。
ベトナムの正月料理の定番「バインチュン」も用意する予定です(そのため、今回に限り有料としました)。
いつも通り、一品持ち寄りも歓迎します。
会員でない方の参加も、もちろん大歓迎です。
ベトナムや各地のお話しを聞いてみたい方、「バインチュンってどんなもの?食べてみたい」という方、どうぞ気軽にお越し下さい。
お問い合わせは、080-2719-4720(村田)までお願いします。
2011年01月29日
沖縄のヒヌカンとベトナムのタオクアン(2)
★タオクアンを送り出す儀式をベトナムで見てきたそうですが、どのような儀式を行っているのですか。
☆今回、タオクアンについて調べるにあたって、琉大に来ている留学生のKくんに、いろいろ質問しました。
Kくんは実家のお母さんに電話して、私の疑問について詳しく問い合わせてくれました。
タオクアンの儀式についても、「ぼくの実家に見に行ってみたら」と持ちかけてくれたので、2009年の2月にベトナムに行って見学させていただきました。
Kくんの実家は北部のタイビン省の農村部にあります。
タオクアンの儀式はお母さんが中心になって行っていましたが、ハノイの大学に行っているKくんの妹さんも帰省してお手伝いをしていました。
お父さんのほうは、料理などを少し手伝ってはいましたが、タオクアンの儀式にはあまり関心はないようでした。
ベトナムの北部では、タオクアンは鯉に乗って天に昇ると考えられています。(こんなイメージ)

陰暦12月23日には、市場の周辺に、鯉を売る人がたくさん集まります。
Kくんの実家でも、妹さんが市場に出かけて、鯉を3匹と祭壇に供える花を買っていました。
家では、お母さんが鶏をさばいて、お供え物の料理の準備をします。
祭壇には、花や果物、お酒、おこわ、線香、紙銭、鯉3匹をお供えして、祭壇の電気をつけます。料理が完成すると、それをお供えして、お母さんがタオクアンへの祈願の言葉を唱えます。
祈願の内容は、家族の健康と幸運、子どもたちの学業の進歩などを祈るものです。
祈願文の一部を紹介すると、
「あなたは私たちを観察する神です
俗世間の私たちの犯した罪を判断します
あなたの心の広さで私たちの過ちを許して下さい」
「今日、あなたは天に帰ります
衷心よりお願いしたいことがあります
百姓(一般の人民)が平穏でありますように
家族が穏やかに仲良くいられますように
葉のように青く、花のように美しく
若者も年寄りも安楽に新年を迎えられますように
(氏名・住所を述べて)一心にお祈りします
南無阿弥陀仏(ナモアジダファット)」
タオクアンへの祈願が終わると、紙銭や「マー」と呼ばれる紙の冥器を、庭で燃やします。
そのあと、祭壇に供えた鯉を、川に放しに行きます。
ひと通り儀式が終わると、祭壇に供えた料理を下げて、家族みんなで食事をして終了です。
★ベトナムでは、タオクアンに関する言い伝えのようなものはあるのでしょうか。
☆いくつかの言い伝えがあります。細かい部分ではそれぞれ違いがあるのですが、大筋ではほぼ共通しています。
共通しているのは、次のようなあらすじです。
「1組の夫婦が、理由はさまざまだが離婚し、その後妻は再婚する。
夫は乞食となり、元の妻の家に、それとは知らずに物乞いに行く。
妻は前夫をもてなすが、新しい夫が戻ってきたので、積んである藁の中に前夫を隠す。
新しい夫は、前夫が隠れているとは知らずに藁を燃やす。
妻は前夫を助けようと火に飛び込み、2人とも焼死してしまう。
新しい夫もそれを悲しんで火に飛び込み、死ぬ。
天の神(または地の神)が、この3人を台所の神とした」
タオクアンの言い伝えは、学校の教科書にも取り上げられているそうで、ベトナムでは誰もが知っている有名な話です。
★そうすると、タオクアンの神様は3人ということになるのでしょうか。また、沖縄のヒヌカンの場合は、どうなのでしょうか。
☆その通りで、タオクアンは女1人と男2人の神様だと考えられています。
これは、かまどが3つの石からできていたことと関連があると思います。
また、かつてベトナムが母系社会だったことと結びつけて解釈する方もいるようです。
沖縄のヒヌカンの場合は、3人の神様だと考えている方もいれば、1人または2人と考えている方もいて、まちまちです。
1人という考え方は、中国の影響を受けているのではとも思いますが、沖縄では、神様の人数についてはあまり重視されていないようです。
★ベトナムのタオクアンと沖縄のヒヌカンで異なっている点は、ほかにはどんなことがありますか。
☆沖縄の場合、家庭で祀られるヒヌカンのほかに、「村・殿・ノロ・地頭・門中などの火の神」がありますが、ベトナムのタオクアンは、家庭で祀られるものだけです。
また、沖縄のヒヌカンには、祭壇の香炉を通してさまざまな神様と交信する、「お通し」といわれるインターネットのような役割があると考えられていますが、ベトナムではこのような考え方はありません。
それと、ヒヌカンの場合は「火の神(ヒヌカン)」という名称が表しているように、火に対する信仰の要素があります。
ベトナムでも、もともとは火を神聖なものとして考えていたようですが、現代のベトナム人には、タオクアンの中に「火の神(than lua)」を信仰するという意識は残ってないようです。
タオクアンの場合、むしろ土地の神様と結びつけて考えられる傾向があります。
★先日、Googleに「tao quan」と入力して検索してみたところ、「Tao Quan 2010」などと題された多くの動画がアップされていました。試しに見てみると、どうもお笑いの劇のようでした。
このお笑い劇は、かまど神のタオクアンとどんな関係があるのですか。
☆毎年、年末になると、タオクアンの3人の神様をはじめ、玉皇上帝やその他の神様が登場して、その年の世相を風刺するというお笑い劇が演じられます。
もちろん本物の神様が出てくるわけではなくて、俳優が演じるわけですが…。

この劇は「タオクアン」というタイトルで全国放映されて、人気を集めています。
この番組は、テト休みの間中、何度も再放送されています。
★なるほど。タオクアンは、単にかまどの神様として信仰の対象であるだけでなく、ベトナムの人たちに親しまれるキャラクターでもあるようですね…。
ところで、ベトナムの共産党政権は「信教の自由は認めるが、迷信は禁止する」という政策をとっていると聞いたことがあります。タオクアンへの信仰が、政府によって禁止されたことはあったのでしょうか。
☆占い師などが、「迷信を広めて社会を混乱させる」という理由で、規制を受けることはあったようですが、タオクアンの信仰が禁止されたことはないようです。
ベトナムの場合、中国の文革やカンボジアのポルポト時代のような極端な政策はとっていないので、タオクアン信仰のように広く普及した習慣を取り締まるようなことはしてこなかったのだと思います。
とはいっても、戦争や貧困の時代が長く続くなかで、タオクアンへの信仰を守り続けるのは、庶民にとって大変なことだったはずです。
今回お話しを聞かせていただいた方々も、「貧しい時代には、生活していくことで精一杯で、儀式の日のお供えもほとんど用意できなかった」と話していらっしゃいました。
それでも、どのような厳しい時代でも、タオクアンへの信仰や儀式は途切れることなく続けられてきたそうです。
★ありがとうございます。最後に、このテーマについて、これからも研究を続ける予定はありますか。
☆今回タオクアンについて調べてみて、ベトナムの民間信仰について知ったというだけでなく、ベトナムの人たちの、家族の健康や幸せを祈る強い気持ちを感じました。
タオクアンについて研究を続ける予定は、いまのところないのですが、ベトナムの人たちともっと話をしたい、ベトナムの人たちの暮らしや考え方をもっと知りたい、という気持ちはさらに強くなりました。
ですから、ベトナム語をもっと勉強して、聞き取りや資料を読む力をつけた上で、もしできれば、将来もう一度このテーマに挑戦してみたいと思っています。
☆今回、タオクアンについて調べるにあたって、琉大に来ている留学生のKくんに、いろいろ質問しました。
Kくんは実家のお母さんに電話して、私の疑問について詳しく問い合わせてくれました。
タオクアンの儀式についても、「ぼくの実家に見に行ってみたら」と持ちかけてくれたので、2009年の2月にベトナムに行って見学させていただきました。
Kくんの実家は北部のタイビン省の農村部にあります。
タオクアンの儀式はお母さんが中心になって行っていましたが、ハノイの大学に行っているKくんの妹さんも帰省してお手伝いをしていました。
お父さんのほうは、料理などを少し手伝ってはいましたが、タオクアンの儀式にはあまり関心はないようでした。
ベトナムの北部では、タオクアンは鯉に乗って天に昇ると考えられています。(こんなイメージ)

陰暦12月23日には、市場の周辺に、鯉を売る人がたくさん集まります。
Kくんの実家でも、妹さんが市場に出かけて、鯉を3匹と祭壇に供える花を買っていました。
家では、お母さんが鶏をさばいて、お供え物の料理の準備をします。
祭壇には、花や果物、お酒、おこわ、線香、紙銭、鯉3匹をお供えして、祭壇の電気をつけます。料理が完成すると、それをお供えして、お母さんがタオクアンへの祈願の言葉を唱えます。
祈願の内容は、家族の健康と幸運、子どもたちの学業の進歩などを祈るものです。
祈願文の一部を紹介すると、
「あなたは私たちを観察する神です
俗世間の私たちの犯した罪を判断します
あなたの心の広さで私たちの過ちを許して下さい」
「今日、あなたは天に帰ります
衷心よりお願いしたいことがあります
百姓(一般の人民)が平穏でありますように
家族が穏やかに仲良くいられますように
葉のように青く、花のように美しく
若者も年寄りも安楽に新年を迎えられますように
(氏名・住所を述べて)一心にお祈りします
南無阿弥陀仏(ナモアジダファット)」
タオクアンへの祈願が終わると、紙銭や「マー」と呼ばれる紙の冥器を、庭で燃やします。
そのあと、祭壇に供えた鯉を、川に放しに行きます。
ひと通り儀式が終わると、祭壇に供えた料理を下げて、家族みんなで食事をして終了です。
★ベトナムでは、タオクアンに関する言い伝えのようなものはあるのでしょうか。
☆いくつかの言い伝えがあります。細かい部分ではそれぞれ違いがあるのですが、大筋ではほぼ共通しています。
共通しているのは、次のようなあらすじです。
「1組の夫婦が、理由はさまざまだが離婚し、その後妻は再婚する。
夫は乞食となり、元の妻の家に、それとは知らずに物乞いに行く。
妻は前夫をもてなすが、新しい夫が戻ってきたので、積んである藁の中に前夫を隠す。
新しい夫は、前夫が隠れているとは知らずに藁を燃やす。
妻は前夫を助けようと火に飛び込み、2人とも焼死してしまう。
新しい夫もそれを悲しんで火に飛び込み、死ぬ。
天の神(または地の神)が、この3人を台所の神とした」
タオクアンの言い伝えは、学校の教科書にも取り上げられているそうで、ベトナムでは誰もが知っている有名な話です。
★そうすると、タオクアンの神様は3人ということになるのでしょうか。また、沖縄のヒヌカンの場合は、どうなのでしょうか。
☆その通りで、タオクアンは女1人と男2人の神様だと考えられています。
これは、かまどが3つの石からできていたことと関連があると思います。
また、かつてベトナムが母系社会だったことと結びつけて解釈する方もいるようです。
沖縄のヒヌカンの場合は、3人の神様だと考えている方もいれば、1人または2人と考えている方もいて、まちまちです。
1人という考え方は、中国の影響を受けているのではとも思いますが、沖縄では、神様の人数についてはあまり重視されていないようです。
★ベトナムのタオクアンと沖縄のヒヌカンで異なっている点は、ほかにはどんなことがありますか。
☆沖縄の場合、家庭で祀られるヒヌカンのほかに、「村・殿・ノロ・地頭・門中などの火の神」がありますが、ベトナムのタオクアンは、家庭で祀られるものだけです。
また、沖縄のヒヌカンには、祭壇の香炉を通してさまざまな神様と交信する、「お通し」といわれるインターネットのような役割があると考えられていますが、ベトナムではこのような考え方はありません。
それと、ヒヌカンの場合は「火の神(ヒヌカン)」という名称が表しているように、火に対する信仰の要素があります。
ベトナムでも、もともとは火を神聖なものとして考えていたようですが、現代のベトナム人には、タオクアンの中に「火の神(than lua)」を信仰するという意識は残ってないようです。
タオクアンの場合、むしろ土地の神様と結びつけて考えられる傾向があります。
★先日、Googleに「tao quan」と入力して検索してみたところ、「Tao Quan 2010」などと題された多くの動画がアップされていました。試しに見てみると、どうもお笑いの劇のようでした。
このお笑い劇は、かまど神のタオクアンとどんな関係があるのですか。
☆毎年、年末になると、タオクアンの3人の神様をはじめ、玉皇上帝やその他の神様が登場して、その年の世相を風刺するというお笑い劇が演じられます。
もちろん本物の神様が出てくるわけではなくて、俳優が演じるわけですが…。

この劇は「タオクアン」というタイトルで全国放映されて、人気を集めています。
この番組は、テト休みの間中、何度も再放送されています。
★なるほど。タオクアンは、単にかまどの神様として信仰の対象であるだけでなく、ベトナムの人たちに親しまれるキャラクターでもあるようですね…。
ところで、ベトナムの共産党政権は「信教の自由は認めるが、迷信は禁止する」という政策をとっていると聞いたことがあります。タオクアンへの信仰が、政府によって禁止されたことはあったのでしょうか。
☆占い師などが、「迷信を広めて社会を混乱させる」という理由で、規制を受けることはあったようですが、タオクアンの信仰が禁止されたことはないようです。
ベトナムの場合、中国の文革やカンボジアのポルポト時代のような極端な政策はとっていないので、タオクアン信仰のように広く普及した習慣を取り締まるようなことはしてこなかったのだと思います。
とはいっても、戦争や貧困の時代が長く続くなかで、タオクアンへの信仰を守り続けるのは、庶民にとって大変なことだったはずです。
今回お話しを聞かせていただいた方々も、「貧しい時代には、生活していくことで精一杯で、儀式の日のお供えもほとんど用意できなかった」と話していらっしゃいました。
それでも、どのような厳しい時代でも、タオクアンへの信仰や儀式は途切れることなく続けられてきたそうです。
★ありがとうございます。最後に、このテーマについて、これからも研究を続ける予定はありますか。
☆今回タオクアンについて調べてみて、ベトナムの民間信仰について知ったというだけでなく、ベトナムの人たちの、家族の健康や幸せを祈る強い気持ちを感じました。
タオクアンについて研究を続ける予定は、いまのところないのですが、ベトナムの人たちともっと話をしたい、ベトナムの人たちの暮らしや考え方をもっと知りたい、という気持ちはさらに強くなりました。
ですから、ベトナム語をもっと勉強して、聞き取りや資料を読む力をつけた上で、もしできれば、将来もう一度このテーマに挑戦してみたいと思っています。
2011年01月28日
沖縄のヒヌカンとベトナムのタオクアン(1)
来週の木曜日は、旧暦の元日。ベトナムでは、最大の年中行事「テト」。
そろそろテトを迎える準備が本格的に始まっている頃だと思います。
青葉奨学会のホーチミン事務局も、明日で仕事納め。来週はお休みします、との連絡がありました。
一昨日は、ベトナムでは、かまどの神様「タオクアン」を天に送る日でした。
多くの奨学生の家でも、ささやかなお供えをしてタオクアンを送り出したことでしょう。
昨年夏に発行した会報25号に、「沖縄のヒヌカンとベトナムのタオクアン」という特集を載せました。
タオクアンについて調べた会員の鍋田さんに話してもらった内容です。
会報に載せたものを、ブログでも2回に分けてご紹介します。
「ヒヌカン(火の神)」といえば、沖縄ではおなじみの「かまどの神様」ですが、ベトナムにも「タオクアン(Tao Quan)」というかまどの神様がいて、多くの家庭で信仰されています。
この「タオクアン」、実は沖縄の「ヒヌカン」と、とても多くの共通点を持った神様なのだそうです。
会員の鍋田尚子さんが、ベトナムの「タオクアン」について2年間にわたって調べて、このほど大学の卒業論文にまとめました。
これまで誰も取り組んだことのないテーマで、とてもユニークな論文になっています。
「タオクアン」の話は、青葉奨学会沖縄委員会の活動とはあまり関係ないのですが、沖縄とベトナムとの共通点や関わりについて考える上で、たいへん興味深いテーマだと思います。
そこで今回は、ベトナムのタオクアンについて、鍋田さんにお聞きしてみました。
(文責は青葉奨学会沖縄委員会事務局にあります。)
★まず、「ヒヌカン」とはどのような神様なのか、私自身はあまりなじみがないので、簡単に教えて下さい。
☆はじめにお断りしておきたいのですが、私は愛知県の出身で、沖縄のヒヌカンについてよく知っているわけではありません。
それと、今回いろいろと資料を調べてみて、一口に「ヒヌカン」といっても、それぞれの地域や人によって、とても多様な祀り方や考え方があることを知りました。
ですから「沖縄のヒヌカンとはこういうものです」と、私が言うことはできません。
ですが、あまりなじみのない方もいらっしゃると思いますので、ごく一般的なことだけを説明すると、ヒヌカンとは、沖縄の家庭の台所に祀られていて、家庭を見守っている神様です。
昔は、かまどの周辺に石3個を安置していましたが、現在では、炊事場の一隅に香炉や花立て、米、水、酒、塩を安置し線香を立てて祈願します。
ヒヌカンは一家の主婦が管理していて、家族の健康や安全を祈ったり、出来事を報告したりします。ヒヌカンを拝むのは陰暦の1日と15日ですが、毎年12月24日には、ヒヌカンは天に昇って、1年間の家族の行いを天の神様に報告するといわれています。
★そのヒヌカンとよく似た神様が、ベトナムの「タオクアン」というわけですね。「タオクアン」について調べてみようと思ったきっかけは、何ですか。
☆私は2003年6月から2年余り、ベトナムのホーチミン市で日本語を教える仕事をしていました。
帰国したあと、もう一度勉強し直したいと思って、沖縄国際大学に入りました。
沖縄で生活を始めてみると、ベトナムとよく似た場所だなあと感じることが、たびたびありました。
それで、沖縄とベトナムで共通しているものについて調べてみたいと、漠然と思うようになりました。
大学1年生のとき、授業で「ヒヌカン」のことを知って興味を持ったのですが、そのあと琉球大学の那須先生の授業を聴講するようになって、ベトナムでも「ヒヌカン」とよく似た「タオクアン」というかまどの神様が信仰されていることを知りました。
ベトナムで仕事をしていたときには、「タオクアン」のことはまったく知りませんでした。
2年間もベトナムにいながら、現地の文化についてあまりにも知らなかったことを痛感しました。
それで、「タオクアン」を糸口にして、ベトナムの生活や文化、沖縄との関わりについてきちんと勉強してみようと考えました。
★「タオクアン」という言葉には、どのような意味があるのですか。
☆タオクアンは、漢字では「灶(タオ)君(クアン)」と書きます。
「灶」は日本では使われない漢字ですが、「竈」の簡体字で、「かまど」という意味です。
中国や台湾でも、かまどの神様のことを「灶君」と呼んでいます。
ただ、ベトナムでは「タオクアン」というのは公式な名称で、多くの人はふだん「オンタオ(Ong Tao)」と呼んでいるそうです。
「オン」は年配の男性への敬称なので、「タオ様(かまど様)」というような感じになります。
★ベトナムのタオクアンは、どの家庭でも祀られているのでしょうか。
また、ヒヌカンと同じように台所に祀られているのですか。
☆かなり多くの家庭で祀られています。中には、「現在ではかまどからガスコンロに変わったから、タオクアンを祀る必要はない」と言う方もいますが…。
1人暮らしの学生などは普通タオクアンを祀っていませんが、結婚して家庭を持つときには、現在でもたいてい新しくタオクアンを祀ります。
タオクアンを祀る場所としては、ホーチミン市など南部では、台所が多いです。
祭壇には、香炉と一緒に、「灶君」とか「定福灶君」などと書かれた字牌が置かれています。
次の写真は、日本語学校のときの教え子の実家で見せていただいたタオクアンの祭壇です。

字牌には漢字が書かれていますが、字の意味は家族の誰にもわからないそうです。
ちなみに、この家の場合は、祭壇は台所ではなく別の部屋に置かれていました。
北部では、タオクアンの独自の祭壇を祀るのではなくて、祖先の祭壇と一緒に祀られています。
次の写真は、タイビン省の民家で見せていただいた祭壇です。

3つの香炉がありますが、そのうち真ん中にあるのがタオクアンの香炉だそうです。
北部では字牌は見かけませんでした。
祖先の祭壇と一緒なので、祀る場所は台所ではありませんが、タオクアンが台所の神様であるということは、はっきり意識されています。
以上は現在の祭壇ですが、過去には、タオクアンは3つの石を祀っていたそうです。
タオクアンには「オンダウラウ(Ong Dau Rau)」という呼び方もありますが、「ダウラウ」とは、煮炊きのときに鍋を乗せるために使う3本の足のことだそうです。
沖縄のヒヌカンでも、かつては3つの石を祀っていて、「オミチモン」などとも呼ばれています。
この点は、タオクアンとヒヌカンの大きな共通点だと思います。
★ベトナムのタオクアンも、陰暦12月24日に天に昇って、天の神様に報告をするのでしょうか。
☆ベトナムの場合は、天に昇る日が沖縄よりも1日早くて、陰暦12月23日になります。
タオクアンはこの日に天に昇って、家族の1年間の行いのすべてを、玉皇上帝という神様に報告すると考えられています。
タオクアンを天に送り出す儀式は、ベトナムではとても大切なものと考えられていて、キリスト教徒など、ふだんタオクアンを祀っていない人たちでも、この日には家でお供えをして儀式を行うそうです。
ベトナム人にとっていちばん大切な年中行事は、なんといってもテト(旧正月)ですが、タオクアンの儀式
が終わると、本格的に新年を迎える準備に入ります。
ですから、1年の締めくくりという意味もあります。
この日に天に昇ったタオクアンは、陰暦の大晦日(12月30日)の深夜に家庭に戻ってくると考えられています。
玉皇上帝というのは、中国の道教で最高神と考えられている神様です。
かまどの神様が年末に天に昇るという考え方は、もともと中国の道教で生まれたものです。
中国で生まれた考え方が、一方ではベトナムに伝わり、また一方では琉球に伝わりました。
ベトナムでも琉球でも、火やかまどに対する土着の信仰がもともとありましたが、その土着の信仰と、中国から伝わった考え方が結びついて、それぞれに発展していったわけです。
ヒヌカンにもタオクアンにも、道教だけでなく、仏教や儒教、祖先崇拝、精霊信仰など、いろいろな要素が入っていますが、ベトナムの場合は「灶君」や「玉皇上帝」という名前がそのまま使われているなど、中国の道教の影響がより強いと思います。
そろそろテトを迎える準備が本格的に始まっている頃だと思います。
青葉奨学会のホーチミン事務局も、明日で仕事納め。来週はお休みします、との連絡がありました。
一昨日は、ベトナムでは、かまどの神様「タオクアン」を天に送る日でした。
多くの奨学生の家でも、ささやかなお供えをしてタオクアンを送り出したことでしょう。
昨年夏に発行した会報25号に、「沖縄のヒヌカンとベトナムのタオクアン」という特集を載せました。
タオクアンについて調べた会員の鍋田さんに話してもらった内容です。
会報に載せたものを、ブログでも2回に分けてご紹介します。
「ヒヌカン(火の神)」といえば、沖縄ではおなじみの「かまどの神様」ですが、ベトナムにも「タオクアン(Tao Quan)」というかまどの神様がいて、多くの家庭で信仰されています。
この「タオクアン」、実は沖縄の「ヒヌカン」と、とても多くの共通点を持った神様なのだそうです。
会員の鍋田尚子さんが、ベトナムの「タオクアン」について2年間にわたって調べて、このほど大学の卒業論文にまとめました。
これまで誰も取り組んだことのないテーマで、とてもユニークな論文になっています。
「タオクアン」の話は、青葉奨学会沖縄委員会の活動とはあまり関係ないのですが、沖縄とベトナムとの共通点や関わりについて考える上で、たいへん興味深いテーマだと思います。
そこで今回は、ベトナムのタオクアンについて、鍋田さんにお聞きしてみました。
(文責は青葉奨学会沖縄委員会事務局にあります。)
★まず、「ヒヌカン」とはどのような神様なのか、私自身はあまりなじみがないので、簡単に教えて下さい。
☆はじめにお断りしておきたいのですが、私は愛知県の出身で、沖縄のヒヌカンについてよく知っているわけではありません。
それと、今回いろいろと資料を調べてみて、一口に「ヒヌカン」といっても、それぞれの地域や人によって、とても多様な祀り方や考え方があることを知りました。
ですから「沖縄のヒヌカンとはこういうものです」と、私が言うことはできません。
ですが、あまりなじみのない方もいらっしゃると思いますので、ごく一般的なことだけを説明すると、ヒヌカンとは、沖縄の家庭の台所に祀られていて、家庭を見守っている神様です。
昔は、かまどの周辺に石3個を安置していましたが、現在では、炊事場の一隅に香炉や花立て、米、水、酒、塩を安置し線香を立てて祈願します。
ヒヌカンは一家の主婦が管理していて、家族の健康や安全を祈ったり、出来事を報告したりします。ヒヌカンを拝むのは陰暦の1日と15日ですが、毎年12月24日には、ヒヌカンは天に昇って、1年間の家族の行いを天の神様に報告するといわれています。
★そのヒヌカンとよく似た神様が、ベトナムの「タオクアン」というわけですね。「タオクアン」について調べてみようと思ったきっかけは、何ですか。
☆私は2003年6月から2年余り、ベトナムのホーチミン市で日本語を教える仕事をしていました。
帰国したあと、もう一度勉強し直したいと思って、沖縄国際大学に入りました。
沖縄で生活を始めてみると、ベトナムとよく似た場所だなあと感じることが、たびたびありました。
それで、沖縄とベトナムで共通しているものについて調べてみたいと、漠然と思うようになりました。
大学1年生のとき、授業で「ヒヌカン」のことを知って興味を持ったのですが、そのあと琉球大学の那須先生の授業を聴講するようになって、ベトナムでも「ヒヌカン」とよく似た「タオクアン」というかまどの神様が信仰されていることを知りました。
ベトナムで仕事をしていたときには、「タオクアン」のことはまったく知りませんでした。
2年間もベトナムにいながら、現地の文化についてあまりにも知らなかったことを痛感しました。
それで、「タオクアン」を糸口にして、ベトナムの生活や文化、沖縄との関わりについてきちんと勉強してみようと考えました。
★「タオクアン」という言葉には、どのような意味があるのですか。
☆タオクアンは、漢字では「灶(タオ)君(クアン)」と書きます。
「灶」は日本では使われない漢字ですが、「竈」の簡体字で、「かまど」という意味です。
中国や台湾でも、かまどの神様のことを「灶君」と呼んでいます。
ただ、ベトナムでは「タオクアン」というのは公式な名称で、多くの人はふだん「オンタオ(Ong Tao)」と呼んでいるそうです。
「オン」は年配の男性への敬称なので、「タオ様(かまど様)」というような感じになります。
★ベトナムのタオクアンは、どの家庭でも祀られているのでしょうか。
また、ヒヌカンと同じように台所に祀られているのですか。
☆かなり多くの家庭で祀られています。中には、「現在ではかまどからガスコンロに変わったから、タオクアンを祀る必要はない」と言う方もいますが…。
1人暮らしの学生などは普通タオクアンを祀っていませんが、結婚して家庭を持つときには、現在でもたいてい新しくタオクアンを祀ります。
タオクアンを祀る場所としては、ホーチミン市など南部では、台所が多いです。
祭壇には、香炉と一緒に、「灶君」とか「定福灶君」などと書かれた字牌が置かれています。
次の写真は、日本語学校のときの教え子の実家で見せていただいたタオクアンの祭壇です。
字牌には漢字が書かれていますが、字の意味は家族の誰にもわからないそうです。
ちなみに、この家の場合は、祭壇は台所ではなく別の部屋に置かれていました。
北部では、タオクアンの独自の祭壇を祀るのではなくて、祖先の祭壇と一緒に祀られています。
次の写真は、タイビン省の民家で見せていただいた祭壇です。
3つの香炉がありますが、そのうち真ん中にあるのがタオクアンの香炉だそうです。
北部では字牌は見かけませんでした。
祖先の祭壇と一緒なので、祀る場所は台所ではありませんが、タオクアンが台所の神様であるということは、はっきり意識されています。
以上は現在の祭壇ですが、過去には、タオクアンは3つの石を祀っていたそうです。
タオクアンには「オンダウラウ(Ong Dau Rau)」という呼び方もありますが、「ダウラウ」とは、煮炊きのときに鍋を乗せるために使う3本の足のことだそうです。
沖縄のヒヌカンでも、かつては3つの石を祀っていて、「オミチモン」などとも呼ばれています。
この点は、タオクアンとヒヌカンの大きな共通点だと思います。
★ベトナムのタオクアンも、陰暦12月24日に天に昇って、天の神様に報告をするのでしょうか。
☆ベトナムの場合は、天に昇る日が沖縄よりも1日早くて、陰暦12月23日になります。
タオクアンはこの日に天に昇って、家族の1年間の行いのすべてを、玉皇上帝という神様に報告すると考えられています。
タオクアンを天に送り出す儀式は、ベトナムではとても大切なものと考えられていて、キリスト教徒など、ふだんタオクアンを祀っていない人たちでも、この日には家でお供えをして儀式を行うそうです。
ベトナム人にとっていちばん大切な年中行事は、なんといってもテト(旧正月)ですが、タオクアンの儀式
が終わると、本格的に新年を迎える準備に入ります。
ですから、1年の締めくくりという意味もあります。
この日に天に昇ったタオクアンは、陰暦の大晦日(12月30日)の深夜に家庭に戻ってくると考えられています。
玉皇上帝というのは、中国の道教で最高神と考えられている神様です。
かまどの神様が年末に天に昇るという考え方は、もともと中国の道教で生まれたものです。
中国で生まれた考え方が、一方ではベトナムに伝わり、また一方では琉球に伝わりました。
ベトナムでも琉球でも、火やかまどに対する土着の信仰がもともとありましたが、その土着の信仰と、中国から伝わった考え方が結びついて、それぞれに発展していったわけです。
ヒヌカンにもタオクアンにも、道教だけでなく、仏教や儒教、祖先崇拝、精霊信仰など、いろいろな要素が入っていますが、ベトナムの場合は「灶君」や「玉皇上帝」という名前がそのまま使われているなど、中国の道教の影響がより強いと思います。
2011年01月22日
会員募集
私たちベトナム青葉奨学会沖縄委員会は、ベトナムの経済的に貧困な家庭の子どもたちに、ささやかな奨学金を送っているグループです。
ホーチミン市のドンズー日本語学校のグエン・ドゥック・ホーエ先生の呼びかけを受けて1994年に発足し、細々とですが活動を続けてきました。
昨年は、132名の小・中・高校生に奨学金を送りました。
今年は、昨年よりやや少ない125名程度を支援する予定をしています。
昨年支援した生徒のうち、9名は高校を卒業、また、残念ながら勉強を途中でやめてしまった生徒たちも、若干名います。
ベトナムからは新たな支援の要望が来ていて、10名程度の小学生を新しく支援する予定です。
青葉奨学会では、基本的に、一人の会員の方(里親)が、一人の生徒(里子)を支援する、という形をとっています。
(「里親」という言葉が適当なのかどうか、ちょっと戸惑いもあるのですが、便宜上、「里親」「里子」という言葉を使っています)
経済発展が注目される昨今のベトナムですが、困難な状況におかれている人たちも、依然たくさんいます。
中部の洪水や北部の旱魃など、自然災害が各地で頻発していますし、環境破壊によって生活を脅かされるなど、新たな問題もあちこちで出てきています。
教育事情もかなり改善されてきてはいますが、経済的な事情で勉強を続けるのが困難な生徒は、いまも多くいるようです。
ベトナム側からは、支援を継続するよう強い要望があり、私たちもあとしばらくはこの活動を続けたいと思っています。
多くの会員の方が今年も支援を続けて下さっていますが、いろいろな事情で支援が継続できない方もいらっしゃいます。
今年、あと何名か、奨学金支援に加わってくださる方を募りたいと思います。
もちろん、沖縄在住ではない方も歓迎します。
会員の方には、以下の会費を負担していただいています(事務・通信費を含みます)。
小学生を支援する場合の年会費 9000円
中学生を支援する場合の年会費 12000円
高校生を支援する場合の年会費 15000円
奨学金は、ホーチミン市にある青葉奨学会の事務局を通して、各地の生徒たちに渡されます。
奨学金の額は、公立学校の学費や設備費などを払ったり、学用品やかばん、制服などを買うためには十分であると聞いています。
支援する生徒は、家庭が経済的に貧しく学校に通うのが困難な生徒のうち、勉強が好きである程度の成績をおさめている子をベトナム側で選んでいます。
奨学金を支援して下さっている方には、原則として年に一度、「里子」からの手紙が届きます。
「里子」と手紙のやりとりをしたり、ベトナムを訪ねて実際に会うことも基本的に可能です(地域によっては、現地に行くのに時間と労力が必要な場合もあります)。
ベトナムと沖縄の間では、文化的に多くの共通点があります。食生活や気候・風土の点でも、よく似ていると思います。
反面、沖縄が発進基地となったベトナム戦争や、1940年代に日本軍がベトナムを侵略したという歴史もあります。
これまでの歴史も踏まえながら、今後は文化や経済など、平和的な交流をいっそう深めていきたいものです。
奨学金支援も、その中の小さなひとつだと考えています。
お金を送るだけでなく、ベトナムの言葉や文化、お互いの関わりについても一緒に勉強できたら、と思っています。
ベトナムの明日を担う子どもたちの成長を、一緒に見守ってみませんか。
興味を持って下さっている方は、下記までご連絡下さい。
電話 098-864-1539(すぺーす結) 携帯 080-2719-4720(村田)
メール muraquang☆ybb.ne.jp(☆を@に変えて下さい)
または、2月5日に、テト(旧正月)のお祝いも兼ねた集まりを持つ予定ですので、そちらに来て下さるのも大歓迎です。詳しくは、近日中にこのブログでお知らせします。
ホーチミン市のドンズー日本語学校のグエン・ドゥック・ホーエ先生の呼びかけを受けて1994年に発足し、細々とですが活動を続けてきました。
昨年は、132名の小・中・高校生に奨学金を送りました。
今年は、昨年よりやや少ない125名程度を支援する予定をしています。
昨年支援した生徒のうち、9名は高校を卒業、また、残念ながら勉強を途中でやめてしまった生徒たちも、若干名います。
ベトナムからは新たな支援の要望が来ていて、10名程度の小学生を新しく支援する予定です。
青葉奨学会では、基本的に、一人の会員の方(里親)が、一人の生徒(里子)を支援する、という形をとっています。
(「里親」という言葉が適当なのかどうか、ちょっと戸惑いもあるのですが、便宜上、「里親」「里子」という言葉を使っています)
経済発展が注目される昨今のベトナムですが、困難な状況におかれている人たちも、依然たくさんいます。
中部の洪水や北部の旱魃など、自然災害が各地で頻発していますし、環境破壊によって生活を脅かされるなど、新たな問題もあちこちで出てきています。
教育事情もかなり改善されてきてはいますが、経済的な事情で勉強を続けるのが困難な生徒は、いまも多くいるようです。
ベトナム側からは、支援を継続するよう強い要望があり、私たちもあとしばらくはこの活動を続けたいと思っています。
多くの会員の方が今年も支援を続けて下さっていますが、いろいろな事情で支援が継続できない方もいらっしゃいます。
今年、あと何名か、奨学金支援に加わってくださる方を募りたいと思います。
もちろん、沖縄在住ではない方も歓迎します。
会員の方には、以下の会費を負担していただいています(事務・通信費を含みます)。
小学生を支援する場合の年会費 9000円
中学生を支援する場合の年会費 12000円
高校生を支援する場合の年会費 15000円
奨学金は、ホーチミン市にある青葉奨学会の事務局を通して、各地の生徒たちに渡されます。
奨学金の額は、公立学校の学費や設備費などを払ったり、学用品やかばん、制服などを買うためには十分であると聞いています。
支援する生徒は、家庭が経済的に貧しく学校に通うのが困難な生徒のうち、勉強が好きである程度の成績をおさめている子をベトナム側で選んでいます。
奨学金を支援して下さっている方には、原則として年に一度、「里子」からの手紙が届きます。
「里子」と手紙のやりとりをしたり、ベトナムを訪ねて実際に会うことも基本的に可能です(地域によっては、現地に行くのに時間と労力が必要な場合もあります)。
ベトナムと沖縄の間では、文化的に多くの共通点があります。食生活や気候・風土の点でも、よく似ていると思います。
反面、沖縄が発進基地となったベトナム戦争や、1940年代に日本軍がベトナムを侵略したという歴史もあります。
これまでの歴史も踏まえながら、今後は文化や経済など、平和的な交流をいっそう深めていきたいものです。
奨学金支援も、その中の小さなひとつだと考えています。
お金を送るだけでなく、ベトナムの言葉や文化、お互いの関わりについても一緒に勉強できたら、と思っています。
ベトナムの明日を担う子どもたちの成長を、一緒に見守ってみませんか。
興味を持って下さっている方は、下記までご連絡下さい。
電話 098-864-1539(すぺーす結) 携帯 080-2719-4720(村田)
メール muraquang☆ybb.ne.jp(☆を@に変えて下さい)
または、2月5日に、テト(旧正月)のお祝いも兼ねた集まりを持つ予定ですので、そちらに来て下さるのも大歓迎です。詳しくは、近日中にこのブログでお知らせします。
2011年01月19日
ハイくんとの再会(3)
私たちは、その後小学校を後にして、ハイ君の家に向かいました。
村の集落の裏側に広がっている広大なゴム園の中にしばらく車を走らせ、いよいよゴム園の外れかなと思ったところに、ハイ君の家がありました。

周囲には、ハイ君の家の手前にもう一軒家があるだけで、この2軒だけが集落と随分離れたところにあるのが、とても不思議な感じです。
水道はなくて井戸があり、電気は来ていませんでした。
しかし、家は6年前とは違って、コンクリート作りになっていました。
ちゃんとした玄関戸と窓ガラスがありました。
ベトナム式の板ベット(?)がある部屋と、その裏に小さい部屋が1つあるだけの小さい造りで、行政からの援助と自分たちもいくらかお金を出して建て替えたそうです。
家の周りはゴム園で砂地のような感じでした。
お父さんは宝くじ売りの仕事に出かけていて、今回も会えなくて残念でしたが、お母さんは以前お会いした時よりも元気そうで、私たちをとても喜んで迎えてくださいました。

ハイ君の家にはジャックフルーツの木があって、ちょうど甘く熟した実がなっていました。
人の顔ぐらいある大きな果実で、外側はごつごつとした緑色の皮でおおわれていますが、中はクリーム色の甘い独特の香りのする、やわらかい果実でした。
ハイ君は皮を剥いて食べやすいようにして、手渡ししてくれました。
ジャックフルーツの実を食べながら、私たちはお母さんも交えてたくさんお話をしました。
主に、高校卒業後の進路のことについてでした。
実はハイ君も成績が優秀で、高校で終わるにはもったいないと私は思っています。
本人は大学に行きたいけれど、家庭の状況を考えれば、専門学校に行って先生になろうかと思っていると話していました。
以前と違って、ハイ君はとてもよく話をします。
2年生までは家庭教師などをしていたけれど、3年生になってからは勉強が忙しくなっていること、電気がないので勉強時間に限りがあり、またIT関係にも疎いなどのハンディがあるとのことでした。
ハイ君は高校に自転車通学をしているのですが、家からミンホア村の集落まで出るにもかなり距離がある上に、隣りのミンタイン村にある高校までとなると、往復にだいぶ明るい時間が取られるのだろうなと思いました。
また、現金収入になる豚が、なかなか売れなくて困っている、とも。
お母さんは、大学の試験を受けて合格したら借金をしてでも行かせたいとおっしゃっていました。
高校に行くのでさえもこの村では難しいことなのに、その上大学に進むということにでもなれば、それは快挙に近いことなのかもしれません。
スアン君も成績が優秀ですので、青葉奨学生出身の2人が先達になれば、あのミンホアの子どもたちにとってもそれは希望になることでしょう。
お母さんは、ゴム園の仕事に毎朝(真夜中?)1時に出かけているそうです。
近頃はゴムの値段も上がって景気がいいみたいですが、ゴム園で働いている人たちにもその恩恵がまわってきているのでしょうか?
あまり立ち入ったことは聞くことができませんでしたが、なんとなく以前に比べたら生活も安定しているようで、活気が感じられました。

何よりも、ハイ君がたくましくなって真剣に将来を考え始めていることで、私は安心することができました。
お母さんもハイ君の進学に前向きであることがわかりましたので、あとは見守っていくだけです。
どうか困難を乗り越えて、大学に進んでほしいと思います。
3泊4日の、あっという間のベトナムの旅でした。また必ず何年後かにはミンホアの村を訪ねたいと思っています。
そのときには、一言二言でもいいからベトナム語が話せたらいいなあとつくづく思っています。
言葉を学ぶというのは、同時にその国の文化を学ぶということにもつながると思います。
ぺらぺらになれるなんてことは夢にも思いませんが、言葉を習いながらベトナムの人たちにもう一歩近づきたい、そんな風に思います。
もし同じ気持ちの方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強はじめてみませんか?
(毎週金曜日の夜、すぺーす結でベトナム語の勉強会を行っています)
そして数年後一緒に里子に会いに行きましょう!
村の集落の裏側に広がっている広大なゴム園の中にしばらく車を走らせ、いよいよゴム園の外れかなと思ったところに、ハイ君の家がありました。
周囲には、ハイ君の家の手前にもう一軒家があるだけで、この2軒だけが集落と随分離れたところにあるのが、とても不思議な感じです。
水道はなくて井戸があり、電気は来ていませんでした。
しかし、家は6年前とは違って、コンクリート作りになっていました。
ちゃんとした玄関戸と窓ガラスがありました。
ベトナム式の板ベット(?)がある部屋と、その裏に小さい部屋が1つあるだけの小さい造りで、行政からの援助と自分たちもいくらかお金を出して建て替えたそうです。
家の周りはゴム園で砂地のような感じでした。
お父さんは宝くじ売りの仕事に出かけていて、今回も会えなくて残念でしたが、お母さんは以前お会いした時よりも元気そうで、私たちをとても喜んで迎えてくださいました。
ハイ君の家にはジャックフルーツの木があって、ちょうど甘く熟した実がなっていました。
人の顔ぐらいある大きな果実で、外側はごつごつとした緑色の皮でおおわれていますが、中はクリーム色の甘い独特の香りのする、やわらかい果実でした。
ハイ君は皮を剥いて食べやすいようにして、手渡ししてくれました。
ジャックフルーツの実を食べながら、私たちはお母さんも交えてたくさんお話をしました。
主に、高校卒業後の進路のことについてでした。
実はハイ君も成績が優秀で、高校で終わるにはもったいないと私は思っています。
本人は大学に行きたいけれど、家庭の状況を考えれば、専門学校に行って先生になろうかと思っていると話していました。
以前と違って、ハイ君はとてもよく話をします。
2年生までは家庭教師などをしていたけれど、3年生になってからは勉強が忙しくなっていること、電気がないので勉強時間に限りがあり、またIT関係にも疎いなどのハンディがあるとのことでした。
ハイ君は高校に自転車通学をしているのですが、家からミンホア村の集落まで出るにもかなり距離がある上に、隣りのミンタイン村にある高校までとなると、往復にだいぶ明るい時間が取られるのだろうなと思いました。
また、現金収入になる豚が、なかなか売れなくて困っている、とも。
お母さんは、大学の試験を受けて合格したら借金をしてでも行かせたいとおっしゃっていました。
高校に行くのでさえもこの村では難しいことなのに、その上大学に進むということにでもなれば、それは快挙に近いことなのかもしれません。
スアン君も成績が優秀ですので、青葉奨学生出身の2人が先達になれば、あのミンホアの子どもたちにとってもそれは希望になることでしょう。
お母さんは、ゴム園の仕事に毎朝(真夜中?)1時に出かけているそうです。
近頃はゴムの値段も上がって景気がいいみたいですが、ゴム園で働いている人たちにもその恩恵がまわってきているのでしょうか?
あまり立ち入ったことは聞くことができませんでしたが、なんとなく以前に比べたら生活も安定しているようで、活気が感じられました。
何よりも、ハイ君がたくましくなって真剣に将来を考え始めていることで、私は安心することができました。
お母さんもハイ君の進学に前向きであることがわかりましたので、あとは見守っていくだけです。
どうか困難を乗り越えて、大学に進んでほしいと思います。
3泊4日の、あっという間のベトナムの旅でした。また必ず何年後かにはミンホアの村を訪ねたいと思っています。
そのときには、一言二言でもいいからベトナム語が話せたらいいなあとつくづく思っています。
言葉を学ぶというのは、同時にその国の文化を学ぶということにもつながると思います。
ぺらぺらになれるなんてことは夢にも思いませんが、言葉を習いながらベトナムの人たちにもう一歩近づきたい、そんな風に思います。
もし同じ気持ちの方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強はじめてみませんか?
(毎週金曜日の夜、すぺーす結でベトナム語の勉強会を行っています)
そして数年後一緒に里子に会いに行きましょう!
Posted by クアン at
21:10
│Comments(0)
2011年01月18日
ハイくんとの再会(2)
学校に入って、校長、教頭先生そしてミンホアの10人の子どもたちと交流会を持ちました。
皆さん緊張した面持ちでしたので、私も最初緊張しました。
沖縄委員会で発行している会誌「ホウオウボク」第22号に、村田さんが2年前にこのミンホア村を訪れて子どもたちと交流会をもった時の様子が報告されていて、子どもたちの写真も一緒に載っているものですから、その「ホウオウボク」を、早速皆さんに見てもらいました。
自分たちが写っているので、なんだかびっくりしたような不思議そうなうれしいような感じで見ていました。

沖縄について、生徒たちにひとつふたつ何か実感してもらいたくて、サトウキビから取れた黒糖を少しばかりお土産に持っていきました。
ベトナムでも同じようなお菓子があるということで、なんだか一歩近づけたかなと思いながら、自己紹介が始まりました。
「近頃とても嬉しかったこと、感動したことも一緒に教えて下さい」とお願いしました。
そうしましたら、皆さん同じように「学校の成績が上がったこと」を挙げてくれました。
中には、今学期学業の成績が振るわなかったという子もいました。
そんな時は、校長先生が横から「この子の場合は、困難な家庭事情のため勉強ができなかった」と申し訳なさそうにいわれました。
私としては、学校の行事や村のお祭り、お母さんお父さんにほめられたことなどを想定しての楽しかったことを知りたかったのですが、あまりに学業成績中心の話題に集中してしまって、ちょっと困惑しました。
今度は、「放課後にはどんな風にして過ごしているか」を訊ねてみましたら、やはり皆同じように、「お父さんお母さんを助けて、ご飯を炊いたりおうちの手伝いをしてすごしている」との事でした。
校長先生は「この子たちは遠いところから通っていて、家の手伝いで精一杯なので楽しいことなどはありませんよ」と言われました。
日々の小さなことでも楽しいことはあるはずですが、なんだか味気ない感じになってしまいました。
そして「学業成績に、これほどまでにこだわらなくてもいいのではないか」と思いました。
でも今沖縄に戻ってきてよくよく考えてみましたら、また私自身の小さい頃を思い出して照らし合わせてみますと、少し納得できるような気がします。
私は1950年生まれで、戦後のモノのない時代に生まれました。
親たちは家族を食べさせるのに精一杯で、私たち子どもなどは、半ばほったらかしの状態でした。
そんな私たちにとっての一番の楽しみは、なんといっても学校生活でした(それに続く放課後ももちろんですが)。
学校というところは、毎日新しいことが学べて、おまけに、歌も歌って体育の時間もあって図画工作もあって裁縫もあって、本当に毎日毎日が楽しいところでした。
戦時中で学校に通えなかった親たちも、子どもの学校の様子が面白いようで、頼みもしないのに興味津々宿題を手伝ってくれたりしました。
また、先生たちの口からは、古い封建主義に対峙した「民主主義」という言葉がボンボン飛び出して来たりして、子ども心にも時代が新しくなっていくのを感じたものでした。
ひるがえって、ミンホアの子どもたちのことを思うと、私の子ども時代のように、やはり彼らにとっても学校が一番の楽しみなのかもしれません。
ましてや、「ベトナム社会主義共和国」ですので、学業の成績が誇りになるでしょうし、また目標となって、それが毎日の励みにもなっているのかもしれません。
今の日本のようなどこかいびつな学力偏重型とは違って、国が発展していく過程での人々の向学心みたいなものが、今のベトナムの人々の底流にあるのかもしれない、と思うようになりました。
ですからこれからは、「学業の成績が上がった」ととても喜んで手紙を書いて来てくれる子どもには、率直に一緒に喜んであげるべきだと思いました。
交流会のことに話を戻しますと、その後子どもたちがみんなで歌を歌ってくれて、お返しに、同行してくれた仲宗根さんが沖縄のわらべ歌を紹介しました。
私は準備していたミニアルバムを見せながら沖縄の紹介をしました。
やんばるのみかんや桜祭りのこと、シーサーのこと、きれいな沖縄の海の風景や鯨の泳いでいる様子、我が家の正月風景、富士山を背景にした家族全員の集合の写真などを紹介しました。
とても興味深そうに熱心に見てくれました。

最後に「みなさんも、手紙でベトナムのことをたくさん教えて下さいね」と頼みました。
短い交流の時間でしたが、ミンホアの子どもたちみんなに会えて、とても良かったなと思いました。
反省としては、子どもたちから自発的に話してもらえるところまでは至らなくて、こちら側からの一方通行が大部分を占めていたかな、ということです。
「写真を見ながらそのつど質問などしてもらって、会話のきっかけをつくれればよかったな」と、あとで後悔しました。
その後校長先生と少しお話する時間がありました。
世界的な不況の中で、ゴム産業中心のこの地域の状況を、ちょっと聞いてみました。
校長先生がおっしゃるには、青葉奨学生たちの親はゴム農園の仕事もできない人たちで、臨時に家を建てる手伝いをしたり、学校の掃除の仕事をしたりなどして、安定した収入はない状態だということでした。
ですから、ハイ君やもう1人の高校生のスアン君のように、高校にまで行けるということ自体が、ものすごく大変なことだそうです。
スアン君は現在高校3年生ですが、非常に成績が優秀で、地域合同の統一テストで総合2位の成績を2回とったそうです。
大学にも十分行ける成績ではないかと思います。
交流会の時には「専門学校に行って警察官になりたい」と発表していましたが、里親に送ってくる手紙には「医師になるのが夢だ」と書いていたそうです。
皆さん緊張した面持ちでしたので、私も最初緊張しました。
沖縄委員会で発行している会誌「ホウオウボク」第22号に、村田さんが2年前にこのミンホア村を訪れて子どもたちと交流会をもった時の様子が報告されていて、子どもたちの写真も一緒に載っているものですから、その「ホウオウボク」を、早速皆さんに見てもらいました。
自分たちが写っているので、なんだかびっくりしたような不思議そうなうれしいような感じで見ていました。
沖縄について、生徒たちにひとつふたつ何か実感してもらいたくて、サトウキビから取れた黒糖を少しばかりお土産に持っていきました。
ベトナムでも同じようなお菓子があるということで、なんだか一歩近づけたかなと思いながら、自己紹介が始まりました。
「近頃とても嬉しかったこと、感動したことも一緒に教えて下さい」とお願いしました。
そうしましたら、皆さん同じように「学校の成績が上がったこと」を挙げてくれました。
中には、今学期学業の成績が振るわなかったという子もいました。
そんな時は、校長先生が横から「この子の場合は、困難な家庭事情のため勉強ができなかった」と申し訳なさそうにいわれました。
私としては、学校の行事や村のお祭り、お母さんお父さんにほめられたことなどを想定しての楽しかったことを知りたかったのですが、あまりに学業成績中心の話題に集中してしまって、ちょっと困惑しました。
今度は、「放課後にはどんな風にして過ごしているか」を訊ねてみましたら、やはり皆同じように、「お父さんお母さんを助けて、ご飯を炊いたりおうちの手伝いをしてすごしている」との事でした。
校長先生は「この子たちは遠いところから通っていて、家の手伝いで精一杯なので楽しいことなどはありませんよ」と言われました。
日々の小さなことでも楽しいことはあるはずですが、なんだか味気ない感じになってしまいました。
そして「学業成績に、これほどまでにこだわらなくてもいいのではないか」と思いました。
でも今沖縄に戻ってきてよくよく考えてみましたら、また私自身の小さい頃を思い出して照らし合わせてみますと、少し納得できるような気がします。
私は1950年生まれで、戦後のモノのない時代に生まれました。
親たちは家族を食べさせるのに精一杯で、私たち子どもなどは、半ばほったらかしの状態でした。
そんな私たちにとっての一番の楽しみは、なんといっても学校生活でした(それに続く放課後ももちろんですが)。
学校というところは、毎日新しいことが学べて、おまけに、歌も歌って体育の時間もあって図画工作もあって裁縫もあって、本当に毎日毎日が楽しいところでした。
戦時中で学校に通えなかった親たちも、子どもの学校の様子が面白いようで、頼みもしないのに興味津々宿題を手伝ってくれたりしました。
また、先生たちの口からは、古い封建主義に対峙した「民主主義」という言葉がボンボン飛び出して来たりして、子ども心にも時代が新しくなっていくのを感じたものでした。
ひるがえって、ミンホアの子どもたちのことを思うと、私の子ども時代のように、やはり彼らにとっても学校が一番の楽しみなのかもしれません。
ましてや、「ベトナム社会主義共和国」ですので、学業の成績が誇りになるでしょうし、また目標となって、それが毎日の励みにもなっているのかもしれません。
今の日本のようなどこかいびつな学力偏重型とは違って、国が発展していく過程での人々の向学心みたいなものが、今のベトナムの人々の底流にあるのかもしれない、と思うようになりました。
ですからこれからは、「学業の成績が上がった」ととても喜んで手紙を書いて来てくれる子どもには、率直に一緒に喜んであげるべきだと思いました。
交流会のことに話を戻しますと、その後子どもたちがみんなで歌を歌ってくれて、お返しに、同行してくれた仲宗根さんが沖縄のわらべ歌を紹介しました。
私は準備していたミニアルバムを見せながら沖縄の紹介をしました。
やんばるのみかんや桜祭りのこと、シーサーのこと、きれいな沖縄の海の風景や鯨の泳いでいる様子、我が家の正月風景、富士山を背景にした家族全員の集合の写真などを紹介しました。
とても興味深そうに熱心に見てくれました。
最後に「みなさんも、手紙でベトナムのことをたくさん教えて下さいね」と頼みました。
短い交流の時間でしたが、ミンホアの子どもたちみんなに会えて、とても良かったなと思いました。
反省としては、子どもたちから自発的に話してもらえるところまでは至らなくて、こちら側からの一方通行が大部分を占めていたかな、ということです。
「写真を見ながらそのつど質問などしてもらって、会話のきっかけをつくれればよかったな」と、あとで後悔しました。
その後校長先生と少しお話する時間がありました。
世界的な不況の中で、ゴム産業中心のこの地域の状況を、ちょっと聞いてみました。
校長先生がおっしゃるには、青葉奨学生たちの親はゴム農園の仕事もできない人たちで、臨時に家を建てる手伝いをしたり、学校の掃除の仕事をしたりなどして、安定した収入はない状態だということでした。
ですから、ハイ君やもう1人の高校生のスアン君のように、高校にまで行けるということ自体が、ものすごく大変なことだそうです。
スアン君は現在高校3年生ですが、非常に成績が優秀で、地域合同の統一テストで総合2位の成績を2回とったそうです。
大学にも十分行ける成績ではないかと思います。
交流会の時には「専門学校に行って警察官になりたい」と発表していましたが、里親に送ってくる手紙には「医師になるのが夢だ」と書いていたそうです。
Posted by クアン at
20:58
│Comments(0)
2011年01月17日
ハイ君との再会(1)
会員の方々が書いて下さったベトナム訪問記、3回目は沖本富貴子さんです。
2004年のベトナムツアー以来、6年ぶりのベトナム訪問。
沖本さんは、里子のハイくんがいるミンホア村訪問の様子を、とても詳しく書いて下さいました。
3回に分けてご紹介します。
私は今回のベトナム訪問で、里子のハイ君と6年ぶりに再会を果たしてきました。
ハイ君とは、私が青葉奨学会に参加した2002年の時からの付き合いになります。
当時はまだ小学校4年生で、履歴書に貼られていた写真はとても愛くるしいものでした。
初めて会ったのは6年前、青葉奨学会里子訪問の旅に参加した時で、ハイ君はちょうど小学校5年を終えて中学に進級したばかりでした。
ハイ君はとても恥ずかしそうにしていて、たくさん話をできたわけではありませんでしたが、新調したばかりの黒光りする手提げカバンを誇らしげに見せてくれた事が、とても印象に残っています。
玄関ドアとか窓ガラスなどがない吹きさらしの家の中では、そのカバンだけが異様に目だって立派に見えたものでした。
ハイ君は「困難な中でも僕はがんばっています」といつも手紙に書いてきていましたが、本当にお父さん、お母さんを助けながら、困難な中、勉強をがんばっていることがよくわかりました。
時間が経つのは早いもので、あれからもう6年。
その間、ハイ君は中学の4年間を終え、高校に進学し、そして今年の9月には最終学年の3年生になりました。
青葉奨学会の支援は基本的には高校までですので、もし今回のベトナム訪問の機会を逃したらもうハイ君と会えるチャンスがないかもしれないと思い、居てもたってもいられなくなって、急遽皆さんと同行して行って参りました。
航空券やホテルの手配がすでに終わったあとでの急な申し出であったために、村田さんには随分ご迷惑をおかけしました。
ハイ君の住んでいるミンホア村は、ビンズォン省北部にある小さな村です。
このビンズォン省は南側がホーチミン市に隣接している省で、北側はカンボジア国境にも近く、いわゆる「ホーチミン・ルート」の南端にあたるところらしいのです。
このビンズォン省はベトナムの中でも有数のゴムの産地ですが、最近、ホーチミン市に近い南側では、大規模な工業団地が建設されて急発展を遂げている最中だそうです。
前回は随分道に迷いましたが、今回はスムーズにミンホア村にたどり着くことができました。
ミンホア村では全部で10人の奨学生がいます。
小学生が7人、中学生が1人、高校生が2人という内訳です。
青葉奨学会の本部と連絡を取り合って、この地域の奨学生の担当をしてくださっているのは、どうやらミンホア小学校の校長先生のようでした。
私たちはまず10人の奨学生みんなが集まって待ってくれている小学校に行きました。6年前に訪問した時と変わらない、小学校の校庭のなつかしい風景でした。
私たちの車が学校に近づくと、1人の青年が駆け寄ってきました。
あのハイ君です。
私たちが到着するのを、今か今かと待っていてくれたのです。
背は私よりも伸びて、立派な青年になっていました。
手を取り合ってしっかりお互いを確かめあった瞬間、ハイ君の目から、大きな涙がボロッとこぼれました。
あわててハイ君は涙をこすりましたが、私も泣いていました。
2004年のベトナムツアー以来、6年ぶりのベトナム訪問。
沖本さんは、里子のハイくんがいるミンホア村訪問の様子を、とても詳しく書いて下さいました。
3回に分けてご紹介します。
私は今回のベトナム訪問で、里子のハイ君と6年ぶりに再会を果たしてきました。
ハイ君とは、私が青葉奨学会に参加した2002年の時からの付き合いになります。
当時はまだ小学校4年生で、履歴書に貼られていた写真はとても愛くるしいものでした。
初めて会ったのは6年前、青葉奨学会里子訪問の旅に参加した時で、ハイ君はちょうど小学校5年を終えて中学に進級したばかりでした。
ハイ君はとても恥ずかしそうにしていて、たくさん話をできたわけではありませんでしたが、新調したばかりの黒光りする手提げカバンを誇らしげに見せてくれた事が、とても印象に残っています。
玄関ドアとか窓ガラスなどがない吹きさらしの家の中では、そのカバンだけが異様に目だって立派に見えたものでした。
ハイ君は「困難な中でも僕はがんばっています」といつも手紙に書いてきていましたが、本当にお父さん、お母さんを助けながら、困難な中、勉強をがんばっていることがよくわかりました。
時間が経つのは早いもので、あれからもう6年。
その間、ハイ君は中学の4年間を終え、高校に進学し、そして今年の9月には最終学年の3年生になりました。
青葉奨学会の支援は基本的には高校までですので、もし今回のベトナム訪問の機会を逃したらもうハイ君と会えるチャンスがないかもしれないと思い、居てもたってもいられなくなって、急遽皆さんと同行して行って参りました。
航空券やホテルの手配がすでに終わったあとでの急な申し出であったために、村田さんには随分ご迷惑をおかけしました。
ハイ君の住んでいるミンホア村は、ビンズォン省北部にある小さな村です。
このビンズォン省は南側がホーチミン市に隣接している省で、北側はカンボジア国境にも近く、いわゆる「ホーチミン・ルート」の南端にあたるところらしいのです。
このビンズォン省はベトナムの中でも有数のゴムの産地ですが、最近、ホーチミン市に近い南側では、大規模な工業団地が建設されて急発展を遂げている最中だそうです。
前回は随分道に迷いましたが、今回はスムーズにミンホア村にたどり着くことができました。
ミンホア村では全部で10人の奨学生がいます。
小学生が7人、中学生が1人、高校生が2人という内訳です。
青葉奨学会の本部と連絡を取り合って、この地域の奨学生の担当をしてくださっているのは、どうやらミンホア小学校の校長先生のようでした。
私たちはまず10人の奨学生みんなが集まって待ってくれている小学校に行きました。6年前に訪問した時と変わらない、小学校の校庭のなつかしい風景でした。
私たちの車が学校に近づくと、1人の青年が駆け寄ってきました。
あのハイ君です。
私たちが到着するのを、今か今かと待っていてくれたのです。
背は私よりも伸びて、立派な青年になっていました。
手を取り合ってしっかりお互いを確かめあった瞬間、ハイ君の目から、大きな涙がボロッとこぼれました。
あわててハイ君は涙をこすりましたが、私も泣いていました。
Posted by クアン at
21:14
│Comments(0)
2011年01月15日
念願のベトナム旅行
会員の方に寄せていただいたベトナム里子訪問の報告。
2回目は、ベトナム初体験の古見美智子さんです。
2010年11月4日、念願だったベトナム旅行の、いよいよ出発の日。
国内旅行と違って、なにか緊張しています。
初めて里子のキム・ガンちゃんに会うのはとても楽しみですが、ベトナムのことを何も勉強しないままで行っていいのだろうかと不安がよぎります。
沖縄から台北経由でホーチミン市までは半日の行程。
夕方ホーチミン市に着き、タクシーから眺める光景に度肝を抜かれました。
噂には聞いていましたが、バイク、バイク、バイクの群れ。
車、車、車、その中で、徒歩で道を渡っている人もいる……思わず顔をしかめてしまいそう。
車内から見ている自分のほうがひかれてしまいそうな気がして、どきどき胸が高鳴っている…。
あ~、ベトナムに来ているんだと、実感しました。
2日目は、朝、地元の人が行くというタンディン市場を見学したあと、ドンズー日本語学校でホーエ先生に会い、いろいろ話を聞かせていただきました。
仲宗根さんの元里子のヤンくんも来てくれて、仲宗根さんと初めての対面、近況報告をしてくれました。
大学生になっているとのことですが、とても素直そうな好青年でした。
ヤンくんと青葉奨学会スタッフのスアンさんを交え、バスに乗って市内の食堂に昼食をとりにいきました。
いったんホテルに戻り休憩した後、中心街の国営デパートなどで買い物。
お金(ドン)の単位があまりに大きすぎて、買い物をするたびにどぎまぎしている自分が情けなくなりました。
夜は、水上人形劇の観劇。意味はよくわからないものの、不思議で楽しい時間でした。
夕食は、村田さんの友人のフオンさんを交えて、きのこ鍋に舌鼓をうちました。
3日目は、いよいよ里子に会う日。
車とフェリーを乗り継いでカンザーのビンカン村へ。
里子のガンちゃんは小学6年生かと思っていたら、今年9月に中学生になったとのこと(小学校が5年間で、中学校が4年間だそうです)。
最初、履歴票の写真で見覚えのある顔がいるので、近寄って握手をしようとしましたが、腕を組んだまま立っていて、ニコリともしないので、私は拒否されたと思い言葉が出ませんでした。
あとでわかったことですが、ベトナムでは腕を組むのは目上の人への正式な挨拶の形だと聞いて、ほっとしました。
笑顔がないのは、とても緊張しているから…とのこと。
文化の違い、言葉の違いを痛感し、勉強不足を反省しました。
ガンちゃんが住んでいるところは、おじいさんの家だということで、コンクリート造りのしっかりした家に見えました。
11月6日はおばあさんの命日とのことで、ガンちゃんのお母さんのきょうだいも集まっていました。
お母さんは33歳で、ホーチミン市のフーニュアン区というところ(ドンズー日本語学校の近く)の大衆食堂に住み込みで働いていて、月に1回程度家に帰ってくる、とのことで、ガンちゃんは、ふだんはおじいさん、おばさんと一緒に暮らしている、ということでした。
ガンちゃんの下半身がとてもがっちりしている、と思ったら、彼女はスポーツウーマンで、1500メートル走ではホーチミン市で1位になり、走り幅跳びでも3位だったとのことです。
好きな学科は数学で、将来はファッションデザイナーになりたいと恥ずかしそうに話していました。
これからも、自分にできる援助は、ぜひ続けたいと改めて感じました。
ガンちゃんのお母さんは、住み込みで働いていても収入は日本円にすると月3000円程度しかなく、生活はとても苦しい様子でした。
おじいさんの家は、つくりはしっかりしていますが、家具等はほとんどなく、狭い部屋でした。
私の勉強不足もあり、まったく言葉が通じないというのは、もどかしいものです。

次に、ロンホア村に行って城間さんの里子のタイちゃんに会い、ホテルに戻りました。
夜はサイゴン川のディナークルーズを楽しんだのですが、昼間に目にしたガンちゃん、タイちゃんの厳しい暮らしを思うと、心の片隅が暗くなりました。
クルースの最後のほうで、石で作られたダンダーという民族楽器の演奏があり、村田さんが目を輝かせて聞き入っていました。
今回の旅は、日程的には短かったのですが、とても充実していて、楽しく有意義な旅でした。
またぜひ、2~3年後にはガンちゃんに会いに行きたいと思います。
その時には、もう女の子らしく変身しているのかも知れませんネ。楽しみです。
村田さん、城間さん、こんな機会を作って下さり、本当にありがとうございました。
2回目は、ベトナム初体験の古見美智子さんです。
2010年11月4日、念願だったベトナム旅行の、いよいよ出発の日。
国内旅行と違って、なにか緊張しています。
初めて里子のキム・ガンちゃんに会うのはとても楽しみですが、ベトナムのことを何も勉強しないままで行っていいのだろうかと不安がよぎります。
沖縄から台北経由でホーチミン市までは半日の行程。
夕方ホーチミン市に着き、タクシーから眺める光景に度肝を抜かれました。
噂には聞いていましたが、バイク、バイク、バイクの群れ。
車、車、車、その中で、徒歩で道を渡っている人もいる……思わず顔をしかめてしまいそう。
車内から見ている自分のほうがひかれてしまいそうな気がして、どきどき胸が高鳴っている…。
あ~、ベトナムに来ているんだと、実感しました。
2日目は、朝、地元の人が行くというタンディン市場を見学したあと、ドンズー日本語学校でホーエ先生に会い、いろいろ話を聞かせていただきました。
仲宗根さんの元里子のヤンくんも来てくれて、仲宗根さんと初めての対面、近況報告をしてくれました。
大学生になっているとのことですが、とても素直そうな好青年でした。
ヤンくんと青葉奨学会スタッフのスアンさんを交え、バスに乗って市内の食堂に昼食をとりにいきました。
いったんホテルに戻り休憩した後、中心街の国営デパートなどで買い物。
お金(ドン)の単位があまりに大きすぎて、買い物をするたびにどぎまぎしている自分が情けなくなりました。
夜は、水上人形劇の観劇。意味はよくわからないものの、不思議で楽しい時間でした。
夕食は、村田さんの友人のフオンさんを交えて、きのこ鍋に舌鼓をうちました。
3日目は、いよいよ里子に会う日。
車とフェリーを乗り継いでカンザーのビンカン村へ。
里子のガンちゃんは小学6年生かと思っていたら、今年9月に中学生になったとのこと(小学校が5年間で、中学校が4年間だそうです)。
最初、履歴票の写真で見覚えのある顔がいるので、近寄って握手をしようとしましたが、腕を組んだまま立っていて、ニコリともしないので、私は拒否されたと思い言葉が出ませんでした。
あとでわかったことですが、ベトナムでは腕を組むのは目上の人への正式な挨拶の形だと聞いて、ほっとしました。
笑顔がないのは、とても緊張しているから…とのこと。
文化の違い、言葉の違いを痛感し、勉強不足を反省しました。
ガンちゃんが住んでいるところは、おじいさんの家だということで、コンクリート造りのしっかりした家に見えました。
11月6日はおばあさんの命日とのことで、ガンちゃんのお母さんのきょうだいも集まっていました。
お母さんは33歳で、ホーチミン市のフーニュアン区というところ(ドンズー日本語学校の近く)の大衆食堂に住み込みで働いていて、月に1回程度家に帰ってくる、とのことで、ガンちゃんは、ふだんはおじいさん、おばさんと一緒に暮らしている、ということでした。
ガンちゃんの下半身がとてもがっちりしている、と思ったら、彼女はスポーツウーマンで、1500メートル走ではホーチミン市で1位になり、走り幅跳びでも3位だったとのことです。
好きな学科は数学で、将来はファッションデザイナーになりたいと恥ずかしそうに話していました。
これからも、自分にできる援助は、ぜひ続けたいと改めて感じました。
ガンちゃんのお母さんは、住み込みで働いていても収入は日本円にすると月3000円程度しかなく、生活はとても苦しい様子でした。
おじいさんの家は、つくりはしっかりしていますが、家具等はほとんどなく、狭い部屋でした。
私の勉強不足もあり、まったく言葉が通じないというのは、もどかしいものです。

次に、ロンホア村に行って城間さんの里子のタイちゃんに会い、ホテルに戻りました。
夜はサイゴン川のディナークルーズを楽しんだのですが、昼間に目にしたガンちゃん、タイちゃんの厳しい暮らしを思うと、心の片隅が暗くなりました。
クルースの最後のほうで、石で作られたダンダーという民族楽器の演奏があり、村田さんが目を輝かせて聞き入っていました。
今回の旅は、日程的には短かったのですが、とても充実していて、楽しく有意義な旅でした。
またぜひ、2~3年後にはガンちゃんに会いに行きたいと思います。
その時には、もう女の子らしく変身しているのかも知れませんネ。楽しみです。
村田さん、城間さん、こんな機会を作って下さり、本当にありがとうございました。
Posted by クアン at
21:45
│Comments(0)
2011年01月13日
タイさんとの再会
会員の方々が会報に寄せて下さった、ベトナムの里子訪問の報告を、ブログでも順次ご紹介したいと思います。
まず、城間博子さんが書いて下さった「タイさんとの再会」の報告です。
11月4日から3泊4日、念願の3度目のベトナム訪問を果たすことが出来ました。2004年の訪問以来6年ぶりの訪問でした。
以前から何度も「ベトナムに連れて行ってほしい」と事務局の村田さんにお願いしていましたが、どういうわけか、サラッとかわされて来ました。
2004年は、同じ里親のOさんと一緒に、里子が通っているカンザーのホアヒエップ小学校まで会いに行きました。
そろそろ雨期が終わるころでしたが、校庭が水浸しで、男の先生が1人ずつオートバイの後ろに乗せて校舎まで運んで下さった事が印象的でした。
Oさんの里子の事は良く覚えていませんが、私の里子のタイちゃんは、小学5年生の割にはやせっぽちの、小さなはにかみ屋さんの女の子でした。
その時印象に残ったのは、タイちゃんの事よりも弟さんの様子でした。
ひとつ違いの小柄な弟さんが漕ぐ自転車の後ろにタイちゃんは乗って小学校までやって来ました。
タイちゃんは白いブラウスに赤いスカーフを結び、靴下と靴をはきキチンとした格好でしたが、裸足で自転車を漕いできた弟さんの身なりが、私の子どもの頃よりも貧しいと感じた事です。
今回は家庭訪問という事で、ご家族にお会いできると楽しみでした。
弟さんには会う事が出来ずに残念でしたが、優しそうなお母さんにお会いできてよかったです。
タイさんは、前回は小学5年生でしたが現在は高校2年生になり、すらっと身長が伸び娘さんらしく成長していました。
ニコニコと常に笑顔を絶やさず、私の質問にハキハキと答えてくださり、歌をリクエストしたところ、恥ずかしそうにしながらもお母さんに促されて歌ってくれました。
地域の共産青年団のリーダーの証も誇らしげに見せてくれました。

お母さんは、タイさんの教育や将来の事を、とても心配そうに話していました。
将来、タイさんは経営管理の仕事に就きたいと望んでいるそうですが、そのための勉強を続けさせられるか、悩んでいらっしゃる様子でした。
今回、里子達の家庭を訪問する事で、私達が想像する以上に貧しい地域の中にあって、さらに貧しい家庭の子どもだと実感しました。

私にとって決して負担にはならない少額のお金ですが、タイさんが学ぶ事に少しでも役に立てれば嬉しいと思いました。
また、このように里子を訪問する事で里子の成長を確認する事が出来て、嬉しかったです。

仲宗根さんの里子も古見さんの里子も、貧しいながら素晴らしい可能性を秘めた子どもたちでした。
今回の訪問は、ガイド役の村田さんを含めて5人の旅でしたが、ベトナム人の親切心あり、笑いありの素晴らしい旅でした。
魅力的な人との出会い、美味しいベトナム料理、ホーチミン市内の散策など、あと1週間くらい残りたいほどのベトナムの旅でした。
諸々のお心遣いを頂いて感謝しています。3~4年に1回の割合で訪問出来ると良いと思いますので、宜しくお願いします。
まず、城間博子さんが書いて下さった「タイさんとの再会」の報告です。
11月4日から3泊4日、念願の3度目のベトナム訪問を果たすことが出来ました。2004年の訪問以来6年ぶりの訪問でした。
以前から何度も「ベトナムに連れて行ってほしい」と事務局の村田さんにお願いしていましたが、どういうわけか、サラッとかわされて来ました。
2004年は、同じ里親のOさんと一緒に、里子が通っているカンザーのホアヒエップ小学校まで会いに行きました。
そろそろ雨期が終わるころでしたが、校庭が水浸しで、男の先生が1人ずつオートバイの後ろに乗せて校舎まで運んで下さった事が印象的でした。
Oさんの里子の事は良く覚えていませんが、私の里子のタイちゃんは、小学5年生の割にはやせっぽちの、小さなはにかみ屋さんの女の子でした。
その時印象に残ったのは、タイちゃんの事よりも弟さんの様子でした。
ひとつ違いの小柄な弟さんが漕ぐ自転車の後ろにタイちゃんは乗って小学校までやって来ました。
タイちゃんは白いブラウスに赤いスカーフを結び、靴下と靴をはきキチンとした格好でしたが、裸足で自転車を漕いできた弟さんの身なりが、私の子どもの頃よりも貧しいと感じた事です。
今回は家庭訪問という事で、ご家族にお会いできると楽しみでした。
弟さんには会う事が出来ずに残念でしたが、優しそうなお母さんにお会いできてよかったです。
タイさんは、前回は小学5年生でしたが現在は高校2年生になり、すらっと身長が伸び娘さんらしく成長していました。
ニコニコと常に笑顔を絶やさず、私の質問にハキハキと答えてくださり、歌をリクエストしたところ、恥ずかしそうにしながらもお母さんに促されて歌ってくれました。
地域の共産青年団のリーダーの証も誇らしげに見せてくれました。

お母さんは、タイさんの教育や将来の事を、とても心配そうに話していました。
将来、タイさんは経営管理の仕事に就きたいと望んでいるそうですが、そのための勉強を続けさせられるか、悩んでいらっしゃる様子でした。
今回、里子達の家庭を訪問する事で、私達が想像する以上に貧しい地域の中にあって、さらに貧しい家庭の子どもだと実感しました。

私にとって決して負担にはならない少額のお金ですが、タイさんが学ぶ事に少しでも役に立てれば嬉しいと思いました。
また、このように里子を訪問する事で里子の成長を確認する事が出来て、嬉しかったです。

仲宗根さんの里子も古見さんの里子も、貧しいながら素晴らしい可能性を秘めた子どもたちでした。
今回の訪問は、ガイド役の村田さんを含めて5人の旅でしたが、ベトナム人の親切心あり、笑いありの素晴らしい旅でした。
魅力的な人との出会い、美味しいベトナム料理、ホーチミン市内の散策など、あと1週間くらい残りたいほどのベトナムの旅でした。
諸々のお心遣いを頂いて感謝しています。3~4年に1回の割合で訪問出来ると良いと思いますので、宜しくお願いします。
Posted by クアン at
21:27
│Comments(0)
2011年01月12日
坊や大きくならないで
昨日の沖縄タイムスの投書欄に、安里さんという方の次のような投書が掲載されていました。
「12月12日午前6時20分ごろ、NHK第1ラジオから1960年代のベトナム戦争のさなかで歌われたというフォークソングが静かに流れた。その番組名や紹介した担当者の名前は覚えていないが、紹介された歌手とその歌は忘れられない。ベトナム人歌手の名前は、チン・コン・ソン。歌の題名は「坊や大きくならないで」である。
当時20代であった青年時代の私も間違いなく聞いていたであろうこの歌にまつわる解説者の短い話によれば、この歌は、ベトナム戦争に反対する反戦歌。2001年に亡くなった彼は、当時南ベトナム軍事政権によって逮捕され、歌は禁止となった。
ベトナム戦争終結=南北ベトナム統一後の現在も、なぜか、解禁されないままだそうだ。軍事大国アメリカや日本で歌われているというのにである。なんという歴史の狡知だろうか。
…坊や、大きくならないで、坊や大きくならないで、戦争がおきている、坊や大きくならないで…。哀調を帯びた静かなメロディと祈るような歌詞は、戦火におびえる子らへの子守歌であり、反戦歌である」
私も印象に残っている歌なので(そのラジオ番組は聴いていませんが)、少し補足をしたいと思います。
この歌は「Ngu di con」というタイトルで、直訳すると「お眠り、坊や」という感じになると思います。
大人になって戦場に送られ、命を落とした息子のなきがらを前に、母親が「お眠り、坊や」と語りかける歌で、まさに「子守歌」です。
これ以上悲しい「子守歌」は、ないかもしれません。
元の歌詞には「坊や、大きくならないで」という言葉はありませんが、邦題としては上手な訳だと思います。
投書にあるように、この歌は当時の南ベトナムで禁止されたそうです。
日本では、1970年代初めごろにベトナム人歌手のカイン・リーが紹介したほか、高石ともやなど数名の歌手がカバーしたと聞きました。
投書には「歌手はチン・コン・ソン」とありましたが、チン・コン・ソンは作曲者の名前です。彼自身が歌うこともありましたが、ラジオで紹介されたというのは、おそらくカイン・リーが歌ったものではないかと思います。
チン・コン・ソンは南ベトナム政府に睨まれていましたが、逮捕までされたかどうかはわかりません(サイゴン解放後、チン・コン・ソンは共産党政権によって、一時期再教育キャンプに送られたそうです)。
この歌は、現在もベトナムでは禁止に準じた扱いになっていると思います。
ベトナムで発行されているチン・コン・ソンの作品集(楽譜)には、120曲以上の作品が紹介されていますが、代表作のひとつであるこの歌は、なぜか載っていません。
反戦歌は、共産党政権にとって好ましくないみたいです。
なんかよくわからない考え方ですが…。
ただ、「禁止」は徹底されてはいないようです。
チン・コン・ソンの追悼コンサートでは、彼を慕っていた女性歌手ホン・ニュンがこの歌を熱唱し、DVDにも堂々と収められています。
ベトナムの文化政策も、だんだん変わってきているようです。
悲しい歌ですが、これからの若い世代の人たちにも伝えたい歌だと思います。
歌詞を紹介します。
お眠り坊や 黄色い肌の私の坊や
私はお前をあやし 傷口を赤く染めた銃弾をあやすの
20年たって 子どもたちは軍隊にとられ 行ったきり戻っては来ない
黄色い肌の私の子 お眠り坊や
あやすのはもう2度目
ああ、この体も昔はあんなに小さかった 胸に抱いたり腕に抱えたりしたのに
ああ お眠り坊や
お眠り坊や 私がお腹を痛めた子の 唇から苦しみの声が聞こえるよう
20年たって 子どもたちが大人になると 戦場へと出て行った
黄色い肌をしたこの大地の子
お眠り坊や 今は風塵になってしまった子よ
ああ、どんな傷がその熱い肌を 深くえぐってしまったのだろう
この骨と肉を私は苦労して育て上げたのに なぜ20歳で眠ってしまうの
(訳:吉井美知子 補訳:鈴木康央)
「12月12日午前6時20分ごろ、NHK第1ラジオから1960年代のベトナム戦争のさなかで歌われたというフォークソングが静かに流れた。その番組名や紹介した担当者の名前は覚えていないが、紹介された歌手とその歌は忘れられない。ベトナム人歌手の名前は、チン・コン・ソン。歌の題名は「坊や大きくならないで」である。
当時20代であった青年時代の私も間違いなく聞いていたであろうこの歌にまつわる解説者の短い話によれば、この歌は、ベトナム戦争に反対する反戦歌。2001年に亡くなった彼は、当時南ベトナム軍事政権によって逮捕され、歌は禁止となった。
ベトナム戦争終結=南北ベトナム統一後の現在も、なぜか、解禁されないままだそうだ。軍事大国アメリカや日本で歌われているというのにである。なんという歴史の狡知だろうか。
…坊や、大きくならないで、坊や大きくならないで、戦争がおきている、坊や大きくならないで…。哀調を帯びた静かなメロディと祈るような歌詞は、戦火におびえる子らへの子守歌であり、反戦歌である」
私も印象に残っている歌なので(そのラジオ番組は聴いていませんが)、少し補足をしたいと思います。
この歌は「Ngu di con」というタイトルで、直訳すると「お眠り、坊や」という感じになると思います。
大人になって戦場に送られ、命を落とした息子のなきがらを前に、母親が「お眠り、坊や」と語りかける歌で、まさに「子守歌」です。
これ以上悲しい「子守歌」は、ないかもしれません。
元の歌詞には「坊や、大きくならないで」という言葉はありませんが、邦題としては上手な訳だと思います。
投書にあるように、この歌は当時の南ベトナムで禁止されたそうです。
日本では、1970年代初めごろにベトナム人歌手のカイン・リーが紹介したほか、高石ともやなど数名の歌手がカバーしたと聞きました。
投書には「歌手はチン・コン・ソン」とありましたが、チン・コン・ソンは作曲者の名前です。彼自身が歌うこともありましたが、ラジオで紹介されたというのは、おそらくカイン・リーが歌ったものではないかと思います。
チン・コン・ソンは南ベトナム政府に睨まれていましたが、逮捕までされたかどうかはわかりません(サイゴン解放後、チン・コン・ソンは共産党政権によって、一時期再教育キャンプに送られたそうです)。
この歌は、現在もベトナムでは禁止に準じた扱いになっていると思います。
ベトナムで発行されているチン・コン・ソンの作品集(楽譜)には、120曲以上の作品が紹介されていますが、代表作のひとつであるこの歌は、なぜか載っていません。
反戦歌は、共産党政権にとって好ましくないみたいです。
なんかよくわからない考え方ですが…。
ただ、「禁止」は徹底されてはいないようです。
チン・コン・ソンの追悼コンサートでは、彼を慕っていた女性歌手ホン・ニュンがこの歌を熱唱し、DVDにも堂々と収められています。
ベトナムの文化政策も、だんだん変わってきているようです。
悲しい歌ですが、これからの若い世代の人たちにも伝えたい歌だと思います。
歌詞を紹介します。
お眠り坊や 黄色い肌の私の坊や
私はお前をあやし 傷口を赤く染めた銃弾をあやすの
20年たって 子どもたちは軍隊にとられ 行ったきり戻っては来ない
黄色い肌の私の子 お眠り坊や
あやすのはもう2度目
ああ、この体も昔はあんなに小さかった 胸に抱いたり腕に抱えたりしたのに
ああ お眠り坊や
お眠り坊や 私がお腹を痛めた子の 唇から苦しみの声が聞こえるよう
20年たって 子どもたちが大人になると 戦場へと出て行った
黄色い肌をしたこの大地の子
お眠り坊や 今は風塵になってしまった子よ
ああ、どんな傷がその熱い肌を 深くえぐってしまったのだろう
この骨と肉を私は苦労して育て上げたのに なぜ20歳で眠ってしまうの
(訳:吉井美知子 補訳:鈴木康央)
2011年01月11日
会報「Cay Phuong」第26号
青葉奨学会沖縄委員会では、年に2回程度、「Cay Phuong」という名前の会報を出していますが、新しい号(26号)が完成しました。
「Cay Phuong」とはベトナム語で「ホウオウボク」の意味です。
ホウオウボクの花はベトナムでもたいへん親しまれていて、「Hoa hoc tro(生徒の花)」とも呼ばれています。
今号の内容は、昨年11月の里子訪問の報告が中心です。
ツアーに参加された4名の会員の方が、それぞれ報告を書いて下さいました。
生徒と6年ぶりに再会した嬉しさや今後への期待、文化や習慣の違いへの率直な戸惑いなど、とても素敵な文章を寄せていただきました。
できたら、このブログでもご紹介したいと思っています。
ほかに、奨学生たちの手紙や絵、昨年の中秋節のつどいの報告なども載せました。
会員の方には、生徒の新しい履歴票と一緒に、近日中にお送りする予定ですので、お楽しみに。
「Cay Phuong」とはベトナム語で「ホウオウボク」の意味です。
ホウオウボクの花はベトナムでもたいへん親しまれていて、「Hoa hoc tro(生徒の花)」とも呼ばれています。
今号の内容は、昨年11月の里子訪問の報告が中心です。
ツアーに参加された4名の会員の方が、それぞれ報告を書いて下さいました。
生徒と6年ぶりに再会した嬉しさや今後への期待、文化や習慣の違いへの率直な戸惑いなど、とても素敵な文章を寄せていただきました。
できたら、このブログでもご紹介したいと思っています。
ほかに、奨学生たちの手紙や絵、昨年の中秋節のつどいの報告なども載せました。
会員の方には、生徒の新しい履歴票と一緒に、近日中にお送りする予定ですので、お楽しみに。